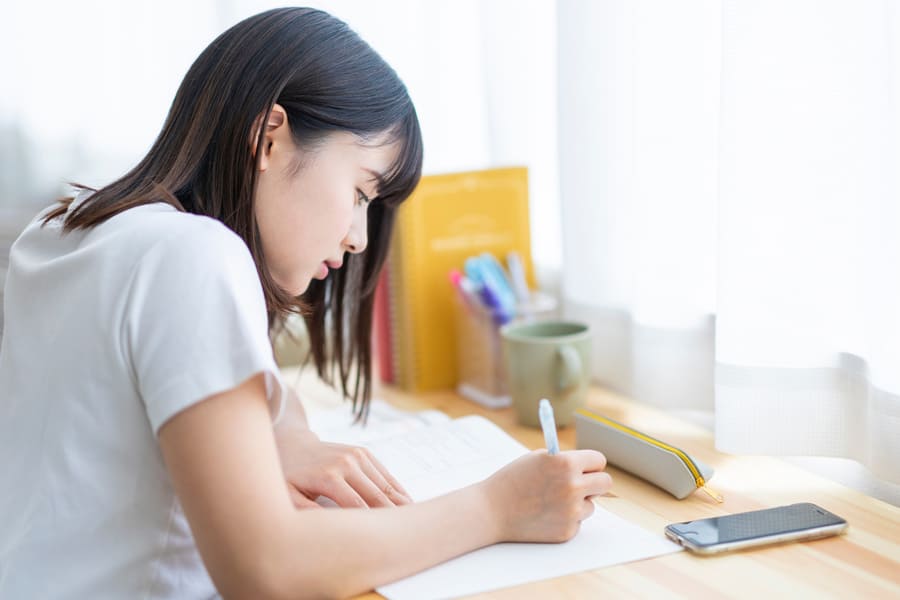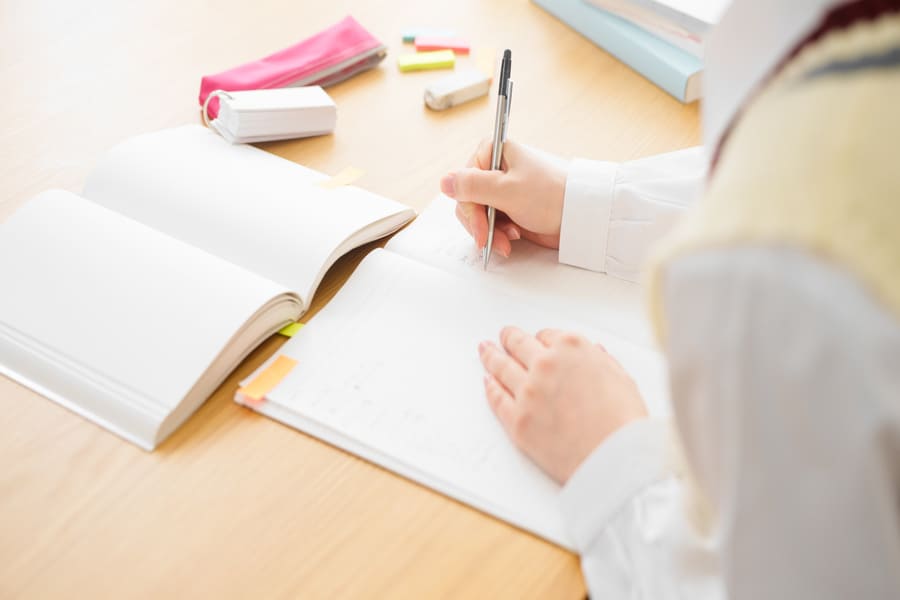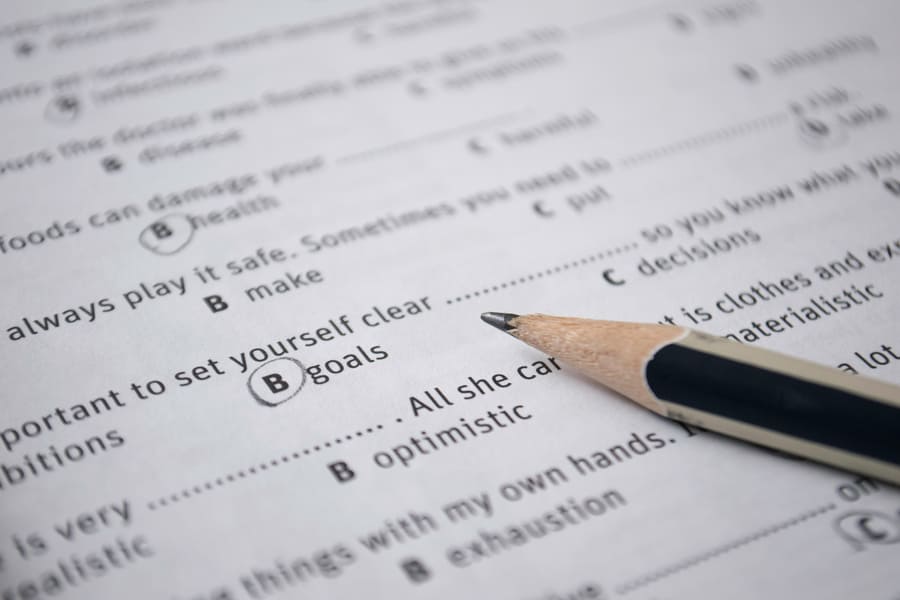「発達障害の子どもは勉強についていけないの?」
「子どもが勉強についていけないとき、家庭ではどのようにサポートするべき?」
発達障害の子どもが学校の勉強についていけないとき、親としてどのようにサポートすべきか悩む方は多いでしょう。
勉強についていくのが難しい発達障害の子どもには、個々の特性による学習面での困りごとを理解したうえで、適切なサポートを行うことが大切です。
そこで本記事では、発達障害の子どもが学習面で抱えがちな悩みやサポートのコツ、保護者の方ができる対処法とおすすめの相談機関を解説します。
「少しでも自信を取り戻して楽しく勉強に取り組んでほしい」と考えている方は、ぜひ参考にしてください。

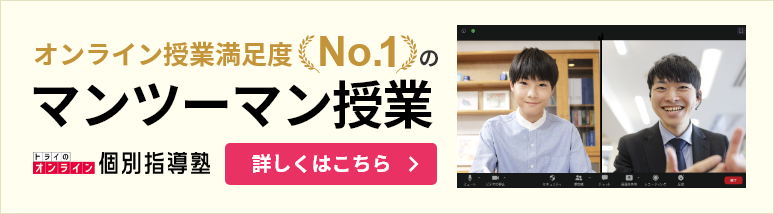
この記事の目次
発達障害の子どもが勉強についていけないときは学習面での困りごとに合わせてサポートしよう

発達障害の子どもが勉強についていけないときは、「どこでつまずいているのか」「何に困っているのか」を把握することが大切です。
前提として「発達障害の子は必ず勉強についていけなくなる」というわけではありません。
ただ、発達障害の特性によって学習面での悩みが増えると、勉強のペースが遅れて周りについていけなくなる場合があります。
とはいえ、焦ってプレッシャーをかけても、勉強への苦手意識を強めてしまいます。
勉強の遅れや自信を取り戻すために、まずは子どもの特性・悩みを正しく理解し、困りごとに合わせた適切なサポートを行いましょう。
【種類別】発達障害の子どもが抱えがちな困りごとや学習をサポートするコツ
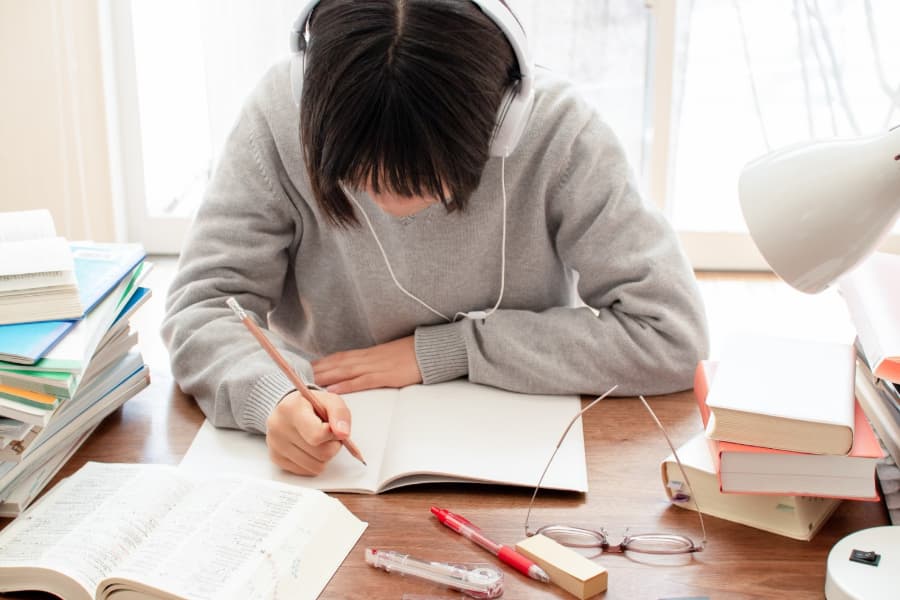
発達障害の種類と、学習面で抱えやすい困りごとは以下のとおりです。
| 発達障害の種類 | 学習面で抱えやすい困りごと |
| ADHD (注意欠如・多動症) | 注意力散漫になることで学習内容が定着しにくい |
| ASD (自閉スペクトラム症) | 曖昧な表現が苦手で得意・不得意の差が大きい |
| SLD/LD (限局性学習症/学習障害) | 学習に必要な基本スキルの習得が難しい |
ただし、同じ発達障害でも個々の特性・悩みは大きく異なります。
上記を参考にしつつ、子どもの様子を観察したり話を聞いたりして、勉強についていけない原因を正しく把握しましょう。
以下で、それぞれの特徴と学習をサポートするコツを詳しく解説します。
ADHD(注意欠如・多動症)|注意力散漫になることで学習内容が定着しにくい
ADHD(注意欠如・多動症)とは、「忘れ物が多い」「集中力が続かない」「急に席を立つ」などの特徴が見られる発達障害です。
ADHDの子どもは、学習面で以下のような困りごとを抱えるケースが多く見られます。
- 他のことに気を取られて教師の話を最後まで聞けず、学習内容が定着しない
- 宿題のやり忘れが多く、授業の予習・復習が十分にできない
- すぐ気が散ってしまうため勉強の進度が遅くなり、周りについていけない
もともと勉強が得意だったとしても、ADHDの特性によって学習内容の定着が遅れることも少なくありません。
ADHD(注意欠如・多動症)の子どもの学習をサポートするコツ
ADHDの子どもの学習をサポートするコツは、以下のとおりです。
- 休憩時間を細かく設定し、短時間で集中することを繰り返す
- クイズ形式にしたり制限時間を設けたりするなどゲーム性を取り入れる
- 動きながらでも勉強できる方法を取り入れる
- 一日の学習計画を見やすい場所に貼っておく
先述したとおり、ADHDの子どもは集中力が切れやすい傾向にあります。
そのため、短時間で勉強を区切ったり、ゲーム感覚で楽しく勉強できる方法を取り入れたりして、集中力を維持することが大切です。
動きながらでも取り組める勉強としては、単語帳や歴史年表などを手に持ち、歩き回りながら音読して覚える方法があります。
学習計画を見やすい場所に貼っておくと、宿題や課題を忘れずこなせるようになり、一つずつクリアすることで達成感も味わえるでしょう。
ASD(自閉スペクトラム症)|曖昧な表現が苦手で得意・不得意の差が大きい
ASD(自閉スペクトラム症)は「相手の立場になって考えるのが苦手」「予定・環境の変化に弱い」など、社会性における困難を抱えやすい発達障害です。
ASDの子どもは、学習面で以下のような困りごとを抱えやすいでしょう。
- 曖昧な言葉のニュアンスを汲み取れず、教師の説明や指示内容を理解できない
- 同時に複数のことに集中するのが苦手で、話を聞きながらノートを取れない
- 自分の学習方法にこだわりがあり、教科書どおりに勉強できない
また、「興味があるもの」と「まったく興味がないもの」の差が激しく、苦手科目の成績が極端に低くなる傾向があります。
ASD(自閉スペクトラム症)の子どもの学習をサポートするコツ
ASDの子どもを学習面でサポートするコツは、安心して勉強に取り組める環境を整えることです。具体的には、以下の方法を取り入れましょう。
- 具体的な言葉や数字、図やイラストを使って説明・指示する
- 「話を聞く」「ノートに書く」「問題を解く」時間をそれぞれ区切る
- 本人の学習方法を無理に変えずこだわりを尊重する
- 毎日同じルーティンで勉強に取り組む
「教科書を机の窓側に、ノートを机の廊下側に置こう」「あと5分間やろう」のように、具体的な言葉や数字を使って伝えると、やるべきことが見え安心して勉強できます。
一つひとつの作業を区切ったり、本人のこだわりを尊重したりするのも効果的です。
「毎日◯時から◯分間勉強する」というルーティンがあると机に向かう習慣がつき、学習量が増えることで少しずつ勉強の遅れを取り戻せます。
SLD/LD(限局性学習症/学習障害)|学習に必要な基本スキルの習得が難しい
SLD/LD(限局性学習症/学習障害)は、知的な発達に遅れはないものの、読み・書き・計算など、特定のスキル習得に困難を抱える発達障害です。
SLD/LDは「識字障害」「書字障害」「算数障害」の3種類に分けられ、特性ごとに学習面で以下の困りごとを抱える傾向にあります。
- 【識字障害】教科書や黒板の文字を正しく読めず、文字の理解や読み取りが難しい。
- 【書字障害】問題を読んで理解し頭の中で答えがわかっていても、それを紙に正確に書き出すことが難しい。
- 【算数障害】九九や簡単な計算問題を解くのが難しく、算数・数学の成績が極端に低い。
「読み・書き・計算」は、幅広い教科で共通して求められる力です。
特に文章の読み書きで大きな遅れが生じると、全教科において学習内容が定着しづらくなり、勉強についていけなくなってしまいます。
SLD/LD(限局性学習症/学習障害)の子どもの学習をサポートするコツ
SLD/LDの子どもには、それぞれの特性に合わせた学習サポートが必要です。具体的には、以下の方法を実践すると良いでしょう。
- 【識字障害】教科書や問題集を拡大コピーし文字を認識しやすくする
- 【書字障害】大きいマスになぞり書きをして文字の形やバランスを身につける
- 【算数障害】日常生活の中で数字を数えたり図形を操作したりする活動を取り入れる
- 【共通】特性に合わせた勉強ができるゲーム・アプリを活用する
習得が難しいスキルについては、子どもが取り組みやすい方法での反復練習がおすすめです。
ただし、反復練習だけでは子どものストレスが大きくなるため、文章の読み書きが不要なアプリや楽しく学べるゲームも活用しましょう。
ハードルの低い課題からクリアすることで、成功体験が増えて自信を取り戻し、学習内容も少しずつ定着していきます。
家庭教師のトライでは発達障害の特性に合わせたサポートでお子さまの困りごとを解消

参照:家庭教師を選ぶなら顧客満足度全国No.1のトライ!丨家庭教師のトライ
家庭教師のトライでは、発達障害の特性に合わせたサポートを徹底しているため、子どもが学習面で抱えがちな困りごとを解消できます。
完全マンツーマン授業を実施しているため、子どもの特性や目標に合わせたオーダーメイドカリキュラムの作成が可能です。子どもの様子を丁寧に見ながら、最適な学習プランをご提案します。
また、定期的な面談を通して、学習の進捗や子どもの悩み・不安を聞き取り、必要に応じて学習プランの見直しにも柔軟に対応します。
子どもの学習進捗だけでなく、子どもをサポートする保護者様のお悩みにも寄り添います。
勉強についていけない発達障害の子どもをサポートするために保護者ができる4つのこと

勉強についていくのが難しい発達障害の子どもをサポートするために、保護者の方は以下4つの方法も実践してみましょう。
- 宿題や勉強に集中して取り組める環境を整える
- 子どもの得意・特性を活かした勉強法を見つける
- できたことに注目して前向きな言葉をかける
- 発達障害に詳しい塾・家庭教師を利用する
学習環境の整備やメンタルケアなどは、子どもに安心感を与えてモチベーションを伸ばすために必要なサポートです。
勉強の土台となる学習意欲を高め、そのうえで発達障害の特性に合わせた適切なサポートを行いましょう。
1.宿題や勉強に集中して取り組める環境を整える
子どもの学習をサポートするときは、まず勉強に集中して取り組める環境を整えましょう。
机の上は勉強道具だけを置くようにし、スマートフォンやゲームを手の届かない場所に隠すと、余計な視覚情報が遮断されて勉強に集中できます。
特に、ADHDの子どもは整理整頓が苦手な傾向にあるため、慣れるまでは片付けを手伝ってあげましょう。
テレビの音や、家族の話し声を小さくする方法も効果的です。学習環境を整えて集中力を高めると、効率的に勉強できるようになり、少しずつ遅れを取り戻せます。
2.子どもの得意・特性を活かした勉強法を見つける
子どもの得意・特性を活かした勉強法を見つけるのもおすすめです。子どもの得意・特性を活かした勉強法には、以下があります。
- ADHDの子ども:好奇心の強さを活かして難易度が高い問題にも挑戦する
- ASDの子ども:興味が強い得意教科の勉強から始める
- SLD/LD(識字障害)の子ども:書いて覚える勉強法を優先する
- SLD/LD(書字障害)の子ども:教科書や単語帳を見て音読しながら覚える
- SLD/LD(算数障害)の子ども:式の横に説明文を書いて計算の流れを習得する
自分の好きなことや得意を活かすことで成功体験が増えるため、徐々に自信もつき、前向きに勉強に取り組めるでしょう。
3.できたことに注目して前向きな言葉をかける
発達障害の子どもは、その特性によって「できない」と感じる瞬間が多く、自信を失いがちです。
そのため、保護者の方は子どもの「できたこと」に注目し、積極的に前向きな言葉をかけましょう。具体例は以下のとおりです。
- 「毎日コツコツ勉強してえらいね。続けるって簡単なことじゃないよ。」
- 「前よりも問題を解くのが早くなったね。」
- 「勉強だけじゃなくて、自分で時間を決めて取り組む姿勢も立派だよ。」
テストの点数や成績などの結果だけでなく、日々の頑張りに焦点を当てることで子どもは安心し「もっと頑張ろう」と学習意欲を高められます。
4.発達障害に詳しい塾・家庭教師を利用する
発達障害に詳しい塾・家庭教師を利用するのも有効な方法です。
発達障害がある子どもへの指導経験が豊富な塾・家庭教師を利用すると、特性に合った適切な勉強法がわかります。
専門性の高いアプローチで効率的な学習内容の定着が図れるため、勉強の遅れも取り戻せるでしょう。
特性にもよりますが、環境の変化に弱い発達障害の子どもには、自宅で学習できる家庭教師がおすすめです。
発達障害の子どもに家庭教師をおすすめする理由や、選び方のポイントは以下の記事で詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。
家庭教師のトライでは発達障害のお子さまの指導経験を持つ教師が徹底サポート

参照:家庭教師を選ぶなら顧客満足度全国No.1のトライ!丨家庭教師のトライ
家庭教師のトライには、発達障害のお子さまの指導経験を持つ教師が多数在籍しています。そのため、専門的な視点から勉強法のアドバイスを受けることで、無理なく学力の定着を目指せます。
また、教師は無料で何度でも交代可能です。お子さまにぴったりの教師を見つけることでモチベーションの向上・維持ができ、効率的に勉強を進められます。
経験豊富な教師が、完全マンツーマン授業による徹底的なサポートを行い、楽しく学びながら成績アップや志望校合格を実現します。
子どもの発達障害に悩む保護者の方が利用できる相談機関

発達障害に関して、学習面以外にもさまざまな悩みを抱えている保護者の方は多いでしょう。
そこで、保護者の方が利用できる相談機関を4つ紹介します。
- 学校の教師やスクールカウンセラー
- 発達障害のサポートを行っている塾・家庭教師
- 児童精神科や発達外来などの医療機関
- 地域の発達障害者支援センター
上記を参考に利用しやすい機関を見つけておくと、不安や悩みが生じても気軽に相談できるため、負担が大きくなる前に問題を解決できるはずです。
学校の教師やスクールカウンセラー
学校の教師やスクールカウンセラーに相談すると、授業中に適切なサポートを受けられるようになるため、安心して学校生活を送れるようになります。
授業を受ける子どもの様子や学校の取り組みを家庭に反映させることができれば、学校と家庭の両方で一貫したサポートが行えるでしょう。
子どもの特性を詳しく理解できると、気持ちに余裕を持って支援できるはずです。
学校の教師やスクールカウンセラーに相談するときは、要望を伝えるだけでなく、家庭での様子も説明しておくと、連携を取りやすくなります。
発達障害のサポートを行っている塾・家庭教師
発達障害のサポートを行っている塾・家庭教師でも、保護者の方からの相談を受け付けている場合があります。
発達障害の特性に合わせた授業を受けることで、学習面の困りごとをスムーズに解消できる点もメリットです。
進学も見据えた授業を受けることができれば、親子ともに大きな不安を抱えず、希望の進路を実現できるでしょう。
トライのオンライン個別指導塾でも、「LINE窓口」や「定期面談」など、保護者の方を支えるフォロー体制が充実しています。
「特性に合った授業を受けるだけでは不安」「適切なサポートについて相談したい」という方は、お気軽にお問い合わせください。
\トライのオンライン個別指導塾について詳しく見る/
児童精神科や発達外来などの医療機関
「子どもが発達障害かどうかを確かめたい」「より専門的なアドバイスが欲しい」という方には、児童精神科や発達外来などの医療機関がおすすめです。
医療機関では発達検査を受けられるため、勉強についていけない根本的な原因を見つけ、悩みを解消するための具体的なアドバイスをもらえます。
発達検査を受けるときのポイントは、結果だけにとらわれず、子どもの「できること」を増やすために何を工夫すべきなのかを考えることです。
ただ、検査結果によっては不安が大きくなる保護者の方もいるかもしれません。その場合は、率直な気持ちや疑問を医師に伝え、結果に納得したうえで必要なサポートを行いましょう。
地域の発達障害者支援センター
地域の発達障害者支援センターでも、発達障害の悩みを持つ保護者の方の相談を受け付けています。
幅広い相談内容に対応し、必要に応じて関係機関も紹介しているため「どこに相談すべきかわからない」「総合的な支援を受けたい」方におすすめです。
発達障害者支援センターでは、子どもの特性に合わせた支援計画の作成や、継続的な助言を行ってくれる場合があります。
現状の悩みを解消するだけでなく、将来も見据えて長期的なサポートを行いたい方は、以下のサイトも参考に相談先を探してみてください。
参考:発達障害者支援センター・一覧 | 国立障害者リハビリテーションセンター
まとめ
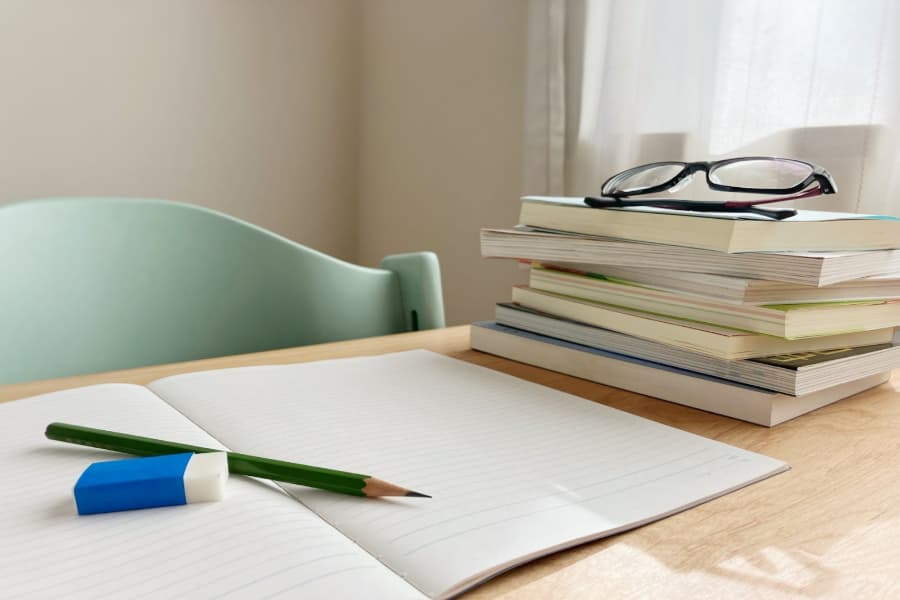
本記事では、発達障害の子どもが学習面で抱えがちな悩みやサポートのコツ、保護者の方ができる対処法とおすすめの相談機関を紹介しました。
本記事のポイントは以下のとおりです。
- 子どもが勉強についていけないときは、発達障害の特性や学習面の困りごとを把握し、それに合ったサポートを行うことが大切
- 子どもの学習意欲を高めるには、環境整備やメンタルケアなどのサポートも必要
- 学習面以外にも悩みがある場合は、相談機関を利用すると良い
家庭だけで学習をサポートするのが難しい場合は、発達障害に詳しい塾・家庭教師の利用も検討しましょう。
子どもが少しでも勉強についていけるよう、本記事で紹介したサポート方法を実践してみてください。