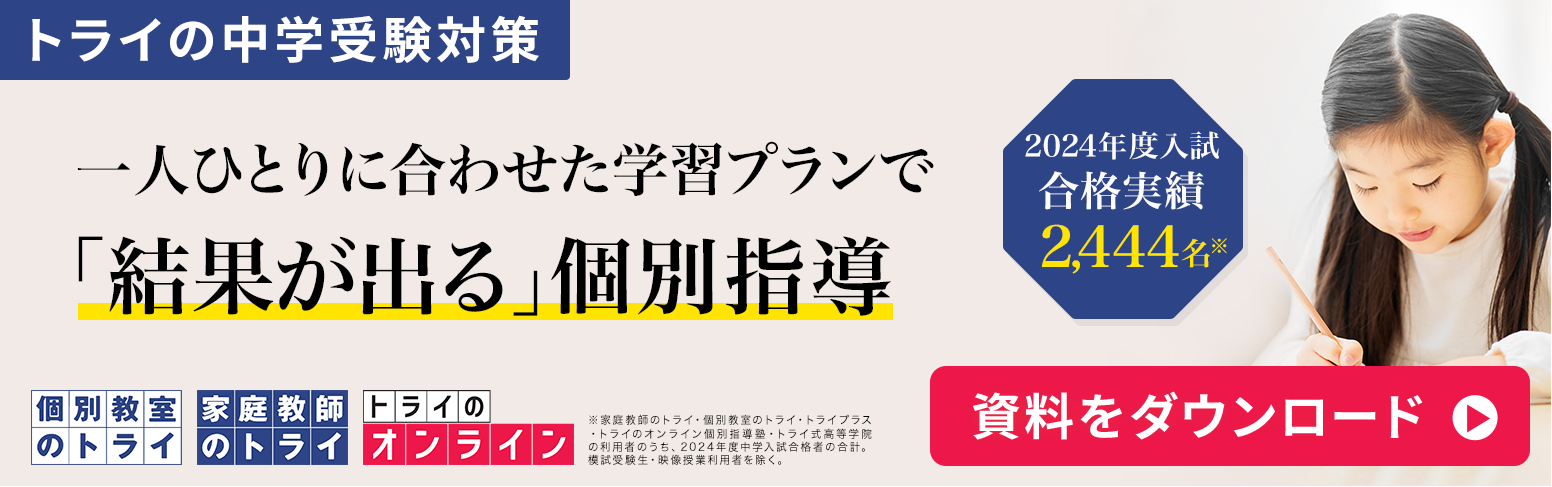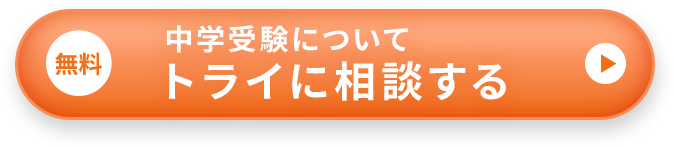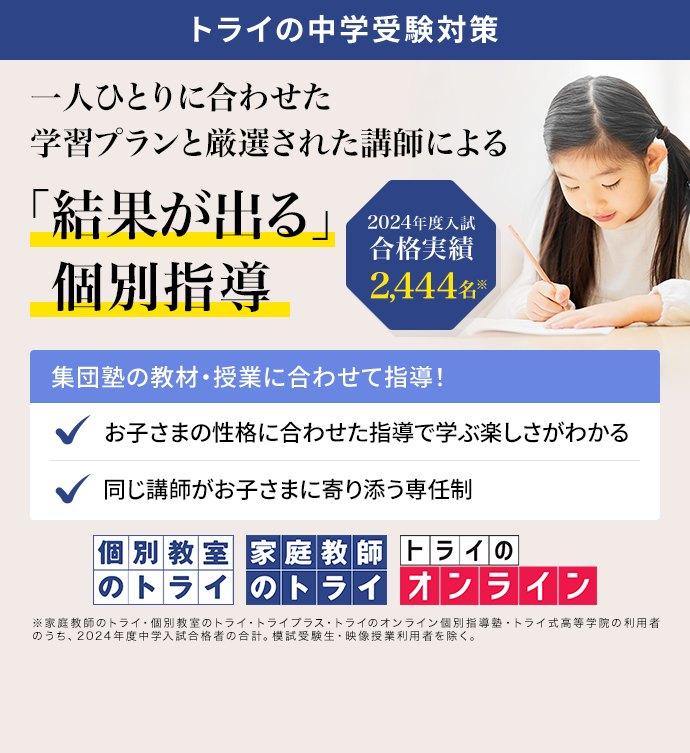学習の進捗や実力を把握するための重要な指標である偏差値。しかし、偏差値は模試を受ける生徒層によって変動するため、塾ごとに差や特性があり、それを理解することが求められます。本記事では、栄光ゼミナールを例にとり、偏差値の役割や正しい活用法、成績向上のためのポイントについて詳しく解説します。適切な塾を選び、偏差値を着実に上げるための一助として、ぜひ参考にしてみてください。
栄光ゼミナールにおける偏差値の役割とは
そもそも偏差値とは
偏差値とは、お子さまが模試を受けた集団の中で、いま現在どれくらいの位置にいるかを把握するための数値です。問題の難易度によって平均点が変わるため、平均点=偏差値50と換算し、そこからどれくらい点数が高いか、または低いかを表しています。偏差値を見ることで相対的に、お子さまの実力を把握することができます。
中学受験における偏差値のからくり
お子さまが外部模試を受けた時、模試ごとに偏差値結果に大きな差があって驚いたことはないでしょうか。実はそれぞれの塾が実施している公開模試の場合、母集団が異なるため、模試ごとに偏差値の基準は大きく変わります。
首都圏の中学受験においてはS偏差値、N偏差値、Y偏差値などがあり、Sはサピックス、Nは日能研、Yは四谷大塚を基準とする偏差値を意味します。サピックスそのものが最難関校を狙う子どもが多く通う塾のため、S偏差値はかなり低く出るのが特徴です。
S偏差値40台のお子さまでも上位校や難関校に合格する子はおり、ここで高い偏差値を取るのは相当難しいです。一方、日能研が出すN偏差値と四谷大塚が出すY偏差値は学力が拮抗しているため、偏差値にあまり差が出ません。サピックスと比べると偏差値がおおむね5~10近く上がります。
難関校を目指す場合を除いては、N偏差値とY偏差値を参考にするのが良いでしょう。
栄光ゼミナールではどのように偏差値を確認するか
栄光ゼミナールでは、外部模試とアタックテストで自分の偏差値を確認することができます。栄光ゼミナールでは外部模試を受けることが推奨されており、中でも合不合判定テストと首都圏模試に関しては、栄光ゼミナールで手続きをして申し込めるため、ほぼ必須の模試となります。外部模試は受験の雰囲気を体感する練習にもなりますし、受験者の母数が多いため正確な偏差値を把握しやすくなります。
もうひとつ偏差値を把握するものとして、栄光ゼミナールにはアタックテストというものがあります。これは栄光ゼミナール受験コースの総合回カリキュラムと連動したもので、4~5週に1回実施されるものです。外部模試とは違い、ある程度範囲の決まったテストとなり、クラス分けの基準にもなっています。
栄光ゼミナールでは偏差値をどう捉えているか
栄光ゼミナールにおいて、偏差値は「前回より上がった、下がった」と直近のものと比較して一喜一憂するものではないとしています。過去にさかのぼって偏差値の推移を正しく把握するため、できるだけ同じ種類の模試を継続して受けることを大切にしています。
また、栄光ゼミナールでは、小学6年生の夏休み以降の偏差値を最重要視しています。それまでの小学4年生・5年生の場合、模試を受ける母集団にはばらつきがあり、偏差値にも波があるため、志望校を検討する際の参考にはしていません。お子さまの苦手を探すための模試として認識しておきましょう。一方、小学6年生の夏休み明けは、周りの気持ちも一斉に受験本番に向き始めます。栄光ゼミナールでも受験校を絞り込んでいくために、偏差値を重要とします。
栄光ゼミナールで偏差値が上がらない要因
宿題が多くて手が回らない
栄光ゼミナールでは、新演習という3段階のレベルで構成されるテキストを使います。基本問題は基本レベル、練習問題は標準レベル、チャレンジ問題は応用レベルという構成となっており、クラスによって扱う問題や宿題に出される問題が異なります。栄光ゼミナールでは、予習、確認、復習、確認の繰り返しを特徴としているため、課題の量が必然的に多くなります。そのため、勉強がやみくもに量をこなす作業になってしまう事態に陥りがちです。
解くべき問題の取捨選択ができない
栄光ゼミナールでは上記に挙げたように、課題がたくさん出されます。そのため非効率的な勉強をしてしまう人が多く見受けられます。例えば、自分が確実に解ける簡単な問題まですべて解こうとすると、応用問題を解く時間が足りなくなってしまい、非効率な勉強になる可能性があります。限られた時間の中で取り組むべき問題なのか、そうではない問題なのか、取捨選択ができない状態です。
アタックテスト対策で丸暗記してしまう
先ほど述べた通り、栄光ゼミナールには4~5週に1回、塾内模試のアタックテストが実施されます。これは外部模試とは異なりある程度の範囲が決まっているため、日頃の授業をしっかり理解できていれば点数を取ることが可能です。しかし、記憶力の良いお子さまや要領の良いお子さまの中には、出題範囲となる新演習の解答や問題の解き方を丸暗記してしまう方もいらっしゃいます。その場合、アタックテストでは良い点数が出せますが、考え方や理屈が理解できていないため、応用問題が解けず、それ以上の成績アップを望めない状況に陥ります。また、丸暗記をしてアタックテストで良い点数が得られたことに満足して、勉強がおろそかになってしまうケースも見られます。
競争心を育めていない
栄光ゼミナールは、数ある塾の中でもアットホームな雰囲気が特徴です。1クラスが多くて12名程度の少人数制となっており、比較的和やかな雰囲気で授業が受けられ、お子さまが伸び伸びと通えることもメリットです。そうした中で偏差値が上がらない場合、競争心が欠けてしまっているのかもしれません。過度なプレッシャーは精神的な負担となってしまいますが、時には刺激を与えることで本人のやる気を高めることもあるでしょう。
栄光ゼミナールで偏差値を上げる対策
予習→確認→復習→確認のサイクルを守る
栄光ゼミナールではAimという、次回の学習内容を予告するプリントがあり、これを使って予習をすると効率よく授業が受けられます。次に、授業ごとに単元確認プリントという確認テストも行われます。また、Practiceという類題演習プリントもあり、これで復習したあとに再度演習するという流れがあります。栄光ゼミナールではこのように、予習、確認、復習、確認を繰り返すことを大切にしているため、このサイクルをきちんと守ることで理解と定着が図れるでしょう。栄光ゼミナールには自習室もあるので、自宅だと集中できないというお子さまにお勧めです。
毎月のアタックテストを大切にする
5年生から始まる塾内模試のアタックテストには、やや応用的な問題も含まれるため、満点を取りにくい出題内容になっています。しかし、問題文をしっかりと読み解くことができれば解答できる基本的な内容が大半を占めているので、こうした基本問題を確実に得点することが大切になります。授業テキストの問題や、授業・宿題で使うマイノートの内容をしっかり復習して、一回ごとのアタックテストを大切にしましょう。
難関校受験生は、合不合判定テストも活用する
栄光ゼミナールは他の塾に比べ、基礎を固めることに重点を置いている塾です。そのため、合不合模試に出題されるような難問を解く機会はさほど多くありません。アタックテストよりも難度の高い問題を解けるようにするには、公式や解き方をしっかり使いこなし、「なぜそのように解くのか」という理屈を説明できるようになるまで理解する必要があります。また、合不合判定テストは時間との勝負でもあるため、本番を想定し、解ける問題から解いていく工夫も必要です。特に難関校への受験を考えているお子さまは、自宅で応用問題が解けるように対策しましょう。
家庭学習のスケジュールを立てるサポートをする
栄光ゼミナールでは課題プリントやテキストの課題に加え、計算や漢字などの副教材も多く使用されています。それらをすべて終えようとするとお子さまがパンクしてしまい、ただの作業に陥ってしまうので注意が必要です。そのため、家庭学習のスケジュールは優先順位をつけるサポートをしてあげることが効果的です。ただし、やみくもに計画を立てるのではいけません。お子さまの苦手な項目や効率よく成績を上げるために本当に重要な項目を、塾の先生に相談しながら組み立てることが大切です。
個別指導という選択
栄光ゼミナールでは、こうした悩みの解決のために個別指導を受けることができます。集団授業と連動した教材で学ぶことができます。その一方で、苦手分野や過去問対策をより異なる視点から対策するため、他塾の個別指導を活用するご家庭もいらっしゃいます。中学入試当日は子ども一人の戦いなので、異なる観点からアドバイスを受けることも重要です。
まとめ
栄光ゼミナールに通っていても偏差値が上がらないとお悩みの方に向けて、偏差値アップのポイントをご紹介しました。偏差値は現状の学習力を把握するだけでなく、志望校を絞り込んでいく上でも非常に大切なものです。一喜一憂するのではなく、長い目で推移を見て合格をつかみ取るために活用してはいかがでしょうか。