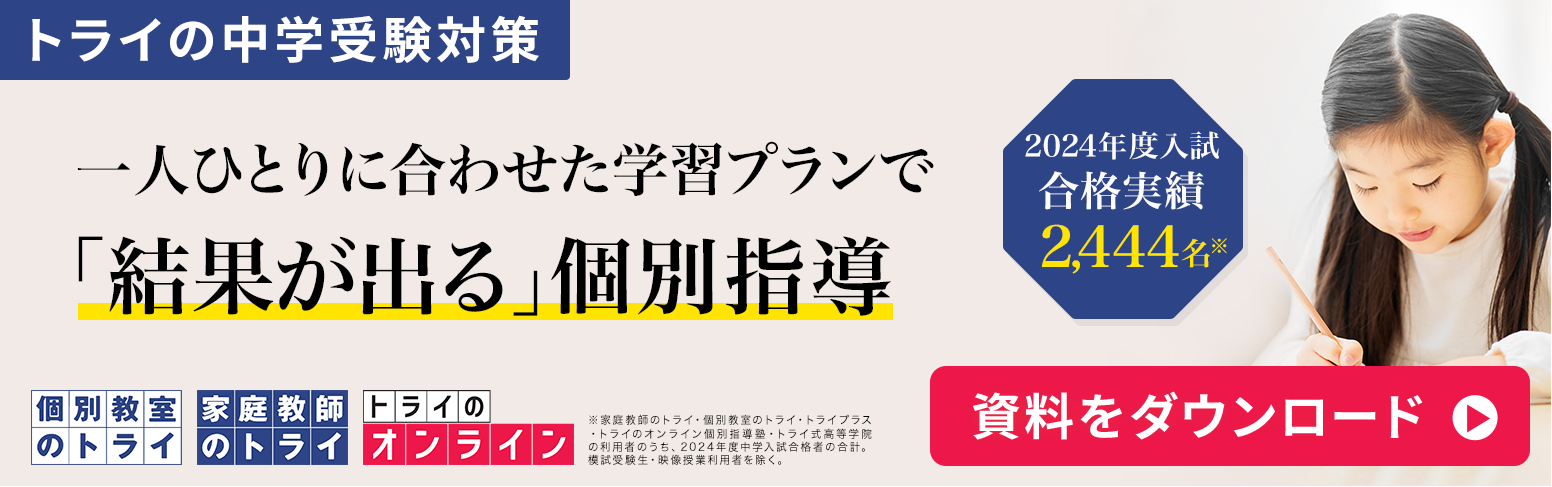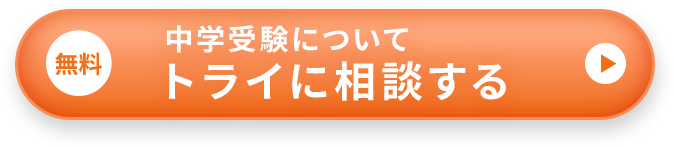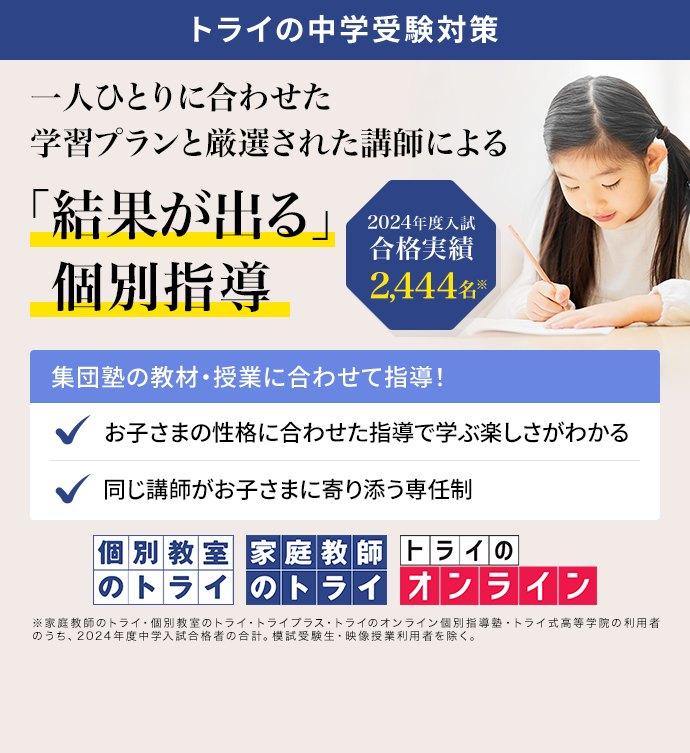中学受験算数は得意なお子さまと苦手なお子さまで差がつきやすい科目です。
「算数に力を入れているにもかかわらず、成績が伸びない」「算数は受験で一番大事と言われているのに、勉強したがらない」とお悩みの保護者様はいらっしゃいませんか。
この記事では成績不振の原因や具体的な解決策、さらにNGサポート例を紹介しています。志望校受験を諦める前に、ぜひ本記事を参考にしてみてください。
解けるはずの問題が解けない。算数が絶望的な状況とは
算数の成績が危機的状況にあるとは、同級生の多くが正答できる基本的な問題、いわば「解けるはずの問題」が解けていないことを意味します。つまり、お子さまは何らかの理由で、本来習得すべき学習内容を十分に理解できていない状態にあるのです。
「文系だから算数の才能がない」「問題を見ても何も思い浮かばない」といった言葉をよく耳にしますが、偏差値60程度まで成績を向上させるのに、特別な才能やひらめきは必要ありません。逆に言うと、算数の学力は正しい方法でコツコツ努力さえすれば、必ず伸ばすことができるのです。
ただし、成績を上げるまでには時間がかかるため、受験が近づくにつれて対策は難しくなります。お子さまの状況が以下に当てはまる場合は、算数の学習に深刻な問題が生じている可能性が高いため、今すぐ対策を始めましょう。
【算数の危機的状況】
- 塾に通って、家でも勉強しているのに、一向に成績が上がらない。
- 受験勉強を始めた当初から算数が苦手。
- 同級生がスラスラ問題を解いている時に、何もできないでいる。
なぜ成績が伸びないのか。算数が絶望的になる原因とは
繰り返しになりますが、算数の成績が低迷しているお子さまは、本来習得すべき学習内容を十分に理解できていない可能性が高いです。
しかし、これは「勉強をサボっている」という意味では全くありません。むしろ、一生懸命に勉強をしているにもかかわらず、思うように成績が伸びないというケースは多く存在します。
ここでは「やっているのになぜか伸びない」と絶望的な気持ちになっている方に向けて、算数でつまずく原因を、具体例を挙げながら3つご紹介します。
計算が苦手
入試では限られた時間内に大量の計算をすることが求められるため、速さと正確さの両方が必要です。しかし、算数が苦手なお子さまの多くは、計算が遅く、ケアレスミスも多い傾向にあります。
算数の土台である計算力が低いと、ミスのせいで本来取れたはずの得点を失う、計算に手間取って制限時間内に解ききれない、計算ばかりに意識が向いて解法や公式を理解できないなど様々な悪影響が生じ、結果として成績が著しく伸び悩んでしまいます。
また「家だと問題なく計算できるのに、模試など緊張する場面だとミスを繰り返してしまう」という場合も、お子さまの計算力が十分に定着していない可能性があるため、注意が必要です。
【計算が苦手なお子さまの事例】
- 模試や過去問の大問1(基本の計算問題)で失点している。
- 間違えた問題の解き直しをすると、計算ミスをしていることが多い。
- テストや演習でいつも時間が足りない。
基礎的な内容や単元の理解に抜け漏れがある
算数は積み上げ型の科目であるため、前の単元の基礎が定着していないと、次の単元を理解することが極めて困難になります。例えば、掛け算を理解していなければ割り算を習得することは難しいですし、割り算を理解していなければ、分数そして小数も習得できません。
このように、算数は一度つまずくと、わからないことがどんどん積み重なり、最終的には授業に全くついていけないという事態に陥ってしまうのです。この点が、理科や社会といった単元ごとに内容が独立している科目とは違う、算数特有の難しさであると言えるでしょう。
お子さまの算数の成績が伸び悩んでいる場合、今まで習った基礎的な内容のどこかに穴があり、それが原因で正しく学力が積み上がっていない可能性が高いです。重要な解法や公式といった基礎知識が一つでも欠けていたり、曖昧な理解のまま放置されていたりしていないか、今すぐ確認をしてください。
【基礎が定着していないお子さまの事例】
- 模試の基本問題であっても、どの公式や解法を使えばよいかわからず、手が止まってしまう。
- 文章題を読んでも、式や図を書くことができない。
- 演習問題を解く時、誰かが隣で一から説明しないと、解くことができない。
つまずきの原因が特定できていない
算数が苦手なお子さまは、問題が解けない時、何が原因で解けないのか自分自身でもわからず、混乱していることが多くあります。計算でつまずいた、問題文の意味が正確に読み取れなかった、公式や解法を覚えていなかったなど、具体的な原因が特定できず「何がわからないのかもわからない」という状況に陥っているのです。
このような状況下では、どうすれば算数を克服できるのか、具体的な方向性を正しく決めることは難しいと言わざるを得ません。そのため、公式や解法を覚えていないのに応用問題に挑戦したり、計算ミスをしただけなのに教科書を最初から復習したりするなど、効率の悪い勉強をしてしまいます。
すると、お子さまにとって算数とは「勉強してもできるようにならない科目」という認識になり、強い苦手意識を持つようになります。苦手意識が強くなればなるほど、学習意欲は低下するため、算数の勉強は後回しになり、結果的にどんどん学習が遅れていってしまうため、注意が必要です。
【悪循環に陥っているお子さまの事例】
- どこがわからないのか尋ねると、「全部」と答える。
- 算数の授業の日は塾に行きたがらない。
- 保護者様が声掛けをしても、算数の勉強をなかなか始めない。
絶望的な状況を打開する。算数の成績を上げる方法とは
ここでは算数の成績が絶望的だと感じた時に実践すべき対策を、3つ解説しています。保護者様ができる具体的なサポート例も紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
毎日計算トレーニングをする
算数の土台である計算力のトレーニングは、スポーツをする上での体力づくりと同様に、決して手を抜くことはできません。算数の成績が極端に落ち込んでいる場合、計算力を上げるだけで偏差値が10以上向上することもあるため、今すぐ対策を始めましょう。
計算力を効果的に高めるには、一度に大量の問題を解くのではなく、毎日コツコツと継続して演習をする必要があります。具体的には、最初のうちは10分程度の短い時間でも構わないので「朝ごはんの前」「学校帰り」など時間を決めて、計算練習を習慣化してください。
なお、計算ミスが多いお子さまの中には、字が雑だったり途中式や筆算を書かなかったりする傾向が見られるため、計算練習をする際には丁寧に取り組むように声掛けをしてください。
【保護者様ができること】
- 毎日決まった時間に計算練習をするよう、声掛けや時間管理をする。
- 計算練習が終わったら褒めるなど、モチベーションを維持してあげる。
- 計算ミスが多い場合は、どのようなミスが多いのか分析し、対策を考える。
- 字が読みづらかったり、途中式を飛ばしていたり、急いで解こうとしていたりする場合は、丁寧に解くように注意する。
基礎固めを徹底し、同じ問題を繰り返し解き直す
基礎を固めるには、これまでに学習した内容の復習が不可欠です。
まず、覚えていない解法や公式がある場合は、習得することから始めましょう。この際、単に知識を丸暗記するのではなく、なぜその式で解けるのかを理解し、解法や公式を使いこなせるようになることが重要です。そこで、ある程度知識を覚えたら、基礎的な問題を演習して、覚えた公式や解法を実際に使う経験を積み重ねてください。
ただし、たくさん演習しようとするあまり、色々な問題に手を広げたり、少しわかるようになったからといって応用問題に挑戦したりすると、学力は正しく身につきません。基礎固めの段階では、同じ問題をじっくりと繰り返し解くように意識しましょう。焦らずに学習を進めれば、一度目の演習では全く解けなかった問題も、二度三度と繰り返すうちに、誰の助けも借りずに自力で解けるようになりますよ。
「できない基本問題はない」と言えるくらいまで基礎を徹底的に固めれば自信もつくため、希望をもって根気強く努力を続けてください。
【保護者ができること】
- 一週間の学習スケジュールを見直し、算数の復習時間を設ける。
- 過去の模試の結果を振り返り、お子さまが習得できていない苦手単元を特定する。
- お子さまが間違えた時は、何が原因でつまずいたのか一緒に確認する。
- シールやチェック表を使って、学習の進捗を可視化する。
成功体験を積み重ねる
算数の学力を定着させるには、基礎的な問題を解くことが最も効果的だとお伝えしましたが、これは学習効果を高めるだけでなく、お子さまのやる気にもつながります。「わかった」という成功体験を積み重ねることで、算数の勉強は楽しくなり、もっと知りたいという意欲が湧いてきます。
ただし、簡単すぎて何も考えなくても答えられる問題を解いても、当然ながら学力は伸びません。お子さまにとって適切な問題のレベルは「少し頑張れば理解できる程度の問題」や「間違えても、どこでつまずいたのかを自分で把握できる程度の問題」です。
このように、達成感をうながすためには、保護者様がお子さまの学力を丁寧に把握し、適切なレベルの課題を与え導くことが求められます。
また、成功体験を得るには、小さな成長でも褒めることも重要です。
算数の成績が危機的な状況だと不安で焦ってしまうのは当然のことですが、無理に勉強をさせるのではなく、お子さまが自分から勉強しようと思える雰囲気を作るようにぜひ意識してみてください。
【保護者様ができること】
- お子さまが算数の勉強を終えたら、ノートを確認して理解度を把握する。/li>
- お子さまに合ったレベルの問題を与える。
- その日できるようになったことを見つけて褒める。
実は逆効果の可能性も。保護者様が陥りがちなNGサポート例
算数は他の科目に比べて、保護者様のサポートが難しい側面があります。良かれと思って行ったサポートが、実は逆効果になるケースは少なくありません。
ここでは保護者様が陥りがちなNGサポート例を紹介します。
手をかけすぎる
お子さまが算数の演習をしている間も、ずっとつきっきりで解き方を教えているという方はいらっしゃいませんか。このようなサポート方法は、新しく学ぶ単元を一から全て説明しないと理解できないという場合には有効ですが、状況によっては逆効果になる可能性もあります。
例えば、解けるはずの内容まで教えてしまったり、考えている途中でヒントを出したりすると、お子さまが自分で試行錯誤する経験を積めなくなってしまいます。
自分で考える習慣がないと、その場では「わかった」と思っても、自力で問題を解く力がつかず、模試や入試本番で得点に繋がりにくいため、注意が必要です。
子どもに任せすぎる
一方で、お子さまの自主性を尊重し、算数の勉強を任せきってしまうのも、時には逆効果になることがあります。
小学生の子どもは、嫌いな算数を後回しにしたり、得意な単元やわかる問題ばかり解いたり、できない問題は答えを写したりと、間違った取り組みをしてしまいがちです。
中学受験の算数は範囲が膨大であるため、正しく計画的に学習をする必要があります。算数の勉強スケジュールを立てる、時間になったら声掛けをする、苦手単元を洗い出す、どの問題を演習すればよいか指示するなど、お子さまの学習を間接的にサポートしてあげましょう。
目標設定が高すぎる
成績が思うように伸びないと、焦りから高い目標を設定してしまいがちです。しかし「偏差値を30から60にしよう」や「志望校の合格者平均点を取ろう」といった高すぎる目標は、お子さまにとって過度なプレッシャーとなり、かえって学習意欲を低下させる可能性があります。
「次回の模試までに偏差値5を伸ばそう」「今週は毎日1時間、算数の勉強をしよう」というように、近い将来に少し努力すれば到達できるレベルの具体的な目標を設定して、お子さまの着実なステップアップをサポートしてあげましょう。
困った時には、個別指導という選択肢も
算数は積み上げ型の教科であるため、成績向上には時間と根気が必要です。
そのため、お子さまの成績が伸び悩んでいる場合、保護者様が算数をサポートするのは、大きな負担となり得ます。時間を割いて何度も説明しているのに、お子さまがサボったり繰り返し間違えたりすると、ストレスを感じてしまうこともありますよね。
そこでおすすめの方法が個別指導の利用です。
個別指導塾や家庭教師の指導では、中学受験のプロ講師がお子さまのつまずきを特定しながら、マンツーマンで理解できるまで丁寧に指導をします。受験まで時間がないという場合でも、お子さまに合わせたカリキュラムで指導するため、無駄なく効率的に志望校対策ができます。
【個別指導のメリット】
- 講師がつきっきりで指導するため、集中して取り組める。
- わかるまで質問できる。
- お子さまのつまずきの原因を特定し、効率的に学習できる。
- お子さまの学習状況や理解度に応じて、オリジナルのカリキュラムで勉強できる。
- 勉強の悩みや入試の不安など、精神的な悩みを共有できる。
- 志望校の出題傾向を踏まえた課題に取り組める。
- 過去問の対策ができる。
正しい努力で必ず伸びる。算数が壊滅的と感じたら今すぐ対処
いかがでしたでしょうか。
算数はどんなに成績が伸び悩んでいても、正しい方法で一歩ずつ努力を重ねれば、必ず成績を伸ばすことができます。
大切なことは諦めないことです。計算トレーニングや基本問題の演習などを徹底的に行い、基礎力を着実に伸ばしていきましょう。
ただし、算数の成績向上には根気が必要なため、保護者様が継続的にサポートするのは大きな負担となる場合があります。
困った時は、個別指導を利用するのも選択肢の一つです。プロのマンツーマン指導で効果的に成績を伸ばし、自信をもって第一志望を受験してくださいね。