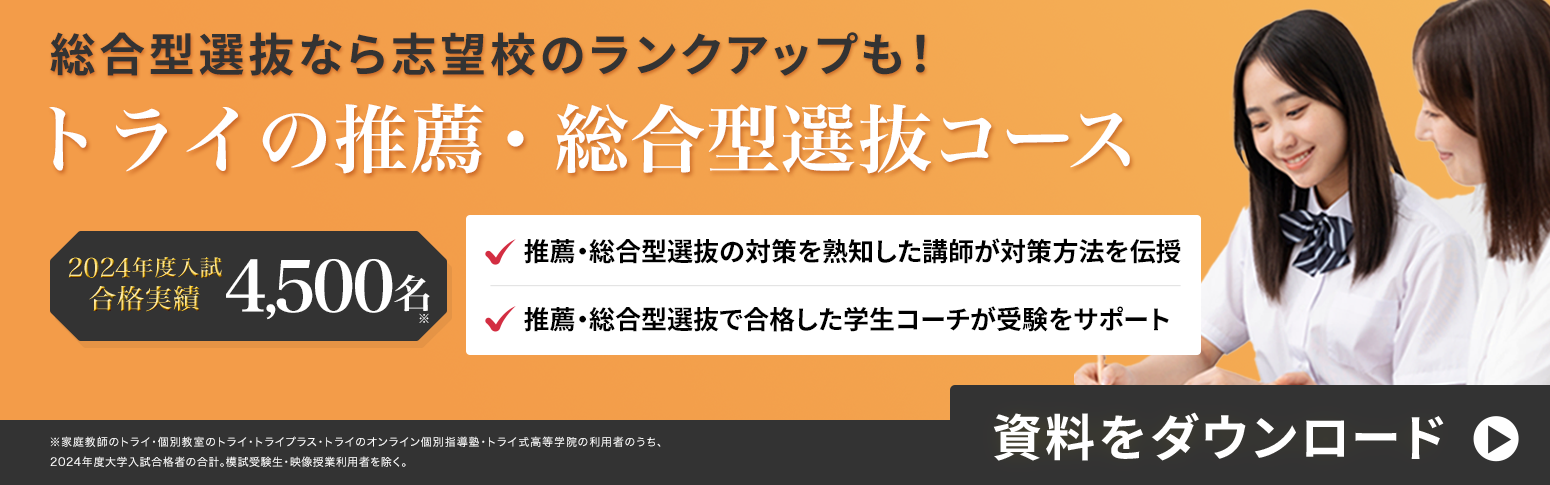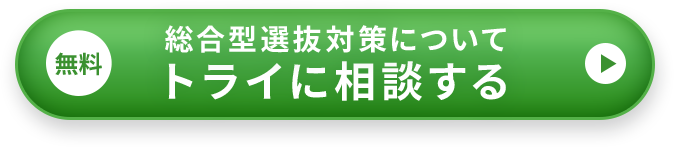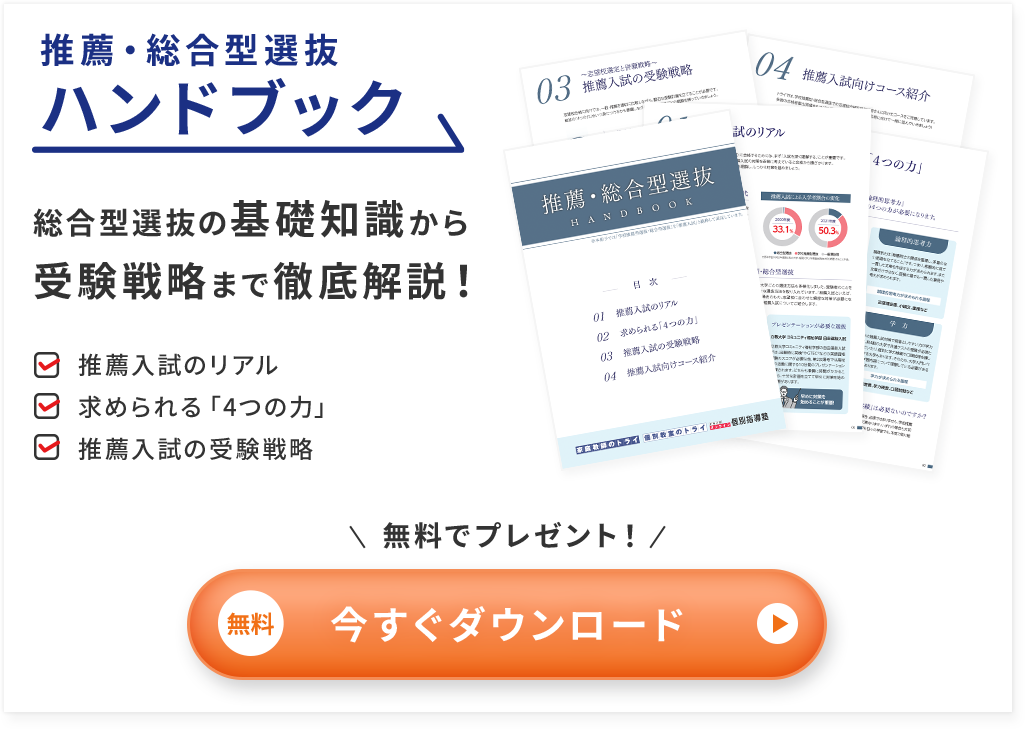総合型選抜において、「講義型小論文」と呼ばれる試験形式が近年増加しています。この形式では、大学教員による講義を聴講した上で、その内容を要約し、自身の考えを論理的に展開する力が求められます。本記事では、講義型小論文の概要や課題文型との違い、具体的な試験対策、過去の出題事例を詳しく解説します。試験の特徴を正しく理解し、効果的な準備を進めることで、合格に向けた大きな一歩を踏み出しましょう。
総合型選抜の講義型小論文の基礎知識
総合型選抜の講義型小論文とは
講義型小論文とは、大学の模擬講義を受講し、その内容を理解した上で要約や考察を行う形式の試験です。単に知識を問うのではなく、講義内で提示された概念を的確に整理し、自身の考えを論理的に展開する力が求められます。
従来の一般的な小論文試験と比較すると、講義型小論文では「講義内容を正しく理解し、それを基に論じる」という点が大きな特徴です。ただし、従来の課題型小論文でも、文学系・芸術系等のアイディア重視の小論文を除けば、自由に論じることはほぼ不可能で、設問の要求に沿う形で答案をまとめていくことになります。講義型では特に講義内容の理解が前提となる点が異なります。
大学によって実施スタイルは異なりますが、主に講義の聴解力、要点を整理する力、論述力が試されます。講義型の小論文試験の大まかな流れは以下のようになります。
①模擬講義が行われる
- 講義時間は50分程度(大学によって異なる)
- 講義レベルは大学1年生を対象とするものが多い
- メモが取れるよう用紙が配布される
- 講義内容のポイントが整理されたレジュメが用意されている場合もある
②講義に関連した小論文/レポートを記述する
- 回答時間は約60分(大学によって異なる)
- 1,000~2,000文字前後の字数制限がある
講義全体の要約を記述した後に自身の考えを述べるスタイルや、講義の中で触れられたポイントの一つを選択し、それについて概要と意見を記述するスタイルなどがあります。
また、講義と小論文の記述の間に、質疑応答の時間が設けられる場合もあるなど、大学によって実施スタイルが異なります。
講義型小論文は、慶應義塾大学の法学部FIT入試、中央大学の法学部チャレンジ入学試験、立命館大学の政策科学セミナー方式、東京女子大学の知のかけはし入試、九州大学の共創学部総合型選抜など、多くの大学で採用されるようになっています。
総合型選抜の講義型小論文の特徴
大学入試の小論文は、課題文型が最も一般的な出題形式となっています。ここでは、課題文型と講義型について、共通点と相違点をまとめてみました。
【共通点】
| 課題文型&講義型 | |
|---|---|
| 必要なスキル | 論理的思考力と文章構成力が必要 要約力が重視される 自分の意見を論理的に展開する力が求められる |
| 解答形式 | 論述の基本構成は同じ 指定された字数内での論述が必要 客観的な文体(である調)での記述が求められる |
【相違点】
| 課題文型 | 講義型 | |
|---|---|---|
| 情報の形態 | 文字情報として提示される | 音声情報として提示される |
| 情報の確認 | 読み返しが可能 | 通常1回のみの聴講 |
| 必要なスキル | 読解力と論述力 | 聴解力と論述力 |
| 情報処理方法 | 文章に印をつけながら読解できる | メモを取りながら聴講する必要がある |
| ペース配分 | 自分のペースで読解可能ではあるが、試験時間の制約や難解な課題文、多量の資料などにより実質的には相当な速読力・理解力が必要 | 講義のペースに合わせる必要がある |
課題文型と講義型の小論文は、どちらも論理的思考力と文章構成力を基盤とし、与えられた情報を整理・要約し、自分の考えを論じる点で共通しています。
一方で、課題文型は文字情報を読んで理解するのに対し、講義型は音声情報を聞いて理解するという大きな違いがあります。課題文型は何度も読み返すことが可能ですが、実際の入試では課題文のあちこちを何度も読み返していては時間的に課題の最後まで答え切ることは不可能になります。現代の入試で比較すると、課題文型でも講義型でも、スピードと理解力を重視した試験であることは共通しています。特に講義型は一度きりの聴講が一般的であり、リアルタイムでメモを取りながら要点を整理する力が強く求められます。
このように、課題文型と講義型は根本的な部分においては共有しながらも、情報の受け取り方と処理方法に大きな違いがあるため、講義型小論文に適した対策を行うことが重要になります。
総合型選抜の講義型小論文への対策・準備
講義型小論文は、講義内容を正確に理解し、それを基に論理的に考察する力が求められる試験形式です。ここでは、受験生が講義型小論文に向けてどのような準備をすればよいかを解説します。
講義型小論文の対策ポイント
聴解力を鍛える
講義型小論文では、講義内容を一度で正確に理解する聴解力が重要です。この力を鍛えるためには、大学の公開講座やオンライン講義を視聴し、要点をメモする練習を取り入れると効果的です。また、ニュースやドキュメンタリー番組を視聴し、その内容を要約する練習も有効です。さらに、ディクテーション(聞き取った内容を書き出す練習)を行うことで、聴解力を向上させることができます。
もちろん、一度聞いただけで理解できるかどうかは、ベースとなる知識や理解力が備わっているかどうかに繋がります。
メモの取り方を練習する
講義中に効率よくメモを取るスキルも必須です。キーワードや重要なフレーズを中心に記録し、箇条書きなどを活用して情報を整理することを意識しましょう。基本的にメモは小論文作成時に持ち込み可能な大学が多いですが、例外もあるため事前に確認が必要です。また、講義の流れを意識し、話の展開を追う練習をすることも大切です。メモを取ることに夢中になり過ぎて講義の内容を聞き逃さないよう注意し、講義の理解を優先することを心がけましょう。
要約力を鍛える
講義内容を簡潔にまとめる要約力も求められます。聞いた内容を要約する練習を行い、その際には「誰が、何を、なぜ、どのように」を意識してまとめると良いでしょう。
論述力を磨く
講義内容を基に自分の意見を論理的に展開する論述力も必要です。過去問や模擬問題を使い、講義内容を基にした小論文を書く練習を繰り返しましょう。書いた小論文は第三者に読んでもらい、論理性や説得力をチェックしてもらうことをお勧めします。
タイムマネジメントを意識する
試験時間内に講義内容を理解し、小論文を完成させるためにはタイムマネジメントが重要です。模擬試験形式で時間を計りながら練習し、講義の聴講、メモ取り、要約、論述の各段階にかける時間配分を意識することで、効率的に対策を進めることができます。
講義型小論文に向けた日常的な準備
幅広い知識を身につける
講義型小論文では、講義内容を理解するための基礎知識が役立ちます。具体的には、高校で学ぶ科目(現代文、古典、地理歴史、公民、数学など)の基本的な知識、最新の時事問題(政治、経済、社会、環境問題など)、さらには志望学部に関連する専門的な基礎知識などを身につけておくことが重要です。これらの知識があることで、初めて聞く内容でも関連付けて理解しやすくなります。
論理的思考力を養う
日常生活の中で、物事を論理的に考える習慣をつけることが重要です。例えば、ニュース記事を読んで自分の意見をまとめたり、ディスカッションやディベートに参加して他者の意見を聞きながら自分の考えを整理したりすることで、論理的思考力を鍛えることができます。
過去の事例を研究する
過去に出題された講義型小論文の事例を研究し、出題傾向を把握することも効果的です。例えば、慶應義塾大学や立命館大学の過去の出題内容を分析し、どのようなテーマが扱われたかを確認することで、試験対策に役立てることができます。
講義型小論文の模擬練習のすすめ
模擬講義を活用する
模擬講義を視聴し、その内容を基に小論文を書く練習を行いましょう。模擬講義は、大学のオープンキャンパスや動画共有プラットフォーム(例:YouTube)、またはオンライン学習プラットフォーム(例:JMOOC)などを確認してみてください。また、履修生以外でも受講できる大学の講義の視聴も参考になるでしょう。
フィードバックを受ける
書いた小論文は、学校の先生や塾の講師に見てもらい、改善点を指摘してもらいましょう。フィードバックを基に、論述の構成や表現をブラッシュアップすることで、より完成度の高い小論文を目指すことができます。
試験環境を再現する
実際の試験と同じ時間配分で練習を行い、試験本番の感覚をつかむことが重要です。時間内に講義内容を理解し、小論文を完成させる練習を繰り返すことで、本番への自信を高めることができます。
講義型小論文で注意すべきポイント
講義内容を正確に理解する
自分の意見を述べる際に、講義内容を誤解していると減点対象になったり、小論文の評価が0点になったりする可能性もあります。講義の要点を正確に把握し、それを基に論述を展開することが重要です。講義を聞く際には、メモを取りながら要点を整理する習慣をつけましょう
独自性を出す
他の受験生との差別化を図るために、自分の経験や独自の視点を盛り込むことが重要です。ただし、講義内容と無関係な話題に逸れないよう注意が必要です。
また、単に奇をてらった表現や独創的な意見を述べれば良いわけではなく、論理的な一貫性を持たせることが求められます。講義の趣旨を正しく理解した上で、自分の考えを適切に展開し、説得力のある論述を心がけましょう。
特に、大学教員が論拠を持って講義している内容である以上、よほど強力な論拠が他にない限り、全面的に否定することは避けた方が無難でしょう。
字数制限を守る
指定された字数内で簡潔かつ論理的にまとめることが求められます。字数オーバーや大幅な不足は減点対象となる可能性があるため注意が必要です。事前に練習を重ね、指定字数内で要点をまとめるスキルを身につけましょう。
総合型選抜の講義型小論文の過去の事例
慶應義塾大学法学部FIT入試 A方式の事例
講義を通じて「ジェリマンダー(ゲリマンダー:選挙区の恣意的な区割り)」の問題と、それが民主主義に及ぼす影響について学び、その理解をもとに論述を行う形式が採用されました。
論述試験では、「ジェリマンダーの防止や認定の難しさは、他の社会的課題の解決の困難さと通じる」という視点をもとに、類似する事例を挙げて説明することが求められました。受験生は、ジェリマンダーの問題点と共通する要素を持つ具体例を選び、それとの関連性を論理的に整理しながら論述する形式でした。
解答はA3原稿用紙形式で2,240字以内、試験時間は45分で行われ、講義内容の理解力、社会課題への洞察力、論理的な思考力が試される構成となっていました。
東京女子大学 現代教養学部 知のかけはし入試の事例
出題の目的は、講義内で示される抽象的で馴染みの薄い概念を、自身の知識や体験と結びつけて理解し、思考を発展させられるかを確認する点とされていました。
現代社会における多様な価値観の衝突に焦点を当て、その対立が生じる背景を考察し、克服の可能性を探ることがテーマでした。特に、社会学者カール・マンハイムが提唱した「知識の存在拘束性」の視点を手がかりに、問題解決の糸口を探るものでした。
レポートは2種類で、講義の要点を約400字で整理したものと「知識の存在拘束性」が自覚されるのはどのような場合が想定されるかについて、具体的な事例や自身の体験を挙げ800文字程度でまとめるものが問われました。
立命館大学政策科学部 政策科学セミナー方式の事例
募集要項によると、講義の内容や資料が意図することを客観的に捉え正確に理解し、より多角的視野から批判的な検討を試み、自身の意見を論理的、建設的に展開していく力があるかが求められました。
「格差社会の解決」のテーマで約50分の講義が行われ、およそ20分の質問時間が設けられました。その後に、講義に関する7つの問題が出題され、講義理解力や受験生の意見が問われました。
総合型選抜の講義型小論文 まとめ
講義型小論文は、模擬講義を受講した後、その内容を要約し、自身の意見を論理的に展開する形式の試験です。聴解力・要約力・論述力が求められ、課題文型とは異なり、音声情報を一度の聴講で的確に処理する能力が重要になります。
試験対策としては、講義を聴きながら要点を整理するメモの取り方を習得し、論理的に意見を述べる訓練を重ねることが不可欠です。また、過去の出題事例を研究し、出題傾向を把握することで、講義型小論文に必要な思考力を養うことができます。
実際に多くの大学で採用されており、慶應義塾大学法学部FIT入試や立命館大学の政策科学セミナー方式などでは、社会問題に関するテーマが扱われる傾向があります。本番では、限られた時間内で講義のポイントを正確に整理し、明確な構成で論述することが求められます。
講義型小論文は、単なる知識の暗記ではなく、思考力・表現力・論理的分析力を総合的に評価する試験形式です。効果的な対策を行うことで、より高い得点を狙うことが可能になります。講義型小論文に向けた準備や、内容についてのアドバイスが欲しい場合は、総合型選抜に特化した個別指導塾の活用も検討してみましょう。志望大学に特化した指導が受けられるため、効率的な準備ができるはずです。