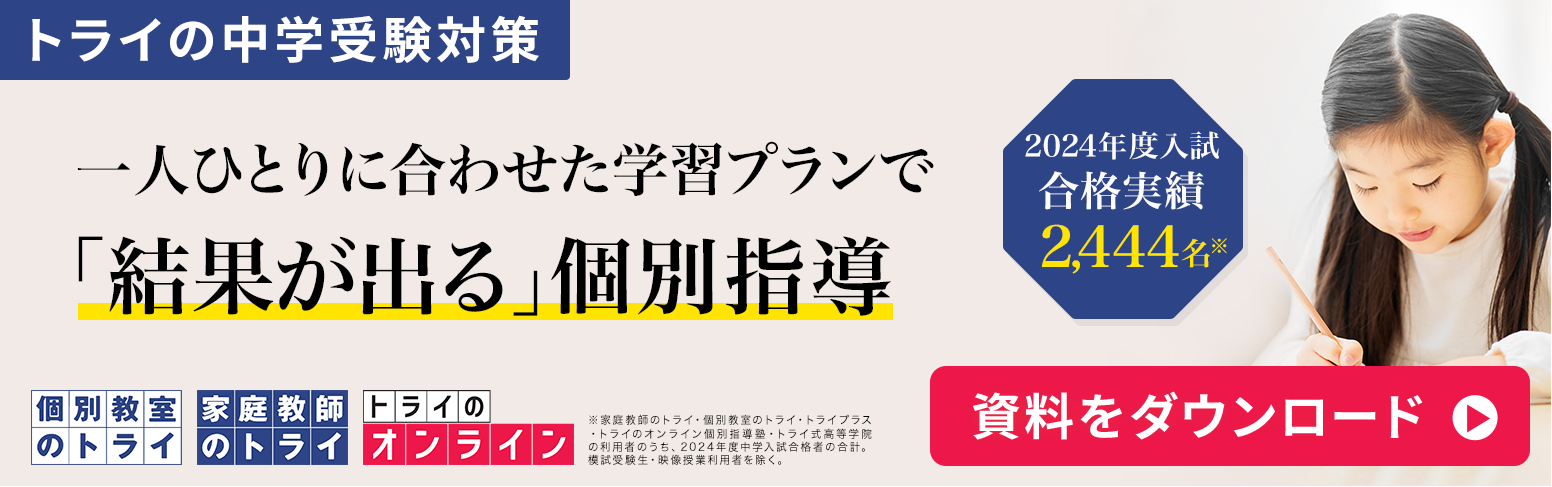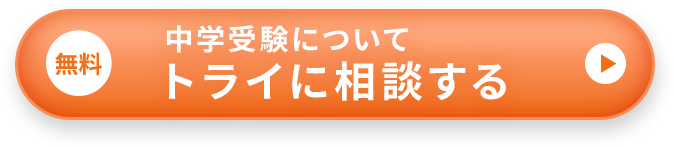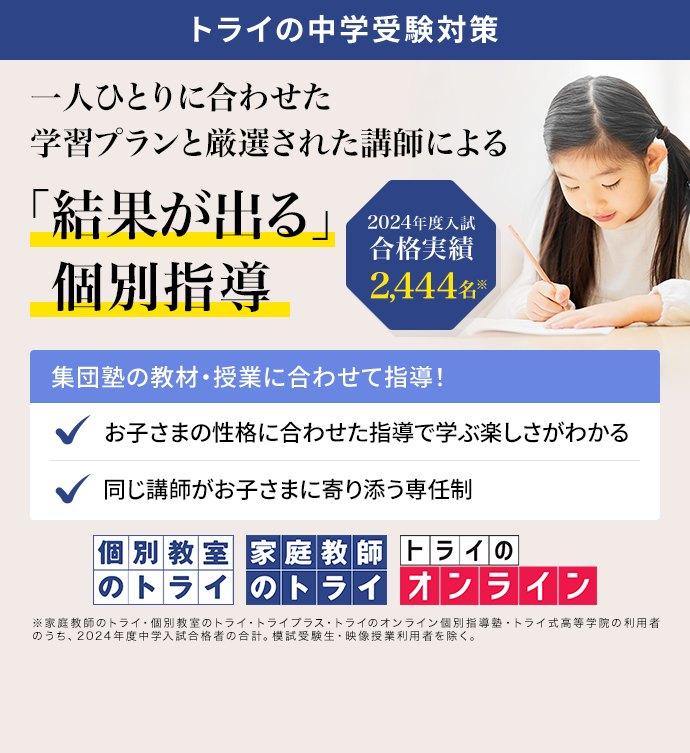中学受験の社会では、限られた時間で効率良く知識を身につけることが求められます。
「暗記が苦手」や「他の科目の勉強で忙しい」など、社会の受験対策にお困りではありませんか。
この記事では社会の特徴と最新の出題傾向を踏まえた上で、正しい勉強法や保護者様ができる具体的な対策をまとめています。
受験対策をする上で知っておきたい社会の特徴
中学受験において、社会は「知識の量」が問われる科目です。
知識の量が求められるということは、覚える作業が不可欠である一方、点数アップが即時狙えるため、お子さまにとって受験対策をするメリットが大きいとも言えます。
ここでは、社会を味方につけるために知っておきたい特徴や受験対策のポイント、最新の出題傾向をまとめています。
膨大な知識が必要
中学受験の社会は、地理・歴史・公民の3分野で構成されており、いずれの分野でも幅広く深い知識が問われます。
他の科目に比べて求められる知識の量が圧倒的に多いため「どれくらい学習し、どれくらい記憶してきたか」が直接的に点数に反映されます。
しかし、他の科目の勉強が忙しい受験生は、社会になかなか時間を割けず「気付いた時には間に合わなくなっていた」ということが少なくありません。
このため、社会の受験対策のポイントは、膨大な量の知識を限られた時間で効率よく定着させることであると言えるでしょう。
覚えた分だけ点数が取れる
知識が問われる社会は、暗記量が多い一方で、覚えたら覚えた分だけ点数が取れる科目とも言えます。
知識を身につければ得点につながるため、成績を上げるまでの時間が他の科目に比べて短く、さらに受験直前まで点数を伸ばし続けることが可能です。
また、記憶が定着していれば大きな失敗をしにくいため、仮に入試本番に緊張したり、問題と相性が悪かったりして他の科目で失点してしまっても、社会で安定して高得点が取れていれば総合点を支えてくれます。
このように、社会は受験対策をしっかりと行えば、お子さまにとって心強い味方となり得る科目なのです。
思考力も問われる
ここで注意すべきは、知識が重要ということは、教科書に出てきた単語をひたすら丸暗記すれば良いというわけではないという点です。
近年は単純な一問一答式の問題は減少し、知識に基づいてお子さま自身に考えさせるような、思考力を問う問題が増加しています。
例えば、複数の知識を組み合わせる問題や、自分の意見や考察を記述する問題、歴史・地理・公民の各分野を融合した問題などが挙げられます。
つまり、これからの入試は、表面的な暗記では通用せず、本質を理解した質の高い知識が問われているのです。
受験対策の基本!社会の成績を上げる正しい方法を紹介
社会は覚えたら覚えた分だけ点数が取れるため、受験対策をするメリットが大きい科目です。ただし、社会の知識は膨大な上、受験生は忙しく十分な学習時間を確保できないのが現実です。
したがって、社会の受験対策においては、限られた時間で効率的に知識を身につけることが重要になります。
ここでは効率よく社会の成績を上げるための方法を、ステップ1~4まで順を追って紹介しています。
ステップ1 興味関心を持つ
入試に合格するためとはいえ、興味のない内容を無理やり頭に詰め込もうとしても思うように記憶は定着しません。知識を効率よく習得するためには、お子さま自身が「知りたい」と思って学ぶことが重要です。
社会の学習内容は、お子さまの身の回りの生活や自然と深く関わっています。
例えば、スーパーに行き食材の産地を調べる、歴史的な名跡に旅行する、ニュースを見て話し合うなど、日々の生活の中で社会に関わる機会をつくり、お子さまの興味関心を育むように意識してみてください。
また、社会に興味を持つきっかけとして、漫画や映画などを活用するのも一案です。ただし、これらはあくまでも勉強の入り口に過ぎず、成績向上に直結するわけではないことに注意しましょう。
【保護者様ができること】
- 保護者様が社会に関心を持っている姿を見せる
- 一緒に楽しみながら社会に関わる活動をする
- お子さまが興味関心を持って取り組めたら褒める
ステップ2 家庭学習の時間を作る
社会の成績が上がらない最大の原因は、学習時間が十分に確保できていないことにあります。たとえ集団塾に通っていたとしても、塾は知識の解説をする場であり、肝心の覚える作業を授業内で行うことはほぼありません。
繰り返しになりますが、社会は知識の量で差がつく科目であるため、塾とは別に家庭での学習習慣を確立し、地道な暗記作業をしていく必要があります。
ただし、他の科目の勉強が忙しい中、週何時間も社会に時間を割くことは難しい可能性があります。そこでおすすめの方法が、「すき間時間」の活用です。
夕飯を食べる前の待ち時間や、塾に行くバスの中、トイレに地図を貼るなど、工夫次第ですき間時間はいくつも生み出すことができます。
短い時間でも積み重ねれば大きな学習効果が得られますので、毎日少しずつでも良いので継続して社会に触れるように意識しましょう。
【保護者様ができること】
- 生活リズムを工夫して、社会を勉強する「すき間時間」をつくる
- 勉強時間になったら声掛けをする
- 「すき間時間」に何を学ぶのか、内容を決める
ステップ3 単語ではなくストーリーで覚える
いよいよ知識の定着に向けて覚える段階になりましたが、ここで教科書・問題集の丸暗記をしてしまうと、これまでのステップ1と2の効果が十分に発揮されなくなります。
丸暗記した知識はすぐに忘れてしまいますし、近年はお子さま自身の考えを問うような深い理解を求める出題傾向にあるため、表面的な知識では得点につながりません。
そこでおすすめの覚え方が、単語ではなくストーリーで覚えるという方法です。社会の出来事はすべてつながりを持っています。
例えば「熊本県には阿蘇山をはじめとする豊かな水源があり、良質な地下水が利用できる」そして「半導体には大量の良質な水が必要」、このため「熊本県には半導体工場が多い」となります。
このように因果関係で結びつけると、分野を問わず知識がどんどん広がる上、ストーリーで覚えることで記憶にも残りやすくなるのです。
新しい知識を身につける時や授業内容を振り返る時は、単語を個別に覚えるのではなく「なぜこの出来事は起きたのか」「どのような影響を及ぼしているのか」というように、因果関係を意識するようにしましょう。
【保護者様ができること】
- お子さまが社会の学習をし終えたら「なぜそうなったのか」「その結果どんなことが起きたのか」と因果関係を尋ねる
- お子さまから社会の質問があった時は、ストーリーで答える
- 地図や年表などを確認するように声掛けする
ステップ4 さまざまな方法を使って繰り返し覚える
一度覚えただけの知識は時間が経つと必ず忘れてしまうので、社会の勉強は繰り返し行うことが重要です。
まず、一度覚えたらすぐに演習問題や一問一答集などを使って記憶を確認し、覚えていなかった内容は暗記し直します。すべて記憶できたと思ったら、数日後に再び確認し、忘れていた内容を暗記し直します。この作業を完璧に覚えるまで、根気強く何度も繰り返してください。
また、覚える際には様々な方法を試すことも効果的です。黙読、音読、音声を聞く、書いて覚える、ノートにまとめるなど、あらゆる方法を試して五感をフル活用して記憶を定着させましょう。
そして、何よりも効果的な暗記方法は、学習して得た知識を使ってたくさん会話をすることです。知識は使うことで定着するため、家庭では社会に関する会話を通して、学んだことを自分の言葉で表現する機会を作り、お子さまの学習をサポートしてください。
【保護者様ができること】
- 覚えているか口頭で確認テストをする
- 繰り返し覚えようと努力する姿勢を褒める
- 家族団欒の時に社会で勉強したことについて話す
分野ごとの受験対策!重要なポイントや注意事項を紹介
ここまで効果的な社会の受験対策を、知識を定着させるまでの順に沿って説明してきました。
次に、地理・歴史・公民の分野ごとに、勉強する上で注意すべきことや重要なポイントを紹介します。
地理の受験対策
地理学習において、地図の活用は不可欠です。手元に地図を置き、用語を覚える際には、必ず場所を確認する習慣をつけるようにしましょう。
また、記憶の確認をする際には、白地図に地名や情報を書き込むことが有効です。これによって、覚えたつもりでも曖昧な部分が明確になり、より確実に知識を身につけることができるようになります。
白地図上に覚えたことを正確に書き出せるまで地図に書くという学習を繰り返してください。
地理の学習範囲は地形、産業、気候など多岐にわたりますが、まずは都道府県の名前や場所、県庁所在地、特産品、伝統工芸品などを覚えることが重要です。
さらに、地形図や雨温図の読み取りも頻出問題です。雨温図については、各地のグラフの形を覚えるだけでなく、なぜその形になるのかという理由も理解するようにしてください。
歴史の受験対策
歴史の出題範囲は旧石器時代から現代史と非常に広範囲です。つい語呂合わせで無理やり頭に詰め込もうとしてしまいますが、歴史の知識は個別に暗記するのではなく、つながりを意識し、ストーリーで記憶することが重要です。
例えば、歴史上の人物を覚える際は、名前だけでなく、その人物が活躍した時代背景、どのような理由で何を行い、その結果どうなったのかという因果関係で覚えていきましょう。
ただし、ストーリーで覚えながらも、入試で得点するためには正確な知識が必要なため、人物の漢字など細部まで記憶することが不可欠です。演習問題などでアウトプットしながら、知識の定着を都度確認するように注意してください。
一通り時代の流れが把握できたら、学問や文化、外交、産業などテーマ別に学習することも有効です。テーマごとに知識を整理することで、より体系的に歴史を理解することができます。
また、教科書や資料集の写真や絵は、そのまま入試問題に出題されることが多いため、重要なものは必ず押さえておくようにしましょう。
公民・時事問題の受験対策
公民の出題範囲は政治や法律、経済などがありますが、まずは日本国憲法を理解することが重要です。日本国憲法の三大原則である国民主権、基本的人権の尊重、平和主義とそれに関連する条文を重点的に学習し、公民で学ぶ基礎事項をまず理解しましょう。
公民にはお子さまが普段聞き慣れない単語がたくさん出てきます。難しい単語は普段使う言葉に置き換えて説明するなどして、お子さまが自分の言葉で学習した内容を説明できるようになるまでサポートしてあげてください。
また、公民を学ぶ際に大切なのは、学習内容が自分の生活にどのように関わっているのか、という視点を持つことです。特に時事問題に対応するためには、教科書の学習だけでなく、日頃からニュースや新聞に触れることが不可欠です。
時事問題では、その年に話題になった出来事や国際社会の動向、環境問題などに関連する問いが出題されます。日頃からお子さまと一緒にニュースや新聞に目を通し、話し合ったり保護者様がわかる範囲で説明してあげたりする習慣を、ぜひご家庭で作ってみてください。
問題形式ごとの受験対策!周囲と差がつく設問への対処法を紹介
社会はさまざまな形式で問題が出されます。「覚えていたのに問題にびっくりして頭が真っ白になってしまった」とならないように、6年生後半になったら入試本番を意識して、出題形式ごとの受験対策をしましょう。
基本問題(空欄補充、正誤判定)の対策
空欄補充問題や正誤判定問題は、基本的な知識が問われることが多いため、大半の受験生が正答します。ここで失点してしまうと、周囲に後れを取ってしまうため、ケアレスミスも含めて失敗のないように対策をしてください。
例えば、空欄補充問題では、漢字のミスによる減点がよく見られます。日頃から漢字を正確に暗記した上で、丁寧に書くように心掛けましょう。
正誤判定問題では、問題文をよく読み、何が問われているのか、正しいものと誤っているもののどちらを答えるのか、冷静に判断する必要があります。問題文には、時代や場所など注目すべきポイントが多数あるため、たくさん演習を積み重ね、正誤の見分け方に慣れることが重要です。
資料読み取り問題の対策
近年の入試では、表やグラフ、雨温図、地形図、写真など様々な資料を読み取る問題が頻出です。とりわけ、受験生が今まで一度も目にしたことがないような、目新しい資料を提示する問題が増加しています。
見慣れない表やグラフを読み取る問題は、多くの受験生が苦手としているため、得点できると周囲に大きく差をつけることができます。
まずは、資料のタイトルや説明文をよく読み、いつの何に関する資料なのか、どの単元の知識と関連するのかを考えましょう。
次に、全体の推移を確認し、右肩上がりなのか、右肩下がりなのか、おだやかな変化なのか、急な変化なのかなど、資料の大きな流れを把握します。
さらに、数値が大きい箇所や小さい箇所に注目し、なぜその数値になったのか考察する習慣をつけてください。
記述問題
記述問題は慣れていないと何を書けばよいのかわからず、大きく失点してしまう可能性がある問題です。本番で空欄を作らないためにも、記述問題集や過去問などを使って日頃から書く練習を積み重ねておきましょう。
新聞のコラムや教科書の資料を自分の言葉で要約したり、考察をまとめたりする練習もおすすめです。
また、お子さまが書いた文章を保護者様が添削して、改善点を具体的に教えてあげると、より効果的に書く力を伸ばすことができます。
困った時は個別指導が選択肢の一つ
繰り返しになりますが、中学受験の社会は、集団塾の授業だけでは不十分で、家庭学習が非常に重要です。しかし、ご家庭でお子さまの社会をサポートするのは、大きな負担となりがちです。
「どんなに工夫しても、暗記は嫌だと拒否される」「社会について質問されてばかりで、答えるのが大変」「なぜか覚えてもすぐ忘れてしまう」「忙しくて家では社会の勉強時間を作れない」などお困りのことはありませんか。
そんな時におすすめの受験対策が個別指導の利用です。個別指導なら、中学受験のプロがお子さまをマンツーマンでサポートします。ご家庭で解決策が見つからずに時間が過ぎてしまう前に、ぜひ個別指導の利用を検討してみてください。
【個別指導のメリット】
- プロの講師がお子さまの興味関心を引き出す
- お子さまに合った覚え方が見つかるため、知識が定着しやすい
- わかるまで質問できる
- 忘れている単元だけを復習できるため、集団塾よりも効率的に進められる
- 志望校の出題傾向に基づいた課題に取り組める
知識量で差がつく社会は効率よく受験対策をして味方に
社会はどれだけ知識を習得したかで差がつく科目です。対策すればするほど点数は伸びますが、他の科目の勉強に忙しい受験生は、効率の良い学習をしなければなりません。
興味関心を持ったり、ストーリーを意識したり、まずは本記事で紹介した勉強法を試してみてください。ご家庭でうまく勉強が進まない時は、個別指導の利用がおすすめです。
社会は直前まで伸びる科目です。最後まであきらめずに努力し続けることで、社会が味方になり、本番合格を掴み取ることができます。