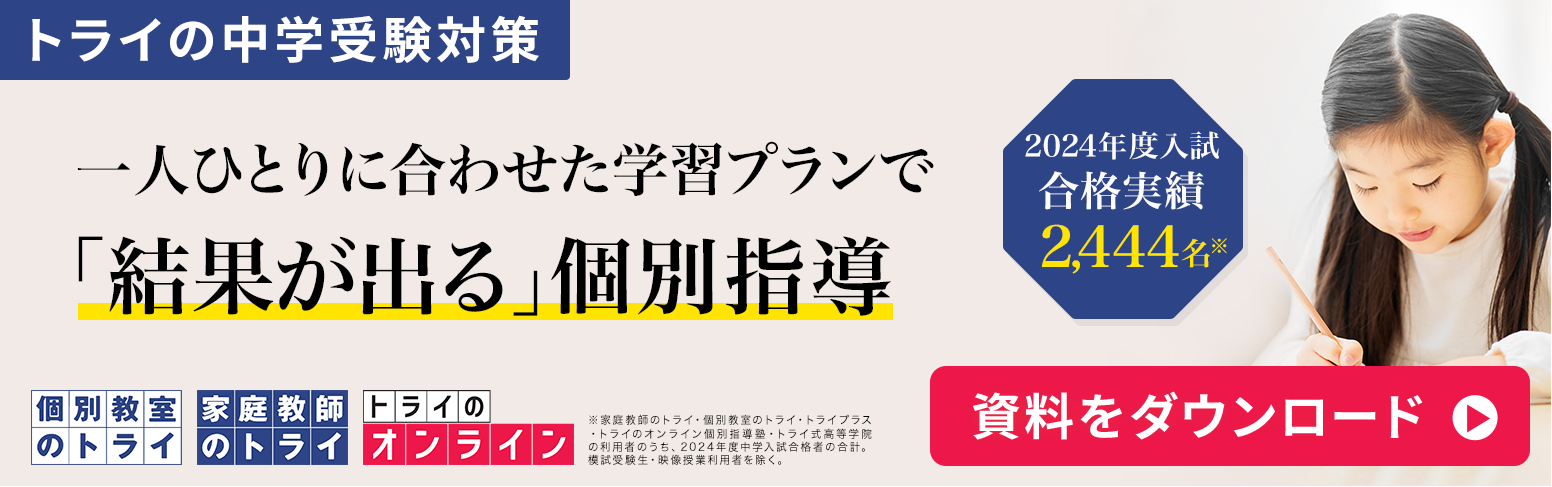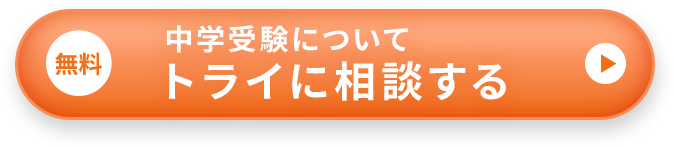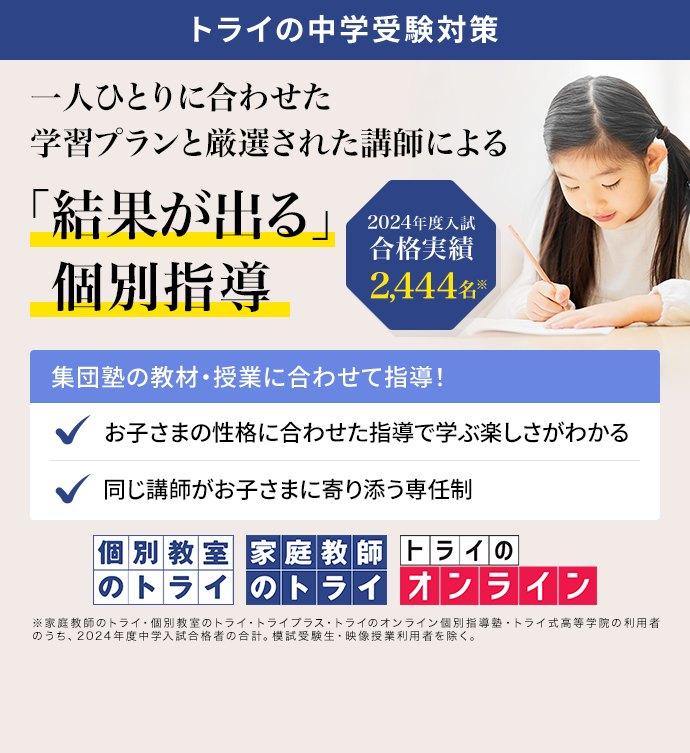中学受験の理科について、保護者様と受験生のお子さまはどのような科目だと捉えているでしょうか。
「暗記科目だから6年生からでも間に合う」や「生物が得意だから他の分野は後回しで良い」などの誤った認識をしていると、受験本番の大量失点が避けられません。
この記事では、理科の特徴と最新の出題傾向を踏まえた上で、正しい勉強法や保護者様ができる具体的な対策をまとめています。
受験対策をする上で知っておきたい理科の特徴
中学受験の理科は塾や保護者様のサポートなしには、お子さまの努力が報われにくい科目です。なぜならば、理科を学習する際には、3つのバランスが求められるからです。
ここでは受験対策をする上で知っておきたい理科の特徴を、3つのバランスに着目しながらまとめていきます。
4分野から満遍なく出題される(分野間の学習バランス)
中学受験の理科は、物理・化学・生物・地学の4分野で構成されています。小学生のお子さまは得意な分野ばかりに集中してしまう傾向があるため、結果的に苦手分野がおろそかになり、成績に偏りが生じることがよくあります。
しかし、中学受験で周囲と差をつけるためには、4分野すべてで安定して高得点を取ることが不可欠です。理科を勉強する際には、特定の分野に偏ることなく、バランスの取れた学習計画を立てることが重要です。
知識と計算のどちらも問われる(文系力と理系力のバランス)
中学受験の理科は、分野ごとに求められる能力が大きく異なります。幅広い知識や原理・法則の深い理解が問われることもあれば、早く正確な計算が求められることもあります。
理科は、暗記や読解といった文系的な力と、論理的思考や数字の処理といった理系的な力の両方が必要な科目なのです。
理科を学ぶ上で重要なのは、お子さまの得意・不得意を把握し、文系と理系の能力をバランス良く伸ばすための効果的な学習方法を見つけることです。そうすることで、お子さまは総合的な理科の力をつけ、合格へと大きく近づくことができます。
他の科目と並行して学習しなければならない(他の科目とのバランス)
中学受験では、一般的に配点が高い国語と算数の学習が優先される傾向があります。
「国算の負担が大きいから、理科は6年生からにしよう」「理科は覚えることが多いから、6年生になったら本気を出そう」と考えている方はいらっしゃいませんか。
難関校を目指すのであれば、理科は4年生(小3の2月)から、国算と並行して学習を進める必要があります。もちろん理科ばかりに時間を費やして、国算の勉強がおろそかになるのはよくありません。
しかし、理科の学習を後回しにしすぎると、いくら国算で高得点を取れても、理科の点数が足をひっぱって不合格になってしまうこともあります。中学受験においては、理科を後回しにせず、他の科目との学習時間をバランス良く配分することが重要です。
受験対策が不可欠!理科の最新の出題傾向
中学受験において、理科は4分野を偏りなく学び、文系力と理系力を共に伸ばし、さらに国算と並行して計画的に学習を進める必要があるため、塾や保護者様のサポートが不可欠です。
さらに、近年は理科の入試問題の質が大きく変化しており、受験対策の重要性が増しています。
ここでは、正しく受験対策をするために、理科の最新の出題傾向をまとめています。
まずは理科の出題形式をおさらい
繰り返しになりますが、中学受験の理科は物理・化学・生物・地学の4分野から出題されます。しかし、出題形式は学校ごとに大きく異なり、記述問題、選択問題、作図問題など様々です。
また、配点も学校によって多岐にわたり、国算と全く同じ配点の学校もあれば、国算の半分の比率になっている学校もあります。
さらに、大問が複数の小問で構成されており、小問どうしが関連性を持つ誘導形式となっている場合があり、1つ間違えると大量失点になる可能性があります。
このように、理科は出題形式、配点、問題構成など、学校ごとに特色があるため、過去問演習が不可欠です。
新しい傾向① 思考力が問われる
従来の理科の入試問題は、用語や公式を暗記さえすればある程度点数が取れる、いわゆる知識型の問題が中心でした。しかし、近年では教科書の内容を覚えているだけでは通用せず、「なぜそうなるのか」考えさせる、いわゆる思考型の問題に変化しています。
例えば、塾や小学校で習ったことがない初見の現象について、リード文やグラフ、表、図などの情報を読み解き、整理しながら考察していく問題などが頻出です。
つまり、これからの入試に対応するためには、知識を丸暗記するのではなく、本質まで理解した上で、論理的に思考することが求められているのです。
新しい傾向② 理科への興味関心が問われる
思考型問題の増加に伴い、近年は塾の学習だけでなく、小学校で行う実験や日常生活で触れる現象など、興味関心を持って理科に取り組んでいるかが問われています。
例えば、実験器具の使い方や手順に関する問題、SDGsなどの時事的テーマを意識した問題、カラー写真を用いた問題などが頻出です。これらの問題に対応するためには、教科書の学びだけでなく、身の回りの現象に対して「なぜだろう」「どういう仕組みだろう」と疑問を持ち、考え、調べる姿勢が求められます。
また、実験や観察などを通して実際に手を動かし、五感を使って学ぶことも重要です。つまり、これからの理科の入試では、興味関心や探求心、そして体験を通して学ぶ姿勢が求められているのです。
分野ごとに異なる!理科の正しい受験対策とは
理科は、物理・化学・生物・地学の4分野ごとに学習内容や問われる能力が異なるため、各々で勉強方法を変えることが鉄則です。お子さまの多くが分野の違いを意識せずに、どの分野も同じように勉強してしまっているので、まずはこの点を改善する必要があります。
ここでは、分野ごとの正しい受験対策を詳しく紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
物理の受験対策
物理の主な単元には、音・光・熱・電気・てんびん・ばね・てこ・滑車などが挙げられます。物理は他の分野に比べて暗記事項は少ないですが、論理的な思考や計算が必要な問題が多く出題されます。
このため、物理で正答するためには、原理や公式を正しく理解した上で、それを使って実際に問題を解く経験を積まなければなりません。つまり、物理攻略の確実な方法は演習問題をたくさん解くことにあると言えるでしょう。
しかし、たくさん解くことにばかり気を取られると、公式の理解が不十分になったりケアレスミスが頻発してしまったりします。途中式や図を書きながら「なぜこの公式を使うのか」説明できるように、丁寧に解く習慣をつけましょう。
化学の受験対策
化学の主な単元には、体積・気体・結晶・金属・pH・濃度などがあり、いずれの単元でも計算問題が出題の中心となっています。このため、化学を伸ばすためには、物理と同様に演習問題を数多く解く必要があります。
特に、化学は比や割合の考えを使う問題が多いため、お子さまの化学の成績にお悩みの際は、まずは算数の比と割合の単元を復習してみてください。
また、近年では化学の実験に関する問題が頻出傾向にあります。塾での勉強はもちろんですが、小学校の授業やご家庭での取り組みなどで、実際に手を動かし目で見て学ぶ経験をたくさん取り入れるようにしましょう。
生物の受験対策
生物の主な単元は植物・動物・人体などで、どの単元も膨大な知識量が求められるという特徴があります。このため、物理・化学のような演習中心の学習とは異なり、生物では覚えることを中心としたインプット型の学習が求められます。
ただし「覚える」とは、知識を丸暗記するのではなく、「なぜこうなるのか」という本質的な理解を伴うものでなければなりません。
生物は身近な事柄を題材としているため、図や写真、時には実物を見ながら、興味関心を持って学ぶことが、確実な知識を得る近道です。
また、生物は覚えれば覚えるほど、直前まで点数を伸ばし続けられる分野であるため、あきらめずに勉強し続けることが重要です。
地学の受験対策
地学の主な単元は天体・天気・地層・河川などで、用語の暗記と原理の理解の両方が必要な分野です。覚えることが重要という点では生物と似ていますが、地学は生物とは異なり、小学生の身近にはない抽象的な題材が多く扱われます。
特に天体は具体的なイメージがつかみづらいため、苦手とするお子さまが多いです。このため、地学では、図やイラストを活用して現象をイメージしながら丁寧に学ぶことが重要です。
また、お子さまにとって身近ではない用語は覚えてもすぐ忘れてしまうため、繰り返し復習する習慣をつけてください。
なかなか伸びない理科にお悩みのお子さまの受験対策
ここまで、中学受験における理科の特徴と最新の出題傾向、そして分野ごとの勉強方法を確認してきました。上に述べてきた「丸暗記ではない勉強」や「分野ごとに最適な勉強」などを意識して、塾や家庭で受験対策をしているにもかかわらず、成績が伸びずに困っているという方はいらっしゃいませんか。
ここでは「受験対策をしているのになぜか成績が伸びない」とお悩みの方に向けて、原因と解決策、そして保護者様ができることをまとめています。
【偏差値50以下】理科が苦手なお子さまの受験対策
お子さまの理科の成績が偏差値50以下の場合は、教科書に載っている基本事項を覚えきれていない可能性があります。近年は理科の出題が、知識を問う問題から考えを問う問題へと変化していますが、このような思考型の問題を解くにも、考える材料となる知識が不可欠です。
お子さまのテストの結果が平均点に満たなかった場合は、もう一度基本に立ち返って用語や公式を頭に入れ直すようにしましょう。場合によっては、過去の学習内容に立ち戻って、知識の抜け漏れがないか再確認することも必要です。まずは興味を持った単元を得意にするなど、科目への興味を引き出すことも大切です。
【保護者様ができること】
- テスト結果を分析して、覚えられていないことを洗い出す
- 復習課題を用意する
- 演習問題の丸付けをして、基本が定着しているか確認する
- 理科の勉強スケジュールを立てて、声掛けをする
【偏差値50~60】模試で点数が伸び悩むお子さまの受験対策
お子さまが普段の復習テストでは良い成績にも関わらず、模試や実力テストになると成績が伸び悩む場合は、知識の定着が不十分である可能性が高いです。
教科書の文章を読むだけの勉強や、解法のパターンを当てはめるだけの演習をしていると、復習テストや基本問題は正解できても、周囲と差がつく応用問題でつまずいてしまいます。
理科の成績を上げるためには、知識を覚えるだけでなく、知識の使い方まで習得できるような、質の高い学習が不可欠です。
例えば、図や表を見たり書いたりしながら学習する、塾で習ったことを自分の言葉で説明する、演習問題を解く際はなぜその解き方をするのかまで答えるなど、お子さまが自分の頭で考え主体的に学べるように工夫してみてください。
【保護者様ができること】
- 塾から帰ってきたら習ったことをお子さまに説明してもらう
- 家庭で普段から理科に関する話題を会話する
- 演習問題を解き終わったら、なぜその解き方をしたのか説明してもらう
- 図が多く、お子さまが理解しやすい参考書を購入する
【偏差値60以上】過去問演習でつまずいているお子さまの受験対策
お子さまが、理科が苦手ではないにもかかわらず、過去問を解くとまったく歯が立たない場合は、入試問題に慣れていない可能性が高いです。
理科の入試問題は、記述問題が多い学校や初見では手が止まってしまうような風変わりな問題を出す学校、昨今の出題傾向とは真逆で知識を細かく尋ねる学校など、学校ごとに大きく異なります。
大切なことは、志望校を決めたら傾向を分析した上で、問題に慣れるまで過去問演習を繰り返すことです。6年生の9月から、第一志望は最低でも5年分、第二志望以降は最低でも3年分、過去問を解くようにしてください。繰り返し過去問演習をしても合格平均点を大きく下回る場合は、基本の抜けがある可能性が高いです。
過去に受けた模試の結果を確認して、苦手な分野(単元)がある場合は早急に復習をするようにしましょう。
【保護者様ができること】
- 過去問を複数年分用意する
- 出題傾向を調査・分析する
- 模試の結果を確認し、苦手な分野(単元)がないかチェックする
個別指導を利用する
ここまで理科の正しい勉強方法と、成績が伸びない場合の解決策をまとめてきましたが、これらの受験対策をすべて保護者様がサポートするのは、負担が大きすぎると言わざるを得ません。
他の科目の勉強もある中で、理科の4分野を偏りなく学べるように計画を立て、お子さまが教科書を丸暗記しないように注視し、適宜質問に答えるというサイクルを、お子さまが合格するまで続けることは困難です。そんな時におすすめの解決策が、個別指導の利用です。
個別指導なら、プロの講師がお子さまに合わせてマンツーマンで受験対策をするため、わからない点をピンポイントで指導でき、理科の成績を着実に上げることができます。「家庭では理科まで手が回らない」「何をやっても成績が上がらない」など理科の勉強でお困りの際は、個別指導塾や家庭教師の利用を検討してみてください。
【個別指導のメリット】
- お子さまの学力に応じて、4分野をバランスよく伸ばせるオリジナルのカリキュラムが組める
- 講師がつきっきりで指導するため、丸暗記が防げる
- わかるまで質問できる
- 苦手な単元だけを学習できるため、集団塾よりも効率的に進められる
- 志望校の出題傾向に基づいた課題に取り組める
理科は必ず伸びる!お子さまに合わせて正しい受験対策を
いかがでしたでしょうか。理科は一つでも苦手な分野があると大きく失点してしまうだけでなく、出題傾向が変化し、教科書の知識だけでは対応できない難易度の高い問題が頻出の教科です。
国語と算数を学びながら、幅広い知識と複雑な計算が必要な理科の学習を進めるには、正しく効率的な勉強法が不可欠であると言えるでしょう。お子さまの理科の成績にお悩みの際は、家庭で抱え込まずに、ぜひプロの講師のマンツーマン授業を頼ってみてください。