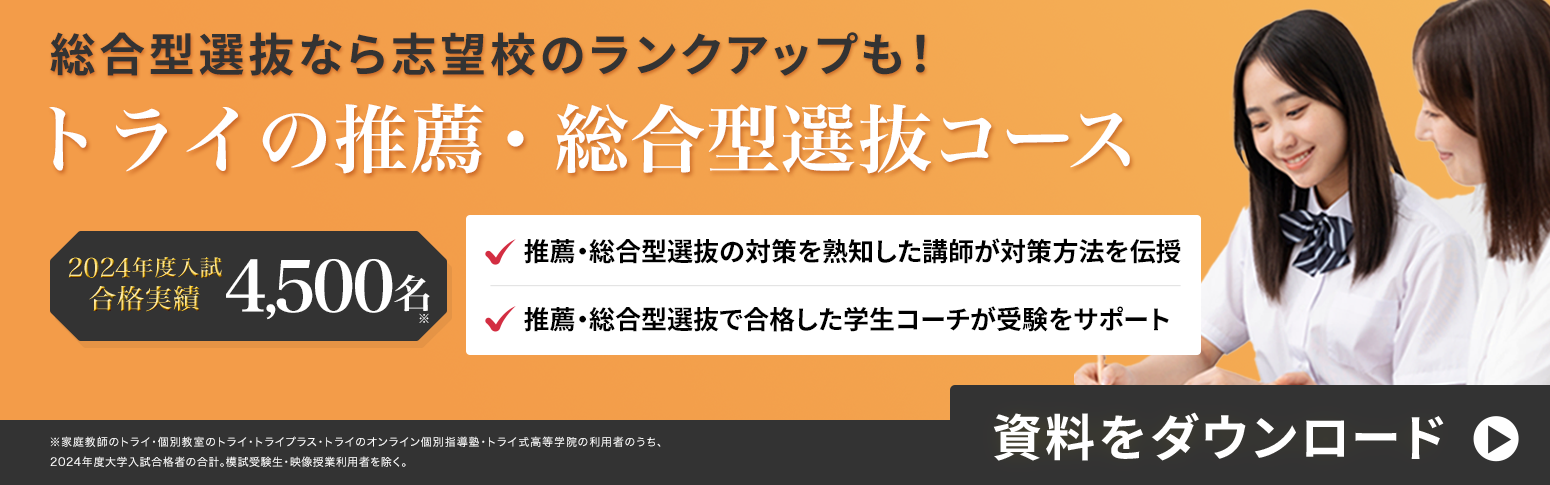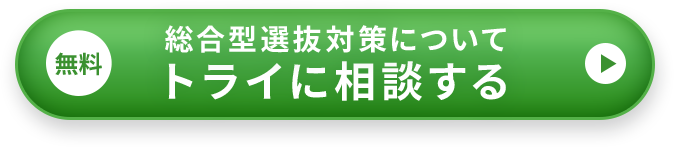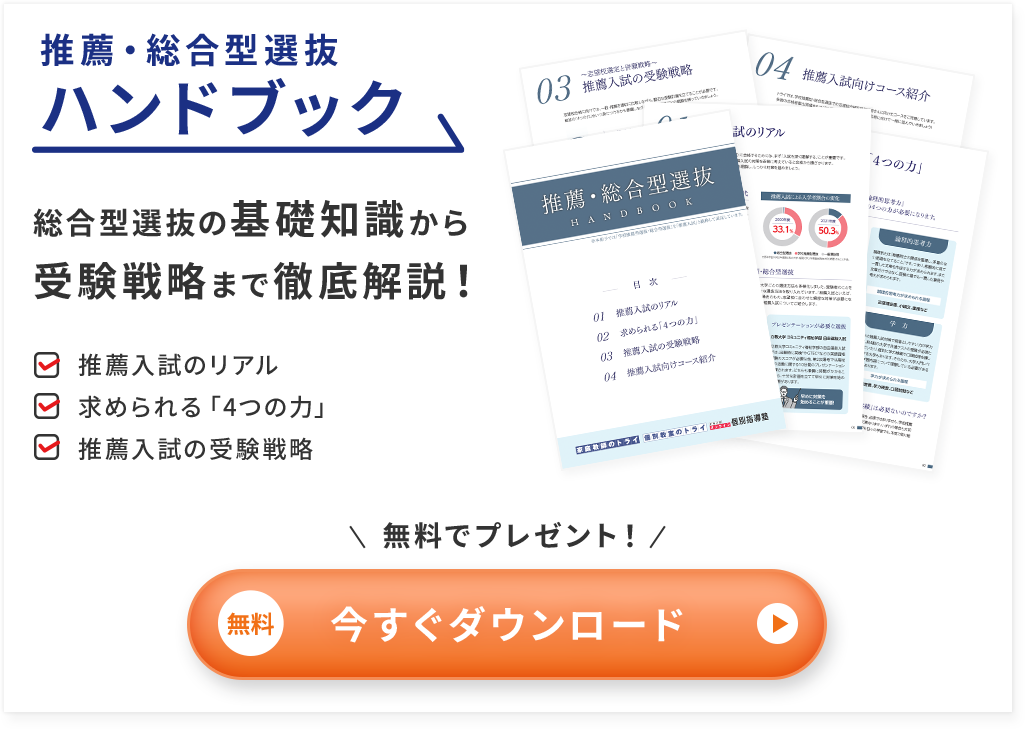総合型選抜では、どのような問題が出題されるのか気になっている方が多いでしょう。総合型選抜の試験の問題内容を把握しておくことで、適切な試験対策がしやすくなります。
この記事では、総合型選抜のメリットやデメリット、問題内容を紹介します。総合型選抜の問題内容を把握したい方は、本記事を参考にしてください。
総合型選抜とは?
総合型選抜とは、大学が求める人物像に沿った人物を探すために提出書類や小論文などの試験を組み合わせて評価する入試方式です。大学で何を学んで将来にどのように活かすのかが見られるため、具体的な志望動機や大学で取り組みたい研究内容を伝える必要があります。
総合型選抜は、基本的に9月から出願が始まり、11月以降に合格発表があるので、対策を早めにしなければなりません。大学や学部により出願条件が異なりますが、場合によっては大学が提示する評定平均を超える必要があります。
そのため、評定が必要になる大学を受ける場合は、総合型選抜への出願のために高校1年生時点から学校の定期テストで良い点数を取り、高い評定を獲得し続けなければなりません。
総合型選抜・学校推薦型選抜・一般選抜の違い
総合型選抜と学校推薦型選抜と一般選抜は、選考方法や時期がそれぞれ異なっています。
総合型選抜は大学が求める人物像と受験生の希望のマッチングを重視しており、原則として学校長の推薦が必要ありません(医学部など、一部必要になるケースもあります)。
学校推薦型選抜は高校での学習状況や課外活動が評価され、学校長の推薦が必要です。選考時期は9月から11月なので、総合型選抜と同じ時期です。学校推薦型選抜は公募制と指定校がありますが、指定校制では9月から校内選抜が始まります。総合型選抜や学校推薦型選抜の選抜方法に共通テストが課される場合は、2月になる場合もあります。
一般選抜は、基本的には学力試験の結果で合格が決まります(医学部など、一部学部では面接などが問われる場合もあり)。選考時期は1月から3月と遅いため、長期間対策ができます。
総合型選抜のメリット
総合型選抜にはどのようなメリットがあるのでしょうか。総合型選抜には、2つのメリットがあります。
- 早い時期に合格できる
- 原則として、学校の推薦状なしで受験できる
総合型選抜のメリットを把握しておけば、自分に合った受験方法が選びやすくなります。それぞれのメリットを参考にした上で、総合型選抜の受験をすべきかを判断してください。
原則として、学校の推薦状なしで受験できる
総合型選抜は、学校推薦型選抜で必要となる学校からの推薦状は原則必要ありません。学校推薦型選抜は、高校から推薦状を貰うことで比較的高い合格率となりますが、1年生の頃から努力をし続ける必要があります。例えば、定期テストで良い点数を取るなど、学校の上位の成績をキープし続けないといけません。また部活動やボランティアなど、課外活動で一定の成果を得る必要がありますし、体調管理をして高校に毎日出席することも求められます。総合型選抜でも評定の高さは必要ですが、学校推薦型選抜の方がその重要度は上がります。
総合型選抜のデメリット
総合型選抜にあるのはメリットだけではありません。総合型選抜のデメリットとして、2つあります。
- 対策方法がわかりづらい
- 試験内容が大学によって大幅に異なる
総合型選抜のデメリットを把握しておくことで、悪い点も理解した上で自分に合った入試方式を選択することができます。それぞれのデメリットを参考にし、総合型選抜を受験すべきかどうかの判断の参考にしていただければと思います。
対策方法がわかりづらい
総合型選抜のデメリットは、対策方法がわかりづらい点です。一般選抜は主に学力で合格を決定するため、合格基準が比較的明確です。しかし、総合型選抜では主に人間性を評価するので、具体的な対策方法が曖昧になる傾向にあります。
総合型選抜の受験を検討している方は、専門の学習塾への通塾がおすすめです。学習塾はさまざまな生徒を合格に導いてきた実績があるため、適切なサポートを受けられます。費用を加味した上で、学習塾へ通うべきか判断してください。
試験内容が大学によって異なる場合がある
総合型選抜の併願を検討している方は、試験内容が大学によって異なる場合がある点はデメリットになりやすいです。大学によって試験内容が異なると対策すべき内容が多くなるため、全ての試験対策に手が回りにくくなる恐れがあります。
例えば、A大学の試験内容で小論文、面接、グループディスカッションが受験項目だったのに、B大学では学力試験、実技試験が受験項目だった場合は、対策すべき範囲がかなり広くなってしまいます。試験内容を確認した上で、併願する大学を決定しましょう。
総合型選抜の問題内容
総合型選抜には、以下のような形式の入試がおこなわれます。
- 書類選考
- 小論文
- 学力試験
- 実技試験
- プレゼンテーション
- 面接
- 集団面接
- 口頭試問
- グループディスカッション
総合型選抜の問題内容を把握すれば、適切な対策がしやすくなります。それぞれの内容を把握し、総合型選抜の対策をしていきましょう。
書類選考
書類選考は、受験生の学力や活動実績を評価するためのプロセスです。書類選考では、以下のような内容が評価されています。
| 主な審査対象 | 説明 |
|---|---|
| 学業成績 | 高校時代の成績や出席率など |
| 志望動機 | 大学や学部を選んだ理由と将来の展望 |
| 学修計画 | 大学で何を学んで将来にどのように活かすのか |
| 活動実績 | 部活動や課外活動など |
| 自己PR | 自身の強みや特性をどのように活かして大学生活を送るのか |
書類審査では、自分の個性や意欲をとことんアピールしていきましょう。
小論文
小論文は、与えられた課題に対して、自身の意見や解決方針を提案するものです。例えば、日本全体の英語力の向上が課題なのであれば「自分の留学経験をもとに英語を教えられる人材を増やす」といった内容も、具体的な対策の提案のひとつになります。
また小論文では、具体例を入れた方が良いとされています。決められた文字数の中でどのようにまとめられるかの能力を高める対策をしていきます。
小論文の具体的な対策については、この記事を参考にしてください。
総合型選抜の小論文対策完全ガイド
学力試験
学力試験は「知識・技能」「主体性・協同性」「思考力・判断力・表現力」を総合的に評価する試験方法です。総合型選抜試験での学力試験は、記述式や口頭試問が多いため、問われている内容も正確に理解した上で解答する必要があります。
学力試験の内容は大学によって異なっているため、一概には言えません。ただ、大学の学部に沿った資格を取得すれば、その大学に合った高い学力を保有している証拠になります。例えば、理数系の学部なら国際科学オリンピックへの挑戦、英語系の学部ならTOEFLの高得点取得も有効です。
実技試験
大学によっては、総合型選抜で実技試験が課される場合があります。特に音楽や芸術、芸能などを取り扱う学部で実技試験がされる傾向にあります。例えば、建築系の学科では、スケッチやデッサンの課題が課されるかもしれません。空間表現能力は、一般的な大学でも問われることもあります。
また、大学の講義を模擬的に受講し、それに基づいたレポートの提出が求められる場合もあります。志望校の過去問を確認し、実技が必要かを確認しましょう。
プレゼンテーション
プレゼンテーションとは、大学への志望理由や将来の目標などを自分で資料を作成して発表する方法です。考える力や臨機応変な対応力、コミュニケーション能力などが試されます。
プレゼンの課題、制限時間、発表の形式、使える機材などは大学によってさまざまで、テーマが自由な場合もあれば、SDGsに関連する内容に限定するなどの場合もあります。プレゼンは繰り返し練習をし、適切な時間管理や質疑応答の準備をしていきましょう。
面接
総合型選抜には、基本的に面接試験があります。総合型選抜は受験生の人物像や将来性を総合的に判断して入学を決定する制度なので、面接での印象が選考に大きな影響を与えるでしょう。
例えば、自己紹介の仕方や態度など受験生としての基本的なマナーを守らなければ、マイナスの評価をされてしまいます。また、興味や関心ごとなど、自分が何に対して関心があって今まで取り組んできたのかをわかりやすく説明する必要があります。
集団面接
総合型選抜では、1対1の面接をする場合もあれば集団面接の場合もあります。集団面接とは、面接官2〜4名に対して受験生が2〜6名で構成される試験です。順番に同じ質問をされることもありますが、一人ひとり異なる質問をされる場合もあります。
なお、他の受験生が質疑応答しているときは意見にうなずきつつ傾聴する姿勢が大切です。ただし、過度な同調は控えましょう。
口頭試問
口頭試問とは、今後専門的な勉強をしていくために必要となる基本的な知識や考え方が身についているか否かを試す試験です。過去問を事前に確認して出題傾向を理解した上で具体的な対策をしましょう。
例えば、面接官の質問に対してただ単に回答をすればいいわけではありません。結論を裏付ける根拠や自分の伝えたいことをわかりやすく簡潔に伝える必要があります。一方で、過度に肉付けをしてしまい質問から逸脱してしまうことの無いように注意しましょう。
グループディスカッション
グループディスカッションとは、特定の話題に対してさまざまな視点から論じて、グループの意見を反映させた結論や解決方法を時間内に見出す試験です。グループディスカッションはチーム戦なので、以下のような大学側から指定されるメンバー間の役回りを理解しておく必要があります。どの役割でも対応できるように準備しておきましょう。
| 役割 | 説明 |
|---|---|
| リーダー |
|
| タイムキーパー |
|
| 書記 |
|
総合型選抜の試験項目を理解して対策しよう
総合型選抜試験の試験項目には、書類選考や小論文、学力試験、実技試験、プレゼンテーション、面接、集団面接、口頭試問、グループディスカッションなどがあります。志望大学が出題する問題に応じ、適切な対策が必要です。
志望大学の募集要項を確認し、どのような問題が出題されるのかを理解した上で、総合型選抜の対策をしていきましょう。
総合型選抜の対策は特別な対策が必要であるため、総合型選抜に特化した指導を行う塾もありますので、合格率を上げたい方は、どの塾に入るべきか検討されることをおすすめいたします。