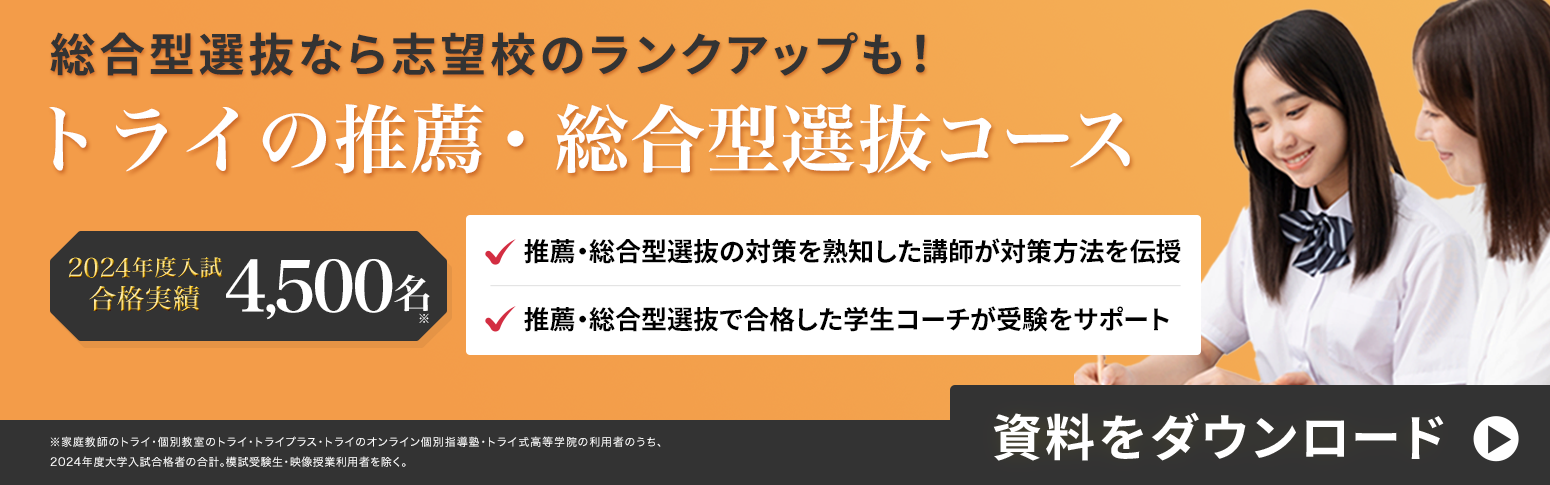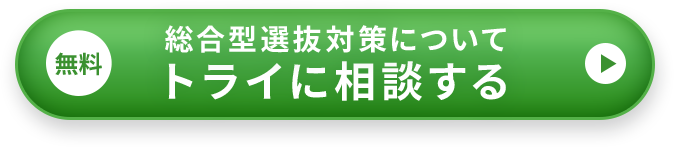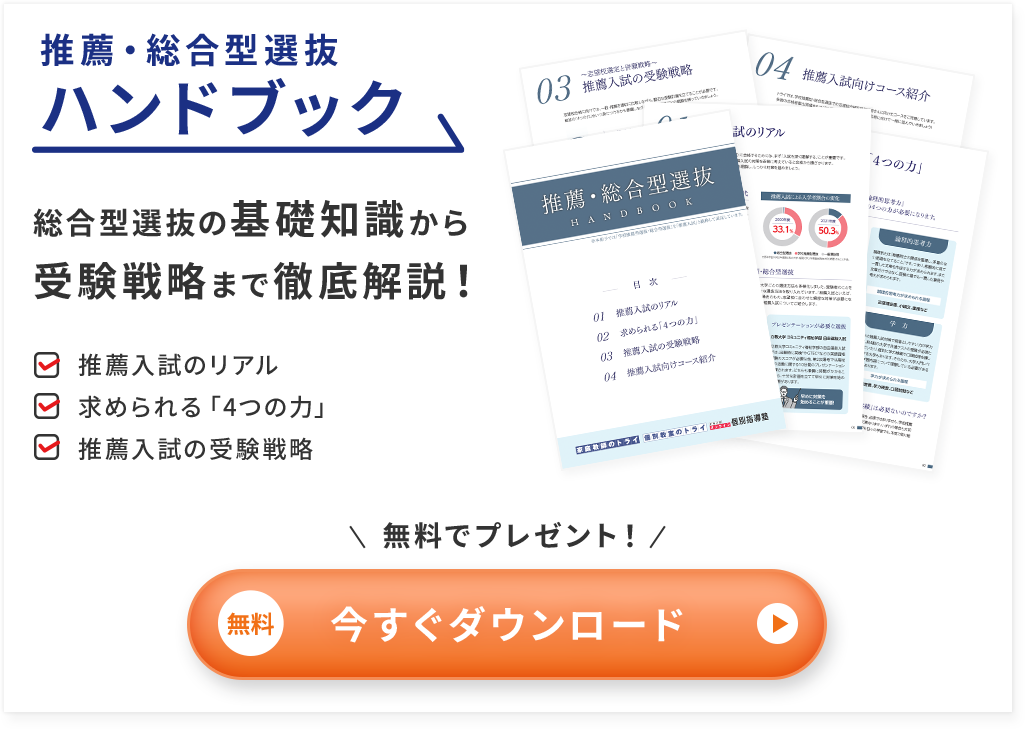総合型選抜(AO入試)では、受験生自身の経験や活動を通じて得た成長や将来ビジョンを大学に伝える力が問われます。その中で、ボランティア活動は多くの受験生が注目するアピールポイントの一つですが、単なる実績としてではなく、一貫性のあるストーリーとして伝えることが評価の鍵となります。
本記事では、総合型選抜においてボランティア活動を最大限に活かすためのポイントや具体的な実践方法について解説します。志望校合格に向けたヒントとしてぜひご活用ください。
総合型選抜(AO入試)でボランティア活動が評価されるのはなぜか?
総合型選抜において、ボランティア活動を主な課外活動の実績としてアピールしようと考えている方々は少なくないと思いますが、大学側が選考においてどのような視点でボランティア活動を位置づけているかを的確に理解することが大切です。
大学側は以下のような見方をしています。
- 受験生がどのようなボランティア活動に参加したのか?
- それによりどのような成長や気づきを得たのか?
- その結果、どのような将来ビジョンを描いているのか?
- その実現のために志望校での学びが本当に必要なのか?
これらが一貫性を持った形で明確にアピールされることで、初めて評価に至ります。
したがって、「総合型選抜(AO入試)で有利になるらしいから、とりあえずボランティアをしておくか……」とか「合格しやすいと言われているボランティア活動に絞って選ぼう……」という発想では、成功を収めるのは難しいと言えます。
どんなに高い活動実績があっても、それが本人の将来ビジョンと結びついていて、その途中のプロセスとして志望大学での深い学びが必要という一貫性がなければ、大学側からの評価には至らないでしょう。
逆に、ボランティア自体で目立った成果などがない場合であっても、それが受験生本人にとって学びや気づき、将来ビジョンの構築に大きな影響を与え、その上でさらに学びたいという意欲が高まったことで志望大学での学びを求める流れであれば、十分に評価される可能性があります。
これが総合型選抜(AO入試)とボランティア活動の本質的な関係性です。本質をしっかり理解した上で、以下を読み進めることで、あなたのボランティア活動が総合型選抜(AO入試)において高い評価を受けることになるはずです。
評価につながるボランティア活動の特徴
前項の総合型選抜(AO入試)におけるボランティア活動の本質を踏まえ、以下の観点から評価されやすいボランティア活動の特徴を解説します。
- 志望学部・学科との関連性がある活動
- 継続的な取り組みが見られる活動
- 社会課題の解決に貢献する活動
志望学部・学科との関連性がある活動
志望学部や学科と関連があることは、説得力のあるアピールとなります。ボランティア活動を通じて将来ビジョンが形成されたことをアピールする流れなので、「志望学部や学科での学び」と「活動内容」との間で一貫性を持つ必要があります。
志望校が先であれ、ボランティア活動が先であれ、結果的に受験生が成長や気づきを得て、貴重な体験をベースに将来ビジョンを明確化し、志望学部での学びを必要としていることを上手く伝えられることが最も重要です。
試行錯誤しながら、ボランティア活動を通じて学びや気づきを深める中で、自分自身が本当に進みたい方向性を明確化し、どのように入学後の学びや将来ビジョンに結びつけるかが大切です。
継続的な取り組みが見られる活動
長期的に取り組んだ活動は、責任感や忍耐力、そして継続性などへの適性をアピールできる重要なポイントとなり得ます。期間が長くなれば、それだけ長い期間にわたり社会と関わってきたことがアピールできる上に、成長や気づき、将来像に影響を及ぼす経験も、より多く体感できる可能性があります。志望理由も、より説得力のある内容となるでしょう。
ただし、単に長期的な取り組みであれば良いということではありません。長期的に取り組んだボランティア活動であっても、成長や気づきなどが伴わなければアピールできる要素を得ることは難しいです。さらに、基本的には高校在学中での活動が評価の中心となることも注意しておくと良いでしょう。もちろん、小学生や中学生の頃から継続して現在まで続いている活動内容であれば、十分評価の対象となるでしょう。
社会課題の解決に貢献する活動福祉活動
地域社会やグローバルな課題解決など、現代の社会問題に貢献する意欲は評価されやすい傾向があります。このような活動は、将来ビジョンの明確化や、受験生本人の主体性や目的意識、社会性や協調性といった「大学が課外活動に求めるポイント」の多くに合致するためです。
例えば、環境保護、貧困地域への支援、SDGsに関連する取り組みは、まさに社会課題の解決に貢献する活動に該当します。
おすすめのボランティア活動例と情報収集
受験生が総合型選抜(AO入試)を視野にしたボランティアとしておすすめの活動を表にまとめました。
- 環境活動
- 教育・福祉活動
- イベント・スポーツ支援
- 社会課題解決型
- オンラインボランティア
上記5つのカテゴリに分けて分類しています。
| 環境活動 |
|
|---|---|
| 教育・福祉活動 |
|
| イベントや スポーツ支援 |
|
| 社会課題解決型の活動 |
|
| オンライン ボランティア |
|
ボランティア活動以外のアピールになる取り組み
ボランティア活動とは異なるものの、良いアピール材料となる取り組みもあります。具体的な一例としては「救命救急講習会」などが挙げられます。この講習会は1日で受講が可能で、修了証も発行されます。医療系志望に限らず、やや危険を伴う野外活動が求められる学科を志望する受験生にとっても、非常に有効なアピール材料となります。
- 環境科学系:山林などでの調査が多い
- 農学・水産学系:農場や水辺でのフィールドワークが必要
- 地理学・地球科学系:地質調査など野外でのデータ収集が多い
- 体育・スポーツ科学系:スポーツの実践や指導の実習が含まれる
- 工学・建築系:土木調査や建設現場での実習がある
「救命救急講習会」はあくまでも一例です。必要なのは大学側への効果的なアピールですので、ボランティア活動以外で良い材料になるような活動にも、意識を向けておくのも良いと思います。
ボランティア活動の情報の集め方
総合型選抜に向け、自分自身が納得できるボランティア活動と出会うために、以下のようなアプローチで探してみることをおすすめします。
ボランティア情報サイトを利用する
ネット上には多くのボランティア情報サイトがあります。全国のボランティアの募集情報が掲載され、自分の目的や地域に合わせた検索が可能です。
地域センターを訪れる
地元で行われている活動の情報を得るには最適と言えます。担当者と直接やりとりできるので、情報サイトの掲載情報などでは知ることができない、よりリアルな情報を得ることも可能です。
学校や同級生に相談してみる
学校の事務局や先生などを通じて地域の活動情報を得られることは、安心して活動できるという面でもおすすめです。また、同級生や友人、先輩などにボランティア経験のある人がいれば、実際の活動体験を通じた情報も得ることもできるでしょう。
志望理由書と面接でボランティア活動を効果的に伝える方法
総合型選抜を見据えてボランティア活動をしたのであれば、志望理由書や面接を通じて、活動実績や問題意識、熱意等を大学側に的確に伝える必要があります。ここでは以下の4つのポイントにフォーカスします。
- 具体的なエピソードを核にする
- 学びと成長を明確にする
- 志望大学の理念や学部との関連性を示す
- アピールのバランスを取る
それぞれ詳しく見ていきましょう。
具体的なエピソードを核にする
ボランティア活動での具体的なエピソードを通じてあなたの人物像を伝えることで、志望理由書や面接での説得力がより高まります。活動内容を単に列挙するだけでは不十分なので、なぜその活動に参加したのか、どのような課題に直面したのか、どう解決したのかなどを明確にしましょう。
その際、次のような構成でまとめると効果的です。
- 活動の背景 →その活動を選んだ動機
- 具体的な行動 → 活動中に直面した課題や解決のための具体的行動
- 結果 → 活動を通じて体感した成果や自身の変化・気づき
このように時系列に沿って整理しつつ、活動の流れや自身の成長過程をわかりやすく伝えましょう。
ただし、エピソードのみに終始せず、活動から得られた学びや成長を一般化して、将来ビジョンや志望理由にどのように結びつけられるかが、評価を大きく左右する重要なポイントです。
学びと成長を明確にする
ボランティア活動の実績を基にして、経験を通じて得た自身の成長や学びを具体的に示すことが大切です。
例えば、「コミュニケーション能力が向上しました」のような抽象的な表現よりも、「異なる年代の方々と関わる中で、相手の立場にできるだけ寄り添って考え、わかりやすく説明できるようになりました」というように、具体的な状況や経験と結びつけることが重要です。
その他の例として以下が挙げられます。
- チーム間の意思疎通を重要視して臨んだことで、コミュニケーション能力が向上した。
- 未知の課題に直面しながら解決策を考える中で、問題解決力が養われた。
- 他者への理解や思いやりの価値を深く認識し、自身の価値観が大きく変化した。
具体例を通じて得た学びを、将来ビジョンや志望理由と結びつける形でアピールすることで、より説得力のある表現となるでしょう。
志望大学の理念や学部との関連性を示す
ボランティア活動での経験と、大学入学後のより深い学びとの関連性を明確に示しましょう。
例えば、
■環境保護のボランティア活動を通じて、持続可能な社会の実現に興味を持ち、環境学部にて専門知識をさらに深めたいと考えるようになった。
■貴学の公共政策学部に入学することで、ボランティア活動を通じて体感した地域課題の解決方法を体系的に学び、実際の政策立案に活かしたい。
など、入学後の学びや大学が求める人物像が、それまでの活動とどう関連しているかを明確にアピールすることが重要です。
アピールのバランスを取る
ボランティアでの経験をアピールする際は、自分の実績や成果を強調しすぎないよう注意が必要です。
ボランティア活動は、チームメンバーや協力者との連携によって成立するものです。過度に個人の功績を強調してしまうと、協調性や他者との関係性を軽視しているかのような誤った印象を与えてしまう可能性もあります。
チームでの成果や他者との協力を意識したアピールをすることで、協調性や社会性といった大学が重視する要素も適切に伝えることができます。バランスの取れた表現を心がけましょう。
まとめ
総合型選抜において、ボランティア活動で大学側の評価を勝ち取るには、単なる実績のアピールではなく、活動を通じて得た成長や学び、さらに将来への明確なビジョンまでを含めた一貫性が鍵となります。
どんなに素晴らしい活動実績であっても、それが受験生本人の将来ビジョンと結びついていなかったり、志望大学での深い学びの必要性との繋がりがなかったりすれば、大学側からの評価には至らないでしょう。
逆に、目立った実績がなくても、活動を通じた一連の経験が貴重な学びや気づき、将来のビジョン形成に大きな影響を及ぼし、その上でさらに深い学びへの意欲がアピールできれば、高い評価を受けられる可能性が高まります。
ボランティア活動を受験のための形式的な実績作りと捉えず、自身の成長と将来の目標をつなぐ貴重な経験として位置づけることこそが、総合型選抜での成功に繋がります。本記事で紹介したポイントを意識しつつ活動に向き合うことで、大学側にあなたの意欲や適性を強くアピールすることができるはずです。ボランティア活動をどのように活かすかをより詳しく理解したい場合は、総合型選抜の対策として個別指導を活用するのもよいでしょう。