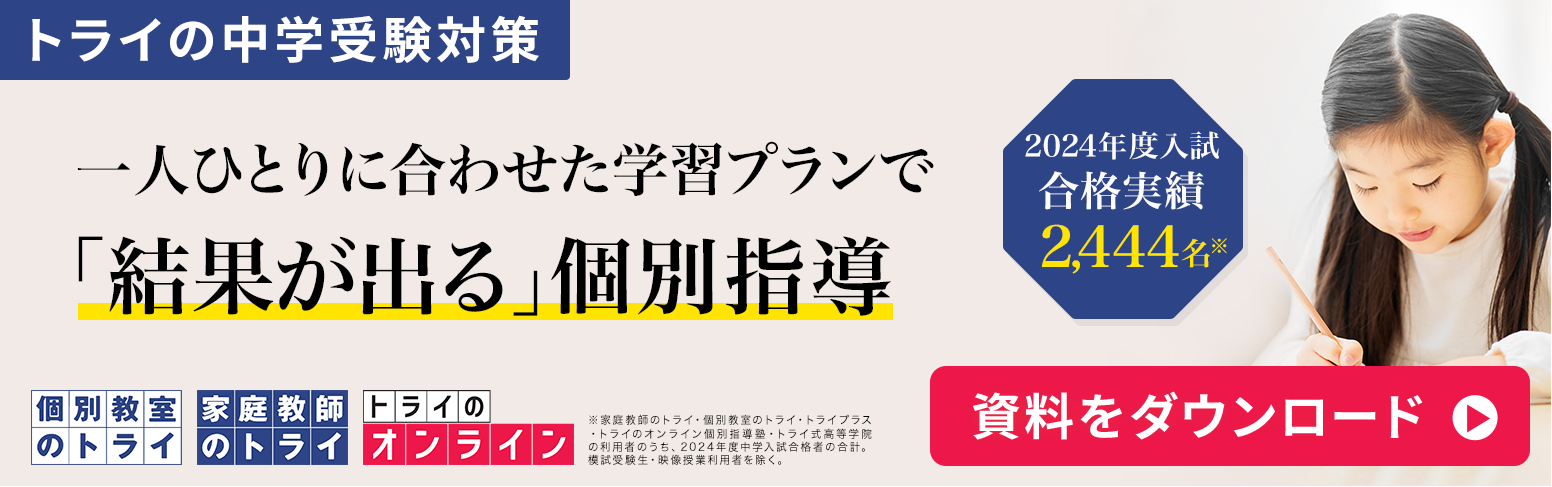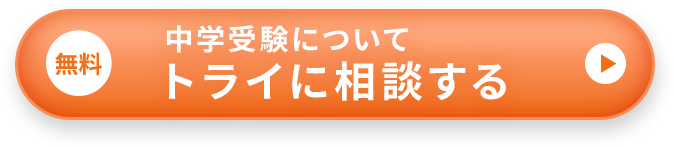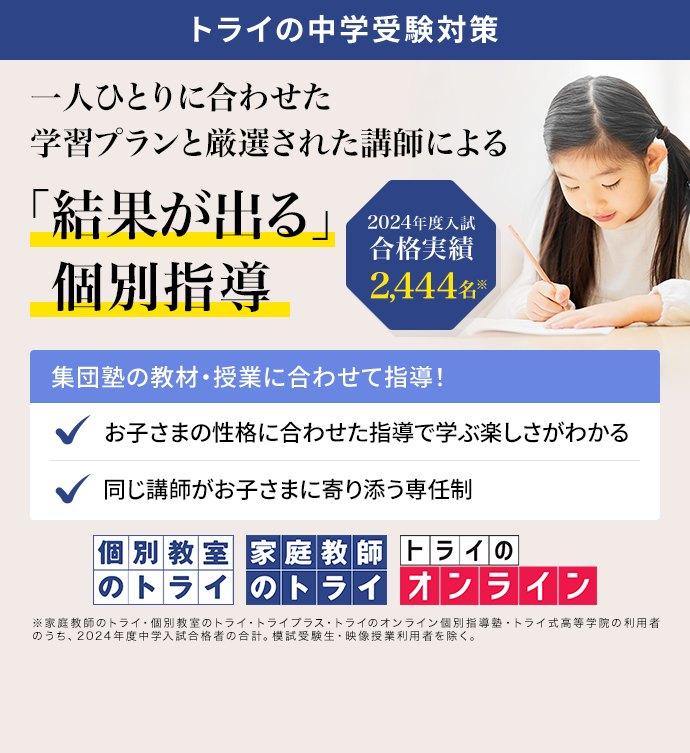中学受験塾のグノーブルで「偏差値が上がらない」と悩んでいる場合、学習方法を見直すと偏差値が上がる可能性があります。偏差値が上がらないと、志望校への合格判定が振るわず不安に思ってしまう保護者様も多いことでしょう。この記事ではグノーブルで偏差値が上がらない場合の原因と、保護者様が気に掛けるべき対策について解説していますので、参考にしていただけますと幸いです。
グノーブルにおける偏差値の役割と確認方法
中学受験における偏差値とは?
まず中学受験において、偏差値がどのような役目を果たしているかを知っておくと、偏差値への対策が見えてきます。中学受験に限らず、試験の偏差値とは「平均点を偏差値50とした場合の、自分の点数の位置」を示すものです。平均点が70点のテストならば70点が、平均点40点のテストならば40点が、それぞれ「偏差値50」となります。偏差値には特殊な計算方法がありますが、一例として、平均点70点のテストで100点を取った場合は、偏差値が65程度と判断できるでしょう。お子さまの偏差値を見ると、そのテストを受けた子どもたち全体のなかでのお子さまの立ち位置がわかります。偏差値65はトップクラスの成績です。一方、偏差値が50を下回れば、平均点以下の成績で努力が必要と判断できます。
グノーブルで偏差値を確認する方法
グノーブルで偏差値を確認する方法は複数あります。例えば、約1ヶ月に1回の頻度で行われているグノレブと呼ばれる試験では、偏差値の算出があるため、塾生全体の中でお子さまがどの立ち位置にいるのかがわかるでしょう。またグノーブルではいくつかの全国模試や、SAPIXが実施するサピックスオープンといった外部模試も採用しており、これらの試験結果でも偏差値を見ることができます。
グノーブルで偏差値が上がらない原因5つ
基礎力がついていない
グノーブルに通っているのに、偏差値が上がらない場合、基礎力がしっかりついていないのかもしれません。グノーブルは、毎回の授業で新しいオリジナルのテキスト「GNOラーニングN授業」を受け取る形式です。次の授業では、前回の復習を簡単に行うだけで新しいテキストに進んでしまいます。1回の授業の中で理解しきれなかった場合、次の授業までに対策を行わなければ、わからないままで各種のテストを受けざるを得ず、偏差値が下がる原因となるでしょう。
応用問題への取り組みが足りていない
偏差値を上げるためには、基礎力を固めることも大切ですが、応用力も伴わなければなりません。グノーブルで採用されている、グノレブや模試といった偏差値に関わるテストは、すべて基本問題から応用問題までが出題されるためです。ところが応用問題は難易度が高いため、日頃の学習でつい敬遠される傾向にあります。苦手科目の応用問題ともなれば、とりあえず後回しにして得意科目を勉強しようというお子さまもいるでしょう。家庭学習をしているけれど、偏差値が上がらないという場合は、応用問題にどの程度取り組めているかに注目してみることをおすすめします。
宿題が終わっていない
偏差値は上がらないけれど、家では何だか余裕のそぶりを見せている、というお子さまは、グノーブルの宿題が全て終えられているかを確認してみましょう。特に宿題の進め方をお子さまに任せている場合は、家庭学習の量が全体的に足りておらず、宿題が終わっていない可能性があります。グノーブルでは季節講習の時期を除き、ブロックやクラスを問わず大量の宿題が出されます。宿題を終えるには、目安で毎日1~2時間以上が必要です。授業で使われるメインのテキスト「GNOラーニング」はもちろん、各科目で渡される復習用のテキスト、基礎力テスト、漢字ドリルなどに取り組めているかを、保護者様が確認する必要があるでしょう。とはいえ、仕事や家事、他のお子さまの育児などでなかなか勉強を見てあげられないというご家庭は多いものです。このような場合、宿題の量や内容をお子さまに合ったものに細かく調整し、かつ進度も講師に丁寧に見てもらえる、個別指導の利用も検討してみると良いでしょう。
グノレブで点数が取れていない
偏差値が上がらないことで悩んでいるときは、グノレブの点数を見てみましょう。偏差値は平均点との差によって算出されるため、周囲の子どもたちの成績によっても上下する数値です。偏差値が多少低くても、正答率自体が高く点数が取れているのであれば、現在の学習方法にひと工夫するだけで偏差値が上がる可能性もあります。しかし、1ヶ月分の復習テストであるグノレブで点数が取れていない場合、在籍クラスの授業についていけていなかったり、学習方法が誤っていたりするケースも考えられるでしょう。次項で偏差値を上げる方法も解説しているので、参照しながら、学習方法を修正してみましょう。
他の子の学力が高い
前述のとおり、偏差値は同じテストを受験した子どもたちの平均点を基準とした数字です。したがって、お子さまの点数が伸びていたとしても、そのテストを受験した他の子どもの点数も伸び、平均点が高ければ、偏差値は上がらないという結果になります。したがって、お子さまの学力の伸びを見るならば、偏差値だけではなく純粋に点数が取れているかどうかにも合わせて注目しなければなりません。前回のグノレブに比べて、今回はどうだったのか、お子さま自身が獲得した成果にもぜひ注目してください。保護者様は、偏差値が周囲の子どもの状態によっても左右されることを念頭に置き、偏差値の上下で一喜一憂しないことが大切です。
グノーブルで偏差値を上げる方法
解説動画を積極的に利用する
グノーブルの大きな特徴として、通塾生には授業の解説動画を公開していることが挙げられます。授業の復習を行う際は、解説動画を積極的に利用し、次の授業までに、前回の授業における疑問点を解消しておくことが大切です。ただ、お子さまはまだ小学生ですから、一人で勉強していても、自分が内容を理解できているのか、いないのかがわからないことがあります。動画を視聴するのが面倒に感じられると、視聴せずに自分一人で頑張ってしまい、つまずきを解消できないことも多く、保護者様がよく様子を見ながら、理解度が不足している項目について動画視聴を補助してあげる工夫が必要です。
わからないところは講師へ質問に行かせる
時折、解説動画を見てもお子さまが単元を理解しきれないことがあります。この場合、積極的に講師へ質問をしに行かせましょう。実は、中学受験の問題の中でも難易度が高いものは、保護者様自身が理解できていても、お子さまが理解できるほど噛み砕いて解説するのは難しいことがあります。またお子さまにも、相手が親であるという甘えや、理解できないイライラがあるため、学習の時間に保護者様に口を出されるとモチベーションが落ちてしまうこともあるのです。したがって理解が難しいと思われる問題については、講師へ質問に行かせる方が確実でしょう。
「G脳ワークアウト」に時間をかける
グノーブルでは授業で使用するテキストとは別に、ほぼ毎週、G脳ワークアウト(グノワークアウト)と呼ばれる算数の問題集が配布されます。この問題集は、グノーブルで約1ヶ月前に学習した内容が掲載されたものです。習ってから期間が空いているため、ほぼ忘れていたことがあってもG脳ワークアウトに取り組めば思い出し、知識を定着させることができます。お子さまの中には、授業で習う範囲からは逸脱していると認識してG脳ワークアウトに時間をかけないケースも見られますが、応用問題や入試問題も掲載されるG脳ワークアウトに取り組めるかどうかは、算数の点数や全体の偏差値を大きく左右するでしょう。
グノレブで点数が取れるようコンスタントに学習を続ける
偏差値を上げたいなら、直近1ヶ月間の復習テストであるグノレブで点数が取れるよう、コンスタントに学習を続けることが欠かせません。グノレブの点数を上げるには、前の授業の復習だけではなく、4週間前の授業にまでさかのぼっての復習が効果的です。1ヶ月が経過すると、記憶が徐々に薄れていくため、せっかく習った解き方を忘れてしまうこともよくあります。グノレブの試験範囲を意識した復習で、グノレブの点数を上げられるでしょう。さらに1ヶ月が経過した頃の学習で解き方が定着すれば、他団体が開催する模試などでもよい成績が取れ、結果として偏差値が上がることが期待できます。
子どもの努力を褒める
偏差値が上がらないと、保護者様がお子さまの努力を疑ってしまう可能性があるでしょう。しかし、グノーブルは子どもたちの学力が全体的に高い学習塾です。そのなかで学習を続けているお子さまは、必ず何かしらの努力をしていることでしょう。偏差値を上げたいなら「偏差値が下がった」「もっと勉強しなさい」と言うよりも、保護者様がお子さまの努力を見つけ、褒めるほうが効果的です。
夜遅くまで学習し過ぎない
グノーブルはどのクラスでも宿題が非常に多いことで知られており、中には宿題が終わらないという理由で夜中の0時を回るまで勉強をしているお子さまもいます。しかし、睡眠リズムが崩れると昼間の脳のパフォーマンスが落ちてしまうため、グノーブルの授業中に頭が回りきらず、授業の理解度も下がるでしょう。夜も眠いなかで、理解度の低いまま宿題に取り組むため、時間がかかるばかりで進まない、ということになりがちです。結果として、早寝早起きをしているお子さんのほうが、遅く寝て睡眠時間の短いお子さんよりも偏差値が上がり、上のクラスに振り分けられるといったケースも出てくるでしょう。いかに宿題が大量でも、睡眠時間をしっかり確保することを優先し、その後で学習スケジュールを立て直すことをおすすめします。
まとめ
グノーブルで偏差値が上がらない場合は、睡眠時間を含めた学習計画を丸ごと見直してみると良いでしょう。また偏差値だけではなく、テストの点数そのものがどう推移しているかに注目すると、お子さまが伸びているのか、そうでないのかがわかりやすくなります。偏差値も上がっていないが、テストの点数も上がっておらず、実際にお子さまが伸び悩んでいるように見える場合は、進みの速い集団塾のスタイルにお子さまが合っていないのかもしれません。偏差値が上がらない、偏差値が下がる、宿題が終わらない、保護者様が多忙のためお子さまの学習をしっかりと確認するのが難しい、といった場合は、専門の講師が丁寧に指導を行う個別指導のご利用もぜひご検討ください。