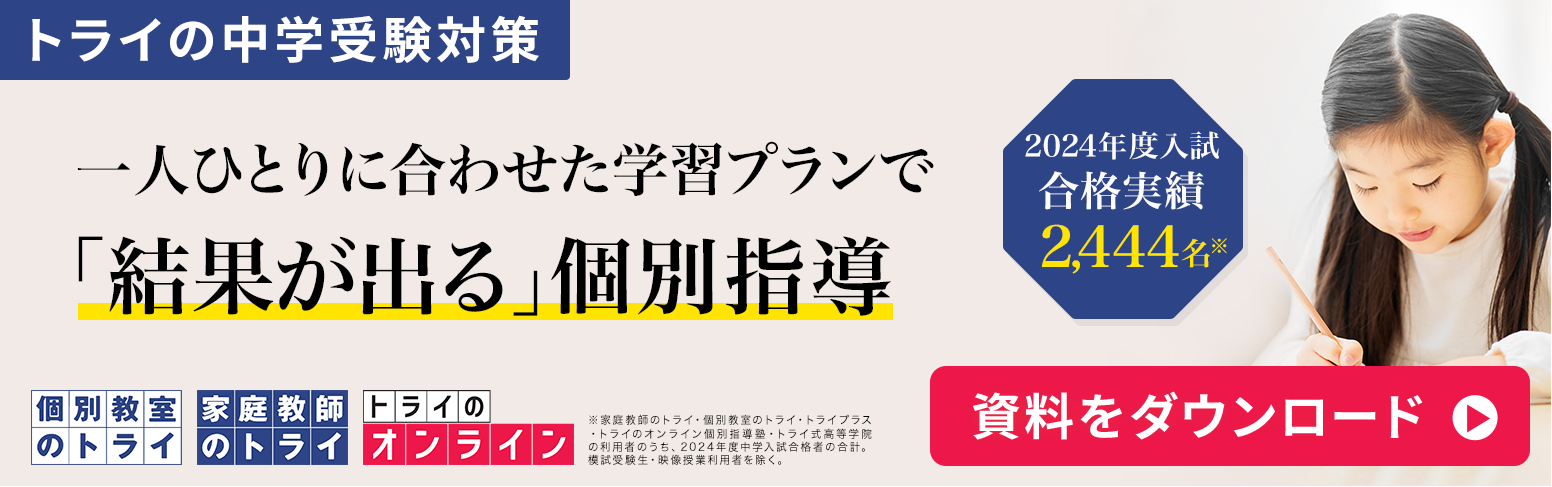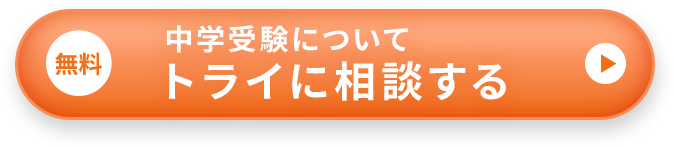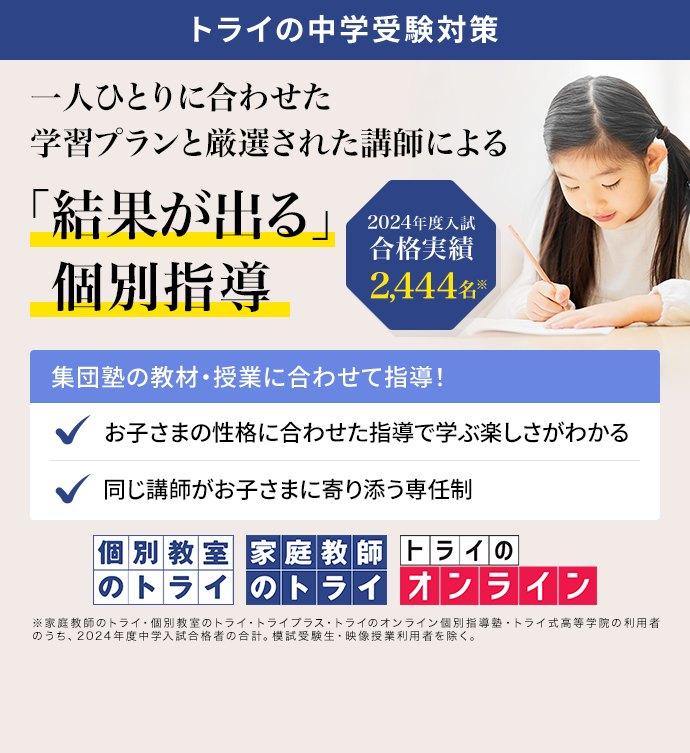中学受験において、算数は最も重要な科目のひとつとされています。
「算数が苦手でいつも足を引っ張っている」「塾に通っているのに成績が伸びない」など、お子さまの成績にお悩みの方はいらっしゃいませんか。
この記事では、最新の出題傾向を踏まえた上で、算数を「いつ」「どのように」受験対策すればよいか、具体的にまとめています。
算数で差がつく。必ず受験対策をしなければならない理由とは
他の科目に比べて算数は受験生の得点に差がつきやすい科目です。
実際に、各学校の合格者平均点と受験者平均点を比較すると、算数で最も差が出る傾向があります。
つまり、入試とは「算数でどれくらい点数を取れるのか」、言い換えると「いかに算数の受験対策をしてきたのか」が問われる場と言っても過言ではないのです。
ここでは、受験対策をする意義を再確認するために、算数で差がつく理由をまとめています。
理由① 小学校の勉強だけでは不十分だから
中学受験の算数は、小学校で習う基本的な知識を身につけていることを前提に、高度な計算と思考を駆使した問題が出題されます。
また、つるかめ算や旅人算など、特殊算と呼ばれる中学受験ならではの解法が数多くあり、これらは小学校の教科書には載っていません。
つまり、入試で合格するためには、小学校の授業とは別に、中学受験に向けて特別に対策をしなければならないのです。
理由② 本質を理解していないと得点できないから
中学受験の算数は、公式を当てはめれば解けるような単純な問題が少なく、多くが応用の文章題になっています。
このため、入試で得点するためには、初めて見る問題であっても、文章から必要な情報を抽出して、どのように解けばよいか判断する力が必要となります。
公式や解法を覚えるだけでなく「どうしてこの解き方をするのか」という本質を理解するためには、時間をかけて算数の勉強に取り組まなければいけません。
受験対策をする前に知っておきたい。算数の出題傾向とは
中学受験の算数は小学校で習う基本的な知識や、単なる公式の丸暗記では歯が立たないため、受験勉強をして応用力をつけていかなければなりません。
このため、算数は4科目の中で最も難しい科目であると言えるでしょう。
しかも、算数の難易度は年々上昇している上、時間制限も厳しさを増しています。
ここでは、正しく受験対策をするために、算数の出題傾向をまとめています。
まずは算数の出題形式をおさらい
算数の出題は学校ごとにさまざまで「必ずこの単元は出題する」という学校もあれば、「毎年どの単元を出題するかわからない」という学校もあります。
ただし一般的には、図形、割合、比、速さなど、小学生が苦手としやすい単元が、多く出題される傾向にあります。
また、問題数は大問が5つ前後であることが多く、大問の中にいくつかの小問が構成されていることが多いです。
なお、小問は互いに関連しているため、一つのミスが大量失点につながる可能性があり、注意が必要です。
最初の大問は、公式を覚えていれば解けるような、基本的な計算問題や一行問題が出題されやすいため、ここでの失点は絶対に避けましょう。
全体を通して見ると、算数は学校ごとに対策すべき事項が異なる上、難易度が高く制限時間も厳しい科目であると言えます。
新しい出題傾向① 問題文が長い
算数の大問の多くは文章題の形式になっていますが、近年は問題文が長くなっている傾向があります。
問題文が長くなっているということは、考慮すべき情報が増えることを意味するため、長ければ長いほど解くために必要な処理が増えていきます。
つまり、近年は問題文が長くなることで、より複雑で難易度が高い問題が出題される傾向が生まれてきているのです。
新しい出題傾向② 記述形式の増加
例年の算数における記述形式の解答とは、途中式を問う問題が一般的でした。
しかし、近年はある事柄について「なぜそうなるのか」という理由を説明させる記述問題も見られ始めています。
このような問題は、公式や解法を「覚えているか」ではなく、一歩踏み込んで「理解しているか」を問いているため、小学生にとって非常に難解です。
さらに、一定の長さの論理的な文章を書くためには時間を要するため、もともと厳しい算数の制限時間を圧迫することになります。
算数の受験対策は、いつから、どのような受験対策をすべきなのか
算数は難解な問題が多く、受験生の得点に最も差がつく科目です。
しかも、近年は難易度が上昇し、時間内に解ききることすら困難なケースもあります。
このことから、入試で合格するためには、受験対策を徹底し、算数の苦手を克服することが重要であると言えるでしょう。
ここでは「いつ」「どのように」受験対策をすべきなのか、具体的に解説しています。
保護者様ができる対策もまとめているので、ぜひ参考にしてください。
いつから対策をするべきか
繰り返しになりますが、中学受験の算数は、解き方を暗記しているだけでは得点できません。
難しい公式や解法の本質を理解して使いこなせるようになるには、勉強の積み重ねが不可欠です。
算数の成績が上がるまでには時間がかかるので、できるだけ早くから受験対策に取り組むように心がけましょう。
多くの塾では新4年生(3年生の2月)から受験に向けた学習が本格化するため、遅くてもこの時期までには入試を意識した対策を始めるようにしてください。
次に、具体的にどのように算数の受験対策をすべきか、順を踏んで具体的に説明します。
ステップ① 計算力をつける
文章題であっても、図形であっても、算数の問題を解くためには必ず計算をしなければなりません。
算数の基礎は計算力であると考え、受験対策をする際は計算練習からスタートしましょう。
計算力をつけるためには、一度に大量の勉強をするのではなく、毎日少しずつ計算問題を解く習慣をつけてください。
具体的には「朝食の前は計算練習」「学校から帰ったら計算練習」など、日常の動作とセットで行うと習慣化しやすいです。
さらに、お子さまの習慣ができあがるまでは、保護者様が「計算練習の時間だよ」と声を掛けてサポートをすると効果的です。
なお「計算は正確さだけでなくスピードも大事」と考えて、計算練習で初めから時間制限を設ける方がいらっしゃいますが、この方法はおすすめできません。
計算力が十分についていない状態で時間を意識すると、焦って途中式を省略したり筆算を書かなかったりして、ケアレスミスが多発します。
雑な計算は癖になってしまうため、初めのうちは時間がかかっても、丁寧に計算練習をするように心がけましょう。
【保護者様ができること】
- 計算練習の時間を決める
- 「計算練習はした?」と声掛けする
ステップ② 繰り返し復習して定着させる
算数はどの単元も小学生にとって難解であるため、一回の学習ですべて理解しきることは困難です。
塾に通っていると、毎週のように新しい公式や解法を習うことになりますが、忙しくてつい授業を「受けっぱなし」にしていないでしょうか。
新しい算数の知識を身につけるためには、最低でも3回は復習する必要があります。
例えば「塾から帰ったらその日のうちに1回目の復習、3日後に2回目の復習、テスト前に3回目の復習」というように、時間を置きながら同じ内容を3度繰り返し演習しましょう。
繰り返すうちに理解が深まり、初めはわからなかった問題も自力で解けるようになれば、復習は成功です。
なお、問題集を使って受験対策をする場合も考え方は同じで、あれこれ色々な問題集に手を付ける勉強法は逆効果です。
問題集は基本的に一つに絞り、何周も繰り返し解くことで、確実に知識を身につけるようにしましょう。
【保護者様ができること】
- 家に帰ってきたら「今日はどういう勉強をしてきたの?」と声掛けする
- 丸付けをして、正しく復習ができているか確認する
ステップ③ 苦手な単元を底上げする
算数の成績が伸び悩んでいるお子さまの多くは、算数全体というよりも、比や図形など、ある特定の単元が足を引っ張っていることが多いです。
入試では全ての大問で点数を取らなければならないため、6年生の夏休みまでには苦手な単元をなくせるように対策しましょう。
苦手対策の第一歩は、お子さまがどの単元でつまずいているのか特定することです。
模試の成績を振り返ったり、塾の講師にヒアリングしたりして、保護者様が率先して苦手単元の洗い出しをしてください。
また、小学生の子どもは一度「できない」や「嫌い」と感じると、どんどん苦手意識が強まってしまう傾向があります。
苦手な単元を勉強する際は、基本的な問題から着手して、解ける体験をさせてあげることが重要です。
例えば「比でつまずいている場合は、割合もしくは分数の計算からおさらいする」というように、お子さまの理解度によっては、前学年、前々学年の問題を用意しても構いません。
お子さまが無理なく解答できる問題から少しずつレベルを上げていくことで、知識の穴埋めができるだけでなく、算数に対する自信が生まれるでしょう。
【保護者様ができること】
- 苦手単元の洗い出し
- 苦手単元に取り組んでいる姿勢を褒める
ステップ④ 本番を意識して演習する
算数は学校毎に出題傾向が異なるため、過去問を解きながら志望校ごとに対策を練る作業が不可欠です。
第一志望は6年生の9月から最低でも4~5年分、第二志望以降は11月から最低でも2~3年分は演習するようにしましょう。
過去問を解く際は「頻出単元はどこか」「基本的な問題と難問の割合はどれくらいか」「記述問題はあるのか」「制限時間内に解ききれるのか」などを確認することが重要です。
また、冬までには本番と同じように時間を計り、大問ごとにどれくらいの時間を掛ければよいのか作戦を立ててください。
お子さまによっては、思うように点数が取れず、落ち込んでしまうことがあるかもしれません。
本番に悪いイメージを抱かないように、保護者様は「間違えた単元は今から復習すれば間に合うよ」などとポジティブな声掛けを意識するとよいでしょう。
【保護者様ができること】
- 志望校の出題傾向をまとめる
- 前向きになれる声掛けをする
「やっているのに伸びない」間違った算数の受験対策と解決策
「算数の勉強に多くの時間を割いているのにもかかわらず、成績が全然伸びない」「算数の才能がないから志望校を諦めるしかない」とお悩みの方はいらっしゃいませんか。
算数が伸び悩む原因は才能の有無ではなく、正しい勉強ができていないことにあります。
ここでは、間違った勉強方法を紹介しますので、お子さまに該当する例がないか確認してみてください。
間違った勉強法① 「わかった」で勉強をやめてしまう
お子さまが授業についていけているにもかかわらず模試では成績が悪くなる場合、「わかった」と思ったら勉強をやめてしまっている可能性があります。
例えば、授業を聞いて講師が話している内容がわかると演習をしなかったり、間違えた問題の解説を読んで「なるほど」と納得するだけだったりすると、実際に解こうと思った時に「解き方はイメージできるのに答えが出せない」という状況に陥ってしまいます。
算数で点数を取るためには、自分で手を動かして答えを導き出さなければなりません。
どんなに「わかった」と思っていても、授業で習った知識は必ず家庭で演習をして、自力で解けることを確認するようにしましょう。
間違った勉強法② わかる問題ばかり解いている
小学生の子どもにとって、できないことを直視するのは大変つらい作業です。
特に傷つきやすいお子さまの場合、わからない問題に挑戦することを避け、好きな単元や正解できる問題ばかり解いてしまう傾向があります。
このような勉強の癖がつくと「正解の丸がつく=勉強がはかどっている」と考えて、わからない問題に出会うと「時間がもったいない」とすぐに諦めるようになってしまいます。
当然のことですが、わかる問題ばかり解き続けていても成績は上がりません。
「わからない問題は伸びしろ」と前向きに捉えて、少しずつできないことに向き合う力をつけていくようにしましょう。
間違った勉強法③ 応用問題ばかり解いている
わかる問題ばかり解きたがるお子さまがいる一方で、知的好奇心が旺盛なお子さまの場合、基礎を無視して応用問題ばかり解いてしまう傾向があります。
難しい問題を解きたいあまり「基本問題は簡単すぎてつまらない」「公式や解法を当てはめれば解けるから、計算は省略しよう」などと地道な努力を怠ってはいませんか。
特に算数が得意なお子さまが、学習内容が比較的わかりやすい4、5年生の間にこのような勉強法を癖づけると、6年生になった途端、今までコツコツ努力してきた同級生に追い抜かれるようになります。
遠回りのように見えますが、算数の成績を上げるためには、基本問題や計算練習など基礎を積み上げることが何よりも大切なのです。
困った時は個別指導が選択肢の一つ
お子さまが間違った勉強法をしている場合、取り組み方を大幅に変えない限り、算数の実力をつけることはできません。
しかし、一度間違った勉強が癖になってしまうと、保護者様の働きかけで正すことは困難です。
「ちゃんと塾の復習をしなさい」「苦手な単元もやりなさい」「基本問題を解きなさい」とあれこれ声掛けしてもお子さまが拒絶するばかりで、親子どちらにもストレスが溜まってしまいます。
そんな時におすすめの解決策が、個別指導の利用です。
個別指導なら、お子さまのつまずきの原因にあわせてマンツーマンで受験対策をするため、算数の成績を着実に上げることができます。
「文系だから算数の苦手は仕方ない」「どうせもう間に合わない」とあきらめる前に、まずはプロの講師を頼ってみてください。
【個別指導のメリット】
- 講師がつきっきりで指導するため、集中して取り組める
- わかるまで質問できる
- お子さまのつまずきの原因を突き止められる
- お子さまの学力に応じてオリジナルのカリキュラムで勉強できる
- 志望校の出題傾向に基づいた課題に取り組める
- 過去問の対策ができる
一人ひとりに合った受験対策をして、算数で差をつけよう
いかがでしたでしょうか。
算数は入試で差がつく科目であるため、必ず受験対策をしなければなりません。
算数の勉強は、計算練習や塾の復習、苦手克服など、どれも定石通りのものばかりです。
しかし、お子さまの多くは間違った勉強法が癖になり、成績が伸び悩んでしまっています。
「やっているのに成績が伸びない」と感じた際は、家庭で抱え込まずに、個別指導の利用を検討してみてください。