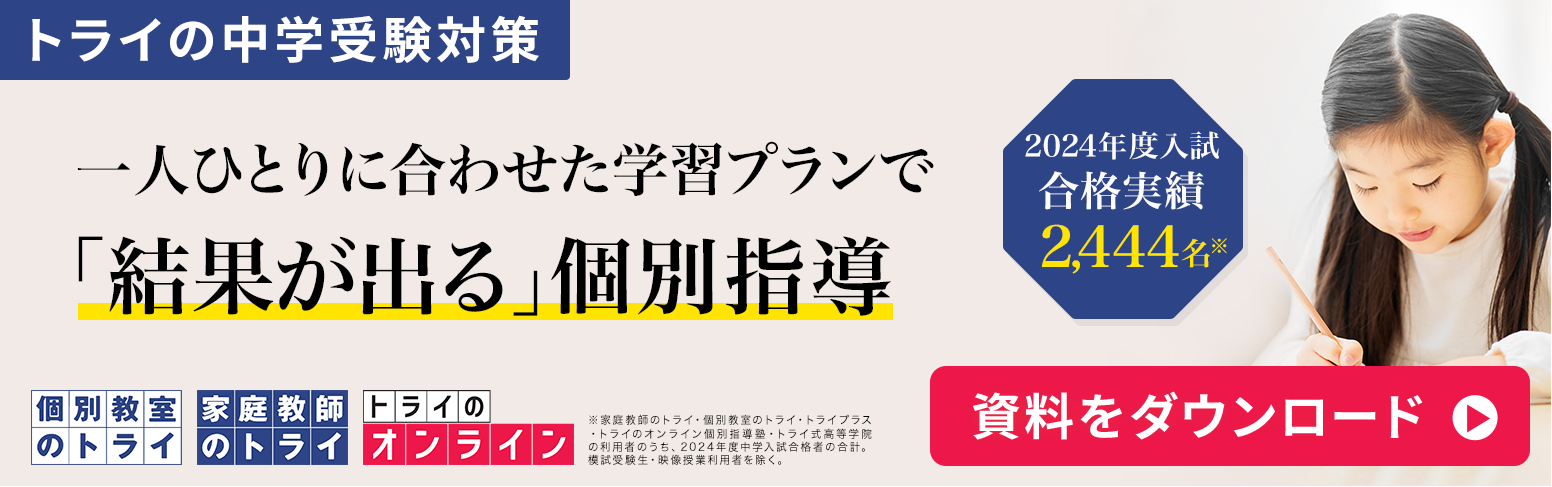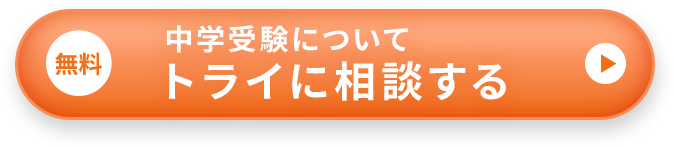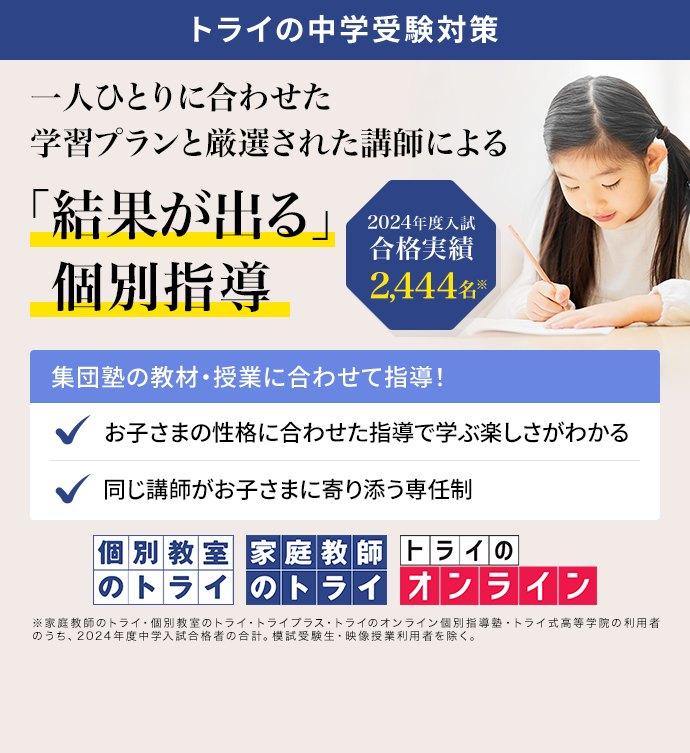中学受験の国語は、他の科目に比べて勉強方法がわかりづらく、対策が難しいように感じられます。
「塾に通っているのに成績が伸びない」「テストによって点数に波がある」など、お子さまの国語の成績にお悩みの方はいらっしゃいませんか。
国語は正しく対策をすれば、しっかりと成績を伸ばせる科目です。
この記事では、最新の出題傾向を踏まえた上で、正しい国語の勉強法を具体的にまとめています。
お子さまがやってしまいがちなNG勉強法も紹介しているので「何をやっても国語がうまくいかない」とお困りの方も、ぜひ参考にしてください。
国語は受験対策をすれば伸びる。中学入試における国語の特徴
国語に時間を割いているにもかかわらず点数が伸びないと、「センスがないから成績を上げるのは無理だ」と考えて、多くのお子さまが勉強をあきらめてしまいます。
しかし、国語は合否に直結する重要な科目である上、センスで解くものではありません。
ここでは、受験対策をする意義を再確認するために、知っておきたい国語の特徴をまとめています。
国語は重要な科目
受験勉強では重要科目の算数や、点数が上がりやすい理社が重視され、国語の対策は後回しにされがちです。
しかし、国語は合否を左右する非常に重要な科目です。
まず、国語は算数と同等に配点が高い上、記述問題を中心に一問ごとの得点も高いという特徴があります。
例えば1問10点の読解問題でミスをすると、比較的配点が低い理社で、他の受験生が間違えた問題を5問以上正解しなければ埋め合わせができません。
また、国語は多くの学校で入試時間割の一限目に設定されているため、国語のでき映えが悪いと、気持ちが乱れてその後の科目の成績に悪影響を及ぼします。
さらに、読解力が低いと他の科目でも問題文を正しく理解できないため、ケアレスミスが頻発してしまいます。
つまり、国語のつまずきを放置すると、どんなに他の科目の勉強をがんばってもカバーしきれず、総合点でライバルに競り負ける恐れがあるのです。
国語にまつわる誤解
「国語の成績向上には読書習慣とセンスが必要」と考える方がいらっしゃいますが、実はこの認識は正しくありません。
中学受験の国語は、文章を正しく読み、根拠を持って論理的に解答する力を問う科目です。
もちろん読書をすると活字に慣れるため、国語を解く上で有利です。
しかし、趣味で本を楽しく読む行為と、テストで文章を読む行為は、同じ「読む」でも全く異なるため、読書習慣があるからといって必ずしも国語が得意になるわけではありません。
また、本が好きなお子さまの中には「読書しているから国語のセンスがある」と考え、感覚的に問題を解く方がいらっしゃいます。
しかし、感覚で解く癖がつくと、論理的に考えるトレーニングがおろそかになり、次第に成績が伸びなくなります。
このため、普段から読書をしていたとしても、国語の成績を伸ばすためには受験対策が必要不可欠なのです。
逆に言うと、国語は勉強すればセンスに左右されず、誰でも成績を伸ばせる科目であるとも言えます。
受験対策が必須。国語の最新出題傾向とは
繰り返しになりますが、中学受験の国語で問われているのは、センスや直感ではなく、文章を正しく論理的に読み解く「読解力」です。
さらに、近年の入試では読解力はもちろんのこと、速読力や思考力など多様な力が求められるようになってきています。
正しい受験対策をするために、ここで国語の最新の出題傾向を確認しましょう。
まずは国語の出題形式をおさらい
一般的に、国語の入試は知識問題と文章問題で構成されています。
知識問題は学校によって出題範囲や形式が大きく異なりますが、国語全体の1〜2割程度の配点であることが多く、漢字が頻出です。
一方で、文章問題は多くの学校で説明的文章(説明文・論説文など)と文学的文章(物語文・随筆など)の1題ずつが出題されます。
そして、近年の文章題では、新しい傾向が見られるようになっています。
新しい出題傾向① 文章量が多い(速読力が必要)
近年は文章の量が増えており、設問の選択肢も長文化しています。
国語の入試時間(50分)に読む文字数は、平均して6,000字、難関校だと10,000字以上にのぼります。
このため、受験生は文章を正しく読解することはもちろん、情報を取捨選択してすばやく要旨をつかめるように、速読力もつけていかなければなりません。
新しい出題傾向② 自分の意見を書く問題(思考力・表現力が必要)
「文章中の言葉を使って書きなさい」という形式の記述問題はいまも頻出ですが、近年は「文章を参考に自分の意見を書きなさい」という問題が増えています。
この設問に答えるためには、文章の内容を理解した上で、自分の意見を考え、他者に伝わるように書き上げなければなりません。
つまり、読解力に加えて思考力、表現力が無ければ、何を書けばよいのかわからず、まったく点数が取れない仕組みになっているのです。
新しい出題傾向③ 初見では驚くような目新しい問題(応用力・対応力が必要)
近年の国語の入試では、受験生が驚いて手を止めてしまうような、趣向を凝らした問題が出題されています。
例えば、グラフの読み取りや計算が必要な教科横断型の問題や、「この先の話を自分で考えて書きなさい」といった創造性が問われる問題、マーケティング・広告など身の回りの社会への興味関心が問われる問題などが見受けられます。
このような目新しい問題を解くためには、応用力と試験本番で常に冷静でいられるような対応力が不可欠です。
国語を伸ばすためには、いつから、どのような受験対策をすべきなのか
近年の中学受験の国語は、文章を正しく理解し論理的に解釈する読解力はもちろんのこと、速読力や思考力、表現力など、いわば総合力がないと解けないような問題になっています。
このため、国語の成績を伸ばすためには、センスの有無にかかわらず、勉強して正しい解き方を身につけなければなりません。
ここでは「いつ」「どのように」受験対策をすべきなのか、具体的に解説します。
いつから対策をするべきか
読解力や思考力が問われる国語は、成績が上がるまでに時間を要する科目です。
このため、国語の受験対策をはじめる時期は、早ければ早いほど有利になります。
多くの塾では4年生(3年生の2月)になると受験に向けた学習カリキュラムがはじまるため、難関校を目指す場合は、この時期までに国語の対策を始めることをおすすめします。
【受験対策 初歩編】活字に慣れる(4年生になる前)
4年生になる前のお子さまや、国語が苦手なお子さまの場合、まずは活字に慣れる必要があります。
具体的には、読書を習慣化することをお勧めします。
いきなり難しい本を渡すと拒絶反応が起きてしまうため、短い物語やお子さまが興味を持てる本、新聞のコラムなどから読みはじめましょう。
ただし、読書習慣はあくまでも活字に慣れるための取り組みであり、本を読むだけで国語の成績が安定することはないため、慣れてきたら次の対策に移ってください。
【受験対策 基礎編①】知識を身につける(4~5年生)
国語の知識分野は漢字や慣用句、ことわざなど覚える量が膨大にあるため、早期から対策をしていきましょう。
知識問題は文章問題よりも配点が低いため軽視されがちですが、覚えれば覚えた分だけ点数が取れるため、対策を怠るとその分ライバルと差がついてしまいます。
また、知識問題の対策をしないと語彙が増えないため、文章問題を解いていても誤読やタイムロスが発生してしまいます。
特に近年は文章が長文化しているため、読む速度を上げるためにも語彙の強化は不可欠です。
【知識を身につける方法】
- 毎日時間を決めて、コツコツ覚える習慣をつける
例:毎日学校に行く前の10分間で、漢字を20個覚える
- 覚えた後は何度もテストをして、確実に暗記できるまで繰り返す
例:夜寝る前にその日覚えた知識、日曜日にその週覚えた知識、月末にその月覚えた知識をテストする
- 覚えられない単語は暗記カードやノートに書き出す
- わからない単語に出会ったら、辞書で意味を調べる
【受験対策 基礎編②】読解力をつける(4~5年生)
読解力を上げるためには、論理的に読み、根拠を持って答える演習を繰り返す必要があります。
そこで、まずは短めでわかりやすいテーマの文章を使って、正しい読解方法を身につけていきましょう。
【正しい読解方法】
- 説明文はテーマと筆者の主張、物語文は出来事と登場人物の心情の変化を、それぞれ意識しながら読み、該当箇所に線を引く
- 接続詞や言い換え表現、対比構造、場面転換など、文章の理解を助けるポイントに目印をつける
- 設問に答える際は、本文のどこを根拠にしたのかメモをする
正しい解き方が身につき、安定して高得点が取れるようになったら、4,000字程度の長文や抽象度の高い文章などに挑戦してください。
【受験対策 応用編】得点力をつける(6年生前半)
読解力がついたら、1点でも多く点数が取れるように、解答を作り上げる練習をはじめましょう。
実は、国語の解答はある程度型が決まっているため、テクニックを身につければ、誰でも点数を伸ばすことができます。
【選択肢問題のテクニックの例】
- 「あてはまるもの」と「あてはまらないもの」のどちらを聞かれているのか確認する
- 誤った選択肢は、どこが本文と異なっているのか説明できるようにする
- 「必ず」や「全く」などの断定表現がある場合は誤りである可能性が高いため、注意する
【記述問題のテクニックの例】
- 出題者の視点に立って「何を問われているのか」理解する
- 理由を問われていたら「~から。」で終わるなど、問いに応じて文末を決める
- 部分点がもらえる可能性があるため、わからなくても文中から要素を拾って何かしら書く
なお、記述は小学生が苦手意識を持ちやすい問題ですが、近年は思考力や表現力が問われるようになり、記述の重要度が増しています。
最初から完璧な答えを目指さなくてもよいので、何度も繰り返し練習をして、書くことに慣れていくようにしましょう。
【受験対策 発展編】本番を意識して演習する(6年生後半)
6年生の秋からは、本番を意識しながら問題を解いていきましょう。
特に過去問演習は志望校の出題傾向を知るためにも、欠かすことができません。
近年は学校によって、説明文の代わりに詩が出題されたり、自由作文が課されたり、ユニークな問題が増えています。
本番で驚いて手が止まってしまわないように、過去問は数年分用意して、各学校の特徴に慣れるようにしてください。
また、国語は制限時間が厳しく、最後まで解ききるためには時間配分を検討する必要があります。
6年生の冬までには本番と同じように、制限時間内に解く練習を始めるとよいでしょう。
「やっているのに伸びない」間違った国語の受験対策と解決策
国語は正しく勉強をすれば、必ず成績が伸びる科目です。
しかし、国語の勉強方法は他の科目に比べてわかりにくいため、多くの受験生が間違った取り組みをしています。
ここでは「勉強しているのに成績が伸びない」とお悩みの方に向けて、間違った勉強法と解決策を紹介します。
間違った勉強法① 正誤だけを確認する
課題が多すぎて忙しかったり、文章を読むことが嫌いだったりすると、とりあえず問題を解くだけの理解が伴わない勉強をしてしまいがちです。
「文章を漠然と読み、深く考えずに答え、丸付けをして、間違った問題は答えを写すだけ」といった取り組みは、身につくものがほとんどありません。
国語の勉強をする際は集中して読解し、丸付けが終わったら必ず解説を読んで、なぜその解答になるのか確認をしましょう。
間違った勉強法② わからない語彙を調べずそのままにする
中学受験の国語の文章には、小学生の子どもが初めて聞くような言葉がいくつも登場します。
国語が伸びるお子さまは、知らない語彙が出てくると積極的に調べて理解しようとしますが、国語が苦手なお子さまは、わからないまま放置してしまう傾向があります。
初めて聞く言葉や意味がわからない語句は、その場で辞書を引いたり、検索して確認したりするようにしましょう。
間違った勉強法はなかなか直せない。困った時は個別指導が選択肢の一つ
間違った勉強法は他にも数多くあり、例えば「事前課題をせずに塾に通い、解説を聞いている」や「あれこれ問題集に手をつける」「基礎的な読解力がないのに、応用問題に挑戦する」などが挙げられます。
これらの取り組みに共通していることは、形だけの勉強で満足してしっかりと理解していないにもかかわらず、国語ができた気になってしまう、という点です。
間違った勉強法は一度くせになると、なかなかご家庭で直すことができません。
そこでおすすめの解決策が、個別指導の利用です。
個別指導なら、プロの講師とマンツーマンで受験対策ができるため、集中して文章を読解し、疑問点はその場でわかるまで質問して、解決することができます。
【個別指導のメリット】
- 講師がつきっきりで指導するため、集中して取り組める
- わかるまで質問できる
- お子さまのつまずきの原因を突き止めやすい
- お子さまの学力に応じてオリジナルのカリキュラムで勉強できる
- 志望校の出題傾向を踏まえた課題に取り組める
- 過去問の対策ができる
合否に直結する国語。正しい受験対策で得意科目にしよう
中学受験において国語は避けては通れない重要な科目です。
そして、国語の成績を上げるために必要なものはセンスではなく、文章を論理的に読み解く力です。
誰でも勉強すれば必ず成績が上がるので「国語はセンスだから勉強をしても仕方ない」という方は、今すぐ受験対策をはじめてくださいね。
ただし、国語の受験対策は間違った取り組みをすると、やっているつもりで実はほとんど身についていない、という状況に陥ってしまうため、注意が必要です。
「やっているのに成績が伸びない」という場合は、家庭であれこれ試行錯誤するより、個別指導の利用がおすすめです。
国語を得意科目にして、余裕をもって入試本番を迎えましょう。