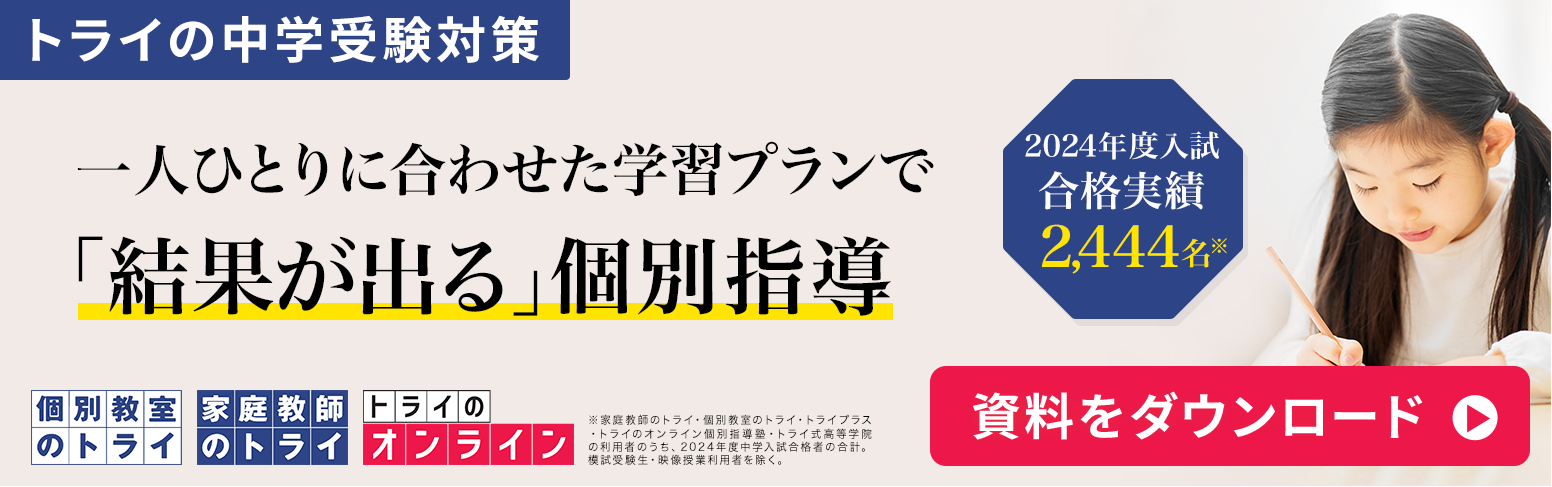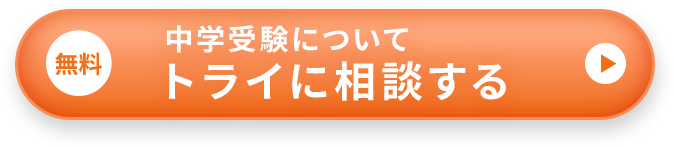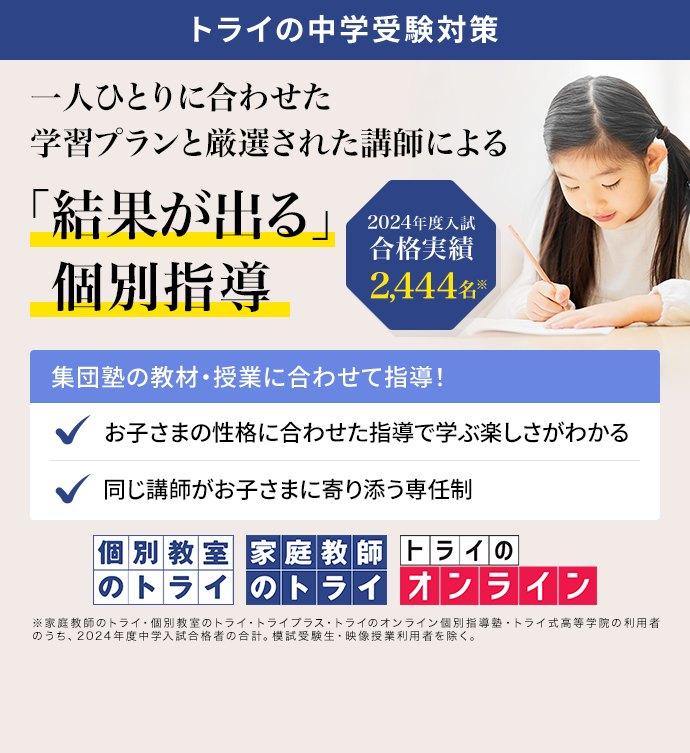受験勉強をしていると、つい社会を後回しにしてしまうこともあると思います。「気付いた時には6年生で社会が間に合わなくなっていた」とお悩みの方は多くいらっしゃいます。
この記事では、社会が間に合わなくなるとどうなるのかを分析したうえで、成績が伸び悩む要因や今後の対策をまとめています。
間に合わないとどうなる?中学受験における社会の特徴
社会の成績不振は、受験において避けるべき事態の一つです。ここでは、中学受験における社会の特徴をまとめながら、社会が間に合わないとどうなるのかについて説明します。
社会の特徴① 知識量で差がつく
中学受験の社会は、地理・歴史・公民の各分野から、万遍なく出題されます。各分野を構成する単元は、地理(日本の地形・産業・気候)、歴史(旧石器時代から現代の日本史)、公民(政治・法律・経済・時事問題)などで、いずれの単元でも広く深い知識が求められます。時事問題から派生して、世界地理や世界史の一部が問われることもあります。
つまり、一般的には、社会は「どれくらい覚えているか」という知識量で差がつく科目だと言えるでしょう。もちろん暗記がすべてではなく、近年は難関校を中心に思考力や読解力を問う問題が増えています。しかし、このような応用問題を解くためにも、前提となる知識は不可欠です。社会を攻略するためには、周囲より一つでも多くの知識をつけるべく、地道に暗記をし続ける必要があるのです。
社会の特徴② 成績が上がりやすい
知識量で差がつく社会は、地道に暗記作業をしなければならない反面、覚えた分だけ伸びる教科であるとも言えます。知識を身につけてさえいれば点数が取れるため、算数のように成績を上げるまでに時間を要しません。しかも、受験当日まで成績を伸ばし続けることができます。
中学受験は1点の差で合否が変わることもあるため、直前まであきらめずに社会の勉強をすれば、合格の可能性がどんどん増していきます。
社会の特徴③ 本番で失敗する可能性が低い
国語や算数は精神状態や問題との相性によって点数がブレやすいですが、社会は知識が定着していれば比較的安定して高得点を狙うことができます。つまり、社会は他の科目に比べて本番で失敗する可能性が比較的低い科目とも言えるのです。
本番の国算で多少失敗してしまったとしても、社会で高得点を取っていれば、補うことが可能です。4科目の総合点を安定させるためにも、社会はしっかりと間に合わせておくべきでしょう。
特徴まとめ 社会が間に合わないと総合点が伸びない
社会は他の科目に比べて暗記が多いため、比較的成績を上げやすく、安定して高得点が出せる科目です。4科目の総合点で競う受験において、得点を固めるのに比較的時間がかからないと考えられる社会が足をひっぱり、国語や算数の努力を台無しにする事態は避けなければなりません。
また、本来成績が安定しているはずの社会で失敗すると、他の科目のミスを埋め合わせできなくなってしまいます。つまり、社会が間に合わないと、4科目の総合点が安定せず、ライバルたちに競り負けてしまう可能性が高まってしまうのです。
当てはまったら要注意。社会が間に合わない具体例とは
4科目で競うためには、社会が間に合わないという局面は、絶対に回避すべきです。では、どのような状況になったら間に合わない可能性が高いのでしょうか。
ここでは、中学受験における社会のカリキュラムを確認した上で、間に合わない可能性があるケースを具体的に紹介します。
中学受験における社会のカリキュラム
多くの塾では、4年生から中学受験に向けた社会の勉強が本格化します。授業は分野ごとに行われ、地理が4年生〜5年生前半のおよそ1年半、歴史が5年生後半〜6年生前半の1年弱、公民は6年生夏前までの3ヶ月程度というカリキュラムが一般的です。
以上のカリキュラムを念頭に置いて、今のお子さまの学習状況を振り返ってみてください。乖離が大きければ大きいほど間に合わなくなる可能性が高くなります。
次の項目で社会が間に合わない具体的なケースを4つ挙げているので、お子さまに当てはまる例がないかチェックしてみましょう。
間に合わないケース① 入塾が遅かった
社会の中でも範囲が広い地理と歴史は時間をかけて繰り返し学習をするため、入塾が遅ければ遅いほど周囲と差がつきやすくなります。例えば5年生から入塾した場合は、地理の学習を繰り返せなくなるため、基本的に1回の授業で全て覚える必要があります。
また、6年生から入塾した場合は、地理を全て自分で覚えた上で、歴史も1回の授業でマスターしなければなりません。社会が趣味でもとから知識がある、暗記がずば抜けて得意などの前提がない限り、入塾が遅かったお子さまは、4年生から勉強していたライバルと知識量に差がついてしまいます。
間に合わないケース② 5年生の夏休みになっても社会が苦手
5年生の夏休みになると、多くの塾で地理のカリキュラムが一通り終了します。この時期になっても社会に苦手意識があるお子さまは、授業で学んだはずの地理の知識が定着していない可能性が高いです。
このままの取り組みを続けると、暗記に対する苦手意識が強まり、歴史と公民も覚えたがらなくなってしまいます。早急に社会の勉強方法を見直して、知識を一つずつ確実に身につけていく必要があります。
間に合わないケース③ 6年生前半の模試で成績が悪かった
6年生前半になると、地理に加えて歴史の授業も終了するため、覚えていないことが多ければ多いほどライバルとの差が大きくなります。この時期に模試の成績が悪いということは、周囲よりも社会の知識量が圧倒的に足りていないことを意味します。
6年生後半の実践演習が始まる前に全範囲を復習することで、受験に間に合う可能性が高くなります。
間に合わないケース④ 過去問演習で成績が安定しない
社会は暗記が大半を占めるため、知識が定着していれば安定して高得点を取れるはずです。一方で近年の入試は、暗記した事項を活用しながら問題を解くケースも多く、知識を連関させながら解く必要があります。そのため事実の羅列として丸暗記学習をしていた受験生は、過去問演習で苦労する可能性があります。過去問演習で成績が安定しない場合は、覚えていない単元があり、知識が虫食い状態であると考えられます。
社会の勉強に時間を割いて、苦手な単元を基本から覚えなおさないと、入試で足をひっぱってしまう可能性があります。
お子さまの特徴でチェック。社会が間に合わなくなる要因とは
ライバルたちと同じように勉強しているはずなのに、お子さまの社会の成績が伸び悩むと「なぜうちはできないのだろうか」と焦ってしまいますよね。実は、社会の成績不振の要因は一人ひとり異なります。
本項目では社会が間に合わなくなる要因を、お子さまの特徴を挙げながら3つ解説しています。
要因① 勉強を後回しにしている【暗記が嫌いなお子さま】
多くのご家庭で、社会は他の科目に比べて優先度が下がりがちです。しかし、社会は膨大な知識量が求められるため、勉強時間が足りないと覚えなければならないことがどんどん溜まって、気付いた時には間に合わなくなってしまいます。
特に暗記が嫌いなお子さまは「社会は受験直前にやった方がいい」と理由をつけて、勉強を後回しにする傾向があります。やればやっただけ成績が上がる社会をないがしろにするのは、受験において得策ではありません。
【お子さまの特徴】
- 国語や算数の勉強で手一杯である
- 暗記をしたがらない
- 社会を受験直前にやろうとしている
要因② 丸暗記をしている【時間が経つと忘れてしまうお子さま】
「単元の復習テストでは良い点数なのに、模試になると成績が悪くなる」というお子さまも多くいらっしゃいます。この場合、覚え方が間違っているせいで成績に結びついていない可能性が高いです。
テストのために一気に無理やり覚えた記憶は、長続きせずテストが終わったらすぐに忘れられてしまうことがほとんどです。他にも、教科書の文章を理解せずに丸暗記したり、語呂合わせばかりで覚えたりするやり方も実力につながりません。
【お子さまの特徴】
- テストの前に一夜漬けで暗記している
- 教科書の文章を丸暗記している
- 語呂合わせをとりあえず多用し、本質的な理解に結び付けられていない
- 勉強しているのに成績が上がっていない
要因③ 家庭学習をしていない【忙しいお子さま】
「塾に通っているのに、なぜか社会の成績が上がらない」とお悩みの保護者様は多くいらっしゃいます。一般的に集団塾の社会の授業は、知識の解説をする場であり、暗記の時間は設けられていません。
つまり、社会においては、塾は理解の助けにはなっても知識定着には不十分なのです。社会の成績を上げるためには、塾での勉強以上に、家庭で必要事項を覚える時間をしっかりと確保する必要があります。
「塾に通っているから大丈夫だろう」と思って家庭学習をおろそかにすると、社会の点数は伸びないままになってしまいます。
【お子さまの特徴】
- 忙しくて家庭学習の時間が取れていない
- 塾に通うだけで満足してしまっている
今すぐ対策したい。社会を間に合わせるための方法
社会の成績が伸びない要因がわかったら、間に合わなくなる前に早急に対策を講じましょう。ここでは社会を受験に間に合わせるための方法を4つ紹介しています。
保護者様がサポートできることを具体的に挙げていますので、お子さまに合った方法を見つけて実践してみてください。
間に合わせる方法① 繰り返し覚える時間を設ける
短期間で社会の成績を上げるためには、確実に記憶に残る暗記をしなければなりません。おすすめの方法は、繰り返し覚えることです。
「覚えたはずなのに、テストをすると忘れている」というお子さまの多くが、暗記を一度しかしていません。一度覚えたら時間をあけず定着確認をして、忘れていた知識は繰り返し暗記してください。
全部覚えたら今度は数日あけて再度確認して、また忘れていた知識を覚え直します。この作業をすべて覚えるまで何度も繰り返すことが重要です。
お子さまによっては「どうして覚えられないのだろうか」と自分を責めたりイライラしたりしてしまうため、保護者様は「〇〇は覚えられたね!」などと前向きな声掛けを意識しましょう。
【保護者様ができること】
- 暗記ができているか問題を出して確認する
- お子さまが覚えられていることを見つけて褒める
間に合わせる方法② すき間時間を活用する
「間に合わない」と焦ると、一度に大量の知識を詰め込もうとしてしまいますが、このやり方では消化不良を起こしてしまいます。また、国語や算数などやるべき課題が大量にある中で、社会に多くの時間を割くのは現実的ではありません。ぜひ、社会はすき間時間を活用してください。
暗記カードを作って通学中に覚える、夕飯前の15分間は社会の時間と決めて毎日勉強する、トイレや寝室にポスターを貼るなど、工夫次第で時間を有効活用できます。
【保護者様ができること】
- 単語カードを作る
- すき間時間を見つける
- すき間時間にやることをリストアップする
間に合わせる方法③ 社会に興味関心を持つ
社会の学習内容は日常生活と密接に関連しています。このため、お子さまが世の中に興味関心を持てば、知識をどんどん吸収するようになります。
例えばスーパーでの買い物で食品の産地を調べたり、旅行に行く際に地図で経路を確認したり、博物館で実物の文化財に触れてみたり、塾の学びを生活の中で復習してみましょう。
また、近年多くの中学校が時事問題を出題するようになっています。小学生向けの新聞を購読したり、家族で一緒にニュースを見たりして、お子さまが社会問題に対して自分なりの意見が持てるようにサポートしてください。
【保護者様ができること】
- 夕飯の時に塾で習った内容について話し合う
- 日常生活のなかに社会の学びを取り入れる
- 子ども向けの新聞を購読する
- 一緒にニュースを見る
間に合わせる方法④ 個別指導を利用する
ここまで社会の成績を上げる方法を挙げてきましたが、暗記が特に苦手なお子さまの場合、保護者様がどんなに工夫しても、なぜか成績が上がらないことが少なくありません。
そんな時におすすめの解決策が、個別指導の利用です。例えば集中力が低くて暗記ができないお子さまの場合は、講師とマンツーマンになれば、必然的に集中力が高まります。
間違った覚え方を改善できないお子さまの場合は、講師が丁寧に正しい覚え方を指導することで、今後の人生にも活かせる記憶術が身につきます。また「入試直前で間に合わない」というお子さまの場合も、個別指導は強い味方です。
社会は覚える知識が多い教科ですが、個別指導であれば志望校の過去問を分析したうえで、必要最小限の範囲に絞って指導ができます。また、暗記した事項を活用しながら問題を解く必要がある入試問題は、解答方法に慣れておく必要もあり、知識を連関させながら解くテクニックなども学ぶことができます。
【個別指導ができること】
- 集中できる環境で、記憶定着をうながす
- 正しい覚え方を指導する
- 志望校の出題傾向を踏まえて覚える内容を絞る
直前まで伸びる。社会が間に合わないと思ったら、今すぐ対策をはじめよう
社会は入試当日まで成績を伸ばし続けることができる教科です。「間に合わない」とあきらめる前に、今すぐ対策を講じて、一つでも多く知識を身につけていきましょう。
最短で効率よく成績を上げたい場合は、個別指導の利用が有効です。中学受験の経験豊富なプロが、志望校の出題傾向を踏まえて範囲を絞ったうえで、確実に覚えるまでつきっきりで指導をしてくれます。特に社会は、単なる暗記ではなく、意味を捉えながら覚え、知識を応用できるように学習を進めていく必要があります。後悔を残さないためにも、最後まであきらめずに、サポートを頼むという選択肢も視野に入れておきましょう。