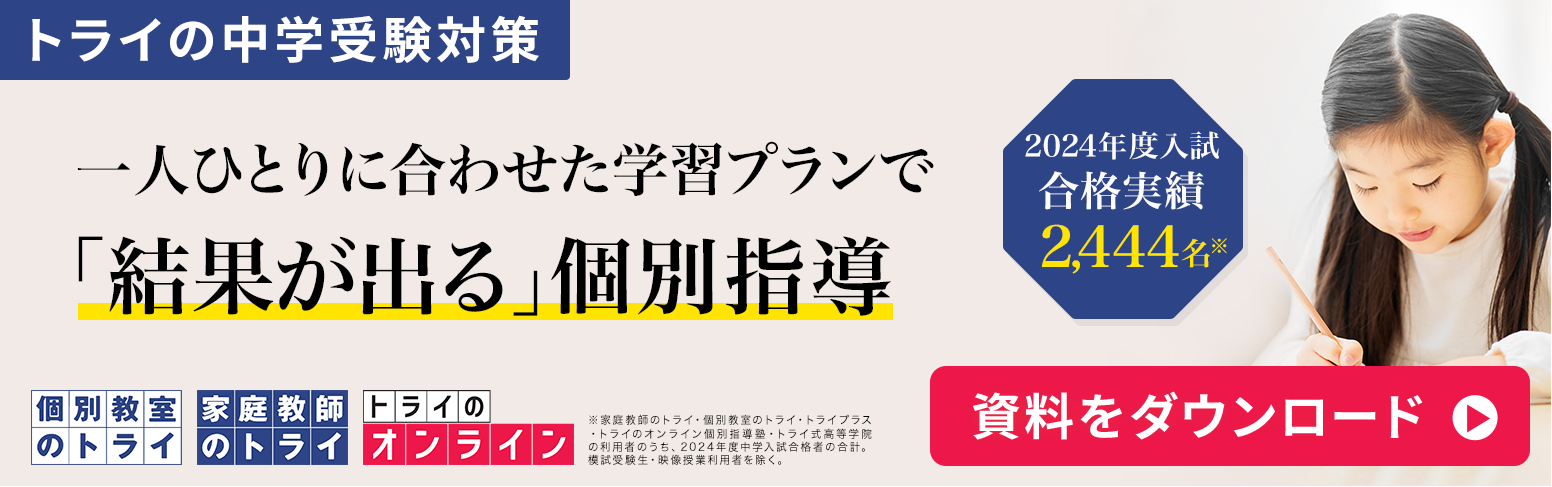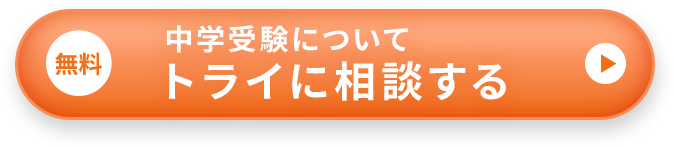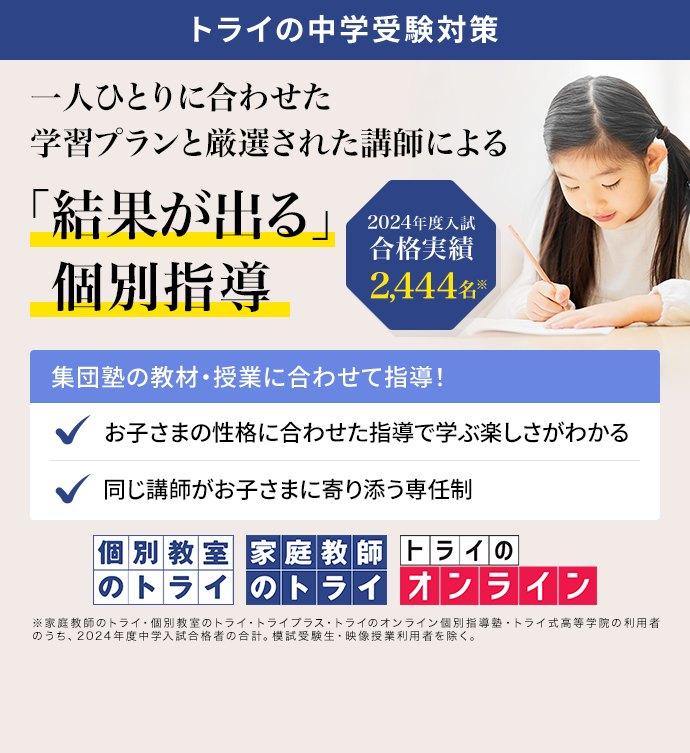創研学院は、東京、神奈川、関西、中国、四国、九州エリアにおいて、50以上の教室を展開する学習塾です。最大の強みを「めんどうみ」としており、中学受験に向けた取り組みをサポートしています。一方で、その「めんどうみ」をうまく活かせず成績に伸び悩み、クラス落ちというスランプに陥っている人もいるのではないでしょうか。本記事では創研学院の強みを改めておさえ直し、塾をどのように活かせば成績を上げられるか、クラス落ちしないか、勉強法について詳しく解説します。
創研学院の特徴
「めんどうみ」が自慢の学習塾
創研学院は、「めんどうみ」のよさを打ち出しています。他の進学塾でよくありがちな、親が勉強のスケジュールを立てなくてはならない、親が宿題のチェックを行わなくてはならない、親が苦手な箇所を教えなくてはならない、などの厄介ごとを“すべて塾内で完結すること”を前面に掲げています。
例えばお子さまが自宅学習をしていた際、「ここがわからないから教えて」と言ってきたとしましょう。その場合、保護者様は「創研学院で聞いておいで」というだけで大丈夫だといい、宿題は自宅で解くものではなく自習室で解くもの、と位置づけています。クラス落ちという事態に陥らないためにはまず、創研学院ならではの「めんどうみ主義」をうまく活用しましょう。
予習よりも復習重視
創研学院では、予習より復習に力を入れています。授業の理解度を深めるために予習は大切ですが、創研学院では原則として予習の必要はありません。独自の学習システムを構築しており、授業→宿題→チェックテスト→補習のサイクルを大切にしています。
なかでも宿題は範囲を提示するだけでなく、「何を」「どのように」「どこまで」復習するべきか明確に提示するとしています。また毎回授業のはじめには、前週に学んだことがどれくらい理解できているかチェックテストが行われます。弱点や疑問点を見つけ出して復習を徹底することで、クラス落ちの回避に向けて活動することができるでしょう。
質問しやすい雰囲気づくり
創研学院では、お子さまが質問しやすい雰囲気づくりに努めています。お子さまのなかには積極的に質問できる子もいれば、消極的でなかなか質問できない子もいます。しかし創研学院では授業中はもちろん、授業の前後に質問できる時間を設けているので、わからない箇所をそのまま放置する心配が少なくなります。また、無料の自習室なども活用できます。
創研学院のクラス編成について
集団授業は1クラス20人以下
創研学院は、地域密着型の少人数制学習塾です。1クラス20人以下で構成されており、先生がお子さま一人ひとりに寄り添って指導しやすくしています。個々のお子さまの学力や学習目標、個性に合わせた指導を行うよう努めています。
クラス編成や座席の決め方
学習塾にお子さまを通わせる保護者様にとって、塾内でのお子さまの成績はかなり気になるものでしょう。上位のクラスに上がれるか、クラスが下がってしまうのではないか、心配でたまらないという保護者様の声はよく聞かれます。
創研学院のクラス分けは、5週に1回行われる月例テストによって決まると言われています。しかしながら、テストの成績だけでクラスが判断されるわけではありません。宿題の状況、志望校、お子さまの性格や学習スピードなどから総合的に判断してクラス分けは行われます。つまり、成績上位者であっても宿題をやってこないお子さまや、授業態度にやる気が見られないお子さまは、上のクラスにあがることはできません。
また座席については、成績順にする校舎もありますが、そうではない校舎もあります。視力や友人関係に考慮してくれるケースもあるので、一概に成績だけでクラス分けが行われるのではないことを留意しておきましょう。
学年で異なるクラス分けの意義
3年生は、中学受験学習をイメージする時期
前述のとおり創研学院では、授業→宿題→チェックテスト→補習という学習スタイルを徹底しています。そのサイクルをじっくりと体験できるのが、小学3年生です。この1年間で塾に慣れ、早い段階からしっかりと基礎を固めて学習習慣を身につけることで、来るべき中学受験に向けて準備をすることができます。この時期はまず勉強に慣れることが一番なので、クラス分けについてはさほど気にしなくてよいでしょう。
4年生は、学習習慣を身につけて基礎学習を磨く時期
創研学院が中学受験で大切にしているのは、学習習慣と基礎学力の構築です。習熟度を高めるためにはどのような工夫が必要か、学力を上げるにはどのようなルーティンが望ましいかなど、お子さま一人ひとりの答えが見つけられるように努めてくれます。小学4年生の段階ではクラス分けを少しずつ意識して、上位クラスを目標にしてみてはどうでしょう。この時期から自習室を活用する習慣をつけておくと、この先の勉強がさらにスムーズに進められるでしょう。
5年生は、志望校を見据えた学習を進める時期
創研学院では、中学受験に必要な知識を小学5年生から習得していきます。そのためこの時期から計画的な学習をスタートさせ、志望校を見据えて合格に必要な学力と知識を積み上げていきましょう。中学受験は志望校によって求められる知識量や難易度が異なるため、それぞれの学校の傾向や特徴を把握しておくことも大切です。また、小学5年生ごろから模試を受ける機会も増えてきますが、この時期はまず塾内のクラスに集中しましょう。ひとつ上のクラスへ上がるぞ、という目の前の目標に取り組むことで、学習の定着にもつながります。
6年生は、志望校合格に向けて徹底的に演習を重ねる時期
創研学院では、学力の定着こそが受験合格へのカギだとしています。そのため小学6年生の前期では、新しい単元に加えて、これまでに学んだ全ての単元を復習し、苦手を特定して補習することに注力していきます。また、問題演習を解く機会を多く設けて、自分で考えて解き切る力も養っていきます。この時期のクラス分けは、志望校も判断材料とされます。中学受験は志望校によっても問題の傾向が大きく異なりますので、志望校をしっかりと定め、求められる学力に適したクラスで学べるよう努めたいところです。
創研学院でクラス落ちする原因と対策
宿題や授業に丁寧に取り組む
前述のとおり、創研学院のクラス分けは成績だけで決まるものではありません。日々出される宿題の状況や塾での授業態度などを考慮して、総合的に判断されます。成績が下がったわけでもないのにクラスが落ちてしまった場合、学力以外に心当たりはありませんか。
一般的に塾での様子を保護者様はあまり把握できませんし、特に創研学院はめんどうみ主義なので、余計にお任せしがちです。ただし注意したいのは、めんどうみ主義だからといって100%お任せではいけないということです。お子さまの学習状況や家庭での様子などは、なるべく先生とこまめに情報交換しましょう。
先生との情報交換は、専用アプリ“Comiru”から個別相談が可能です。クラス分けについて納得いかないのなら成績以外の原因があるかもしれません。塾での様子を早めに確認してみましょう。
毎週のチェックテストにしっかりと向き合う
復習に重点をおく創研学院では、毎週の授業のはじめに必ずチェックテストを行います。これは前週の学習内容や宿題の問題がどれだけ理解できているか、学力としてしっかり定着しているかを見極めるテストです。
毎週行うことでお子さまの弱点を発見して、学力向上へつなげることを目的にしていますが、毎週のことなのでお子さまの気持ちが多少緩んではいないでしょうか。緊張感が薄れてただ問題を解くモードでは、高得点はもちろん、学力の正確な理解度も捉えることができません。チェックテストが直接クラス分けの指標になるわけではありませんが、判断材料の一つにはなりますので、一回ごとに真剣に挑むように声掛けしましょう。
月1回の月例テストで高得点を取る
創研学院では月に1回、お子さまの習熟度を確認するための月例テストが行われます。前週の問題が出るチェックテストとは異なり、日々の授業で学んだ内容を出題範囲として、お子さまそれぞれの弱点部分をあぶり出していきます。この月例テストによってクラス分けが判断されるともいわれていますので、確実に得点を取っておきたいところです。もしクラス落ちとなってしまった場合、まずは直近の月例テストの見直しを重点的に行うとよいでしょう。
苦手克服のために個別授業を受ける
創研学院のクラス分けは成績重視ではなく、お子さまの性格なども考慮されます。しかし苦手なものがあって学力が届かない場合、いくら宿題や授業に真面目に取り組んでいたとしても、上位クラスへ行くことは難しく、その状態でお子さまが上のクラスに上がったとしても勉強についていけず、苦しい思いをしてしまうでしょう。
創研学院でクラス落ちしてしまった場合は、お子さまとの相性が悪かったということでもあるので、個別指導という選択もお薦めです。一人ひとりの学力や学習姿勢に配慮したフォローを行ってくれる個別指導塾は多くありますので、クラス落ちで悩んでいる人は、検討してみてはいかがでしょう。
まとめ
創研学院のクラス落ちについて、その原因や対策を詳しくご紹介しました。クラス落ちの原因には保護者様が気づいていない、お子さまの弱点が隠れているケースもあります。お子さまと先生が普段からコミュニケーションをとるのはもちろんですが、保護者様も積極的に相談してみてはいかがでしょうか。それでも成績向上が難しそうな場合は、より相性の良い個別指導塾の検討へと進むのをおすすめします。