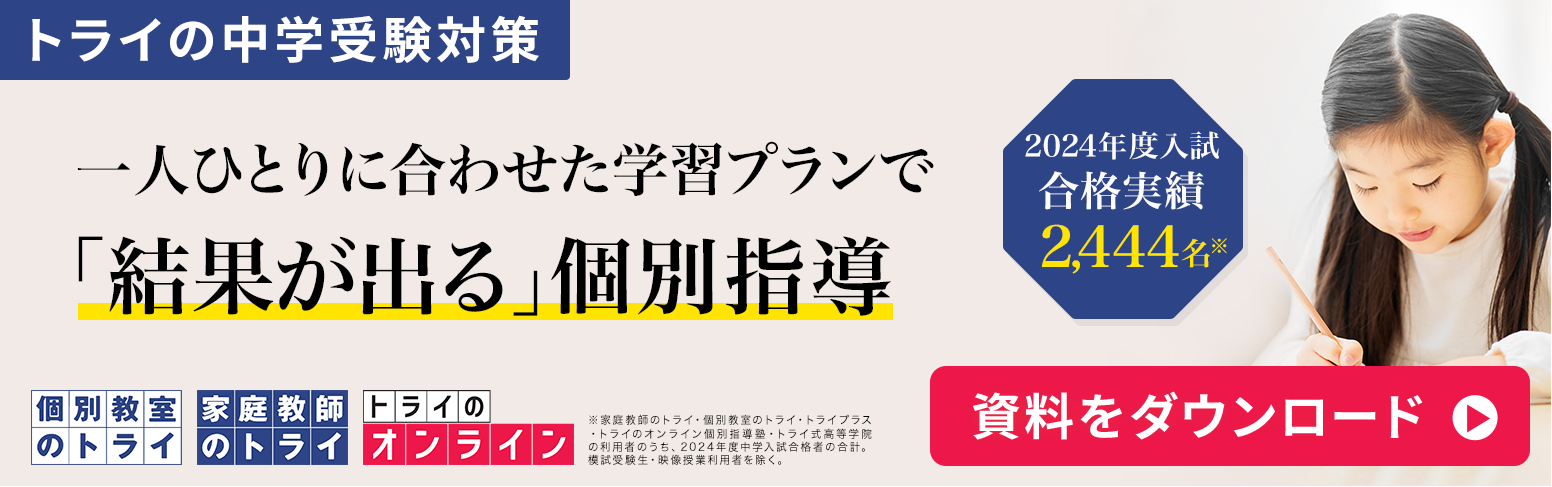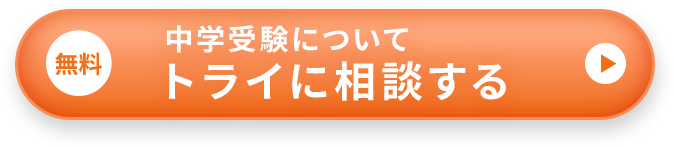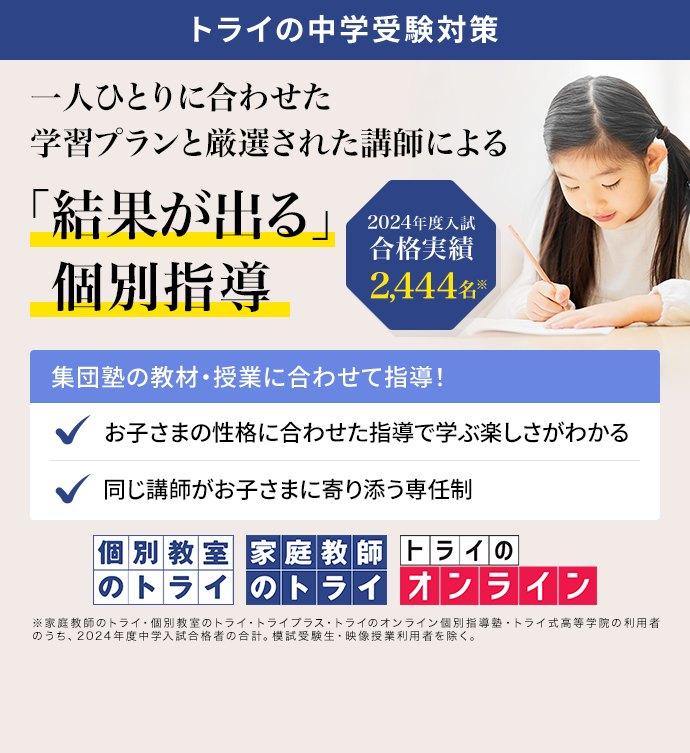中学受験において算数は悩みが尽きない科目です。集団塾に通い、家で宿題をして、保護者様がつきっきりで教えても模試の成績が下がっていると、「もう間に合わないのでは…」と疲れてしまいますよね。
この記事では、お子さまの算数の成績にお悩みの保護者様へ、受験に間に合わなくなる状況や成績不振の要因、そして今後の対策をご紹介します。
「間に合わない」は合否に直結。中学受験における算数の特徴
算数は多くの塾で、最も力を入れて学習すべき科目に位置付けられています。では、なぜ中学受験では算数が重視されるのでしょうか。
ここでは中学受験における算数の特徴をまとめた上で「算数が間に合わないと、どのような問題が起きるのか」について考察しています。
算数の特徴① 小学校の勉強では対応できない
「学校の算数はいつも満点なのに、塾だと偏差値が低い」というお子さまも多いですよね。中学受験の算数は、小学校で習う算数とは質が異なります。
まず「つるかめ算」や「旅人算」に代表されるように、中学受験ならではの特殊な解法の知識が必要です。さらに「割合」や「比」など小学校で習う単元であっても、入試では高度な計算や応用力が求められます。
このため、いくら小学校で勉強していても、中学受験用の算数を習得しなければ太刀打ちができないのです。
算数の特徴② 大人でも解けないほど思考力が問われる
中学受験において、算数は4科目の中で最も難易度が高い科目と言われています。なぜなら、入試では公式を暗記していれば解けるような単純な問題は少なく、複雑な条件や設定を読み、どの解法を当てはめるべきか自分で考えて答えを導き出さなければならないからです。
つまり、中学受験の算数では、単に覚えているだけではなく、知識を理解して使いこなす力が要求されているのです。
算数の特徴③ 成績アップに時間がかかる
繰り返しになりますが、中学受験の算数では、公式や解法などの知識を覚えるだけではなく、使いこなす力が求められます。そのためには、難しい学習内容を完全に理解した上で、反復演習を繰り返し自分のものにしなければなりません。しかも、入試は出題範囲が広いため、身につけるべき知識量が膨大です。
以上の理由から、算数の成績を短期間で上げることはなかなか難しいと言えるでしょう。
算数の特徴④ 配点が大きい
算数は、多くの学校で国語と同等に配点が高くなっています。しかも、他の科目に比べて問題数が少ないため、1問あたりの点数が高い傾向にあります。
例えば、理科や社会の記号問題は1問が1〜2点であることが多いのに対して、算数の問題は5点以上の配点が一般的です。このため、算数で大きく失点してしまうと、理科や社会でより多く正答を出さなければいけなくなります。
特徴まとめ 差がつきやすく合否に影響する
ここまでをまとめると、中学受験における算数とは、小学校では習わない難解な知識を長期間かけて習得する必要がある上、配点が高く1問の失点が合否に比較的大きな影響を与える科目ということになります。
このため、算数を学習していなかったり、苦手なままにしていたりすると、算数が得意なお子さまと大きく得点差がつき、志望校合格が難しくなります。
「算数が間に合わない=入試に間に合わない」となる可能性も考え、お子さまの成績に危機感を感じた際は、早めに対策を講じることをおすすめします。
具体例を紹介。算数が間に合わない状況とは
中学受験において算数は非常に重要な科目であり、間に合わないと志望校合格が遠のいてしまいます。では、どのような状態になったら危険信号なのでしょうか。
ここでは算数が間に合わない状況の具体例を挙げていますので、お子さまに当てはまるものがないかチェックしてみてください。
算数が間に合わない例① 塾に入るのが遅かった
上に述べたとおり、入試に出題される算数の問題は小学校の知識だけでは解けないため、塾などで中学受験用の勉強に取り組まなければなりません。
多くの塾では4年生から中学受験特有の単元に着手しはじめ、5年生までに基本の公式・解法を学習し終え、6年生からは応用演習を中心とするカリキュラムを組んでいます。
お子さまの入塾が新4年生(3年生の2月)から遅くなればなるほど、受験に必要な知識を得る機会が減り、入試に間に合わなくなる可能性が高くなります。
算数が間に合わない例② 6年生になっても計算問題や基本問題で失点する
ほとんどの入試や模試では、最初の大問に計算問題や基本問題が出題されています。これらの問題は、計算ルールや決まった解法を当てはめれば解ける単純な問いであるため、お子さまが最初の大問(大問1)で大きく失点しているようであれば、算数が非常に苦手な可能性が高いです。
誰でも得点できるような基本問題で失点すると、周囲との得点差が大きくなります。また、そもそも公式や解法を覚えていないのであれば、応用問題を解くことは困難です。
6年生になっても大問1を落とす状況が続いている場合は、入試に間に合わなくなる前に、早急に基礎から学習しなおす必要があります。
算数が間に合わない例③ 過去問を解いても3割以下しか正解しない
難関校であれば6年生の9月頃から過去問演習が始まりますが、お子さまが初めて過去問を解いた時の正答率をチェックしてみてください。
中学受験の過去問はレベルが高いため、初めから合格点を狙う必要はありませんが、正答率が3割以下、もしくは合格点の半分以下だった場合は危険なサインです。基礎が定着していないか、学校独自の出題傾向に対応できていない可能性があります。
算数が間に合わない例④ 偏差値が伸びないまま放置している
算数は難しい科目であることがわかっているからこそ、手をつけるのが億劫でつい苦手を放置してしまいがちです。
「算数はできないけど国語は得意だから大丈夫」「算数の勉強を嫌がっているから強制できない」という保護者様は多くいらっしゃいます。
けれども、算数も成績を上げるまでに時間がかかる科目であるため、放置すればするほど周囲との差が広がって、気づいた時には間に合わなくなっている可能性もあります。
算数が間に合わなくなる要因とは。お子さまの特徴まとめ
算数が苦手なお子さまは多くいらっしゃいますが、つまずきポイントは一人ひとり異なります。正しい対処をするためにも、まずは「なぜ算数の成績が伸びないのか」を分析してみましょう。
ここでは、お子さまの特徴を挙げながら、算数が間に合わなくなる要因を紹介します。
間に合わない要因① 計算力が低い
算数の問題は、図形であっても文章題であっても、必ず計算をする必要があります。言わば算数の土台である計算力が低いことは、受験において致命的となってしまいます。
計算の精度が低いお子さまの場合は、計算ミスを繰り返してしまうため、どんなに公式や解法を覚えていても正答にたどり着くことができません。仮に計算ミスをしなくても、計算だけに手一杯で解き方を試行錯誤する余裕がないと、途中で頭が真っ白になってしまいます。
また、入試には時間制限があるため、計算のスピードが遅いと最後の問題まで手がつけられない可能性があります。
【該当するお子さま】
- 模試の大問1(計算問題や基礎問題)で複数失点しているお子さま
- 学校や塾で集中力の低さを指摘されているお子さま
- 算数の偏差値が40以下のお子さま
間に合わない要因② 算数の勉強を後回しにしている
算数は配点が高く周囲と差がつく重要な科目であると同時に、たくさんの労力を掛けなければ成績が上がらない難しい科目です。
本来であればたくさんの時間を算数に割くべきにもかかわらず「嫌いだからやりたくない」「やってもわからないから意味がない」などと言ってお子さまが勉強を後回しにしていませんか。
塾の復習をしなければせっかく習った公式や解法を覚えることすらできませんし、家庭で反復演習をしなければ知識が身につかず、応用問題に手も足も出なくなってしまいます。
【該当するお子さま】
- 他の科目に比べて、算数の成績が明らかに悪いお子さま
- 算数の学習時間を確保しようとしないお子さま
- 算数の家庭用教材に手をつけていないお子さま
間に合わない要因③ 子どもに合った勉強法ではない
算数の勉強に時間をかけているにもかかわらず成績が伸びない場合は、勉強方法がお子さまに合っていない可能性があります。例えば公式や解法の仕組みを理解せずに丸暗記しているだけだと、解き方が複雑な応用問題になると手が止まってしまいます。
特に、5年生の夏以降から徐々に内容が難しくなるため、この時期から成績が低迷し始めている場合は、勉強方法を見直してみましょう。
他にも、好きなところばかり勉強しているため単元ごとの出来に偏りがあったり、基本問題が理解できていないにもかかわらず応用問題に手をつけていたりなど、間違った勉強方法は多数あります。まずはお子さまがどのように算数の学習に取り組んでいるか、確認してみてください。
【該当するお子さま】
- 基本問題は解けるのに、応用問題になると何も書けなくなるお子さま
- 5年生の中盤以降に成績が落ち始めたお子さま
- 模試で大問ごとの正答率に偏りがあるお子さま
- レベルの高い問題集に着手しているのに成績が伸びないお子さま
算数を間に合わせるための方法
「算数がこのままでは入試に間に合わない」とわかっていても、何からどう対処すれば良いのか悩んでしまいますよね。せっかく努力しても、やり方を間違えてしまうと、成績が上がるどころかますます苦手意識が強くなってしまいます。
ここでは、今すぐに始められる算数の成績を伸ばすための方法を、具体的に説明します。
間に合わせる方法① 計算練習をする
算数の成績を上げるために最初にすべきことは、計算力の強化です。計算力は一気に大量の演習をしても身につかないので、地道にトレーニングしなければなりません。
おすすめの方法は、計算練習の習慣化です。「朝ごはんの後は計算練習」「お風呂の前は計算練習」というように、日常の動作にしてしまえば、着実にお子さまの計算力を鍛えることができます。
お子さまが慣れるまでは、保護者様から「計算やった?」と声掛けしたり、丸付けなどのサポートをしたりしてください。
間に合わせる方法② ノートを丁寧に書く
計算ミスの多いお子さまは、板書や途中式、図などが乱雑に書かれていていることが多いです。ノートを丁寧に整理して書くと計算ミスを防げるだけでなく、たとえミスをしても後からすぐ見返せるため、間違いの原因や傾向を特定しやすくなります。
また、式を丁寧に書く過程で「なぜこうなるのだろうか」と仕組みを理解しようとする意識が生まれます。さらに、入試で途中式が要求された際、普段から式を見やすく書く習慣があると、部分点獲得に有利です。
ノートを丁寧に書くことにはメリットがたくさんあるため、お子さまが面倒くさがって途中式や図などを書きたがらない際は、保護者様から根気強く声掛けをしてあげてください。
間に合わせる方法③ 算数の勉強時間を最優先に確保する
小学生の子どもにとって、自分で勉強のスケジュールを立て、その進捗を管理することは困難です。お子さまが算数の勉強をサボってしまったり、好きな科目や単元ばかりを解いていたりする場合には、算数の勉強を優先できるように保護者様がサポートする必要があります。
具体的には「何曜日の何時に何をする」というように、週単位で細かなスケジュールを立て、その時間になったら声掛けをすると良いでしょう。
間に合わせる方法④ 基本問題を繰り返し解く
成績が伸び悩むと、焦ってたくさんの問題に手をつけたくなりますが、基本がわかっていない状態であれこれ挑戦するのは逆効果です。
算数が苦手と感じたら、基本の徹底を意識しましょう。具体的には、塾のテキストを復習したり、家庭用教材の基本問題を繰り返し演習したりすることです。
月曜日に1回目、木曜日に2回目、日曜日に3回目などと、時間を置きながら繰り返し解くことで、公式や解法の仕組みが自然と理解できるようになります。
特に苦手意識が強いお子さまは、わからないことがストレスになり算数嫌いが強まってしまうため「できて楽しい」と思えるレベルの問題を解かせてあげてください。
間に合わせる方法⑤ 個別指導を利用する
ここまで算数の成績を上げる方法を挙げてきましたが、実際に対策しようと思うと、保護者様の負担が大きいですよね。
毎日計算練習をさせたり、丸付けをして途中式を書いているかチェックしたりするのは面倒ですし、お子さまに最適なペースと難易度で学習計画や課題を決めていくには、専門の知識が不可欠です。
「子どもに毎日算数の質問をされるけれど、難しくて困っている」というケースもあるでしょう。そんな時は、個別指導を検討してみてください。
個別指導であれば、算数の知識はもちろん、中学受験に関する経験豊富なプロがサポートしてくれます。お子さまの伸び悩みの要因を正確に見抜いて、適切なカリキュラムを設定できるマンツーマン指導は、集団塾や家庭学習よりも早く成績を上げることができる場合があります。
算数は重要な科目です。お子さまに合った方法で「間に合わない」を回避
数は中学受験において非常に重要な科目です。算数が間に合わないと志望校合格が難しくなってしまうこともあるので、今すぐお子さまの伸び悩みの要因を分析して、対策を講じてください。
ただし、算数は成績を上げることが難しい科目であるため、家庭での対処が困難な場合も多いです。「集団塾で算数の勉強をしているけれど、成績が上がらない」「入試まで時間がなくて緊急事態」「算数の家庭学習は親子にとってストレス」などとお悩みの方は、個別指導を検討してみてください。