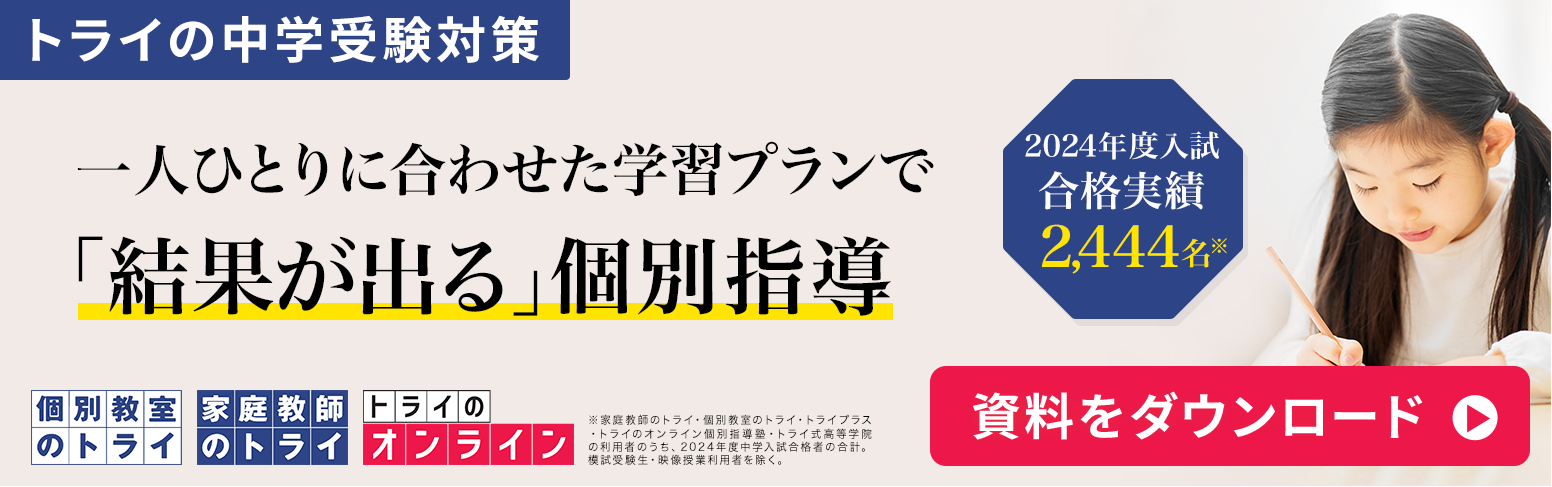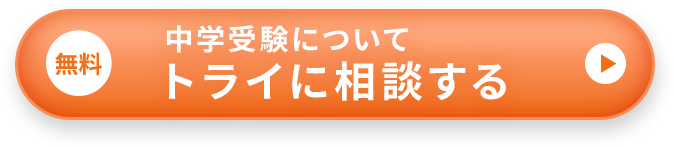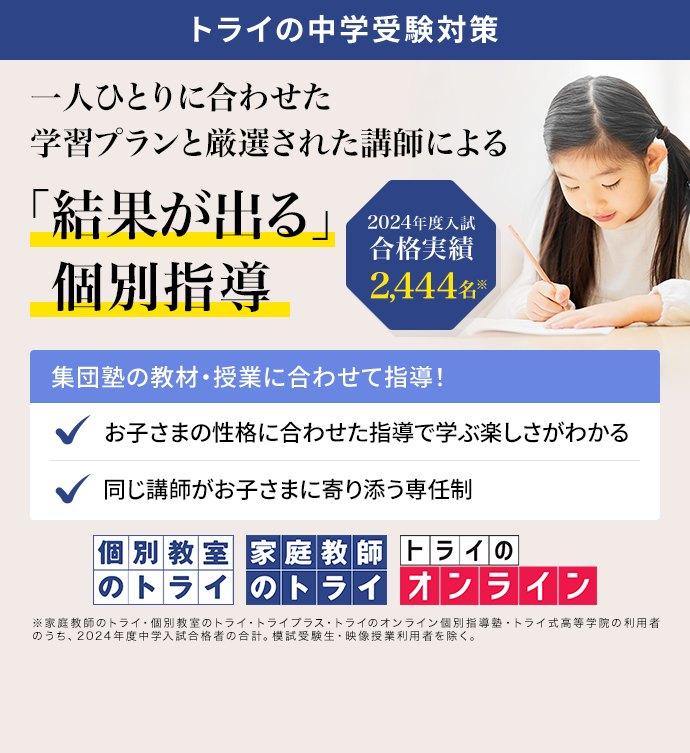中学受験において、国語は非常に重要な科目です。しかし、どう勉強すれば良いのか明確な方法がわかりづらいため、一度つまずくと、成績が下がり続けてしまう傾向にあります。
この記事では、お子さまの国語の成績にお悩みの保護者様へ、受験に間に合わなくなる状況や成績不振の要因、そして今後の対策をご紹介します。
国語の科目特性
国語は他の科目よりも、安定した点数を取り続けることが難しい科目です。また、国語は単なる暗記とは異なるため、一朝一夕で成績が上がりづらい科目とも言われています。さらに、近年の入試では問題文の量が多くなる傾向にあるなど、より対策の必要性が増しています。このため「受験に間に合うか否か」という視点で、お子さまの国語の現状を見極める必要があります。
ここでは、「具体的にどのような状況になったら間に合わない可能性があるのか」についてまとめています。
合否に直結する。国語は重要な科目
現状を把握する前に、まず「国語の成績は伸びないけれど、他の科目でカバーすれば大丈夫ではないか」という疑問にお答えします。
端的に言うと、国語の成績を他の科目でカバーすることは、非常に困難です。なぜならば、中学受験は4科目(場合によっては2科目)で合否を判断するため、科目数の多い大学受験のように、国語の失点を他の科目で補うことが難しいからです。
しかも、多くの学校で、国語は算数と同等に配点が高くなっています。このため、比較的暗記で対応しやすい理科・社会を頑張っても、国語の失点が大きく響いてしまいます。さらに、国語は入試時間割の1時間目に設定されやすい科目であり、国語の出来が悪いと、入試当日の精神状態に悪影響を及ぼすでしょう。
このように、中学受験において国語は、合否に直結する重要な科目なのです。
いつまでにどれくらいの力が必要か。国語の進捗目標
漠然と「間に合わない」と感じるけれども、黄色信号なのか赤信号なのか、国語の成績の伸び悩みは判断が難しいものです。そこで、まずは入試本番に向けて国語の進捗はどうあるべきか、6年生の理想的な学習スケジュールを考えてみましょう。
2月~春休み(新6年生)
新6年生としてのカリキュラムがスタートする段階のこの時期に求められることは、5年生までの学習範囲の定着です。
文章を客観的に正しく読み取る力や、答えの根拠を文中から探し、指示通りに記述する力は、国語の基礎内容になります。また、4,000字程度の文章を精読できる集中力も求められます。
4月~夏休み
この時期に求められることは、抽象度の高い説明文や、登場人物の感情が読み取りにくい物語文への対応です。5年生までの文章と比較すると難易度が上がるため、要旨を簡潔に把握する力や論理的な思考が求められます。
文章量も増え、6,000字程度は集中して読み続けなければなりません。さらに、受験対策が本格化する前に、知識問題(漢字・四字熟語・ことわざ・慣用句など)の定着を目指したいです。
夏休み明け~12月
志望校が決まり、受験本番期になると、応用問題や過去問の演習がはじまります。この時期は、時間を計りながら適切なペースで解いたり、出題者の意図を汲んで解答したり、実践力をつけていく必要があります。
志望校によっては10,000字程度を精読しなければならないため、情報処理のスピードアップを図るようにしましょう。
冬休み~入試直前
応用問題や過去問演習を繰り返し、確実に合格点に到達できる実力をつける時期です。知識問題で失点しないように暗記を繰り返したり、読解問題の点数を安定させるために繰り返し問題演習をしたりするなど、直前まで対策を続けることが肝要です。
目標と現状の差が大きいと、頑張っても間に合わないこともある
上記のスケジュールと照らし合わせて、今のお子さまの実力はどの位置にあるでしょうか。国語の成績は一朝一夕には上がらないため、乖離が大きければ大きいほど、間に合わない可能性が高くなります。
特に多く見られるパターンは以下のとおりです。
間に合わない可能性がある例
受験勉強をはじめた頃からずっと国語が苦手
小学生は苦手科目を後回しにしがちなため、到達すべき学力からどんどん遠ざかる傾向にあります。まずは国語という科目に向き合うことからスタートする必要があります。
6年生になって国語の成績が伸び悩み始めた
5年生まで「何となく」国語を解いてしまっていたため、抽象度の高い6年生の学習範囲に対応できていない可能性があります。「書かれていることを正確に読み取り、根拠を持って解答する」という初歩に立ち返る必要があります。
応用問題や過去問で点数が取れない
本来であれば、基礎がしっかり定着していれば、応用問題や過去問に歯が立たないことはありません。基礎が不安定にもかかわらず、応用演習をしていると、間違いを繰り返し苦手意識が本番まで残ることになります。
国語が間に合わなくなる要因とは。お子さまの特徴まとめ
ここまで、国語の進捗目標とお子さまの現状を照らし合わせ、今まで漠然としていた「間に合わないかもしれない」という状況を明確化しました。
次に、国語の成績が伸び悩む要因を、その要因に当てはまりやすいお子さまの特徴と共に考察します。
【読書習慣がないお子さま】基礎的な読解力がついていない
はじめて見る文章を短い時間で正確に読むためには、活字への慣れ、幅広い語彙知識、一般常識の理解など、様々な前提がそろっている必要があります。活字に慣れていなければ、読むのが遅くなりますし、語彙の知識がないと誤読が増えるでしょう。
また、ある程度の一般常識がないと、文章のテーマが読み取れなくなってしまいます。そして、これらの前提があるか否かは、幼い頃から読んできた文章量に左右されます。
つまり、読書習慣がないお子さまは、基礎的な読解力が定着していないために、国語の成績が伸び悩んでいる可能性があるのです。
【作文が苦手なお子さま】自分の考えを上手く表現できない
自分の思考をアウトプットするためにも、語彙力や客観的視点、文章構成力などが求められます。いくら文章を読めていても、頭の中に思い浮かんだ考えを、正しい日本語で他者にわかるように論理立てて記述することができなければ、得点に結びつかないのです。
国語嫌いなお子さまの中でも、特に作文が苦手な方は、この「表現下手」に当てはまるかもしれません。
【あがり症・繊細なお子さま】苦手意識が大きくなっている
明確な暗記知識の範囲や解答のための公式が存在しない国語は、他の科目以上に精神状態の影響を受けやすいです。このため、あがり症や繊細なお子さまの場合、「また失敗したらどうしよう」と考え、問題に集中できなくなっている可能性があります。
苦手意識は早めに取り除かないと、時間を追うごとにどんどん大きくなります。お子さまが、家ではスムーズに解いているにもかかわらず、模試になると点数が取れない場合は、苦手意識が大きくなって極度の緊張状態に陥っているかもしれません。
【集中力が続かないお子さま】問題文が読めていない
国語の問題に正解するためには、かなりの情報量の文章と設問を読み取る必要があります。集中力が続かないと、文章を読んでいるつもりで実は字面を眺めているだけだったり、設問の意味を取り違えてケアレスミスを頻発したりします。
また、集中できていないせいで「国語は疲れる科目」と感じ、解くことをあきらめて、できるはずの問題に手を付けていない可能性もあるでしょう。
【算数好きなお子さま】国語の勉強を後回しにしている
いわゆる「理系」のお子さまの場合は、言葉や物語に興味が持てない場合もあるため、国語を退屈に感じているかもしれません。小学生にとって興味がない勉強を強いられることは、大人が思う以上に苦痛です。
このため、国語の勉強が後回しになってしまい、周囲と差が広がっていき、ますます国語嫌いが加速する、という負のスパイラルに陥ってしまいます。
【お子さま自身の問題ではない可能性も】中学受験における国語の難化
ここまで挙げた例に全く当てはまらないのに、なぜか成績が上がらないというお子さまの場合、伸び悩みの要因は国語という科目自体にあるかもしれません。
入試で出題される文章は情報量が多く、平均して6,000~7,000字に上ります。
また、児童本ではなく大人向けの本から出題されることが多いため、語彙や扱っているテーマが難解です。
さらに、最近は思考力を問う設問が増え、文章を正しく読むだけでなく、論理的に自身の考えをまとめる力が必要になってきています。現在の中学入試の問題は、大学入試問題に匹敵するほどで、そもそも小学生が解くには難度が高いのです。
国語を間に合わせるための方法
ここまで「なぜ国語が間に合わなくなるのか」という要因をまとめました。国語の苦手を放置すると、どんどん目標との差が広がり挽回が困難になるため、早急に対処する必要があります。
そこで、ここでは国語を間に合わせるための具体的な方法を紹介します。
読書習慣をつける
読書には、活字に慣れる、語彙が増える、言葉・物語への興味がわく、国語への苦手意識がなくなる、集中力を養うなど、様々なメリットがあります。
遠回りのように感じるかもしれませんが、お子さまが小学5年生以下の場合は、国語嫌いを解決する第一歩は日常的に本に触れることです。読書がお子さまの習慣になるように、以下に挙げる方法を試してみてください。
読書習慣をつける方法
- お子さま自身に本を選んでもらう
興味がある内容や短編の話など、お子さまが「読みたい」と思える本に出会えると、自発的に本を開くようになります。
- 大人が本を読む
「本は楽しい」という様子を保護者様が見せることで、お子さまの興味を刺激してみてください。
- 読み聞かせをする
どうしても自分で本を読むのを嫌がる場合は、新聞のコラムなど短い文章で構わないので、読み聞かせをしてみてください。
国語の復習を大人が手伝う
お子さまだけで問題に取り組んでいると、何となく解いて終わりにしてしまったり、わかっていないのにわかっていると勘違いしてしまったりするものです。
そこで、お子さまが解き終わった後に保護者様が以下に挙げる点を確認することで、復習をサポートしてみてください。
復習をする際の声掛け例
- 文章のテーマは何か。言いたいことは何だったのか(物語文の際は、どんな出来事が起きて登場人物の心情はどう変わったのか)
- 出題者はどんなことを聞いていたか
- 自分の解答の根拠は何か
- 文章を要約させて、添削する
問題集を一冊やり切らせる
成績が伸び悩むと焦ってしまい、何冊も問題集をやらせたくなってしまいますが、まずは一冊腰を据えてやり切るようにしてください。
国語への苦手意識が強いお子さまの場合は、自信をつけさせるために、あえて簡単な問題集から取り組ませるのもよいでしょう。
基礎問題だけは得点できるようにする
応用問題はあきらめて、基礎的な問題だけに集中する方法もあります。大きく得点することは狙わず、基礎的な問題を着実に回答し得点の土台を作ることを目指す考え方です。
こうすることで、高みを目指しすぎず、ストレスを減らし受験に立ち向かうことを継続することを優先するという捉え方もあります。
子どもが集中できる環境をつくる
スマートフォンやテレビ、時計など、気が散るものを取り除き、文章に集中できる環境をつくってください。
また、お子さまの部屋に本や子ども新聞をおいて、自然と文章に親しめる空間を作ることも有効です。
個別指導という選択肢
ここまで、国語の成績を伸ばすための方法を挙げましたが、全てご家庭で対応するのは、負担が大きいと言えます。
勉強をサポートするためには、保護者様も問題を解かなければなりませんし、参考書を買うにしても、どれがお子さまに最適か判断が難しいでしょう。
また、昨今の入試問題は非常に難化しているため、受験国語に特化した学習のためには、プロの力が不可欠です。
そこで、有効な選択肢が個別指導の利用です。
個別指導(塾や家庭教師)であれば、教育のプロがお子さま一人ひとりのつまずきの要因を見極めてサポートするため、最短のスピードで挽回に向けて活動することができます。
間に合わなくなる前に対処。国語の成績を上げる方法は人それぞれ
国語は地道な努力が不可欠な科目であるため、成績が落ちはじめたら、受験に間に合わなくなる前に対処することが必要です。
国語が苦手になる要因は一人ひとり異なるため、対処の仕方も様々です。ご家庭でできることをやっても状況が改善しない場合は、個別指導塾を活用するという選択肢もあります。
国語の点数が伸び悩んでいるのであれば、取れなかった部分は全て伸びしろと言えます。
基礎的な部分だけでもしっかりと点数をとれるようになっていきたいところですね。適切な対処をすれば、苦手な教科ほど、入試本番の強みになるでしょう。