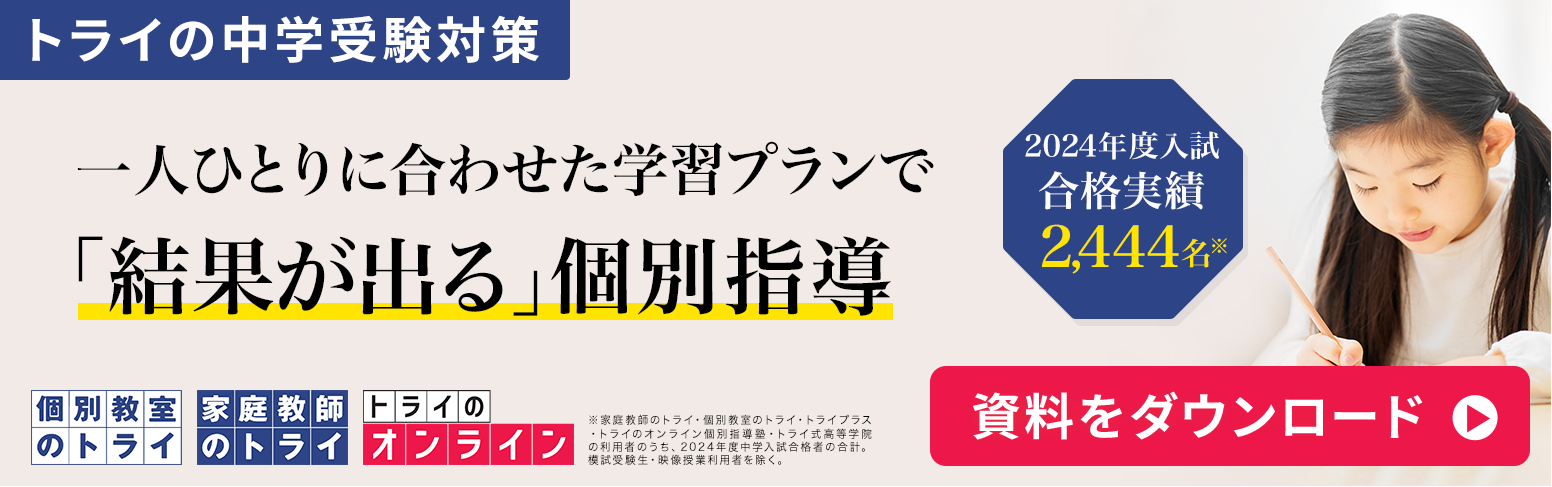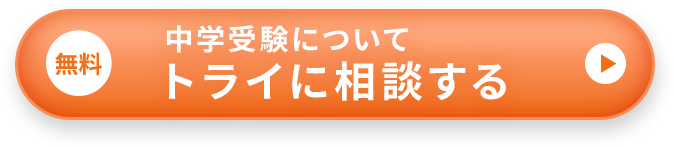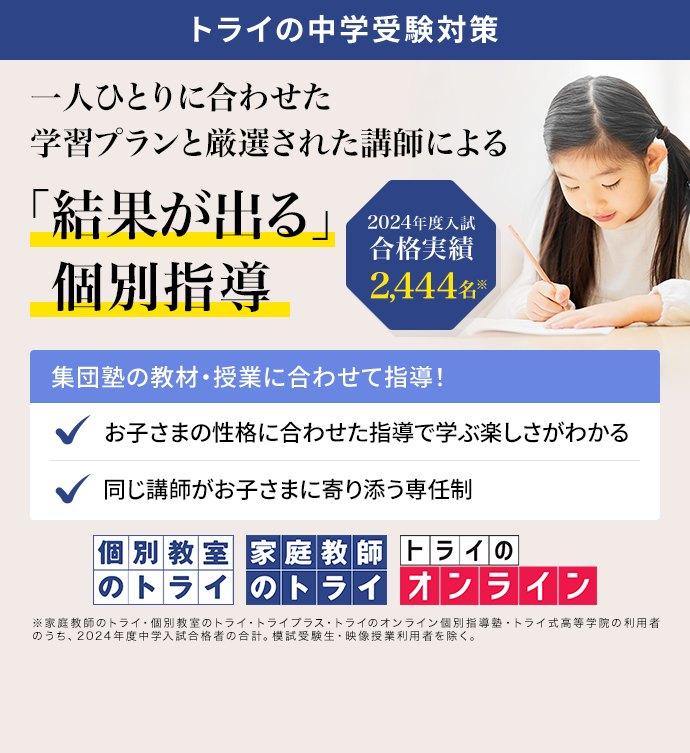お子さまの中学受験において、テストの点数が全然伸びない、宿題が多すぎて終わらない、塾とのコミュニケーションがうまくとれない、先生に質問しにくい、などでお悩みの方は多いことでしょう。せっかく学習塾に通っていてもその塾をうまく活用できていなければ、偏差値を上げることはできません。本記事ではお子さまが創研学院に通っていても偏差値が上がらず、どうしたらよいか迷っている方に向けて、偏差値を着実に上げるための対策を詳しく解説します。
中学受験における創研学院の強み
徹底した「めんどうみ主義」でサポートしてくれる
創研学院では徹底した「めんどうみ主義」を掲げ、生徒一人ひとりに寄り添いながら、それぞれの学力や学習目標、個性に合わせた授業や指導を推進しています。
中学受験は家庭でのサポートが非常に重要で、宿題のチェックやスケジュール管理などに追われて悲鳴を上げている保護者様も多いことでしょう。しかし創研学院では、塾のサポートによって家庭の負担を最小限にして中学受験に臨めることを強みとしています。
中堅校から難関校まで幅広い合格実績
創研学院では例年、筑波大駒場、開成、女子学院、渋谷幕張、聖光学院、豊島岡といった最難関校にも合格実績を残していますが、特に中堅校レベルの中高一貫校への合格者が多く見られるようです。
創研学院では適正の人数で授業を行うため、生徒の数が全体的に少なめです。そのため合格者の人数としては他の塾より少なく見えますが、合格者の割合は高めの比率となっています。
地域密着型で、校舎ごとに独自の取り組みを実施
創研学院は、地域密着型の学習塾です。各校舎で地域に合った独自の取り組みを行っており、特に教室がある地域の中高一貫校の対策に力を入れています。
各校舎で独自の授業のほか、勉強合宿や合同訓練など、他校舎のライバルとの特別授業も実施しています。本格的な受験シーズンには志望校特訓により、お子さま一人ひとりに個別に対応しながら偏差値アップを目指します。
短時間で効率的に学習を進められる
創研学院では、アレもコレも詰め込む勉強法は推奨していません。これまでの30年以上の実績を活かしながら重点的な分野にカリキュラムを絞り、合格に必要な点数を確実に取るためのサポートに努めてくれます。
また、復習することを非常に大切にしているので、原則として予習は必要ありません。習ったことを着実に、短時間で効率的に学習を進める復習システムが確立されているので、お子さまも集中して取り組めるのではないでしょうか。
創研学院での偏差値の捉え方
中学受験における偏差値とは
中学受験の偏差値は特殊なもののため、まずは保護者様がその数字についてしっかり理解しておくことが大切でしょう。中学受験の偏差値は、高校受験の偏差値とは全く異なるものです。中学受験の偏差値を高校受験の偏差値に換算するとすれば、プラス10〜15と考えるのが一般的だと言われています。つまり高校の場合、偏差値50だと平均的な学力ですが、中学の場合の偏差値50は60〜65にあたります。中学受験をしない全小学生を含めた同世代の中では、非常に優れた学力だと言えるでしょう。
中学受験における“偏差値50”とは
中学受験においては、偏差値50とはどのようなレベルかご存じでしょうか。偏差値50とは、中学受験の膨大なカリキュラムについていくことができ、基本的なものは理解できていて、応用問題までの理解はあと一歩、というレベルです。中学受験で偏差値50台後半、特に60を超えると、中学受験者層の中でもトップクラスという位置づけとなります。
創研学院で偏差値が確認できるタイミング
創研学院ではさまざまな独自テストを行っており、それぞれのタイミングでお子さまの偏差値を確認することができます。
前の週に勉強した内容の確認を行う「毎時間のチェックテスト」、月または学期ごとの学習定着度を確認する「月例テスト」や「学力判定テスト」、季節講習でこれまでの指導内容の定着度を確認する「季節講習修了」テストなど、実にさまざまなテストが用意されています。
偏差値はこうした塾のテストで確認するだけでなく、外部模試でも確認するようにしましょう。四谷大塚の合不合判定テストや、首都圏模試センターが実施する合判模試など、実際に受験を戦うライバルの中での偏差値を知ることも非常に大切です。
特に志望校に御三家や最難関校を検討している場合は、よりハイレベルなサピックスオープンや学校別模試で自分の偏差値を把握するのがよいでしょう。
創研学院で偏差値が上がらない原因
復習ができていない
創研学院は徹底した「めんどうみ主義」を掲げていますが、お子さま本人の復習がしっかりできていないと、偏差値を上げることはなかなか難しいでしょう。
創研学院では基礎知識の定着はもちろん、発展的な問題で基礎知識をどう応用して問題を解くか、このふたつの習得が非常に大切だとしています。
お子さまの偏差値が上がらない場合、復習がおろそかになってはいないか確認してみましょう。
スケジュール管理ができていない
中学受験においては、テストや受験までのスケジュール管理が合格を左右すると言っても過言ではないでしょう。「めんどうみ主義」で、先生とお子さまが一緒になって宿題の進め方を計画し、志望校に合わせたプランニングや受験までのスケジュールの作成を行ってくれると言います。
しかしそれでもお子さまの偏差値が上がらない場合、そのスケジュールがお子さまには合っていないということになります。スケジュールがしっくりこないから復習が中途半端になってしまい、結果、偏差値が上がらないという事態に陥っている可能性もあるでしょう。
先生とスケジュールを立ててみたものの、お子さま自身が理解できていない場合もあるかもしれません。
「わかる」と「できる」の違いがあいまいになっている
中学受験の勉強の場合、わかったつもりでいてもいざ解答しようとすると、解けないことが案外あります。それは、「わかったつもり」になってしまっていて、問題が「できる」状態まで定着できていない状況だと言えるでしょう。
創研学院では宿題の内容や頻度、量だけでなく、間違えた箇所の直しを行っているか、わかったつもりになっていないかを確認し、やり遂げられるようにサポートするとしています。
復習を何度も繰り返すことで学力を定着させることが大切ですが、お子さまの偏差値が上がらない場合、まだ完全に「できる」領域に達していない可能性があります。お子さま自身で「わかる」と「できる」の違いを捉えることは、年齢的にかなり難しいことでしょう。そのため第三者が客観的に、お子さまを「できる」状態へ導いていく必要があります。
創研学院で偏差値を上げるための対策
先生とのコミュニケーションを強化する
お子さまの偏差値を上げるためには、まずお子さまの状況を保護者様や先生など周りの大人がしっかり把握しているかどうかが大切です。創研学院には専用アプリ“Comiru”があり、保護者様と担当講師との架け橋となってくれます。前述に挙げた復習への取り組みやスケジュール管理なども、電話ではなくアプリを通じて相談できるようなので、活用してみてはいかがでしょうか。保護者様には塾内のお子さまの様子は見えにくいものなので、思わぬ一面が知れるかもしれません。
自習室を徹底的に活用する
創研学院では、お子さまたちに自習室を活用するよう指導されます。創研学院の自習室は先生が駐在しているので、個別で質問することができます。また、苦手な分野は対策プリントなどを用意してフォローしてくれるそうです。自宅ではなかなか集中できないというお子さまも多いことでしょう。集中できる勉強空間として、自習室を活用してはいかがでしょうか。
土曜日に行われる無料補習を受ける
創研学院では土曜日に、弱点補強のための無料補習を実施しています。お子さま一人ひとりの弱点を見極め、穴のない学力をつけられるようサポートするというものです。
無料補習は少人数で行われるため、日々の集団授業と組み合わせることでより理解を深められます。間違いやすい問題はできるまで反復練習を行い、1週間後、1ヶ月後にも同様の問題が解けるかをチェックすることで、弱点強化や偏差値アップへとつなげています。
創研学院で偏差値を着実にアップさせるための対策 まとめ
創研学院での偏差値を上げるための勉強法についてご紹介しました。中学受験において偏差値は切っても切り離せないもので、上がったり下がったりと保護者様もヤキモキすることでしょう。まずは日ごろの復習を徹底することを大切に、あらゆる模試を受けて偏差値の把握に努めてはいかがでしょう。
集団指導塾では合わない、うまくいかない、そう感じた場合は、個別指導塾という選択肢も視野に入れて、早めの対策を行うことが重要です。