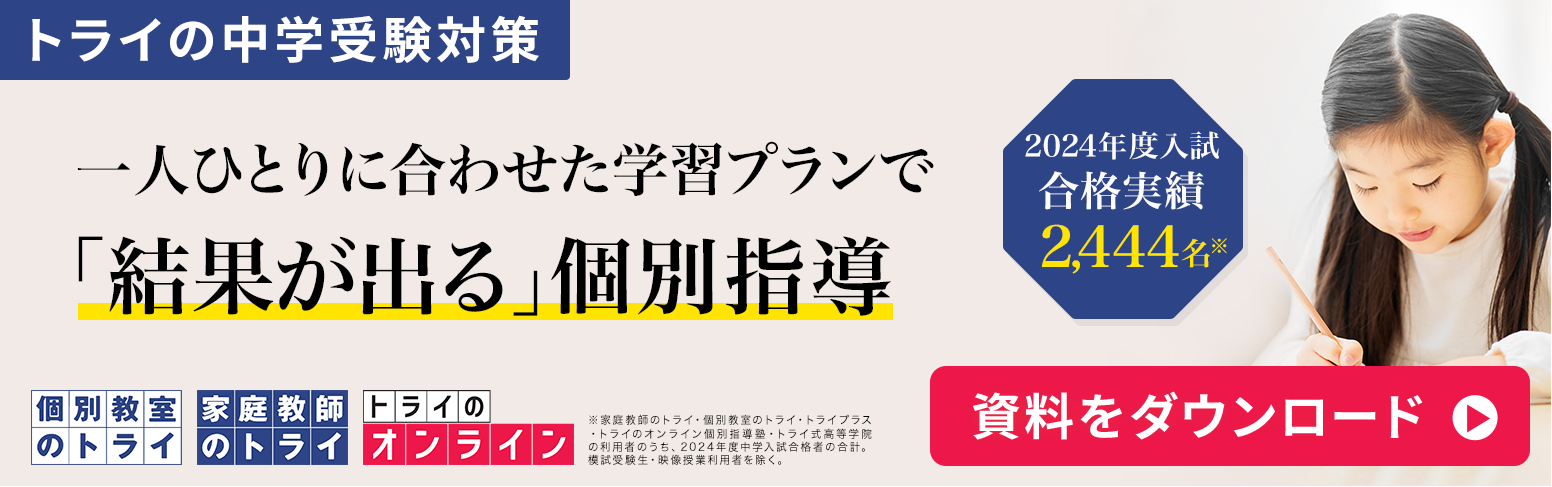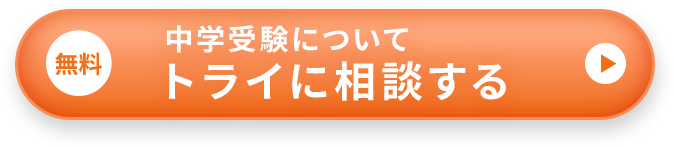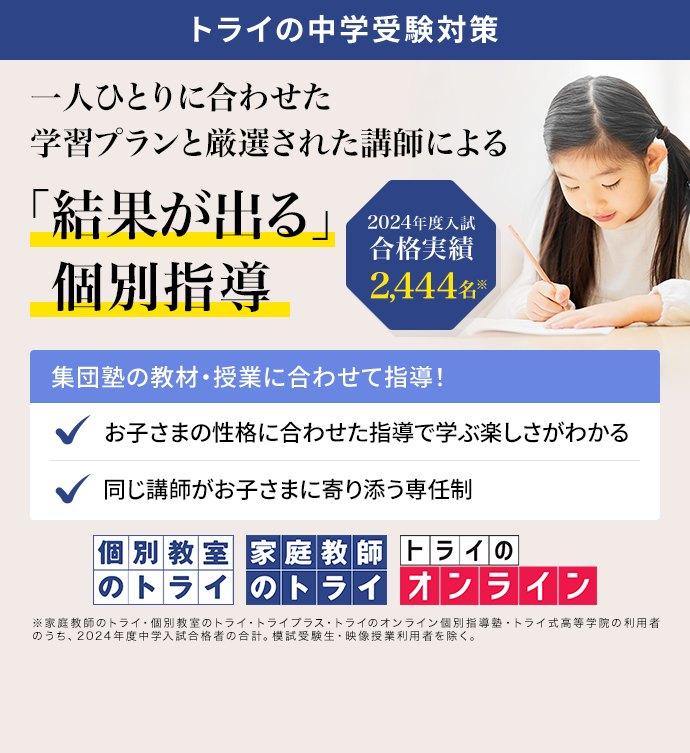お子さまを市進学院に入塾させていると、頻繁に定例試験があり、その度に偏差値の伸びが気になってしまいますよね。
「勉強させているのに偏差値が上がらない」「偏差値が上がらないせいでクラス落ちしそう」などお悩みの方はいらっしゃいませんか。
この記事では、保護者様向けに市進学院における偏差値の位置づけと、偏差値が上がらない要因と対処法を紹介しています。
偏差値が上がらないとは?市進学院における学力の把握方法
偏差値は中学受験において重要な指標ですが、特に市進学院では偏差値が塾内での立ち位置を決めるといっても過言ではありません。
ここでは、そもそも偏差値とは何かを振り返った上で、市進学院ではどのように偏差値を測っているのか、偏差値が下がるとどうなるか解説します。
そもそも偏差値とは何か
お子さまが中学受験を始めると、偏差値という言葉をよく耳にしますよね。偏差値とは、テストや模試などを受けた際、受験者全体の中でお子さまの学力がどの位置にあるかを表す数値です。
偏差値計算では、平均点を50と換算するため、お子さまの偏差値が50よりどれくらい上なのか(または下なのか)でお子さまの学力が判断できます。また、偏差値は全体の中での立ち位置を表すため、過去の偏差値と比較することができます。
例えば、過去のテストと比較して偏差値が上がっていない場合は、相対的にお子さまの学力が上昇していない、という意味です。つまり、偏差値とは「お子さまの学力を客観的に捉えるための物差し」だと言えるでしょう。
偏差値を確認するメリット
- 受験者全体の中でお子さまの学力の立ち位置がわかる
- 過去のテストと比較して、学力の変化を確認できる
- 志望校選びや合格可能性の判断に使える
市進学院ではどのように偏差値を測っているのか
市進学院で偏差値を測るタイミングは、年8回実施されている定例試験(実力テスト)が主です。頻度は1ヶ月〜1ヶ月半に1回程度で、春・夏・冬の講習後にも必ず試験が実施されています。
さらに、小学6年生になると「首都圏模試」をはじめとする外部模試を受験する機会が多くなります。ここで注意すべきことは、市進学院の生徒が受験する定例試験とは異なり、首都圏模試は受験生の学力幅が広いため、偏差値が高めに出るという点です。逆に言うと、市進学院の定例試験で測定される偏差値(いわゆる市進偏差値)は、首都圏模試の偏差値よりも約10程度低く出ます。つまり市進学院は、高頻度かつシビアにお子さまの偏差値を測る塾であると言えるでしょう。
市進学院における偏差値の位置づけとは
市進学院では定例試験のたびに、こまめに偏差値を確認しています。そして、測定された偏差値は、お子さまの学力を正確に把握するために活用されるだけでなく、クラス編成の基準にもなっています。
市進学院では、レベル別に標準・応用・発展の3コースが編成されていますが、クラス分けの際に最も参考にするのが、偏差値です。おおよその目安として、発展クラスは偏差値60、応用クラスは偏差値50を、それぞれ継続して超えていることが求められます。
さらに、高い偏差値をキープできると、最難関中学に特化した講座(プレップコース)への参加認定を得ることができます。つまり、市進生にとって偏差値とは、学力を客観的に見るための指標であるだけでなく、クラスの上下や、プレップコースへの参加可否を決めるための重要な数値になるのです。
市進学院において偏差値が上がらないということは、学力が伸び悩んでいるサインであると同時に、クラス落ちやプレップコース落ちの危険信号にもなるのです。
具体例でチェック。市進学院で偏差値が上がらない要因とは
「偏差値が上がらない」とは、お子さまの学習が上手く身についていないことを意味します。このまま放置すると周囲との差が広がり、入試に間に合わなくなる可能性があるため、早めの対策が必要です。正しく対処するためにも、なぜ偏差値が上がらないのか要因を突き止めましょう。
最初にチェック。市進偏差値と外部模試の偏差値を混同していないか
先ほども触れましたが、市進学院の定例試験で測る偏差値、通称「市進偏差値」は外部模試(とりわけ首都圏模試)の偏差値より10程度低く出る傾向があります。偏差値は受験者のレベルや人数などで変動するため、市進学院生が受験する定例試験の偏差値と、外部模試の偏差値を直接比較することはできません。
もし「前回と比べて偏差値が大きく低下している」という場合は、同じ模試の偏差値どうしで比較しているか、再確認してください。
授業の内容が身についていないかも。チェックテストの成績が悪い場合
定例試験で良い成績が取れず、市進偏差値が伸び悩んでいる際に、まず考えられることは、授業の内容が身についていない可能性です。この場合、チェックテストの成績を確認することが有効です。
チェックテストとは授業前に行われる前回の内容を確認するための小テストで、この成績が悪いと授業内容が定着していないことを意味します。では、なぜ授業が身につかず、チェックテストで悪い点数を取ってしまうのでしょうか。具体例を挙げて要因をまとめていますので、お子さまに当てはまる例がないか確認してみてください。
授業についていけていない
市進学院は他塾と比較して授業時間が短いことが特徴です。そのため、解説のスピードが速く、場合によっては授業についていけなくなる可能性があります。しかし、小学生の子どもは授業を聞いているだけで「なんとなくわかった」と思ってしまうため、自身が理解できていないことに気付いていないかもしれません。
具体例
- 復習のための家庭学習用教材『ホームタスク』の正答率が低い
- 「○○ってどういう意味って習った?」と聞くと、答えがあいまい
宿題が多すぎてこなすだけで精一杯になっている
市進学院は家庭学習に重きが置かれています。復習教材『ホームタスク』の他にも、応用演習の『トライアルシリーズ』、漢字や計算の『ベーシックトレーニング』など、配布されている教材を並べるだけで相当な分量があります。
宿題が多すぎると「とりあえずこなす」という機械的な作業になるため、ほとんど身についていない可能性があります。
具体例
- わからない問題は、答えを丸写ししている
- 塾に行く直前に、大急ぎで宿題をしている
- 授業を聞いていない
市進学院は少人数制でアットホームな雰囲気の塾です。楽しく通うのは良いことですが、友だちに会うことが塾に通う目的になると、肝心の授業を真剣に聞かなくなってしまいます。
他にも、寝不足や習い事の掛け持ちで疲れていると、授業中にぼーっとしてしまうお子さまもいるので要注意です。
具体例
- 塾の帰り道に友だちと遊んだ話ばかりしている
- 習い事が多く、いつも疲れている
モチベーションが低下している
市進学院では、4科目受験であれば最低週4日の通塾が必要です。小学生の子どもにとって、週4日間塾に通い、高頻度で実力テストを課されることは、時につらく退屈なものです。
モチベーションが下がっているにもかかわらず勉強を強制し続けると、やる気が燃え尽きてしまい取り返しがつかなくなります。
具体例
- 「塾に通いたくない」と言っている
- いつもスマホをいじったり寝ていたりしていて元気がない
勉強方法が間違っているかも。チェックテストの成績は良いのに実力テストで点が取れない場合
チェックテスト(授業前小テスト)では良い点数を取れているにもかかわらず、定例試験(実力テスト)になると成績が伸び悩んでしまう場合は、日々の学習が「詰め込み」になっているかもしれません。
理由や理屈を考えず丸暗記で頭に叩き込む学習は、深く理解することができておらず、せっかく身につけた知識の多くが時間と共に薄れていってしまいます。
特に5年生からは学習量が増加するだけでなく、内容が格段に難しくなるため、詰め込み学習では歯が立たなくなっていきます。
具体例
- チェックテストを数週間後にもう一度解かせると、正答率が下がっている
- 4年生までは点数が良かったのに、5年生になってから成績が伸び悩み始めた
本番に弱いタイプかも。頑張っているのに結果に結びつかない場合
授業をしっかり聞き、復習を行い、正しい勉強方法を身につけているにもかかわらず、なぜか模試になると成績が伸び悩む場合は「本番に弱い」状態に陥っているかもしれません。
例えば繊細なお子さまだと「また失敗したらどうしよう」「クラスが落ちるかもしれない」などと悪いことばかり考えて、本来の実力が出ない場合があります。また、気が散りやすいお子さまだと、ケアレスミスによって思わぬ失点をしている可能性があります。
具体例
- テストが終わると「できなかった」と言って泣いている
- 日頃から計算ミスや誤字などを指摘されている
定例試験で好成績を出す。市進学院で偏差値を上げる方法
市進学院で偏差値を上げるためには、定例試験(実力テスト)で好成績を安定して出す必要があります。ここでは、お子さまの実力を養成し、偏差値を上げるための方法をまとめています。保護者様ができることを具体的に紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
チェックテストで良い点数を取れるようにする
定例試験で好成績を出すためには、家庭で復習し、授業で習った内容を定着させる必要があります。
そこで、おすすめしたいのが「いきなり定例試験の好成績を目指すのではなく、まずはチェックテスト(授業前小テスト)で良い点数を取るようにする」というスモールステップ法です。チェックテストは前回の授業の要点がまとまっているため、復習ができているかの確認に最適です。
ただし、直前に丸暗記で詰め込む勉強法では、チェックテストで良い点数を取れてもすぐに忘れてしまうため意味がありません。正しい家庭学習のサイクルを習慣化し、確実に知識を積み重ねるように注意してください。
おすすめの学習サイクル
- 授業中にわからなかったことは「授業後フォロー」の時間に質問する
- 帰宅後(遅くても翌日まで)に授業プリントと教科書『必修シリーズ』を見直す
- 授業についていけていない場合は、映像授業で再度学習する
- 一週間の中で曜日と時間を決めて、家庭学習教材『ホームタスク』を演習する
- 家庭で復習してわからなかったとことは「授業前フォロー」の時間に質問する
- チェックテストを受け、間違えたところを再度復習する
保護者様ができること
- 家に帰って来たら復習をするように声を掛ける
- ホームタスクの演習を可能な限りでサポートする(丸付けなど)
- お子さまのチェックテストの結果を把握する
定例試験対策を徹底する
チェックテストで良い点数を安定して取れるようになったら、いよいよ定例試験対策に着手しましょう。まずは、学習日程カレンダーに記載されている定例試験の日程と出題範囲を確認し、対策スケジュールを立てます。
日々の授業の復習が疎かにならないように、保護者様が主導して余裕のある計画を立ててください。定例試験対策では、教科書『必修シリーズ』、授業プリント、『ホームタスク』の再復習に加えて、チェックテストの見直しを行います。
チェックテストは授業の要点がまとまっているため、時間がない場合も必ず見返すようにしましょう。余力がある場合は『トライアルシリーズ』に着手しても良いですが、消化不良にならないように演習内容には注意が必要です。
基本問題の理解が不十分な段階で応用問題を解いても、身につかないばかりか苦手意識が残ってしまいます。お子さまが「わかって楽しい」と思える問題から徐々に取り組むように、演習内容を取捨選択してください。
保護者様ができること
- 定例試験の日程と出題範囲を確認する
- 定例試験対策スケジュールをお子さまと一緒に立てる
- お子さまが「わかった」と思える程度に演習内容を取捨選択する
モチベーションを上げる
どんなに一生懸命勉強しても、偏差値はすぐに上昇するものではありません。お子さまによっては、頑張っているのに結果が出なくて自信がなくなったり、やる気がなくなったりするかもしれません。
その際は、努力したプロセスを保護者様が褒めてあげることが重要です。「計画どおりに勉強して偉かったね」「途中式をちゃんと書けるようになったね」などと、点数につながらなくても、お子さまができたことを見つけてほめるようにしてください。
「頑張っている所を見ていてくれる、認めてくれる」という安心感が「次回も頑張ろう」というやる気につながります。特に繊細なお子さまの場合は「なんで成績が上がらないんだろうね」などのネガティブな発言で、ますます緊張が高まってしまいます。定例試験後は笑顔で出迎え、明るく声を掛けてあげてください。
保護者様ができること
- お子さまができたことを見つけて褒める
- 定例試験後はポジティブな雰囲気づくりを心掛ける
個別指導を取り入れる
中学受験は保護者様にとって負担が大きいものです。日々の復習に付き合ったり学習計画を作ってあげたり、時間をかけてお子さまに向き合っているにもかかわらず、思い通りに偏差値が上がらないとがっかりしてしまいますよね。
保護者様の焦りや疲れ、イライラなどはお子さまの成績に悪影響を与えてしまいます。お子さまの受験が保護者様の大きな重荷になっているようであれば、個別指導を取り入れてみましょう。
プロ講師がお子さまのつまずきの原因を特定し、専用の学習プログラムを立案するため、偏差値を上げるためのより詳細な道筋を立てることができます。
塾での立ち位置が決まる。市進学院で偏差値が上がらない時は早急に対処しよう
「市進学院で偏差値が上がらない」とは、学力が思うように定着していないだけでなく、クラス落ちやプレップコース落ちの危険信号です。放置すると塾内での立ち位置がどんどん下がって、お子さまの自信を損なうことになってしまいます。早急に要因を分析して、保護者様が率先して対処をしてあげてください。
「いろいろと手を尽くしても偏差値が上がらない」や「何から手を付ければ良いかわからない」という場合は、個別指導も選択肢の一つです。保護者様だけで抱え込まず、お子さまとポジティブに受験ができるように意識してみてください。