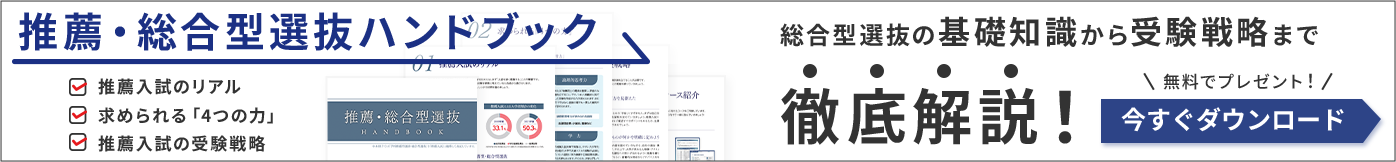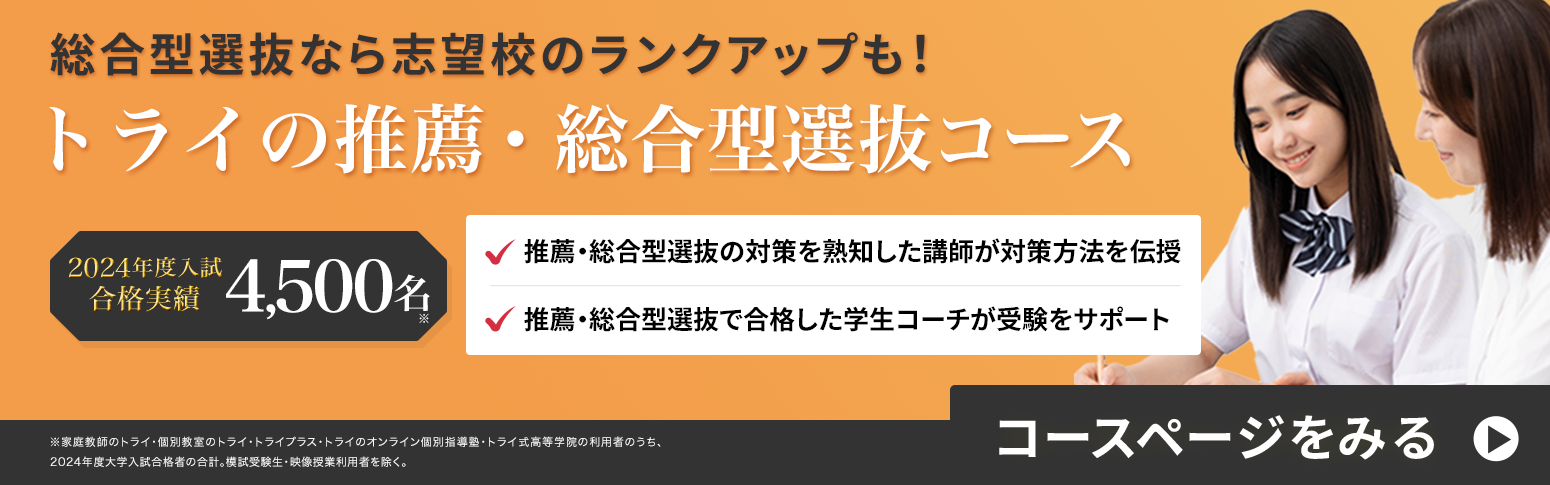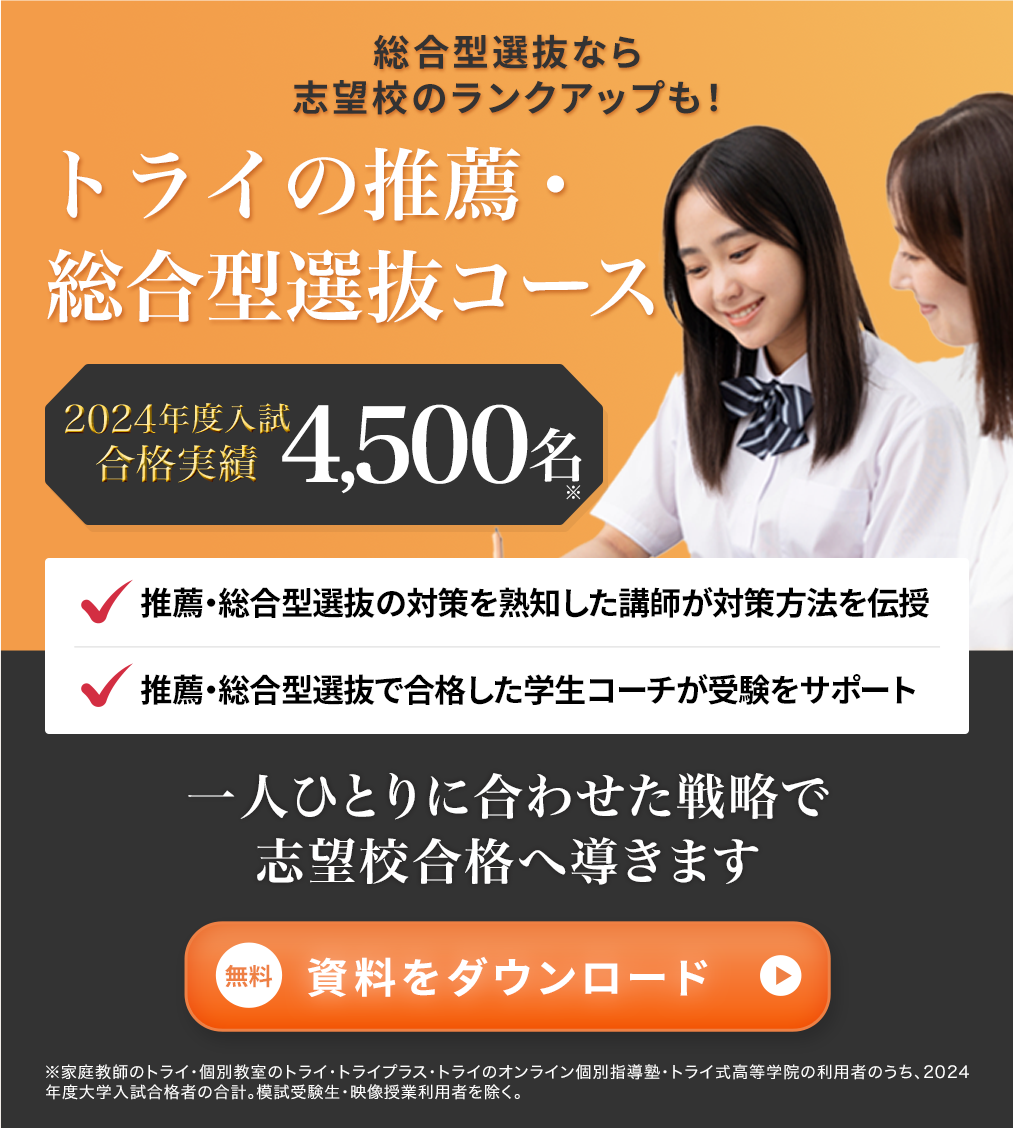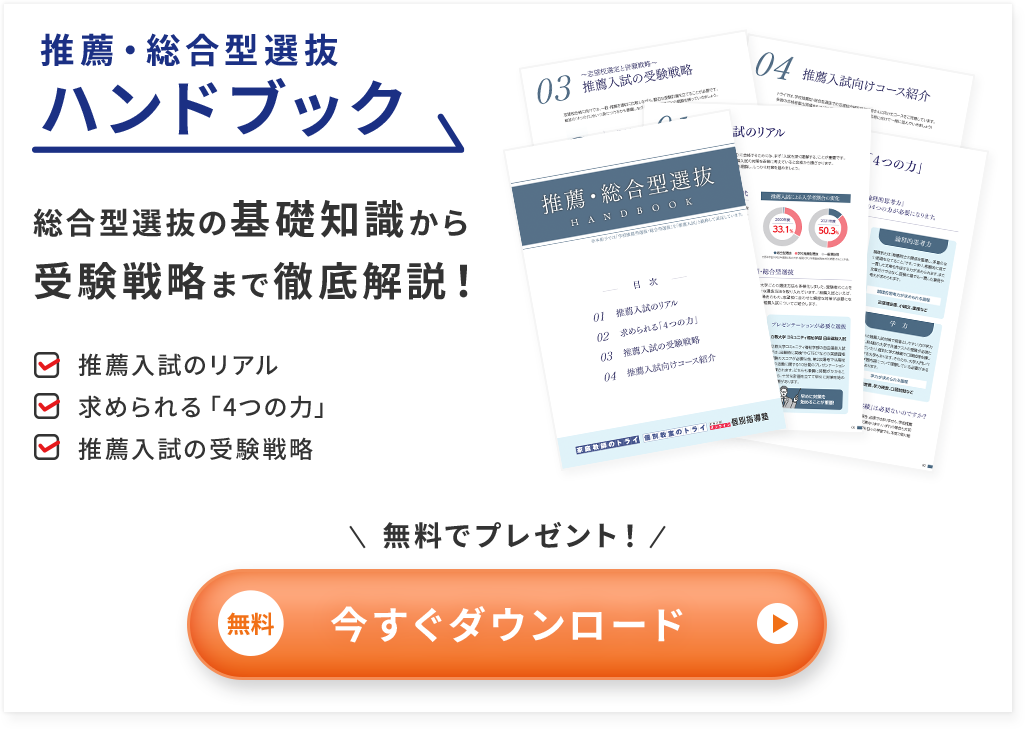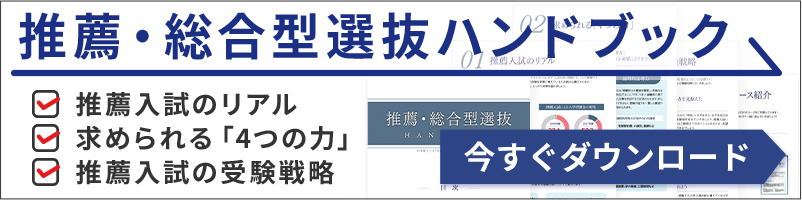同志社大学 文学部のアドミッションポリシー
文学部は、キリスト教主義・自由主義・国際主義に基づく人間形成を根本的な教育理念として、人文学の諸領域(英文学・哲学・美学芸術学・文化史学・国文学)における専門的な教育・研究をとおして、現代のグローバル社会の諸課題に自立的かつ実践的に対応する力を備えた人物を養成することを目的としています。そのために、次のような学生を求めています。
文学部の求める学生像
知識・技能:言語、文学、思想、宗教、芸術、文化、歴史、社会などの基本的知識を有し、これらに対して幅広い興味と関心を持っている学生。
思考力・判断力・表現力:高等学校までに培った確かな基礎学力に加え、それに基づく論理的思考力や判断力、それを的確に表現する力を身につけている学生。
主体性・多様性・協働性:何事も自明のことと思わず、自ら問題を発見し、合理的な手続きを踏んで、説得力のある解答を求めようとする学生。多様な価値観を持った人々との協働作業を通じて、グローバル社会の問題の解決策を探ろうとする学生。
- ※国際教養コースのアドミッション・ポリシーは、国際教育インスティテュートのウェブサイトを参照すること。
同志社大学のアドミッションポリシー
同志社大学は、創立者新島襄の建学の精神に基づき、「深く学問・技芸を探求するとともに、自治自立の精神を涵養し、国際感覚豊かな人物を育成する」ことを目的に、キリスト教主義を基本として人格を陶冶する教育を行っています。この教育理念を基本に置きながら、同志社大学では、140年を越える長きにわたって、社会的視野と倜儻不羈(てきとうふき・『才気がすぐれ、独立心が旺盛で、常軌では律しがたいこと』)の精神を兼ね備え、良心を手腕に運用しながら社会の発展に貢献できる人物を育成してきており、現在もその責務を果たすべく努力を積み重ねてきています。
同志社大学の学生受入に対する基本理念(アドミッション・ポリシー)は、上述の教育理念に基づいており、1)専門的・実学的能力を高める上で土台となる、幅広い教養と論理思考能力を育成するために必要な基礎学力を有し、2)知識の量だけでなく、社会的視野を持ち、大学での学習に対する意欲と熱意があり、3)多様な背景を持つ者と協働して学ぶ寛容の精神と主体性を持ち合わせ、4)優れた感性と特性を持った学生を受け入れることを目指し、次のような多彩な選抜制度を用意しています。
一般選抜入学試験
同志社大学の一般選抜入学試験は、高等学校教育を尊重しつつ、大学教育を受けるにふさわしい能力と適性を備えたものを公正かつ妥当に選抜することを目的としています。
入試問題の作成にあたっては、全学的に組織された科目ごとの出題委員会において長期間にわたって慎重に審議し、検討を重ね、高等学校での着実な学習努力が報われるように難問や奇問を避け、公平で偏りのない出題に留意しています。解答形式についても、マークシート方式をとらずにできるだけ記述式とし、論理的思考力や正確な表現力をみるよう努めています。特に計算力を問う出題については、記述式解答の方法をとり、丁寧に採点しています。
大学入学共通テストを利用する入学試験
同志社大学の大学入学共通テストを利用する入学試験は、入学志願者の高等学校までの学習の達成・定着度合いを判定するとともに、各学部での教育に必要とされる能力と適性を備えたものを選抜することを目的とするものであり、大学教育を受けるにふさわしい基本的な能力等を判定しています。学部・学科・コース・方式によっては、個別学力検査において小論文や口頭試問などを課すことにより、志願者の能力や意欲、適性などをより多面的・総合的に評価・判定できるように工夫しています。
アドミッションズ オフィス方式による入学者選抜
同志社大学のAO入試は、学力のみを重視する選抜方法ではありません。同志社大学で学びたいという意志を持ち、かつ学力試験では評価できない多様な能力、大きな可能性を秘めている学生を積極的に迎え入れようとする能動的な選抜方法です。
同志社大学のAO入試は、いわゆる一芸一能入試とは大きく異なります。一芸一能でいかに優れていても、総合的な評価の結果不合格になる場合もあります。つまり、AO入試は知識の多寡だけを問うのではなく、ましてや一芸一能だけを評価するものでもなく、一人ひとりの能力や個性と真の学力を適切に評価し、学習意欲や将来的な可能性までをも含めて総合的に評価する選抜方式です。本学で勉強することを強く望み、独自の考えを持ち、自ら問題を発見し、それを解決する能力を有している生徒、すなわち“自ら学び、自ら考える”自治自立の人物を求めています。
同志社大学のAO入試は、大学教育を受けるに十分な基礎学力があり、出願資格を満たしていれば、自分の意志で出願できる公募制の自己推薦入試です。第一次審査(書類)と第二次審査で合格を判定します。提出書類をひとつひとつじっくり時間をかけて審査し、さらに直接会ったうえで、意欲・能力・適性・目的意識や将来性等を多面的・総合的に評価し、合格者を決定します。
推薦選抜入学試験・自己推薦入学試験
学力・人物ともに優秀で、本学で学ぶことを強く希望する生徒が、学校長などの推薦を受けて、あるいは推薦を受けなくても、出願できる制度です。学部・学科・コースによって様々な出願資格を定めており、個人的研鑽を通して高度な技能や資格を習得した方や、スポーツ活動、競技会等で顕著な成績をあげた方々、あるいは、ボランティア活動や福祉活動で指導的な役割を果たした方など、多様な経験とそれに裏打ちされた能力や資質・適性などを、書類審査や小論文、面接、口頭試問などの判定方法により、幅広く多面的・総合的に評価し、合格者を決定します。
指定校制推薦入学試験
学力・人物ともに優秀で、本学で学ぶことを特に強く希望する者が、学校長の推薦を受けて出願できる専願制の入学試験です。本学の教育理念である、キリスト教主義、自由主義、国際主義に対する深い共感と理解を有し、入学後の勉学について明確な志向と意欲を持つ方を求めています。調査書や小論文、面接、口頭試問などを通じて、能力や資質等を多面的・総合的に評価し、合格を判定します。
法人内各学校推薦入学試験
学校法人同志社が設置する4つの高等学校で、創立者新島襄の人生やその思想、同志社建学の精神や教育理念についてより深く接し、「キリスト教主義」「自由主義」「国際主義」に基づく「知・徳・体」の全人格教育を受けた者が、学校長の推薦を受けて出願できる専願制の入学試験です。良心を手腕に運用する人物、つまり自治・自立の精神にあふれ、博愛精神に富み、個人の尊厳を重んずる人物、高いモラルや高潔な人格を有する人物、そして国際社会で創造的な活動のできる人物を育成することを目的とする同志社一貫教育の精神を理解し、入学後の勉学について明確な目的意識を持つ方を求めています。調査書や小論文、面接、口頭試問などを通じて、能力や資質等を多面的・総合的に評価し、合格を判定します。
同志社大学 文学部 英文学科のアドミッションポリシー
高等学校段階までの学習で身につけてほしいこと
英語:グローバル社会に対応し、貢献できる人物を育成することを目的とする英文学科は、高い英語能力を習得した人物をつよく求めています。具体的には、英語で話された内容を正確に聞き取って把握する力、自らの意見や考えを英語で主体的に表現できる発話力、英文で書かれた長い文章を読みこなし、その趣旨を的確に理解できる読解力、さらには論理的で適切な表現を用いて英文を書くことができる作文力を身につけることが重要です。こんにち国内外で展開する事象に対する広範な知識を得るためにも、また自発的発信をするためにも、このような英語運用技能は必要不可欠です。入学までに、正しい文法知識、豊富な語彙力といった英語力の基礎を習得し、多くの英文を読み、書く力をつけるように努力してください。
国語(現代文):英語を用いた高度なコミュニケーション能力、また、グローバル社会で必要とされる豊かな感性と柔軟な思考力、的確な表現力を育むためには、論理的思索を支える国語能力が不可欠です。具体的には、文章の内容を正確に理解し、その趣旨を要約できる読解力、提起された課題に対して、問題の所在を正確に判断し、多角的な視点からの分析と考察をとおして、自らの見解を構築することができる論理的思考力、さらに、それを順序立てて論拠を示しつつ、わかりやすく説明することができる表現力および文章構成力が必要です。国語による思考力・判断力・表現力の向上は英語使用時にも反映されますので、日頃から、論説文や文学作品など、多様な文章に親しみ、国語での語彙力や表現力を磨くように心がけてください。
地理歴史(世界史・地理):多様化するグローバル社会における諸問題の理解およびそれらの解決への貢献には、これらの諸問題の歴史的・風土的な背景の理解が不可欠です。英語圏およびその関連地域の歴史や文化は、近現代のグローバル社会の形成そのものに大きな役割を果たしてきました。英米の文化および言語という英文学科における専門的学問領域を研究することは、こんにちの世界の動向とその諸問題への多角的な理解と、その解決方法策定の資質を培うことへと繋がっています。異文化への鋭敏な感性と柔軟な判断力を身につけ、協働的に社会貢献しうる主体性を養うために、世界の各地域の歴史と地理について深い関心と共感を持って学び、正確な知識を習得することが必要です。
取得しておくことが望ましい資格等
TOEIC®LISTENING AND READINGテスト、TOEFL®テスト、IELTSのいずれかを受験しておくことが望まれます。
入学者選抜制度
文学部英文学科では、高等学校で学習する教科の学力のほかに、英米文学・英米文化、英語学・英語教育に対する関心、学習意欲、表現力やコミュニケーション力などを評価する多様な入学者選抜を行うことにより、多様な学生を受け入れています。本学独自の学力試験のほかに、大学入学共通テスト、書類審査、口頭試問、小論文などを取り入れることにより、学力の3要素「知識・技能」、「思考力・判断力・表現力」、「主体性・多様性・協働性」について、それぞれの入試方式において重み付けを行い評価し、志願者の能力や資質等を総合的に審査しています。
一般選抜入学試験:高等学校教育を尊重し、高等学校までの学習の達成・定着度を測るとともに、文学部の教育を受けるにふさわしい能力と適性を備えたものを公正かつ妥当に選抜するために一般選抜入学試験を実施しています。入試問題の作成にあたっては、全学的に組織された科目ごとの出題委員会において長期間にわたって慎重に審議し、検討を重ね、高等学校での着実な学習努力が報われるように難問や奇問を避け、公平で偏りのない出題に留意しています。とりわけ、本入試においては、マークシート方式ではなく記述式を用いた独自の入試問題による選抜を行うことで、知識・技能のみならず出題意図を正確に理解する力や論理的思考力、正確な表現力の評価にも重点を置き、総合的に審査しています。計算力を問う出題についても同様に記述式解答方法を用いており、結論に至るプロセス等も含め、丁寧に採点しています。
大学入学共通テストを利用する入学試験:入学志願者の高等学校までの学習の達成・定着度を測るとともに、文学部英文学科の教育を受けるために必要な学力が備わっているかを大学入学共通テストによって評価しています。英文学科では、英語特化型のA方式と3科目試験型のB方式を実施し、特にA方式では、学科独自の英語および日本語での口頭試問を課すことにより「思考力・判断力・表現力」や「主体性・多様性・協働性」の評価に重点を置くと同時に、文学部英文学科での学修に必要な日本語の運用能力とともに、高い英語力と分析力が備わっているかについても、総合的に審査しています。
推薦選抜入学試験(公募制):高等学校での学習及び課外活動を通じてこれまでに培われた基礎学力、「知識・技能」、「思考力・判断力・表現力」等を備え、文学部英文学科で学ぶ高い意欲を持つ人物を選抜するために、出願書類では一定水準以上の「知識・技能」が備わっているかを、TOEFL®テスト、TOEIC®LISTENING AND READINGテストのスコアによって審査しています。小論文では文学部英文学科で学ぶために必要な「思考力・判断力・表現力」が備わっているか、口頭試問では「主体性・多様性・協働性」が備わっているかなどを適正に評価しています。とりわけ、本入試においては、高い英語力が備わっているかの評価にも重点を置き、上記と合わせて総合的に審査しています。
指定校制推薦入学試験:高等学校での学習及び課外活動を通じてこれまでに培われた基礎学力、「知識・技能」、「思考力・判断力・表現力」等を備え、かつ文学部英文学科で学ぶ高い意欲を持つ優れた人物を受け入れるために、学校長の推薦に基づき、出願書類では一定水準以上の「知識・技能」および文学部英文学科で学ぶために必要な「思考力・判断力・表現力」が備わっているか、口頭試問では「主体性・多様性・協働性」が備わっているかなどを適正に評価しています。加えて、一般指定校推薦入学試験では、小論文によって「思考力・判断力・表現力」が備わっているかなどを評価しています。とりわけ、本入試においては、入学後の勉学に対する明確な志向及び意欲の評価に重点を置き、総合的に審査しています。
法人内諸学校推薦入学試験:同志社の一貫教育を通じて、同志社大学の建学の精神を深く理解し、文学部英文学科で学ぶ高い意欲や相応しい学力を備え、学部の核となり他の学生をリードし、ひいては大学全体の活性化にも寄与できるような優れた人物を受け入れるために、出願書類では一定水準の「知識・技能」が備わっているかを、TOEFL®テスト、TOEIC®LISTENING AND READINGテストのスコアによって審査しています。口頭試問では「思考力・判断力・表現力」および「主体性・多様性・協働性」が備わっているかなどを適正に評価しています。本入試においては、「主体性・多様性・協働性」の評価に重点を置くと同時に、高い英語力が備わっているかについても審査しています。
- ※国際教養コースのアドミッション・ポリシーは、国際教育インスティテュートのウェブサイトを参照すること。
同志社大学 文学部 哲学科のアドミッションポリシー
高等学校段階までの学習で身につけてほしいこと
英語:哲学科では、哲学・倫理学の古典を研究するうえで、英語、ドイツ語、フランス語、さらにはギリシャ語やラテン語等の外国語の学びが不可欠と考えています。とくに、哲学科の教育課程は、英語、ドイツ語、フランス語のうち、二カ国語を学ぶ仕組みになっています。しかし、どのような外国語であろうと、その習得には時間がかかります。それゆえ、まずは、日本の学校教育の制度からいっても、英語の学習を基本としてください。英語を勉強するさいにも、やはり、文献読解の基礎的技能としての読む力、書く力、話す力が重要になります。わけても、読む力を身につけることが肝要です。学習の目標は、辞書がなくても英語の文献を読めるようになるところにありますが、他方で、辞書を使いながら内容を正確に理解して、各人の視点からそれを分析できるようになるまで読み抜くことも大切です。辞書を使わないで文献を読み大意を掴む訓練と、辞書を丹念に調べて文献を丁寧に最後まで読む進める作業の二つに取り組んでほしいものです。
国語(現代文):哲学科では、文献を読むこと、自分が思っていることを他者に伝えること、自分が理解し考えたことを書くことが学習の基本となります。それゆえ、自分たちの母語である日本語については、読む力、書く力、話す力はもちろんのこと、日本語についての深い理解も求められます。その意味で、哲学は、言葉を駆使して物事を原理的にかつ批判的に考察する営みです。聖書の言うように、「初めに言葉ありき」ということです。そこで要求されるのは、自己の経験に根ざした論理的思考力、他者に伝わる自己表現力、さまざまな文章を書き分ける言語能力です。しかも、言葉は、他者とのコミュニケーションを成立させている、いわば道具の役目を担っています。言葉の力を身につけるためにも、国語(現代文)の学習を通じて、読書、対話、作文に取り組むことで、日頃から言葉についての意識を仲間とともに協動的に高めていってください。
地理歴史(世界史・日本史):哲学科では、哲学・倫理学の古典を学ぶことを旨としています。哲学を学ぶうえで欠かせないのが哲学史の勉強です。哲学史を学ぶうえでは、どうしても歴史の理解が必要になってきます。古典ギリシャを初めとする古代から現代まで、広く、西洋、東洋、日本の歴史の理解が要ります。そのさいに歴史的事実の把握が必要になることは言うまでもありません。歴史(世界史、日本史)の学習を通じて、まずは、哲学史を学ぶための土台として、そうした知識を蓄えていってください。つぎに大切になるのは、そのような知識を結びあわせて歴史的な流れを掴む思考力です。歴史についての知的教養がなければ、哲学的な洞察も浅いものに終わるでしょう。それゆえ、物事に対する原理的かつ批判的な目で、人間とそれを取り巻く世界について主体的に考えていくには、歴史感覚なり歴史観なり、世界の歴史についての鋭い意識がなければなりません。世界のさまざまなあり方に敏感になれる多様性の精神、世界でこれまで起こってきたできごとを通覧できる大局的なものの見方、それらを身につけてほしいと思います。
入学者選抜制度
文学部哲学科では、高等学校で学習する教科の学力のほかに、哲学・倫理学に対する関心、学習意欲、表現力やコミュニケーション力などを評価する多様な入学者選抜を行うことにより、多様な学生を受け入れています。本学独自の学力試験のほかに、大学入学共通テスト、書類審査、口頭試問、筆記試験などを取り入れることにより、学力の3要素「知識・技能」、「思考力・判断力・表現力」、「主体性・多様性・協働性」について、それぞれの入試方式において重み付けを行い評価し、志願者の能力や資質等を総合的に審査しています。
一般選抜入学試験:高等学校教育を尊重し、高等学校までの学習の達成・定着度を測るとともに、文学部の教育を受けるにふさわしい能力と適性を備えたものを公正かつ妥当に選抜するために一般選抜入学試験を実施しています。入試問題の作成にあたっては、全学的に組織された科目ごとの出題委員会において長期間にわたって慎重に審議し、検討を重ね、高等学校での着実な学習努力が報われるように難問や奇問を避け、公平で偏りのない出題に留意しています。とりわけ、本入試においては、マークシート方式ではなく記述式を用いた独自の入試問題による選抜を行うことで、知識・技能のみならず出題意図を正確に理解する力や論理的思考力、正確な表現力の評価にも重点を置き、総合的に審査しています。計算力を問う出題についても同様に記述式解答方法を用いており、結論に至るプロセス等も含め、丁寧に採点しています。
大学入学共通テストを利用する入学試験:入学志願者の高等学校までの学習の達成・定着度を測るとともに、文学部哲学科の教育を受けるために必要な学力が備わっているか、大学入学共通テストにより評価しています。
指定校制推薦入学試験:高等学校での学習及び課外活動を通じてこれまでに培われた基礎学力、「知識・技能」、「思考力・判断力・表現力」等を備え、かつ文学部哲学科で学ぶ高い意欲を持つ優れた人物を受け入れるために、学校長の推薦に基づき、出願書類では一定水準以上の「知識・技能」および文学部哲学科で学ぶために必要な「思考力・判断力・表現力」が備わっているか、口頭試問では「主体性・多様性・協働性」が備わっているかなどを適正に評価しています。とりわけ、本入試においては、入学後の勉学における明確な志向及び意欲の評価に重点を置き、総合的に審査しています。
法人内諸学校推薦入学試験:同志社の一貫教育を通じて、同志社大学の建学の精神を深く理解し、文学部哲学科で学ぶ高い意欲や相応しい学力を備え、学部の核となり他の学生をリードし、ひいては大学全体の活性化にも寄与できるような優れた人物を受け入れるために、出願書類では一定水準の「知識・技能」が備わっているか、筆記試験では文学部哲学科で学ぶために必要な「思考力・判断力・表現力」が備わっているか、口頭試問では「主体性・多様性・協働性」が備わっているかなどを適正に評価しています。とりわけ、本入試においては、「主体性・多様性・協働性」の評価に重点を置き、総合的に審査しています。
- ※国際教養コースのアドミッション・ポリシーは、国際教育インスティテュートのウェブサイトを参照すること。
同志社大学 文学部 美学芸術学科のアドミッションポリシー
高等学校段階までの学習で身につけてほしいこと
英語:美や芸術をめぐる思索は、日本文化の枠内で完結するわけではありません。西洋の美学や芸術を西洋的な視点から学ぶために英語の知識や技能が必要であるのは当然ですが、日本や東洋の美学や芸術の研究をするうえでも、英語で書かれた研究書の読解はとても重要になります。比較的なじみのある身の回りの文化を外からの目で再発見する驚きは、新たな視点をもち、思考力を身につけるために、とても有意義なものとなります。またグローバル化や情報化が進む現代の多様な状況において、主体的に自分の考えや日本の美を海外に発信し表現するために、更に相互のコミュニケーションを通じて協働するためにも、英語力は不可欠のものです。世界に開かれた美や芸術の世界にふれあうために、英語力の基礎を身につけるよう努力してください。
国語(現代文):美学芸術学科での学びでは、高度な国語の知識や技能が求められます。それは研究書や古典的なテキストを正確に読解したり、それを的確に要約したりするためだけではありません。その研究書の論に論理的な乱れはないのか、反論の余地はないのかと考え、さらに思考し判断する力を深めるためにも鍛え抜かれた国語力が必要です。さらには豊富な語彙を的確に用い、確かな根拠に基づいて自分の考えをわかりやすく論理的に表現することも求められます。授業のレポートやゼミ発表、最終的には卒業論文の作成へと至る過程で、複雑な内容を主体的に考え、多様な意見を取り入れる協働性に基づいて表現するようになりますが、そのような言葉との関わりに耐えうるような基礎力を、日頃から鍛えておいてください。
地理歴史(世界史・日本史):西洋や日本・東洋の美や芸術をめぐる思索を深めるにあたって、それぞれの歴史についての素養が必要になります。現代芸術について研究するなら必要ないと思う人がいるかもしれません。しかし現代の芸術や、芸術をめぐる思索は歴史的に積み重ねられてきた文化のうえに成り立つものであり、そのような知識を前提としたうえで、なぜ、どのようにして我々に身近な芸術が生じてきたかを知ることが大切です。また世界の多様性に満ちた美や芸術を知らずに日本の美や芸術の魅力が真に理解できるはずもありません。自分の視野を狭く限定することなく、広範な歴史的素養を身につけ、国際的交流や協働のうえで解決しうる能力を目指し、美学芸術学科での学びを楽しめるように準備してください。
入学者選抜制度
文学部美学芸術学科では、高等学校で学習する教科の学力のほかに、美学芸術学に対する関心、学習意欲、表現力やコミュニケーション力などを評価する多様な入学者選抜を行うことにより、多様な学生を受け入れています。本学独自の学力試験のほかに、大学入学共通テスト、書類審査、口頭試問、小論文などを取り入れることにより、学力の3要素「知識・技能」、「思考力・判断力・表現力」、「主体性・多様性・協働性」について、それぞれの入試方式において重み付けを行い評価し、志願者の能力や資質等を総合的に審査しています。
一般選抜入学試験:高等学校教育を尊重し、高等学校までの学習の達成・定着度を測るとともに、文学部の教育を受けるにふさわしい能力と適性を備えたものを公正かつ妥当に選抜するために一般選抜入学試験を実施しています。入試問題の作成にあたっては、全学的に組織された科目ごとの出題委員会において長期間にわたって慎重に審議し、検討を重ね、高等学校での着実な学習努力が報われるように難問や奇問を避け、公平で偏りのない出題に留意しています。とりわけ、本入試においては、マークシート方式ではなく記述式を用いた独自の入試問題による選抜を行うことで、知識・技能のみならず出題意図を正確に理解する力や論理的思考力、正確な表現力の評価にも重点を置き、総合的に審査しています。計算力を問う出題についても同様に記述式解答方法を用いており、結論に至るプロセス等も含め、丁寧に採点しています。
大学入学共通テストを利用する入学試験:入学志願者の高等学校までの学習の達成・定着度を測るとともに、文学部美学芸術学科の教育を受けるために必要な学力が備わっているか、大学入学共通テストにより評価しています。
推薦選抜入学試験(公募制):高等学校での学習及び課外活動を通じてこれまでに培われた基礎学力、「知識・技能」、「思考力・判断力・表現力」等を備え、文学部美学芸術学科で学ぶ高い意欲を持つ人物を選抜するために、出願書類では一定水準以上の「知識・技能」および「主体性・多様性・協働性」が備わっているか、小論文では文学部美学芸術学科で学ぶために必要な「思考力・判断力・表現力」が備わっているか、口頭試問では「主体性・多様性・協働性」が備わっているかなどを適正に評価しています。とりわけ、本入試においては、「主体性・多様性・協働性」の評価に重点を置き、総合的に審査しています。
法人内諸学校推薦入学試験:同志社の一貫教育を通じて、同志社大学の建学の精神を深く理解し、文学部美学芸術学科で学ぶ高い意欲や相応しい学力を備え、学部の核となり他の学生をリードし、ひいては大学全体の活性化にも寄与できるような優れた人物を受け入れるために、出願書類では一定水準の「知識・技能」が備わっているか、小論文では文学部美学芸術学科で学ぶために必要な「思考力・判断力・表現力」が備わっているか、口頭試問では「主体性・多様性・協働性」が備わっているかなどを適正に評価しています。とりわけ、本入試においては、「主体性・多様性・協働性」の評価に重点を置き、総合的に審査しています。
- ※国際教養コースのアドミッション・ポリシーは、国際教育インスティテュートのウェブサイトを参照すること。
同志社大学 文学部 文化史学科のアドミッションポリシー
高等学校段階までの学習で身につけてほしいこと
英語:英語、外国語は、国際化した現代において不可欠というだけではなく、私たちが無意識に使っている自国語を相対化し、普遍的な思考と叙述をトレーニングさせる機能もあります。西洋史・東洋史を専攻する学生にとっては、いうまでもなく外国文献を読み解くことが研究の前提です。留学にも不可欠な能力となります。また、日本史を専攻する学生でも近現代史研究においてはもちろんのこと、前近代の研究でも外国の日本学の研究成果に目配りするために必要です。学術雑誌に載せる論文が英文要旨を要求しているように、研究内容を他言語で表現することは普遍的な分析概念を自覚的に設定させる契機ともなります。
国語(現代文・古典):卒業論文の作成につながる大学の歴史研究では、先行研究を正確に把握する理解力、文献史料を深く読み解く技能、そして自分の見解を論理的に伝える表現力、この三者が不可欠です。正確な読解力と表現力は思考の写し鏡なのです。また、日本史を専攻する学生は、1年次生から漢文・古文で書かれた史料を日常的に扱うことになり、東洋史を専攻する学生にとっても漢文講読は必須となりますから、それらの基礎学力は不可欠です。入試で漢文が出題されようとされまいと、きちんと学習しておいてください。
地理歴史(世界史・日本史):大学で専門の学問として歴史学を勉強するのですから、日本史や世界史の基礎的な知識と考え方を身につけておくことが必要です。大学での主体的・能動的な学びのためには、暗記だけではなく、歴史の大きな流れや時代・地域の特徴を理解することが大事です。歴史的な重要事項についての基本的な知識を習得しておくことは、総合的な歴史観を養う大学での授業を理解し、現代社会の諸問題を発見するのに役に立ちます。
入学者選抜制度
文学部文化史学科では、高等学校で学習する教科の学力のほかに、文化史学に対する関心、学習意欲、表現力やコミュニケーション力などを評価する多様な入学者選抜を行うことにより、多様な学生を受け入れています。本学独自の学力試験のほかに、大学入学共通テスト、書類審査、口頭試問、筆記試験などを取り入れることにより、学力の3要素「知識・技能」、「思考力・判断力・表現力」、「主体性・多様性・協働性」について、それぞれの入試方式において重み付けを行い評価し、志願者の能力や資質等を総合的に審査しています。
一般選抜入学試験:高等学校教育を尊重し、高等学校までの学習の達成・定着度を測るとともに、文学部の教育を受けるにふさわしい能力と適性を備えたものを公正かつ妥当に選抜するために一般選抜入学試験を実施しています。入試問題の作成にあたっては、全学的に組織された科目ごとの出題委員会において長期間にわたって慎重に審議し、検討を重ね、高等学校での着実な学習努力が報われるように難問や奇問を避け、公平で偏りのない出題に留意しています。とりわけ、本入試においては、マークシート方式ではなく記述式を用いた独自の入試問題による選抜を行うことで、知識・技能のみならず出題意図を正確に理解する力や論理的思考力、正確な表現力の評価にも重点を置き、総合的に審査しています。計算力を問う出題についても同様に記述式解答方法を用いており、結論に至るプロセス等も含め、丁寧に採点しています。
大学入学共通テストを利用する入学試験:入学志願者の高等学校までの学習の達成・定着度を測るとともに、文学部文化史学科の教育を受けるために必要な学力が備わっているか、大学入学共通テストにより評価しています。
指定校制推薦入学試験:高等学校での学習及び課外活動を通じてこれまでに培われた基礎学力、「知識・技能」、「思考力・判断力・表現力」等を備え、かつ文学部文化史学科で学ぶ高い意欲を持つ優れた人物を受け入れるために、学校長の推薦に基づき、出願書類では一定水準以上の「知識・技能」および文学部文化史学科で学ぶために必要な「思考力・判断力・表現力」が備わっているか、口頭試問では「主体性・多様性・協働性」が備わっているかなどを適正に評価しています。とりわけ、本入試においては、入学後の勉学における明確な志向及び意欲の評価に重点を置き、総合的に審査しています。
法人内諸学校推薦入学試験:同志社の一貫教育を通じて、同志社大学の建学の精神を深く理解し、文学部文化史学科で学ぶ高い意欲や相応しい学力を備え、学部の核となり他の学生をリードし、ひいては大学全体の活性化にも寄与できるような優れた人物を受け入れるために、出願書類では一定水準の「知識・技能」が備わっているか、筆記試験では文学部文化史学科で学ぶために必要な「思考力・判断力・表現力」が備わっているか、口頭試問では「主体性・多様性・協働性」が備わっているかなどを適正に評価しています。とりわけ、本入試においては、「主体性・多様性・協働性」の評価に重点を置き、総合的に審査しています。
- ※国際教養コースのアドミッション・ポリシーは、国際教育インスティテュートのウェブサイトを参照すること。
同志社大学 文学部 国文学科のアドミッションポリシー
高等学校段階までの学習で身につけてほしいこと
英語:国文学科は、日本文化について深い理解を持って世界と真に対話できる総合的な人間力を養うことを大切にしています。グローバル化・情報化が急速に進む現代社会だからこそ、日本文学と日本語を探求することで得た知識・技能により、日本文化を正しく理解し、その魅力を世界に向けて広く発信できる人物を養成して、社会に送り出していきたいと考えるのです。日本語と異なる言語習得に必要な思考力と判断力を養い、英語特有の表現力を身につけることは、日本語と日本文学を客観的に見つめ直し、再認識するための重要な手段となります。また、海外の文化を吸収し、世界の多様性を理解したうえで、主体性を持って日本文化を世界に発信し、国際社会に貢献できる人間としての協働性を発揮できるようになるためには、相応の英語運用能力が必要になります。入学までに可能な限り英語力の向上に努力してください。
国語(現代文・古典):文章の内容を正確に理解し、また、自己の主張を明確に伝えるうえで、国語の知識・技能は不可欠です。現代文、古文・漢文を読んでその内容を的確に読み取ることのできる文章読解能力、明確な根拠に基づく思考力と判断力、自分の考えを他者にわかりやすく伝えることのできる論理的な表現力、文章構成力は、国文学科で学ぶために必要な能力ですから、その向上に努めてください。また、日頃から多くの書物を読むように心がけ、世界や物事の多様性を学んでください。さらに、論理的思考力を養うためにも、折にふれ、積極的に自分の考えを文章化する主体性と、他者との議論を通じて協働性を身につけてほしいと思います。
地理歴史(世界史・日本史):日本文学・日本語は、古代から現代に至る幅広い時代の知の結晶です。各時代に使われている言葉、各時代に生み出された文学作品について、実証的かつ理論的に研究するためには、対象となる言葉や作品を支えている歴史的背景を理解するための知識と技能が必要不可欠です。日本語・日本文学を取り巻く諸問題を歴史の中に位置づけて考える思考力と判断力が、それらの問題のより深い理解をもたらし、国際社会に求められるこまやかな表現力を習得する手助けともなります。世界と日本の歴史に関心を持って、世界の多様性を認識するとともに、主体性を持って国際社会に関わり、国際社会に自立的かつ実践的に対応するための協働性を身につけていくために有益な知識となる歴史関連諸科目を十分に学んでください。
入学者選抜制度
文学部国文学科では、高等学校で学習する教科の学力のほかに、国文学に対する関心、学習意欲、表現力やコミュニケーション力などを評価する多様な入学者選抜を行うことにより、多様な学生を受け入れています。本学独自の学力試験のほかに、大学入学共通テスト、書類審査、口頭試問、小論文などを取り入れることにより、学力の3要素「知識・技能」、「思考力・判断力・表現力」、「主体性・多様性・協働性」について、それぞれの入試方式において重み付けを行い評価し、志願者の能力や資質等を総合的に審査しています。
一般選抜入学試験:高等学校教育を尊重し、高等学校までの学習の達成・定着度を測るとともに、文学部の教育を受けるにふさわしい能力と適性を備えたものを公正かつ妥当に選抜するために一般選抜入学試験を実施しています。入試問題の作成にあたっては、全学的に組織された科目ごとの出題委員会において長期間にわたって慎重に審議し、検討を重ね、高等学校での着実な学習努力が報われるように難問や奇問を避け、公平で偏りのない出題に留意しています。とりわけ、本入試においては、マークシート方式ではなく記述式を用いた独自の入試問題による選抜を行うことで、知識・技能のみならず出題意図を正確に理解する力や論理的思考力、正確な表現力の評価にも重点を置き、総合的に審査しています。計算力を問う出題についても同様に記述式解答方法を用いており、結論に至るプロセス等も含め、丁寧に採点しています。
大学入学共通テストを利用する入学試験:入学志願者の高等学校までの学習の達成・定着度を測るとともに、文学部国文学科の教育を受けるために必要な学力が備わっているか、大学入学共通テストにより評価しています。
推薦選抜入学試験(公募制):高等学校での学習及び課外活動を通じてこれまでに培われた基礎学力、「知識・技能」、「思考力・判断力・表現力」等を備え、文学部国文学科で学ぶ高い意欲を持つ人物を選抜するために、出願書類では一定水準以上の「知識・技能」および「主体性・多様性・協働性」が備わっているか、小論文では文学部国文学科で学ぶために必要な「思考力・判断力・表現力」が備わっているか、口頭試問では「主体性・多様性・協働性」が備わっているかなどを適正に評価しています。とりわけ、本入試においては、「主体性・多様性・協働性」の評価に重点を置き、総合的に審査しています。
指定校制推薦入学試験:高等学校での学習及び課外活動を通じてこれまでに培われた基礎学力、「知識・技能」、「思考力・判断力・表現力」等を備え、かつ文学部国文学科で学ぶ高い意欲を持つ優れた人物を受け入れるために、学校長の推薦に基づき、出願書類では一定水準以上の「知識・技能」および文学部国文学科で学ぶために必要な「思考力・判断力・表現力」が備わっているか、口頭試問では「主体性・多様性・協働性」が備わっているかなどを適正に評価しています。とりわけ、本入試においては、入学後の勉学における明確な志向及び意欲の評価に重点を置き、総合的に審査しています。
法人内諸学校推薦入学試験:同志社の一貫教育を通じて、同志社大学の建学の精神を深く理解し、文学部国文学科で学ぶ高い意欲や相応しい学力を備え、学部の核となり他の学生をリードし、ひいては大学全体の活性化にも寄与できるような優れた人物を受け入れるために、出願書類では一定水準の「知識・技能」が備わっているか、口頭試問では「思考力・判断力・表現力」および「主体性・多様性・協働性」が備わっているかなどを適正に評価しています。とりわけ、本入試においては、「主体性・多様性・協働性」の評価に重点を置き、総合的に審査しています。
- ※国際教養コースのアドミッション・ポリシーは、国際教育インスティテュートのウェブサイトを参照すること。