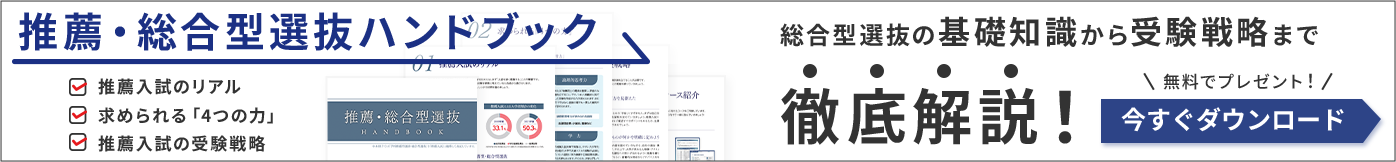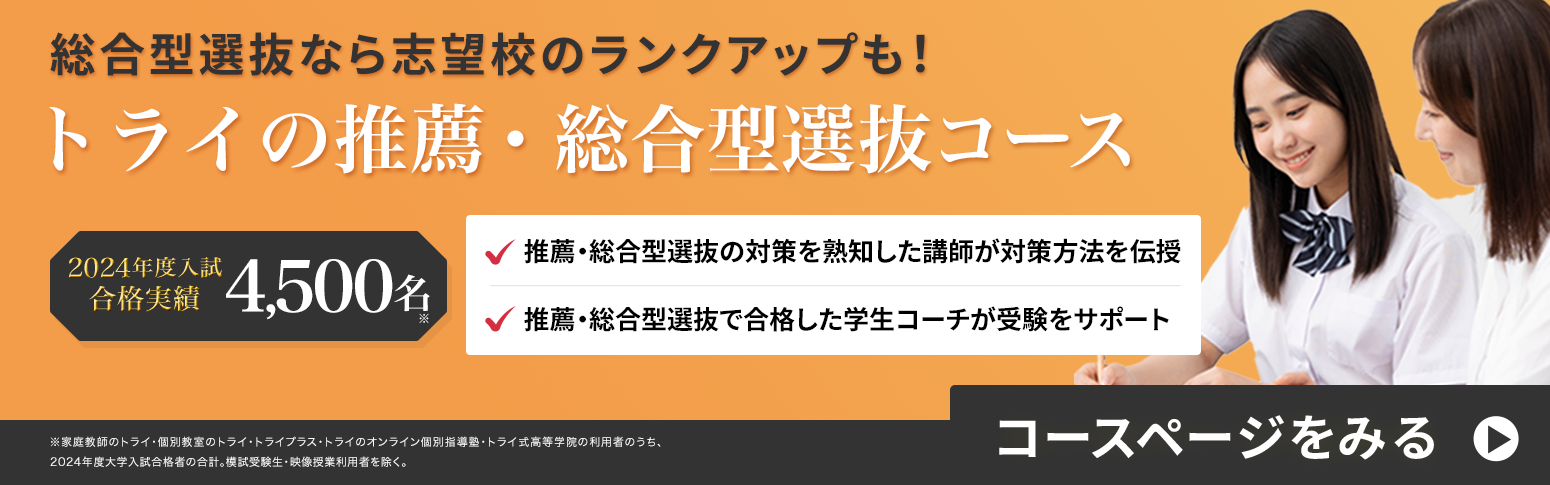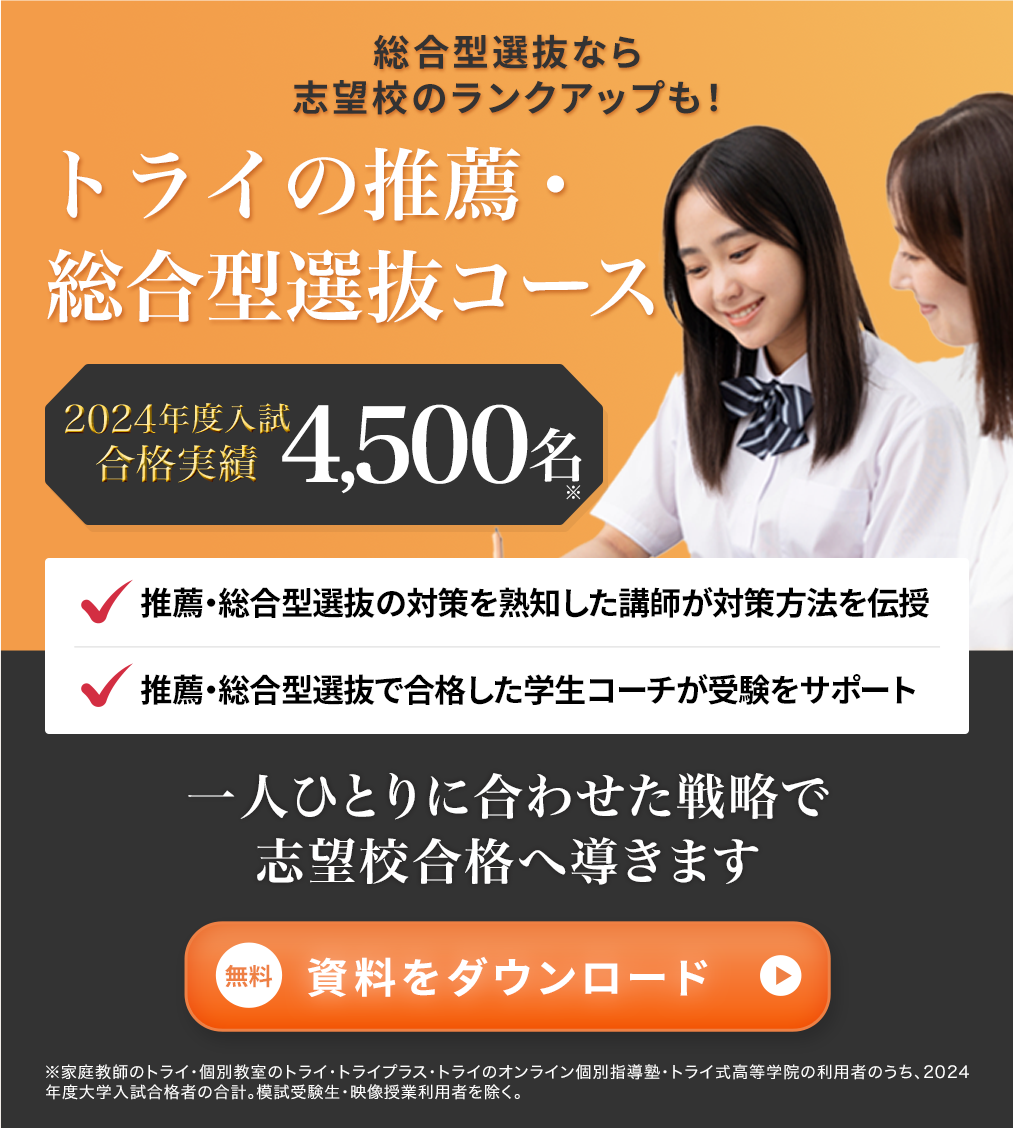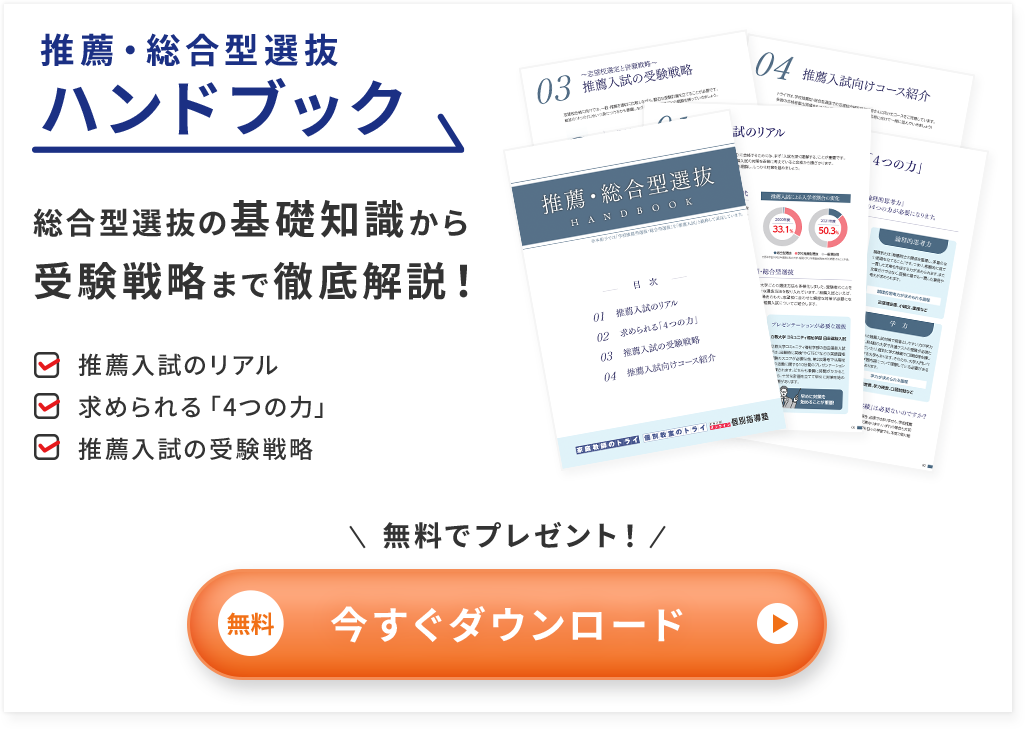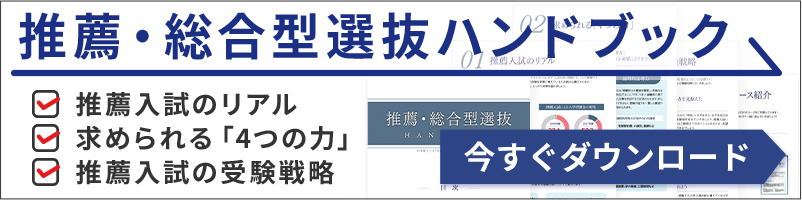同志社大学のアドミッションポリシー
同志社大学は、創立者新島襄の建学の精神に基づき、「深く学問・技芸を探求するとともに、自治自立の精神を涵養し、国際感覚豊かな人物を育成する」ことを目的に、キリスト教主義を基本として人格を陶冶する教育を行っています。この教育理念を基本に置きながら、同志社大学では、140年を越える長きにわたって、社会的視野と倜儻不羈(てきとうふき・『才気がすぐれ、独立心が旺盛で、常軌では律しがたいこと』)の精神を兼ね備え、良心を手腕に運用しながら社会の発展に貢献できる人物を育成してきており、現在もその責務を果たすべく努力を積み重ねてきています。
同志社大学の学生受入に対する基本理念(アドミッション・ポリシー)は、上述の教育理念に基づいており、1)専門的・実学的能力を高める上で土台となる、幅広い教養と論理思考能力を育成するために必要な基礎学力を有し、2)知識の量だけでなく、社会的視野を持ち、大学での学習に対する意欲と熱意があり、3)多様な背景を持つ者と協働して学ぶ寛容の精神と主体性を持ち合わせ、4)優れた感性と特性を持った学生を受け入れることを目指し、次のような多彩な選抜制度を用意しています。
一般選抜入学試験
同志社大学の一般選抜入学試験は、高等学校教育を尊重しつつ、大学教育を受けるにふさわしい能力と適性を備えたものを公正かつ妥当に選抜することを目的としています。
入試問題の作成にあたっては、全学的に組織された科目ごとの出題委員会において長期間にわたって慎重に審議し、検討を重ね、高等学校での着実な学習努力が報われるように難問や奇問を避け、公平で偏りのない出題に留意しています。解答形式についても、マークシート方式をとらずにできるだけ記述式とし、論理的思考力や正確な表現力をみるよう努めています。特に計算力を問う出題については、記述式解答の方法をとり、丁寧に採点しています。
大学入学共通テストを利用する入学試験
同志社大学の大学入学共通テストを利用する入学試験は、入学志願者の高等学校までの学習の達成・定着度合いを判定するとともに、各学部での教育に必要とされる能力と適性を備えたものを選抜することを目的とするものであり、大学教育を受けるにふさわしい基本的な能力等を判定しています。学部・学科・コース・方式によっては、個別学力検査において小論文や口頭試問などを課すことにより、志願者の能力や意欲、適性などをより多面的・総合的に評価・判定できるように工夫しています。
アドミッションズ オフィス方式による入学者選抜
同志社大学のAO入試は、学力のみを重視する選抜方法ではありません。同志社大学で学びたいという意志を持ち、かつ学力試験では評価できない多様な能力、大きな可能性を秘めている学生を積極的に迎え入れようとする能動的な選抜方法です。
同志社大学のAO入試は、いわゆる一芸一能入試とは大きく異なります。一芸一能でいかに優れていても、総合的な評価の結果不合格になる場合もあります。つまり、AO入試は知識の多寡だけを問うのではなく、ましてや一芸一能だけを評価するものでもなく、一人ひとりの能力や個性と真の学力を適切に評価し、学習意欲や将来的な可能性までをも含めて総合的に評価する選抜方式です。本学で勉強することを強く望み、独自の考えを持ち、自ら問題を発見し、それを解決する能力を有している生徒、すなわち“自ら学び、自ら考える”自治自立の人物を求めています。
同志社大学のAO入試は、大学教育を受けるに十分な基礎学力があり、出願資格を満たしていれば、自分の意志で出願できる公募制の自己推薦入試です。第一次審査(書類)と第二次審査で合格を判定します。提出書類をひとつひとつじっくり時間をかけて審査し、さらに直接会ったうえで、意欲・能力・適性・目的意識や将来性等を多面的・総合的に評価し、合格者を決定します。
推薦選抜入学試験・自己推薦入学試験
学力・人物ともに優秀で、本学で学ぶことを強く希望する生徒が、学校長などの推薦を受けて、あるいは推薦を受けなくても、出願できる制度です。学部・学科・コースによって様々な出願資格を定めており、個人的研鑽を通して高度な技能や資格を習得した方や、スポーツ活動、競技会等で顕著な成績をあげた方々、あるいは、ボランティア活動や福祉活動で指導的な役割を果たした方など、多様な経験とそれに裏打ちされた能力や資質・適性などを、書類審査や小論文、面接、口頭試問などの判定方法により、幅広く多面的・総合的に評価し、合格者を決定します。
指定校制推薦入学試験
学力・人物ともに優秀で、本学で学ぶことを特に強く希望する者が、学校長の推薦を受けて出願できる専願制の入学試験です。本学の教育理念である、キリスト教主義、自由主義、国際主義に対する深い共感と理解を有し、入学後の勉学について明確な志向と意欲を持つ方を求めています。調査書や小論文、面接、口頭試問などを通じて、能力や資質等を多面的・総合的に評価し、合格を判定します。
法人内各学校推薦入学試験
学校法人同志社が設置する4つの高等学校で、創立者新島襄の人生やその思想、同志社建学の精神や教育理念についてより深く接し、「キリスト教主義」「自由主義」「国際主義」に基づく「知・徳・体」の全人格教育を受けた者が、学校長の推薦を受けて出願できる専願制の入学試験です。良心を手腕に運用する人物、つまり自治・自立の精神にあふれ、博愛精神に富み、個人の尊厳を重んずる人物、高いモラルや高潔な人格を有する人物、そして国際社会で創造的な活動のできる人物を育成することを目的とする同志社一貫教育の精神を理解し、入学後の勉学について明確な目的意識を持つ方を求めています。調査書や小論文、面接、口頭試問などを通じて、能力や資質等を多面的・総合的に評価し、合格を判定します。
同志社大学 神学部のアドミッションポリシー
神学部は、人類が作り上げ蓄積してきた生きるための知恵である宗教、とりわけキリスト教、ユダヤ教、イスラーム教という3つの一神教とその世界について、文献の分析やフィールド調査などによって様々な角度から研究を行います。そうした研究をとおして、3つの一神教を、人間・言語・歴史・文化・社会の様々な側面と連関させつつ、客観的に考察するための知識と技能を身につけます。そして、それらの知識・技能に基づいて、3つの一神教に関する問題を主体的に発見し、その問題を他者と共有するとともに、学術的に解決を導くための思考力・学問的方法論・語学力などを養います。
神学部は、上記の知識・技能・思考力・表現力などを活用し、キリスト教会において、あるいは、企業人・公務員・研究者などとして、ビジネス・福祉・教育・研究・文化事業・国際貢献などの多様な分野で、国内外を問わず、主体性と協働性をもって活躍できる人材を育成することを目的としています。そのために、次のような学生を求めています。
神学部の求める学生像
知識・技能:宗教、とりわけキリスト教、ユダヤ教、イスラーム教という3つの一神教に関する諸問題を客観的に考察するための知識・技能を積極的に習得しようとする学生を求めています。そのため、地理歴史・公民、宗教、国語、英語、美術、音楽などの様々な教科の学習をとおして、あるいは、報道や普段の生活、教会活動、課外活動、ボランティア活動などをとおして、上記の3つの一神教に対する強い関心を抱くようになり、それらの宗教の思想や、それらの宗教が人間の精神や芸術、社会や文化、政治や経済などとの間に取り結んできた豊かな関係について、高等学校の教科書程度の基礎的な知識を身につけていることが望まれます。
思考力・判断力・表現力:キリスト教、ユダヤ教、イスラーム教という3つの一神教とその世界について様々な角度から学習・研究を行うためには、物事を筋道たてて考察する論理的な思考力と的確に批評する判断力を身につけ、調べたり考えたりしたことを明快に表現して他者と共有し、積極的に議論しようとする姿勢が求められます。そのため、高等学校の基礎的な数学の学習などをとおして論理的な思考方法を訓練し、国語や英語、美術や音楽などの学習をとおして建設的な批評を経験し、教会活動、課外活動、ボランティア活動などをとおして自分の考えを他者に説明して議論することを体験しておくことが望まれます。
主体性・多様性・協働性:神学部では、宗教という人間の精神や価値観の根本に関わる事柄について、学生自身が主体的に問題を発見し、自発的に学習・研究を進めていくことを重視しています。そのため、自らの精神を見つめ、人間の生きるべき道について謙虚に問い求める学生を求めています。同時に、世界には様々な宗教があり、キリスト教、ユダヤ教、イスラーム教という3つの一神教の間にも、多くの共通点とともに多くの相違点もあります。そのため、人間・言語・歴史・文化・社会の多様性を重んじ、異なるものの見方を学術的に理解し、他者と協働しながら様々な問題を究明する態度を育もうとすることが望まれます。
高等学校段階までの学習で身につけてほしいこと
英語:英語で書かれた基礎的な文献を読解でき、基本的な口語表現を用いて意思疎通ができ、自分の考えを正確に文章化することを学んでおくことが望まれます。英文法、語彙、リスニング、発音、英作文の基礎をしっかりと身につけておくことが期待されます。
3つの一神教を、人間・言語・歴史・文化・社会の様々な側面と連関させて学ぶためには、英語文献を読みこなし、フィールド調査などで諸外国の人々と交流する必要があります。ひとつの水準として、実用英語技能検定(英検)2級(あるいはTOEFL®テスト、TOEIC®LISTENING AND READINGテストなどの同等水準)程度の英語力を身につけておくことが望ましいでしょう。学んだ知識・技能を国際的な環境で活用し、分析や思考の成果を諸外国の人々と共有していくためにも、英語運用能力はますます必要となってきています。
国語(現代文):宗教に関する様々な問題を分析するためには、日本語で書かれた文献を正確に読解する力が必須です。分析の成果を的確に表現し、他者と協働していくためには、論理的な日本語を用いて自らの考えを文章化するとともに、発表・議論することも学んでおくことが望まれます。また、小説、評論、随想、古典など、読書の幅を広げておくことも期待されます。キリスト教、ユダヤ教、イスラーム教という3つの一神教には、それぞれ経典(聖典)があり、それらの経典を読み解き、豊かに理解していくことは、神学部での学びの基本であり、そのための基礎として国語力と幅広い読書経験が必要とされるからです。
さらに、3つの一神教に関する研究を主体的に深めていく知識・技能として、ヘブライ語、ギリシア語、アラビア語といった、経典で使われている様々な言語を習得することが求められます。母語としての日本語の読解力と表現力を高めておくことは、外国語の習得にも不可欠の力となります。
地理歴史・公民:キリスト教、ユダヤ教、イスラーム教は長い歴史を持つ宗教です。これら3宗教の信徒は、現在の世界人口の半分以上を占め、世界各地の歴史や社会と深く関わってきました。たとえば、日本におけるキリスト教は、戦国時代に伝来し、江戸幕府による禁教と明治政府による解禁を経て現在に至っています。ユダヤ教とイスラーム教は、中東の長く豊かな歴史に深く根ざすとともに、過激派の台頭など、現在の国際社会が直面する問題とも関連しています。
こうした3宗教に関して高度な専門的知識を学び、主体的に考察するための知的洞察力を身につけるための基礎として、高校までの学習で、日本史、世界史、あるいは、現代社会の教科書程度の知識を充分に理解しておくことが期待されます。その際、学んだ知識を相互に関連づけて、歴史や現代社会の流れをつかむように心がけてください。
数学:基本的な数学の知識と技法を学んでおくことが望まれます。これらは論理的思考力の基盤となります。3つの一神教に関する諸問題を、学術的・科学的見地から分析する思考力を身につけるためにも、高校までの数学の学習をとおして、論理的なものの考え方を学んでおくことが重要です。ある問題に対して、筋道を立てて厳密に論証していく能力は、神学部における学びにも必須だからです。さらに、3つの一神教に関して主体的に学んだ知識や分析・考察した成果を他者と共有し、様々な問題に対して他者と協働するための表現力を身につけるためにも、数学的な思考法に親しんでおくことは有用です。
入学者選抜制度
神学部では、高等学校で学習する教科の学力のほかに、宗教、とりわけキリスト教、ユダヤ教、イスラーム教という3つの一神教に対する関心、学習意欲、表現力やコミュニケーション力などを評価する多様な入学者選抜を行うことにより、多様な学生を受け入れています。本学独自の学力試験のほかに、大学入学共通テスト、書類審査、面接、小論文などを取り入れることにより、学力の3要素「知識・技能」、「思考力・判断力・表現力」、「主体性・多様性・協働性」について、それぞれの入試方式において重み付けを行い評価し、志願者の能力や資質などを適正かつ総合的に審査します。
一般選抜入学試験:高等学校教育を尊重し、高等学校までの学習の達成・定着度を測るとともに、神学部の教育を受けるにふさわしい能力と適性を備えたものを公正かつ妥当に選抜するために一般選抜入学試験を実施しています。入試問題の作成にあたっては、全学的に組織された科目ごとの出題委員会において長期間にわたって慎重に審議し、検討を重ね、高等学校での着実な学習努力が報われるように難問や奇問を避け、公平で偏りのない出題に留意しています。とりわけ、本入試においては、マークシート方式ではなく記述式を用いた独自の入試問題による選抜を行うことで、知識・技能のみならず出題意図を正確に理解する力や論理的思考力、正確な表現力の評価にも重点を置き、総合的に審査しています。計算力を問う出題についても同様に記述式解答方法を用いており、結論に至るプロセス等も含め、丁寧に採点しています。
大学入学共通テストを利用する入学試験:大学入学共通テストを利用する入学試験を利用することで、高等学校卒業程度の学習達成度を測り、神学部の教育を受けるために必要な学力が備わっているかを評価します。加えて、個別試験として学部独自に小論文を課し、「思考力・判断力・表現力」に重点を置きつつ「主体性・多様性・協働性」も評価し、総合的に審査します。
推薦選抜入学試験(公募制):高等学校での学習と課外活動あるいは教会活動をとおして、充分な学力と素養を身につけ、神学部で学ぶ高い意欲と積極性を持った優れた学生を受け入れるために、学校長の推薦に基づく出願書類、小論文、面接によって、「知識・技能」、「思考力・判断力・表現力」、「主体性・多様性・協働性」を適正かつ総合的に審査します。出願書類では、高等学校での学習内容を確実に身につけ、神学部での学習・研究の基礎として充分な「知識・技能」が備わっているかを中心的に評価します。小論文では、神学部での学習・研究に必要な「思考力・判断力・表現力」が備わっているかを中心的に評価し、面接では、神学部で何を学びたいのか、その理由は何かなどを中心に、「主体性・多様性・協働性」を重点的に評価します。
この入試方式は、次の二とおりの方を対象とします。(1)キリスト教主義の高等学校での学習や課外活動あるいはキリスト教会での活動をとおして、キリスト教もしくはユダヤ教やイスラーム教の学習・研究を志すようになった方。(2)高等学校の課外活動(文化活動もしくはスポーツ活動)で顕著な業績を残し、宗教、とりわけ3つの一神教に強い関心を抱くようになった方。
自己推薦選抜入学試験:神学部で学ぶ高い意欲と多様な背景を持つ学生を選抜するために、出願書類と口頭試問によって、「主体性・多様性・協働性」を重点的に評価しつつ、「知識・技能」、「思考力・判断力・表現力」などとあわせて総合的に審査します。出願書類では、神学部で学ぶ高い意欲とその背景を確認し、高等学校卒業程度の学力を持ち、神学部での学習・研究の基礎となる「知識・技能」と「思考力・判断力・表現力」を身につけているかを中心的に評価します。口頭試問では、神学部で学ぶ高い意欲がどのような背景に支えられ、それらが神学部での学習・研究の内容と合致しているかといった点を中心に、「主体性・多様性・協働性」を重点的に評価します。
指定校制推薦入学試験:同志社大学の建学の精神であるキリスト教主義に基づき、キリスト教主義精神の素地を身につけ、それをキリスト教あるいはユダヤ教、イスラーム教の学習・研究に活かしていこうという高い意欲を持つ学生を選抜します。また、もう一つの建学の精神である国際主義に基づき、国際的な環境での学習経験を持ち、その経験を基礎として3つの一神教の学習・研究に積極的に取り組もうとする学生を選抜します。そのため、「キリスト教主義学校の連携ネットワーク」などをとおして同志社大学が指定する高等学校またはインターナショナルスクールから志願者を募り、学校長の推薦に基づく出願書類と口頭試問によって、「主体性・多様性・協働性」に重点を置きながら、「知識・技能」、「思考力・判断力・表現力」とあわせて総合的に審査します。出願書類では、キリスト教主義精神の素地もしくは国際的な学習経験を背景として神学部で学ぶ高い意欲を持つことを確認し、高等学校卒業程度の学力を充分に習得していることと、神学部での学習・研究の基礎となる「知識・技能」と「思考力・判断力・表現力」を持っていることを中心的に評価します。口頭試問では、キリスト教主義精神の素地や国際的な学習経験を神学部での学習・研究にどのように活用していこうとしているかといった点を中心に、「主体性・多様性・協働性」を重点的に評価します。
法人内諸学校推薦入学試験:同志社大学の建学の精神を深く理解し、神学部で学ぶ高い意欲と相応しい学力を備え、学部の核となって他の学生をリードし、ひいては大学全体の活性化にも寄与できるような優れた人物を選抜することを目指します。出願書類では、一定水準の「知識・技能」と「思考力・判断力・表現力」が備わっているかを重点的に評価し、口頭試問では、神学部で学ぶ高い意欲と、「主体性・多様性・協働性」が備わっているかを重点的に評価することで、適正かつ総合的に審査します。
同志社大学 文学部のアドミッションポリシー
文学部は、キリスト教主義・自由主義・国際主義に基づく人間形成を根本的な教育理念として、人文学の諸領域(英文学・哲学・美学芸術学・文化史学・国文学)における専門的な教育・研究をとおして、現代のグローバル社会の諸課題に自立的かつ実践的に対応する力を備えた人物を養成することを目的としています。そのために、次のような学生を求めています。
文学部の求める学生像
知識・技能:言語、文学、思想、宗教、芸術、文化、歴史、社会などの基本的知識を有し、これらに対して幅広い興味と関心を持っている学生。
思考力・判断力・表現力:高等学校までに培った確かな基礎学力に加え、それに基づく論理的思考力や判断力、それを的確に表現する力を身につけている学生。
主体性・多様性・協働性:何事も自明のことと思わず、自ら問題を発見し、合理的な手続きを踏んで、説得力のある解答を求めようとする学生。多様な価値観を持った人々との協働作業を通じて、グローバル社会の問題の解決策を探ろうとする学生。
- ※国際教養コースのアドミッション・ポリシーは、国際教育インスティテュートのウェブサイトを参照すること。
同志社大学 経済学部のアドミッションポリシー
経済学部は、長い歴史に培われてきた教育研究環境の下で、幅広い教養を身につけるための科目、経済学の系統的・段階的理解をはかる科目、および問題発見と問題解決能力の強化をはかる科目を提供し、主体的な学修を促すことにより、国際化する経済・社会の状況に対応し、広く社会のために行動しうる、自治自立の人物を養成することを目的としています。そのために、次のような学生を求めています。
経済学部の求める学生像
知識・技能:経済学部では、文章表現能力、語学能力、情報処理能力をはじめとする技能を活用して、理論的、制度的あるいは歴史的な経済学的知見をもとに、国際化する経済・社会の状況を理解できるようになるために、表現・コミュニケーションの基礎となる言語的能力や論理的思考の基礎となる数理的能力といった基礎学力を有する学生を求めています。
思考力・判断力・表現力:経済学部では、系統的・段階的に学んだ経済学的知見をもとに、国際化する経済・社会に対応した適切な問題解決方法を提案できるようになるために、同志社の建学の精神を尊重し、経済学部の教育目標の下、経済学部における専門的知識および幅広い教養の修得に意欲を有する学生を求めています。
主体性・多様性・協働性:経済学部では、良心を手腕に国際化する経済・社会の諸課題に自ら関わり、幅広い教養や経済学的知見をもとに、主体的に行動できるようになるために、問題発見・問題解決能力の修得に意欲を有し、国際化する経済・社会に貢献しようとする意志を有する学生を求めています。また、その過程で、他者との関わりの中で自らの役割を認識し、その役割を果たせるよう不断の努力を惜しまない学生を求めています。
高等学校段階までの学習で身につけてほしいこと
英語:国際化する経済・社会の状況に対応し、広く社会のために行動していくためには、海外の文献や海外サイトの情報を読み解き、広く情報収集して考えたことを国内外に発信していくこと、そして様々な国の人とコミュニケーションをはかり、国際社会で身につけた能力を発揮していくことが求められます。また、こうした能力は、経済学部で経済・社会の世界的な潮流を学ぶ上でも必要となります。経済学部では、そうした国際的なコミュニケーション能力の基礎として一定の英語力を習得した人を求めます。
国語:すべての学修の基礎となる読解力、思考力、表現力を身につける上で、国語能力は不可欠です。長い文章を読み、文章の意味や論理的構成を把握し、言語的に思考を巡らせ、自分の考えを的確に表現する力は、幅広い教養を身につけ、経済学の系統的・段階的理解をはかり、問題発見と問題解決能力を身につけるために必須の能力です。そうした能力の修得と向上に努めることを期待します。そのためには、教科としての国語の履修とともに、普段から新聞や書籍等を読んで、思考力を養うことが大切です。
地理歴史・公民:経済学を学ぶ上で、広く経済・社会に関心を持っていることは必須の条件です。様々な地域に目を向け学ぶこと、歴史から学ぶこと、社会や経済の仕組みを学ぶこと、これらは経済学を学ぶ基本的な姿勢となります。経済学部では、幅広い教養と経済学を学ぶ基礎として、地理、歴史、公民に強い関心を持っていることを期待します。
数学:経済学を学ぶ上で、論理的思考力の基礎となる数学の素養は、学修をおおいに助け、学修範囲を広げることに役立ちます。経済学部では、高校で少なくとも数学Ⅰ・数学Aを履修し、大学入学後も必要に応じて数学・統計学の学修に努力する意思を持っていることを期待します。
入学者選抜制度
経済学部では、高等学校で学習する教科の学力のほかに、経済学に対する関心、学修意欲、表現力やコミュニケーション能力等を評価する多様な入学者選抜を行うことにより、多様な学生を受け入れています。本学独自の学力試験のほかに、大学入学共通テスト、書類審査、面接等を取り入れることにより、学力の3要素「知識・技能」、「思考力・判断力・表現力」、「主体性・多様性・協働性」について、それぞれの入試方式において重み付けを行い評価し、志願者の能力や資質等を総合的に審査しています。
一般選抜入学試験:高等学校教育を尊重し、高等学校までの学習の達成・定着度を測るとともに、経済学部の教育を受けるにふさわしい能力と適性を備えたものを公正かつ妥当に選抜するために一般選抜入学試験を実施しています。入試問題の作成にあたっては、全学的に組織された科目ごとの出題委員会において長期間にわたって慎重に審議し、検討を重ね、高等学校での着実な学習努力が報われるように難問や奇問を避け、公平で偏りのない出題に留意しています。とりわけ、本入試においては、マークシート方式ではなく記述式を用いた独自の入試問題による選抜を行うことで、知識・技能のみならず出題意図を正確に理解する力や論理的思考力、正確な表現力の評価にも重点を置き、総合的に審査しています。計算力を問う出題についても同様に記述式解答方法を用いており、結論に至るプロセス等も含め、丁寧に採点しています。
大学入学共通テストを利用する入学試験:入学志願者の高等学校までの学習の達成・定着度を測るとともに、経済学部の教育を受けるために必要な「知識・技能」が備わっているかを多面的に評価するため、大学入学共通テストにより評価しています。
自己推薦入学試験:高等学校での学習および課外活動を通じてこれまでに培われた基礎学力、「知識・技能」、「思考力・判断力・表現力」等を備え、かつ経済学部で学ぶ高い意欲を持つ人物を選抜するために、出願書類では一定水準以上の「知識・技能」が備わっているか、筆記試験では経済学部で学ぶために必要な「思考力・判断力・表現力」が備わっているか、面接では「主体性・多様性・協働性」が備わっているか等を適正に評価しています。とりわけ、本入試においては、「主体性・多様性・協働性」の評価に重点を置き、総合的に審査しています。
指定校制推薦入学試験:高等学校での学習および課外活動を通じてこれまでに培われた基礎学力、「知識・技能」、「思考力・判断力・表現力」等を備え、かつ経済学部で学ぶ高い意欲を持つ優れた人物を受け入れるために、学校長の推薦に基づき、出願書類では一定水準以上の「知識・技能」が備わっているか、口頭試問では経済学部で学ぶために必要な「思考力・判断力・表現力」や「主体性・多様性・協働性」が備わっているか等を、多面的に適正に評価しています。とりわけ、本入試においては、入学後の勉学における明確な志向および意欲の評価に重点を置き、総合的に審査しています。
法人内諸学校推薦入学試験:同志社の一貫教育を通じて、同志社大学の建学の精神を深く理解し、経済学部で学ぶ高い意欲や相応しい学力を備え、学部の核となり他の学生をリードし、ひいては大学全体の活性化にも寄与できるような優れた人物を受け入れるために、出願書類では一定水準の「知識・技能」が備わっているか、口頭試問では経済学部で学ぶために必要な「思考力・判断力・表現力」や「主体性・多様性・協働性」が備わっているか等を多面的に適正に評価しています。とりわけ、本入試においては、「主体性・多様性・協働性」の評価に重点を置き、総合的に審査しています。
- ※国際教養コースのアドミッション・ポリシーは、国際教育インスティテュートのウェブサイトを参照すること。
同志社大学 商学部のアドミッションポリシー
商学部では、現代産業社会の経済活動について、基礎的な知識の修得をはかるとともに豊かな教養を培い、専門領域の体系的かつ系統的な教育方針に基づく学習と実践的能力の育成を通して、企業や産業に関わる諸問題を的確に分析し、その解決のための判断能力を身につけ、多様な価値観が共存する世界の人々とともに「良心を手腕に運用する」有為な人物を養成することを目的としています。こうした観点から、商学部では、次のような学生を求めています。
商学部の求める学生像
知識・技能:商学部では、経済社会のさまざまな現象に対して、日頃から関心と興味をもち、実践的かつ高度な専門知識及び技能を身につけ、それらを用いて、経済社会の諸課題の解決に向けて、主体的かつ積極的に取りくむ学生を求めています。「好きこそものの上手なれ」というように、興味関心こそ意欲を持って学ぶうえでの必要条件です。
思考力・判断力・表現力:商学部では、物事を判断・主張・批判する際に、常に明確な根拠(理由)を立てて説明することができ、また複雑な状況を整理し順序立てて考えられる論理的思考力、それを記述(発言)することのできる表現力(説得力があり、分かりやすい文章が書ける能力)に優れている学生を求めています。
主体性・多様性・協働性:商学部では、目的意識が明確で、多様な背景をもつ仲間とともに困難に立ち向かうことのできる学生を求めています。明確な目的意識とそれを実現しようとする強い意欲があれば、大きく成長することができます。また、グローバル化が進むビジネスの世界では、多様な文化的背景を持つ同僚や顧客と協働し、価値を創造していくことが必要になります。したがって、何のために商学部に入学するのかが明確であり、その目的に向かって多様な仲間たちと困難を乗り越え努力しようとする強い意志をもつ人物こそが求める人物像です。たとえば、「経営者・ビジネスリーダーになる」「将来、起業する」「公認会計士、税理士になる」「経営コンサルタントになる」「専門的なビジネス知識を身につけた社会人になる」「大学院に進学して産業・企業活動の研究者になる」「経済人としてグローバルに活躍できる能力を身につける」など、一人一人目的は違っても明確であることが望まれます。
高等学校段階までの学習で身につけてほしいこと
英語:経済活動はますます国境を越えて相互に浸透し、グローバル化が今後いっそう進むことは間違いありません。日本企業も欧米にとどまらずアジア、南米、アフリカへと活動領域を急速に拡大しています。また、インターネットによる情報通信手段のグローバル化が日本国内の経済活動と世界各地を緊密に結びつけるのみならず、大学を巣立った人材が世界各地の企業で活躍する現代では、世界で通用する英語力を体得することが重要です。企業と産業の経済諸活動に関わる学問を学び、それに関わる人材を養成して広い世界に送り出すことを目的とする商学部においては、高い英語能力を習得した人物をつよく求めています。望ましい1つの水準としては、実用英語技能検定(英検)2級(あるいはTEAP、TOEFL®テスト、TOEIC® LISTENING AND READINGテストなどの同等水準)以上を挙げることができます。入学までに可能な限り英語力の向上に努力してください。
国語(現代文):文章の内容を正確に理解し、また自己の主張を明解かつ正確に伝える上で、国語能力は不可欠です。長い文章を苦にせず読み、その趣旨を的確に理解し、短文に要約することができる文章読解能力、根拠や事例を示して自己の考えを説得的に文章化する論理的表現力、複雑な内容を順序立てて文章化する文章構成力、これらは商学部での学びのみならず企業の業務でも要求される必須の能力ですから、その向上に努めてください。また日頃から、新聞に掲載される社説・評論など、身近なところにある論理的な文章を読むように心懸けることも大切です。
歴史:産業と企業が現在追求している経済諸活動や現在抱えている諸問題には、必ず歴史的な背景や歴史的経緯があります。たとえば、地球環境問題や資源問題など企業と社会の関係に関わる諸問題、企業管理手法や経営思想、企業法制・会計システム・金融システム・貿易制度など企業を取り巻く諸制度の諸問題は、商学部で学ぶほとんどすべての学問分野のみならず実社会においても、歴史的背景の中に位置付けて考えることでより深く理解できるようになります。世界と日本の歴史、とりわけ経済と社会の近現代史に関心を持って歴史関連諸科目を学ぶことが大切です。
数学:商学部での専門科目の習得と卒業に数学が必須ということはありません。しかし、統計学的能力を身につける上では数学の基礎的能力が必要です。統計学は企業・産業活動を分析し解決策をみずから考える上で必要となります。また、金融、マーケティング、会計など、商学部が開設する一定の専門科目を深く理解し、専門的能力を身につける上でも、また高い専門性を要求される現代の企業における業務においても、数学・統計学の基礎的知識は必要になります。さらに、数学は論理的思考力を育てる上でも非常に大切な科目です。高校生のうちに数学の基本的知識を身につけるように努力してください。
入学者選抜制度
商学部では、高等学校で学習する教科の学力のほかに、商学に対する関心、学習意欲、表現力やコミュニケーション力などを評価する多様な入学選抜を行うことにより、多様な学生を受け入れています。本学独自の学力試験のほかに、大学入学共通テスト、書類審査、面接、小論文などを取り入れることにより、学力の3要素「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」「主体性・多様性・協働性」について、それぞれの入試方式において重み付けを行い評価し、志願者の能力や資質を総合的に審査しています。
一般選抜入学試験:高等学校教育を尊重し、高等学校までの学習の達成・定着度を測るとともに、商学部の教育を受けるにふさわしい能力と適性を備えたものを公正かつ妥当に選抜するために一般選抜入学試験を実施しています。入試問題の作成にあたっては、全学的に組織された科目ごとの出題委員会において長期間にわたって慎重に審議し、検討を重ね、高等学校での着実な学習努力が報われるように難問や奇問を避け、公平で偏りのない出題に留意しています。とりわけ、本入試においては、マークシート方式ではなく記述式を用いた独自の入試問題による選抜を行うことで、知識・技能のみならず出題意図を正確に理解する力や論理的思考力、正確な表現力の評価にも重点を置き、総合的に審査しています。計算力を問う出題についても同様に記述式解答方法を用いており、結論に至るプロセス等も含め、丁寧に採点しています。
大学入学共通テストを利用する入学試験:入学志願者の高等学校までの学習の達成・定着度を測るとともに、商学部の教育を受けるために必要な学力が備わっているか、大学入学共通テストにより評価しています。
アドミッションズ・オフィス方式による入学者選抜:従来の教科・科目の筆記試験だけでは測ることができない一人一人の多様な能力や将来の可能性、商学部で学びたいという目的意識・学習意欲を持って、自ら課題を発見し、その解決に向けて主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度を備えた人物を適正に評価するために、出願書類に加えて、小論文、面接など丁寧な選抜を行っています。とりわけ、本入試においては、国際社会で活躍するための実践的かつ高度な外国語運用能力、学びに対する高い意欲、「主体性・多様性・協働性」の評価に重点を置き、総合的に審査しています。
指定校制推薦入学試験:高等学校での学習及び課外活動を通じてこれまでに培われた基礎学力、「知識・技能」、「思考力・判断力・表現力」等を備え、商学部で学ぶ高い意欲を持つ優れた人物を受け入れるために、学校長の推薦に基づき、出願書類では一定水準以上の「知識・技能」が備わっているか、小論文では商学部で学ぶために必要な「思考力・判断力・表現力」が備わっているか、面接では「主体性・多様性・協働性」が備わっているかなどを適正に評価しています。とりわけ、本入試においては、入学後の勉学における明確な志向及び意欲の評価に重点を置き、総合的に審査しています。
法人内諸学校推薦入学試験:同志社の一貫教育を通じて、同志社大学の建学の精神を深く理解し、商学部で学ぶ高い意欲や相応しい学力を備え、学部の核となり他の学生をリードし、ひいては大学全体の活性化にも寄与できるような優れた人物を受け入れるために、出願書類では一定水準以上の「知識・技能」が備わっているか、小論文では商学部で学ぶために必要な「思考力・判断力・表現力」が備わっているか、面接では「主体性・多様性・協働性」が備わっているかなどを適正に評価しています。とりわけ、本入試においては、「主体性・多様性・協働性」の評価に重点を置き、総合的に審査しています。
- ※国際教養コースのアドミッション・ポリシーは、国際教育インスティテュートのウェブサイトを参照すること。
同志社大学 政策学部のアドミッションポリシー
政策学部は、グローバル化や情報化が進む現代社会において、多様化・複雑化する諸課題に対し、自ら問題を発見し、解決する能力を備えた自律的人材の養成を目的としています。そのため政治、経済、法律、組織を柱とした政策学の体系的かつ系統的な教育方針に基づき、社会科学横断的な知識と具体的課題を客観的に調査分析する技能を学び、その実践的能力の育成を目指します。そして問題解決に至る政策の理論と方法を学ぶとともに、公的機関や民間企業、NPO・NGOなどの現場を重視した実践的な教育も行います。こうした観点から、政策学部では、次のような学生を求めています。
政策学部の求める学生像
知識・技能:政策学部では、日本国内外で起きている社会の出来事、組織の中の人々の活動など、現代社会のさまざまな現象や問題に対して、日頃から関心をもち、かつ地域やグローバル社会が直面する課題解決に自ら貢献しようとする学生を求めています。
思考力・判断力・表現力:政策学部では、意欲ある学生が互いに切磋琢磨する中で視野を広げ、柔軟で革新的な発想や工夫を生んでいくことが、課題解決に向けた重要なプロセスであると考えています。したがって、物事を判断・主張・批判する際に、常に明確な根拠(理由)を立てて説明することができ、また複雑な状況を整理し順序立てて記述(発言)することのできる論理的思考力がある学生を求めています。
主体性・多様性・協働性:政策学部では、現代社会の諸問題に関心をもち、かつこうした問題の解決に自らが関わり、貢献しようとする主体的で積極的な学生を求めています。問題解決の実践にあたっては、主体性や意欲だけではなく、他者の意見を尊重し、多様性を受け入れ、異なる立場の人とも協働して学ぶ態度を身につけていなければなりません。
高等学校段階までの学習で身につけてほしいこと
英語:グローバル化の進展の中で、国際共通語である英語力の向上は日本の将来にとって重要であるだけでなく、海外での問題や課題を発見し、その解決を検討する場合はもちろん、世界共通の価値観や世界規模の課題に対応する場面では、英語の能力が極めて重要となります。グローバルに活躍できる人材の養成を目的とする政策学部においては、高い英語能力の習得を目指す人材を強く求めています。望ましい1つの水準としては、実用英語技能検定(英検)2級(あるいはTOEFL®テスト、TOEIC® Testsなどの同等基準)以上を挙げることができます。入学までに可能な限り英語力の向上に努力しておいてください。
国語(現代文):文章の内容を正確に理解し、また自己の主張を明確かつ正確に伝える上で、国語能力は不可欠です。長い文章を苦にせず読み、その趣旨を的確に理解し、短文に要約することができる文章読解能力、根拠と事例を示して自己の考えを説得的に文章化する論理的表現力、複雑な内容を順序立てて文章化する文章構成力、これらは政策学部で学ぶ上で必要となる能力ですから、その向上に努めておいてください。また日頃から、新聞に掲載される社説・評論など、身近なところにある論理的な文章を読むように心懸けることも大切です。
地理歴史:政策学部が柱とする政治、経済、法律、組織をめぐる諸問題には、必ず歴史的な背景があります。たとえば、国際連合という組織はなぜ誕生し、どのような機能を持っているのか、憲法はなぜ必要とされ、国家においてどのような位置づけにあるのか。それらの答えは歴史的背景に求めることになります。もちろん新たに生じる問題や課題も歴史に学べることは言うまでもありません。歴史は単に過去を振り返るものではなく、現在を適確に観察し、将来の「政策」を定めるために不可欠なのです。そして将来を見通す「眼」を養うためには、単に史実を知るだけでなく、いつ・どこで・なぜ、その出来事が起きたのかという、地理的・歴史的背景を理解することが重要です。特に、国内外の近現代史に関心をもって地理的感覚と歴史的思考力の向上を目指してください。
政治・経済:政治経済は政策学部の基礎学力として極めて重要です。現代政治と民主社会、国際政治と日本、現代の経済と国民生活に関する知識はいずれも政策学部が開設する専門科目と深くかかわります。特に、世界の情勢を概観して、国際関係を動かす基礎となる事柄や国際社会における日本の地位と役割について理解しておくことが必要です。また選挙権年齢の引下げは日本社会の在り方を大きく変える可能性があります。日頃から社会情勢に関心をもって政治・経済をめぐる知識の習得に取り組んでおいてください。
数学:政策学部での専門科目の履修や修業に数学が必須ということはありません。しかし、統計学的能力を身につける上では数学の基礎的能力が必要です。経済学、組織論などを中心に統計学は実証分析を伴う分野において必須の学問といえます。社会科学、企業・産業活動を分析し解決策を自ら考える上で必要となります。さらに、数学は論理的思考力を育てる上でも非常に大切な科目です。高校生のうちに数学の基本的知識を身につけるように努力してください。
入学者選抜制度
政策学部では、高等学校で学習する教科の学力のほかに、現代社会のさまざまな現象や問題に対する関心、学習意欲、表現力やコミュニケーション力などを評価する多様な入学者選抜を行うことにより、多様な学生を受け入れています。本学独自の学力試験のほかに、大学入学共通テスト、書類審査、口頭試問、小論文などを取り入れることにより、学力の3要素「知識・技能」、「思考力・判断力・表現力」、「主体性・多様性・協働性」について、それぞれの入試方式において重み付けを行い評価し、志願者の能力や資質等を総合的に審査しています。
一般選抜入学試験:高等学校教育を尊重し、高等学校までの学習の達成・定着度を測るとともに、政策学部の教育を受けるにふさわしい能力と適性を備えたものを公正かつ妥当に評価するため、一般選抜入学試験を実施しています。「地理歴史または公民または数学」の配点を加重することで、多様な学生の受け入れを行っています。入試問題の作成にあたっては、全学的に組織された科目ごとの出題委員会において長期間にわたって慎重に審議し、検討を重ね、高等学校での着実な学習努力が報われるように難問や奇問を避け、公平で偏りのない出題に留意しています。とりわけ、本入試においては、マークシート方式ではなく記述式を用いた独自の入試問題による選抜を行うことで、知識・技能のみならず出題意図を正確に理解する力や論理的思考力、正確な表現力の評価にも重点を置き、総合的に審査しています。計算力を問う出題についても同様に記述式解答方法を用いており、結論に至るプロセス等も含め、丁寧に採点しています。
大学入学共通テストを利用する入学試験:入学志願者の高等学校までの学習の達成・定着度を測るとともに、政策学部の教育を受けるために必要な学力を公正かつ妥当に評価するため、大学入学共通テストを実施しています。「外国語」「国語」を必須とし、「数学」「地理歴史」「公民」「理科」の選択科目を組み合わせて、3科目方式と4科目方式という2つの選抜方式を用意することで、本学部の求める明確な目的意識と実現意欲を備えた多彩な学生の受け入れを行っています。
指定校制推薦入学試験:高等学校での学習及び課外活動を通じてこれまでに培われた基礎学力、「知識・技能」、「思考力・判断力・表現力」等を備え、かつ政策学部で学ぶ高い意欲を持つ優れた人物を受け入れるために、学校長の推薦に基づき、出願書類では一定水準以上の「知識・技能」が備わっているか、小論文では政策学部で学ぶために必要な「思考力・判断力・表現力」が備わっているか、口頭試問では「主体性・多様性・協働性」が備わっているかなどを適正に評価しています。とりわけ、本入試においては、入学後の勉学における明確な志向及び意欲の評価に重点を置き、総合的に審査しています。
法人内諸学校推薦入学試験:同志社の一貫教育を通じて、同志社大学の建学の精神を深く理解し、政策学部で学ぶ高い意欲や相応しい学力を備え、学部の核となり他の学生をリードし、ひいては大学全体の活性化にも寄与できるような優れた人物を受け入れるために、出願書類では一定水準の「知識・技能」が備わっているか、小論文では政策学部で学ぶために必要な「思考力・判断力・表現力」が備わっているか、口頭試問では「主体性・多様性・協働性」が備わっているかなどを適正に評価しています。とりわけ、本入試においては、「主体性・多様性・協働性」の評価に重点を置き、総合的に審査しています。
- ※国際教養コースのアドミッション・ポリシーは、国際教育インスティテュートのウェブサイトを参照すること。
同志社大学 文化情報学部のアドミッションポリシー
文化情報学部は、文化に関する確かな情報が社会問題の解決において枢要であることを理解し、課題の解決のために実践的にデータを利活用する学問としての「データサイエンス」の方法論に基づいて、新たな価値を析出・創造できる人物を養成することを目的としています。そのために、次のような学生を求めています。
文化情報学部の求める学生像
知識・技能:広い意味での文化についての知識や関心とともに、データサイエンスの技法を学ぶための基礎となる知識と技能を身につけている学生
思考力・判断力・表現力:本学部の探究的カリキュラムを十分に生かすための言語の運用能力に加え、数理的な理解力・表現力・思考力を身につけている学生
主体性・多様性・協働性:人間をとりまくさまざまな文化現象の中に新しい価値を見いだし、それを社会問題の解決につなげようとする開拓的かつ向社会的な精神をもつ学生
高等学校段階までの学習で身につけてほしいこと
英語:文化情報学部では、幅広い文化領域の知識とデータサイエンスの手法を学び、文化と人間に関わる様々な現象の解明を目指します。そのためには、日本のみならず、世界の多様な文化を研究対象とし、英語で書かれた資料を読み解き、自らの意見や考えを英語で発信することが求められます。国語力は言うに及ばず、バランスのとれた高度な英語運用能力が必要になります。入学前までに、豊富な語彙力と正しい文法知識を習得しておくよう努めるとともに、4技能(読む・書く・聞く・話す)の一層の向上を心掛けてください。高等学校での学修に加えて、TOEFL®テスト・TOEIC®LISTENING AND READINGテストなどの外部試験を活用することも有用でしょう。
国語(現代文):文化情報学部では、大量で複雑なデータを分析し、深く理解した上で、わかりやすく伝える力が必要です。具体的には、先行論文や口頭発表の内容を正確に把握し、客観的な証拠をもとに自らの意見を組み立て、豊富な語彙によって的確で簡明な方法で表現する能力、すなわち、国語力の涵養が求められます。できるだけさまざまなジャンルの本、特に論説文を中心に、初めて出会った語句や表現、論理展開の方法などに留意しながら、多読・精読に努めてください。これは、単にレポートや論文を書く時に役立つだけではなく、論理的思考力を養うのに必要な基本的訓練です。国語力は、大学での勉学・研究に求められる思考力そのものなのです。
数学:文化情報学部では、データサイエンスの手法を用いて、広い意味での文化現象の解明に取り組みます。そこでは、数学の諸概念の知識や数学的な考え方が非常に重要になります。単に計算ができる、問題が解けるなどの表面的な力ではなく、物事を論理的に深く考える力が必要となります。高等学校での数理系の学びにおいて、意識的にこれらの力を身につけるように努めてください。データサイエンスを用いてデータを解析するための知識技能として、統計学、情報学などの知識が必要であり、それらの知識の根幹をなすのは数学です。高等学校で学ぶ数学は、より高度な科学の基礎となるものであり、大学での学修のみならず、社会での活動において有用なものです。高等学校での数学の積極的な学びに期待します。
情報:文化情報学部では、実験や調査などを通して得たデータを意味のある情報に変換し、情報技術を活用することで文化が関わる問題の発見・解決に取り組みます。こうした学びを通して、情報社会で活躍するために必要な資質と能力を養っていきます。そのためには、高等学校の学びにおいて、情報に関する科学的な考え方を習得し、情報社会と人との関わりについて理解を深めておくことが重要です。情報や情報技術の活用に欠かせないメディアの特性や、情報に関する法規や制度、情報セキュリティや情報モラルについて十分に理解しておくことが大学におけるより高度な学びの基盤となります。さらに、情報デザインをふまえた効果的なコミュニケーションを身につけておくことも、大学における知的な共同作業には欠かせません。高等学校において積極的に情報を学ぶことを望みます。
入学者選抜制度
文化情報学部では、高等学校で学習する教科の学力のほかに、文化やデータサイエンスに対する関心、学習意欲、表現力やコミュニケーション力などを評価する多様な入学者選抜を行うことにより、多様な学生を受け入れています。本学独自の学力試験のほかに、大学入学共通テスト、書類審査、口頭試問、小論文などを取り入れることにより、学力の3要素「知識・技能」、「思考力・判断力・表現力」、「主体性・多様性・協働性」について、それぞれの入試方式において重み付けを行い評価し、志願者の能力や資質等を総合的に審査しています。
一般選抜入学試験:高等学校教育を尊重し、高等学校までの学習の達成・定着度を測るとともに、文化情報学部の教育を受けるにふさわしい能力と適性を備えたものを公正かつ妥当に選抜するために一般選抜入学試験を実施しています。入試問題の作成にあたっては、全学的に組織された科目ごとの出題委員会において長期間にわたって慎重に審議し、検討を重ね、高等学校での着実な学習努力が報われるように難問や奇問を避け、公平で偏りのない出題に留意しています。とりわけ、本入試においては、マークシート方式ではなく記述式を用いた独自の入試問題による選抜を行うことで、知識・技能のみならず出題意図を正確に理解する力や論理的思考力、正確な表現力の評価にも重点を置き、総合的に審査しています。計算力を問う出題についても同様に記述式解答方法を用いており、結論に至るプロセス等も含め、丁寧に採点しています。
大学入学共通テストを利用する入学試験:入学志願者の高等学校までの学習の達成・定着度を測るとともに、文化情報学部の教育を受けるために必要な学力が備わっているか、大学入学共通テストにより評価しています。加えて、個別試験では、学部独自に学力試験(数学・英語)を実施することにより「思考力・判断力」に重点を置くなど、総合的に審査しています。
アドミッションズ・オフィス方式による入学者選抜:従来の教科・科目の筆記試験だけでは測ることができない一人ひとりの多様な能力や将来の可能性、文化情報学部で学びたいという目的意識・学習意欲を持って、自ら問題を発見し、その解決に向けて主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度を備えた人物を適正に評価するために、出願書類に加えて、プレゼンテーションを含む面接および口頭試問を行い、丁寧な選抜を行っています。とりわけ、本入試においては、学びに対する高い意欲、「主体性・多様性・協働性」の評価に重点を置き、総合的に審査しています。
推薦選抜入学試験(公募制):高等学校での学習及び課外活動を通じてこれまでに培われた基礎学力、「知識・技能」、「思考力・判断力・表現力」等を備え、文化情報学部で学ぶ高い意欲を持つ人物を選抜するために、出願書類では一定水準以上の「知識・技能」が備わっているか、小論文では文化情報学部で学ぶために必要な「思考力・判断力・表現力」が備わっているか、口頭試問では「主体性・多様性・協働性」が備わっているかなどを適正に評価しています。とりわけ、本入試においては、「思考力・判断力・表現力」の評価に重点を置き、総合的に審査しています。
指定校制推薦入学試験:高等学校での学習及び課外活動を通じてこれまでに培われた基礎学力、「知識・技能」、「思考力・判断力・表現力」等を備え、かつ文化情報学部で学ぶ高い意欲を持つ優れた人物を受け入れるために、学校長の推薦に基づき、出願書類では一定水準以上の「知識・技能」が備わっているか、口頭試問では「主体性・多様性・協働性」が備わっているかなどを適正に評価しています。とりわけ、本入試においては、入学後の勉学における明確な志向及び意欲の評価に重点を置き、総合的に審査しています。
法人内諸学校推薦入学試験:同志社の一貫教育を通じて、同志社大学の建学の精神を深く理解し、文化情報学部で学ぶ高い意欲や相応しい学力を備え、学部の核となり他の学生をリードし、ひいては大学全体の活性化にも寄与できるような優れた人物を受け入れるために、出願書類では文化情報学部で学ぶ意欲および一定水準の「知識・技能」が備わっているか、口頭試問では「主体性・多様性・協働性」が備わっているかなどを適正に評価しています。とりわけ、本入試においては、「主体性・多様性・協働性」の評価に重点を置き、総合的に審査しています。
同志社大学 スポーツ健康科学部のアドミッションポリシー
スポーツ健康科学部では、スポーツと健康、及びそれらを取り巻く社会環境に関する知見や諸理論、技能を総合的・体系的に修得し、スポーツ活動、国や地方自治体、教育機関、スポーツ関連産業及びヘルスケア産業等の現場で、専門的な立場から「健康の増進」やスポーツの「パフォーマンス向上」及び「社会的発展」に寄与・貢献できる多様な人材の養成を目指しています。そのために、スポーツ健康科学部では、次のような学生を求めています。
スポーツ健康科学部の求める学生像
知識・技能:スポーツ健康科学部では、スポーツ健康科学に関する専門的知識・技能を修得するために必要な基礎知識や外国語の読解・表現能力等を有する学生を求めています。自然科学と人文社会科学にまたがる文理融合型のスポーツ健康科学を学ぶために幅広い基礎学力が必要となります。
思考力・判断力・表現力:スポーツ健康科学部では、高等学校までに培った確かな基礎学力に加え、それに基づく論理的思考力やスポーツと健康に対して幅広い関心を有し、既成の事実や価値観に捉われることなく、自ら課題を見出し、探究し、的確に表現できる学生を求めています。
主体性・多様性・協働性:スポーツ健康科学部では、様々な立場にある人々の意見を取り入れ、相互理解を深めようとする協調性や高いコミュニケーション能力を有する学生を求めています。「スポーツを通じた健康づくり」、「トレーニング科学に基づいたスポーツパフォーマンスの向上」、「スポーツを取り巻く社会環境の整備・充実」などスポーツ健康科学に関わる課題に対して主体的かつ積極的に取り組む学生を求めています。
高等学校段階までの学習で身につけてほしいこと
英語:グローバル化が加速しているスポーツは、世界共通の文化として普及・発展を遂げています。われわれがスポーツの価値や情報を共有するためには、英語によるコミュニケーション能力を身につけることがますます必要になっています。入学までに、英語能力をできるだけ向上させるための努力をしてください。TOEIC®LISTENING AND READINGテスト、TOEFL®テスト、IELTS、実用英語技能検定(英検)、国際連合公用英語検定などの試験を受けて、自分の英語能力を確かめることを心掛けましょう。
国語(現代文):スポーツ健康科学を学ぶ上で、専門書や論文を読みこなすには、文章の内容を正確に理解し、その趣旨を的確に要約する文章読解能力が必要になります。そして、レポートや論文を作成するには、根拠を示して自分の考えを説得力のある文章にする論理的表現力や表現すべき文章を論理的に組み立てる文章構成力が要求されます。常日頃から読書に親しみ、国語能力の向上に努めてください。また、新聞や雑誌などの活字体の文章に目をとおして、スポーツと健康についての現代的課題の動向を知るようにすることも大切です。
地理歴史・公民:スポーツ健康科学部で学ぶ社会科学の学修領域には、スポーツを取り巻く社会環境の整備やスポーツビジネスの経営的課題に取り組むスポーツ・マネジメント領域があります。スポーツ・マネジメント関連の科目を修得するには、スポーツと社会の関係をより深く理解するため、歴史、地理、現代社会、政治・経済などの文系科目に関する基礎知識を有することが望まれます。
理科:スポーツ健康科学部で学ぶ自然科学の学修領域には、身体の構造や機能に関する医科学的理解を基礎とする健康科学領域と、スポーツパフォーマンスの向上や運動習慣の獲得のためにスポーツ科学を活用するトレーニング科学領域があります。健康科学やトレーニング科学に関連する科目を修得するには、物理、化学、生物といった理系科目の基礎知識が必要になるため、自然科学の複数の領域に関心をもって学ぶように心掛けてください。
数学:スポーツ健康科学の学修領域において数学の役割は重要です。健康科学、トレーニング科学、スポーツ・マネジメントの3領域ともに、数学的手法を用いて身体のパフォーマンスや社会経済データの解析を行います。例えば、スポーツパフォーマンスの向上やトレーニングの最適化、スポーツのビジネスやマーケティング戦略を立案する際にも数学的手法が活用されます。そのため、数学の基礎知識を身につけることを心掛けましょう。
入学者選抜制度
スポーツ健康科学部では、高等学校で学習する教科の学力のほかに、スポーツと健康に対する関心や学習意欲、並びに論理的思考力、表現力、コミュニケーション力などを評価する様々な入学者選抜を行うことにより、多様な学生を受け入れています。本学独自の学力試験のほかに、大学入学共通テスト、書類審査、面接、口頭試問、小論文などを取り入れることにより、学力の3要素「知識・技能」、「思考力・判断力・表現力」、「主体性・多様性・協働性」について、それぞれの入試方式において重み付けを行い評価し、志願者の能力や資質等を総合的に審査しています。
一般選抜入学試験:高等学校教育を尊重し、高等学校までの学習の達成・定着度を測るとともに、スポーツ健康科学部の教育を受けるにふさわしい能力と適性を備えたものを公正かつ妥当に選抜するために一般選抜入学試験を実施しています。入試問題の作成にあたっては、全学的に組織された科目ごとの出題委員会において長期間にわたって慎重に審議し、検討を重ね、高等学校での着実な学習努力が報われるように難問や奇問を避け、公平で偏りのない出題に留意しています。とりわけ、本入試においては、マークシート方式ではなく記述式を用いた独自の入試問題による選抜を行うことで、知識・技能のみならず出題意図を正確に理解する力や論理的思考力、正確な表現力の評価にも重点を置き、総合的に審査しています。計算力を問う出題についても同様に記述式解答方法を用いており、結論に至るプロセス等も含め、丁寧に採点しています。
大学入学共通テストを利用する入学試験:入学志願者の高等学校までの学習の達成・定着度を測るとともにスポーツ健康科学部の教育を受けるために必要な学力が備わっているか、大学入学共通テストにより評価しています。「知識・技能」の学力評価に比重を置いた3科目方式及び5科目方式の試験のほかに、3科目の得点にスポーツ競技成績の書類審査による評価得点を加えたスポーツ競技力加点方式の試験を設けています。
アドミッションズ・オフィス方式による入学者選抜:スポーツを「する・観る・支える」のいずれかの観点から深く関わった経験を有し、スポーツや健康の学びに対する高い意欲を持つ優れた人物を評価するため、出願書類に加えて、小論文及び面接による丁寧な選抜を行っています。小論文ではスポーツ健康科学部で学ぶために必要な「思考力・判断力・表現力」が備わっているか、面接では従来の教科・科目の筆記試験だけでは測ることができない一人ひとりの多様な能力や将来の可能性、学びに対する目的意識・学習意欲を評価し、総合的に審査しています。
自己推薦(スポーツ)入学試験:高等学校での学習及び課外活動を通じてこれまでに培われた基礎学力、「知識・技能」、「思考力・判断力・表現力」等を備え、高等学校在学中に優れたスポーツ競技成績をおさめ、スポーツ健康科学部で学ぶ高い意欲を持つ人物を選抜するために、出願書類ではスポーツ競技成績および「知識・技能」を評価しています。また、小論文ではスポーツ健康科学部で学ぶために必要な「思考力・判断力・表現力」が備わっているか、面接では「主体性・多様性・協働性」が備わっているかなどを適正に評価しています。とりわけ、本入試においては、スポーツ活動と学びに対する高い意欲や「思考力・判断力・表現力」の評価に重点を置き、総合的に審査しています。
指定校制推薦入学試験:高等学校での学習及び課外活動を通じてこれまでに培われた基礎学力、「知識・技能」、「思考力・判断力・表現力」等を備え、かつスポーツ健康科学部で学ぶ高い意欲を持つ優れた人物を受け入れるために、出願書類では一定水準以上の「知識・技能」が備わっているか、口頭試問では学力の3要素「知識・技能」、「思考力・判断力・表現力」、「主体性・多様性・協働性」が備わっているかなどを適正に評価しています。とりわけ、本入試においては、入学後の勉学における明確な志向及び学びに対する意欲の評価に重点を置き、総合的に審査しています。
法人内諸学校推薦入学試験:同志社の一貫教育を通じて、同志社大学の建学の精神を深く理解し、スポーツ健康科学部で学ぶ高い意欲や相応しい学力を備え、学部の核となり他の学生をリードし、ひいては大学全体の活性化にも寄与できるような優れた人物を受け入れるために、出願書類では一定水準の「知識・技能」が備わっているか、口頭試問では学力の3要素「知識・技能」、「思考力・判断力・表現力」、「主体性・多様性・協働性」が備わっているかなどを適正に評価しています。とりわけ、本入試においては、「主体性・多様性・協働性」の評価に重点を置き、総合的に審査しています。
京都府立高等学校特別入学試験:健康とスポーツ活動及びそれらを取り巻く社会環境に関する知見と諸理論を包括したスポーツ健康科学の知識と理論を学修することを充分に理解し、将来、地域社会に貢献することを強く意識した人物を選抜するために、出願書類では一定水準の「知識・技能」が備わっているか、小論文ではスポーツ健康科学部で学ぶために必要な「思考力・判断力・表現力」が備わっているか、面接では「思考力・判断力・表現力」や「主体性・多様性・協働性」が備わっているかなどを適正に評価しています。とりわけ、本入試においては、「思考力・判断力・表現力」や学習意欲の評価に重点を置き、総合的に審査しています。
海外修学経験者(帰国生)入学試験:海外での学習・生活による豊かな体験を通じて培われた基礎学力、「知識・技能」、「思考力・判断力・表現力」等を備え、スポーツ健康科学部で学ぶ高い意欲を持つ人物を選抜するために、出願書類では一定水準以上の「知識・技能」が備わっているか、小論文ではスポーツ健康科学部で学ぶために必要な「思考力・判断力・表現力」が備わっているか、面接では「主体性・多様性・協働性」が備わっているかを適正に評価しています。とりわけ、本入試においては、「主体性・多様性・協働性」の評価に重点を置き、総合的に審査しています。
社会人特別選抜入学試験:プロスポーツあるいはアマチュアスポーツでトップレベルの競技経験を有し、スポーツ健康科学部で学ぶ高い意欲を持つ人物を選抜するために、出願書類では一定水準以上の競技スポーツ経験を有しているか、小論文ではスポーツ健康科学部で学ぶために必要な「思考力・判断力・表現力」が備わっているか、面接では「主体性・多様性・協働性」が備わっているかなどを適正に評価しています。とりわけ、本入試においては、学びに対する高い意欲や「主体性・多様性・協働性」の評価に重点を置き、総合的に審査しています。
アスリート選抜入学試験:高等学校在学中に優れた競技成績をおさめ、トップアスリートとして高みを目指す意志を持ち、かつスポーツ健康科学部で学ぶ高い意欲を持つ人物を選抜するために、出願書類ではスポーツ競技成績を評価し、口頭試問では学力の3要素「知識・技能」、「思考力・判断力・表現力」、「主体性・多様性・協働性」が備わっているかなどを適正に評価しています。とりわけ、本入試においては、スポーツ活動と学びに対する高い意欲や「主体性・多様性・協働性」の評価に重点を置き、総合的に審査しています。
同志社大学 心理学部のアドミッションポリシー
心理学部では、心の仕組みに関する知識や技能を基礎から応用まで体系的に学び、論理的な思考とデータによる実証を重視する姿勢を身につけることで、習得した知識や技能を適切に運用し、心理学の成果を社会に向けて主体的に発信できるようになることを目的としています。心理学の専門家として、人の心に関心を持ち、心の問題に科学的にアプローチする能力を備え、現代社会のさまざまな分野において貢献できる人物の育成を目指しています。こうした観点から、心理学部では、次のような学生を求めています。
心理学部の求める学生像
知識・技能:心理学部では、基礎心理学と応用心理学のバランスの取れた教育を通じて、心や行動の仕組みと機能に関する知識と技術の習得を目指しています。そのため、文系・理系を問わず、幅広い基礎知識が求められます。特に、一般的教養知識の習得や心理学の専門知識を身につける上で必要となる、日本語と英語の読解能力・表現能力を備えた学生を求めています。
思考力・判断力・表現力:自らの主張や論理を組み立てる力、現象を客観的に観察・分析する力、そして、得られた実証データについて主体的に発信する力に優れた学生を求めています。これらの能力は入学後に培われますので、すべてを兼ね備えておく必要はありませんが、論理と実証を基礎とした科学的な心理学の探求に強い関心を持つ人物こそ心理学部の求める人物像です。
主体性・多様性・協働性:入学後は、同志社心理の伝統である「少人数教育」に基づいて、教員と学生はもちろん、学生同士もしっかりと向き合って学び合う機会が設けられます。そのため、他者と協働して社会における問題の解決を試みる行動力を持ち、社会のどのような領域でも活躍できるような幅広い関心やコミュニケーション能力を備えた学生を求めています。
高等学校段階までの学習で身につけてほしいこと
英語:英語の基礎学力やコミュニケーション能力は、大学において広い範囲で一般的教養知識を深めるために必要です。また、心理学部では、心理学の最新の知識を得るために外国書や英語論文を読み込む機会も多くあることから、入学時より高い英語力が求められます。国際社会に貢献する人材となるためにも、高い英語の基礎学力や優れたコミュニケーション能力が求められることになります。
国語:国語の基礎学力は、講義やゼミで文献を読んだり、実験レポートを提出したりする際に必要な能力です。論文で書かれていることを正確に読み取り、自らの実験・調査で得られたデータについて正確な解釈を行うためには、高い国語の運用能力が求められます。また、結果を的確かつ正確に発信する表現力にも国語の能力が求められます。このような読解能力と表現能力は、社会のどのような領域においても根幹となる重要な力になります。
地理歴史・公民:現代社会で発生する多様な問題への感度を高め、理解を深めるには、歴史的な視点と社会情勢に関わる基礎知識を有していることが望まれます。このような知識や感性は、キリスト教主義を原点とした国際的な視点と結びつきながら、現代社会の諸問題を把握し、その解決を目指す行動力につながっていきます。
数学:心理学においては、統計学の手法や知識が求められます。必ずしも、これらを入学前に習得する必要はありませんが、数学的な論理的思考力を身につけておくことが望まれます。客観的な観察力や分析力の基盤といえる統計学の手法や知識は、メーカー、金融、商社、サービス、情報、公共など幅広い業界で有益なツールとなるでしょう。
理科:心理学の一般知識には、脳・神経科学、生理学などに関する分野が含まれます。理科、特に生物についての一定の基礎学力を有していることが望まれます。生物に関する知識は、物事の原理・原則を見抜く力、生命に対する倫理観を培うとともに、健康、保健、福祉、医療などの分野で活躍するための応用力につながります。
入学者選抜制度
心理学部では、高等学校で学習する教科の学力のほかに、心理学に対する関心、学習意欲、表現力やコミュニケーション力などを評価する多様な入学者選抜を行うことにより、多様な学生を受け入れています。本学独自の学力試験のほかに、大学入学共通テスト、書類審査、口頭試問などを取り入れることにより、学力の3要素「知識・技能」、「思考力・判断力・表現力」、「主体性・多様性・協働性」について、それぞれの入試方式において重み付けを行い評価し、志願者の能力や資質等を総合的に審査しています。
一般選抜入学試験:高等学校教育を尊重し、高等学校までの学習の達成・定着度を測るとともに、心理学部の教育を受けるにふさわしい能力と適性を備えたものを公正かつ妥当に選抜するために一般選抜入学試験を実施しています。入試問題の作成にあたっては、全学的に組織された科目ごとの出題委員会において長期間にわたって慎重に審議し、検討を重ね、高等学校での着実な学習努力が報われるように難問や奇問を避け、公平で偏りのない出題に留意しています。とりわけ、本入試においては、マークシート方式ではなく記述式を用いた独自の入試問題による選抜を行うことで、知識・技能のみならず出題意図を正確に理解する力や論理的思考力、正確な表現力の評価にも重点を置き、総合的に審査しています。計算力を問う出題についても同様に記述式解答方法を用いており、結論に至るプロセス等も含め、丁寧に採点しています。
大学入学共通テストを利用する入学試験:入学志願者の高等学校までの学習の達成・定着度を測るとともに、心理学部の教育を受けるために必要となる「知識・技能」や「思考力・判断力・表現力」が備わっているかを、大学入学共通テストの評価により審査しています。
自己推薦入学試験:高等学校での学習及び課外活動を通じてこれまでに培われた基礎学力、「知識・技能」、「思考力・判断力・表現力」等を備え、心理学部で学ぶ高い意欲を持つ人物を選抜するために、出願書類では一定水準以上の「知識・技能」が備わっているか、また、小論文では心理学部で学ぶために必要な「思考力・判断力・表現力」が備わっているか、口頭試問では「知識・技能」とともに「主体性・多様性・協働性」が備わっているかなどを適正に評価しています。とりわけ、本入試においては、「主体性・多様性・協働性」の評価に重点を置き、総合的に審査しています。
指定校制推薦入学試験:高等学校での学習及び課外活動を通じてこれまでに培われた基礎学力、「知識・技能」、「思考力・判断力・表現力」等を備え、かつ心理学部で学ぶ高い意欲を持つ優れた人物を受け入れるために、学校長の推薦に基づき、出願書類では一定水準以上の「知識・技能」が備わっているか、また、心理学部で学ぶために必要な「思考力・判断力・表現力」が備わっているか、口頭試問では「知識・技能」とともに「主体性・多様性・協働性」が備わっているかなどを適正に評価しています。とりわけ、本入試においては、入学後の勉学における明確な志向及び意欲の評価に重点を置き、総合的に審査しています。
法人内諸学校推薦入学試験:同志社の一貫教育を通じて、同志社大学の建学の精神を深く理解し、心理学部で学ぶ高い意欲や相応しい学力を備え、学部の核となり他の学生をリードし、ひいては大学全体の活性化にも寄与できるような優れた人物を受け入れるために、出願書類では一定水準の「知識・技能」が備わっているか、また、心理学部で学ぶために必要な「思考力・判断力・表現力」が備わっているか、口頭試問では「知識・技能」とともに「主体性・多様性・協働性」が備わっているかなどを適正に評価しています。とりわけ、本入試においては、「主体性・多様性・協働性」の評価に重点を置き、総合的に審査しています。
同志社大学 グローバル・コミュニケーション学部のアドミッションポリシー
グローバル・コミュニケーション学部では、一定期間の留学を含むカリキュラムを通して、実践的外国語運用能力を伸長すると共に、幅広い知識と教養を身につけることにより、グローバル社会で卓越したコミュニケーション能力を駆使し、facilitator、negotiator、administratorとして活躍できる人材の育成を目的としています。そのために、次のような学生を求めています。
グローバル・コミュニケーション学部の求める学生像
知識・技能:グローバル社会を舞台に活躍するためには、多様な価値観に目を向け、背後にある社会や文化に関する確かな理解が求められます。また、外国語で発信された情報を正しく理解できることはもちろん、自らの考えを外国語で的確に表現する能力を磨いていく必要があります。本学部の数値的な到達目標は、英語コースはTOEFL iBT®テスト79点(ITP550点)以上及びTOEIC® Listening & Reading Test 850点以上、中国語コースは中国語検定2級ないしHSK 6級(合計点の6割以上のスコア獲得を合格とみなす)、日本語コースは日本語実用テスト(Jテスト)準A級ないしビジネス日本語能力テスト(BJT)J1レベルです。これらの目標に向かい、継続的に努力ができる学生を求めています。
思考力・判断力・表現力:グローバル社会の様々な問題についての議論に加わっていくためには、多様な視点が存在することを十分考慮しながら、筋道を立てて考えることが必要です。状況に対して十分な観察を行い、問題点を整理し、自らの分析をしっかりした根拠と共に説明できなければいけません。論理的に思考し、自らのことばで意見を述べることができる学生を求めています。
主体性・多様性・協働性:世界には多様な文化、言語、社会があり、政治・経済や環境問題などもこれらと密接に関わっています。そのような中で、グローバルな人材となるためには、異なる文化や価値観を持つ人々に対する寛容の精神と、偏見にとらわれず相互理解に向けての努力を惜しまない姿勢が求められます。異なる背景を持つ人々と様々な違いを乗り越えて協働しながら、1つ1つの課題に対して主体的に取り組むことができる学生を求めています。
英語コース
高等学校段階までの学習で身につけてほしいこと
英語:人間の豊かなコミュニケーションは「ことば」を基本に成り立っています。21世紀に入り、人びとの諸活動は世界規模で国境を越えて相互に浸透するようになり、ビジネスではもちろん、政治や教育、文化交流などあらゆる分野で、異なる文化の人と人とを結ぶコミュニケーションの能力が求められています。その際、世界で最も広く使われている「ことば」の一つが英語です。グローバル社会を舞台にfacilitator、negotiator、administratorとして活躍し得る人材の養成を目標に掲げる本学部は、高い英語力を習得した人物を強く求めています。望ましい水準の目安としては、実用英語技能検定(英検)2級(あるいはTOEFL®テスト、TOEIC® Testsなどの同等水準)以上を挙げることができます。これは、本学部英語コースの卒業要件の一つである英語圏での一年間のStudy Abroadを実りあるものにするために、最低限必要な水準です。
けれども、この数値は一つの目安であって、外国語能力試験の成績を伸ばすことだけが英語学習の目的ではありません。日ごろから、英語ということばに関心を持ち、「聞く、話す、読む、書く」の4技能をバランスよく伸ばすことに留意してください。また、英文の内容を正確に理解し、趣旨を的確に把握し、その内容について批判的に考察できる読解力や、根拠や例を示して自己の考えを論理的に組み立て、まとめることのできる表現力を身につけるようにしてください。外国語を学ぶということは、単に文法や語彙を学ぶだけではなく、その背後にある文化を学ぶことであり、新しいものの見方や考え方、表現法やコミュニケーションの方法を学ぶことでもあります。ことばの学習に対する積極的な姿勢を何よりも大切にしてください。
国語(現代文):コミュニケーション能力とは「ことば」で物事を伝える力です。本学部英語コースは卓越した英語コミュニケーション能力を有する人材の育成をその教育目標に掲げていますが、この目標を達成するためには、まず、ことばに関心を持ち、その働きを理解したうえで、ことばを使って物事を伝える力を身につける必要があり、国語(日本語、特に現代文)の学習は不可欠です。具体的には、日本語の文章の内容を正確に理解し、趣旨を的確に把握し、その内容について批判的に考察できる読解力や、根拠や例を示して自己の考えを論理的に組み立てまとめることのできる表現力が必要となります。また、国語(日本語)力は単に日本語を「読む、書く」能力だけを指すのではなく、相手の言うことを正確に理解し、自分の意見を効果的に発信するという「聞く、話す」能力も含まれています。可能な限りこれらすべての能力向上に努めてください。日頃からことばに対する感覚を磨き、ことばに対する関心を深めることが最も大切です。新書や新聞の社説・評論など、身近なところにある論理的な文章を積極的に読むように心がけてください。
地理歴史・公民:「ことば」は人間社会のなかで機能します。ことばの働きを理解し、ことばを使って効果的にコミュニケーションができるようになるためには、ことばの背後にある社会、文化の理解が不可欠です。上記の教科は受験のための必須教科ではありませんが、できるだけ幅広く履修し、社会、文化に関する基礎的知識を身につけてください。世界と日本の歴史・文化や、グローバル化する現代の政治・経済に関心を持ち、主体的に考える力を養うことで、本学部での学びはより豊かなものになります。こうした力を養うためにも、新書、入門的な専門書、新聞の社説・評論などを積極的に読むように心がけてください。
入学者選抜制度
グローバル・コミュニケーション学部では、高等学校で学習する教科の学力のほかに、グローバル化社会に関する関心、学習意欲、表現力、コミュニケーション力などを評価する多様な入学者選抜を行うことにより、幅広い学生を受け入れています。各種の推薦入学試験では、書類審査、小論文、口頭試問あるいは面接を取り入れることにより、学力の3要素「知識・技能」、「思考力・判断力・表現力」、「主体性・多様性・協働性」について、それぞれの入試方法において重み付けを行い評価し、志願者の能力や資質等を総合的に審査しています。
一般選抜入学試験:高等学校教育を尊重し、高等学校までの学習の達成・定着度を測るとともに、大学教育を受けるにふさわしい能力と適性を備えたものを公正かつ妥当に選抜するために一般選抜入学試験を実施しています。
入試問題の作成にあたっては、全学的に組織された科目ごとの出題委員会において長期間にわたって慎重に審議し、検討を重ね、高等学校での着実な学習努力が報われるように難問や奇問を避け、公平で偏りのない出題に留意しています。とりわけ、本入試においては、マークシート方式ではなく記述式を用いた独自の入試問題による選抜を行うことで、知識・技能のみならず出題意図を正確に理解する力や論理的思考力、正確な表現力の評価にも重点を置き、総合的に審査しています。計算力を問う出題についても同様に記述式解答方法を用いており、結論に至るプロセス等も含め、丁寧に採点しています。
大学入学共通テストを利用する入学試験:入学志願者の高等学校までの学習の達成・定着度を測るとともに、グローバル・コミュニケーション学部英語コースの教育を受けるために必要な学力が備わっているか、一般選抜入学試験とは異なる側面から測定できる大学入学共通テストにより評価することで多様な学生の受け入れを行います。
自己推薦入学試験(公募制):グローバル・コミュニケーション学部英語コースで学ぶ高い意欲を持つ人物を選抜するために、出願書類では志望理由書の提出を求め「主体性・多様性・協働性」を評価します。また、英語の運用に関して高い「知識・技能」が備わっているかを評価するため、所定の英語外部試験を用いた出願資格条件を設定しています。小論文では学部で学ぶために必要な「知識・技能」と「思考力・判断力・表現力」が備わっているかを測るべく、英語の長文を読んだ上で、その内容や自分の考えを論理的に述べてもらいます。さらに口頭試問では英語による質問を行い、「知識・技能」や「思考力・判断力・表現力」を測るとともに、日本語でも質問を行い、「主体性・多様性・協働性」が備わっているかなどを適正に評価します。このように自己推薦入学試験では、出願書類、小論文、口頭試問を通じて、学力の3要素「知識・技能」、「思考力・判断力・表現力」、「主体性・多様性・協働性」を総合的に審査しますが、とりわけ本入試においては英語に関する優れた「知識・技能」と、それに基づいた高い「思考力・判断力・表現力」を重視します。
指定校制推薦入学試験:グローバル・コミュニケーション学部英語コースで学ぶ高い意欲を持つ人物を学校長の推薦に基づいて選考するために、出願書類では志望理由書の提出を求め、「主体性・多様性・協働性」を評価します。また、英語の運用に関して一定水準以上の「知識・技能」が備わっているかを評価するため、所定の英語外部試験を用いた出願資格条件を設定しています。小論文では学部で学ぶために必要な「思考力・判断力・表現力」が備わっているかを測るべく、与えられたテーマに関する論述を行ってもらいます。口頭試問では、英語による質問を行い「知識・技能」や「思考力・判断力・表現力」を測るとともに、日本語でも質問を行い、入学後の勉学における明確な志向及び意欲があるか、「主体性・多様性・協働性」が備わっているかなどを適正に評価します。このように指定校制推薦入学試験では、出願書類、小論文、口頭試問を通じて、学力の3要素「知識・技能」、「思考力・判断力・表現力」、「主体性・多様性・協働性」を総合的に審査しますが、とりわけ本入試においては優れた「思考力・判断力・表現力」と「主体性・多様性・協働性」を重視します。
法人内諸学校推薦入学試験:法人内学校での教育を通じて、同志社大学の建学の精神を深く理解し、グローバル・コミュニケーション学部英語コースで学ぶ高い意欲を備えた人物を選考するため、出願書類では志望理由書の提出を求め、「主体性・多様性・協働性」を評価します。また、英語の運用に関して一定水準以上の「知識・技能」が備わっているかを評価するため、所定の英語外部試験を用いた出願資格条件を設定しています。口頭試問では、英語による質問を行い「知識・技能」と「思考力・判断力・表現力」を測るとともに、日本語でも質問を行い、高い「主体性・多様性・協働性」を備えた人物であることを審査します。このように法人内諸学校推薦入学試験では、出願書類と口頭試問を通じて、学力の3要素「知識・技能」、「思考力・判断力・表現力」、「主体性・多様性・協働性」を総合的に審査しますが、とりわけ本入試においては優れた「思考力・判断力・表現力」と「主体性・多様性・協働性」を重視します。
中国語コース
高等学校段階までの学習で身につけてほしいこと
英語:人間の豊かなコミュニケーションは「ことば」を基本に成り立っています。21世紀に入り、人びとの諸活動は世界規模で国境を越えて相互に浸透するようになり、ビジネスではもちろん、政治や教育、文化交流などあらゆる分野で、異なる文化の人と人とを結ぶコミュニケーションの能力が求められています。その際、世界で最も広く使われている「ことば」の一つが英語です。グローバル社会を舞台にfacilitator、negotiator、administratorとして活躍し得る人材の養成を目標に掲げる本学部は、高い英語力を習得した人物を強く求めています。望ましい水準の目安としては、実用英語技能検定(英検)2級(あるいはTOEFL®テスト、TOEIC® Testsなどの同等水準)以上を挙げることができます。
けれども、この数値は一つの目安であって、外国語能力試験の成績を伸ばすことだけが英語学習の目的ではありません。日ごろから、英語ということばに関心を持ち、「聞く、話す、読む、書く」の4技能をバランスよく伸ばすことに留意してください。また、英文の内容を正確に理解し、趣旨を的確に把握し、その内容について批判的に考察できる読解力や、根拠や例を示して自己の考えを論理的に組み立て、まとめることのできる表現力を身につけるようにしてください。外国語を学ぶということは、単に文法や語彙を学ぶだけではなく、その背後にある文化を学ぶことであり、新しいものの見方や考え方、表現法やコミュニケーションの方法を学ぶことでもあります。ことばの学習に対する積極的な姿勢を何よりも大切にしてください。
国語(現代文):コミュニケーション能力とは「ことば」で物事を伝える力です。本学部中国語コースは卓越した中国語コミュニケーション能力を有する人材の育成をその教育目標に掲げていますが、この目標を達成するためには、まず、ことばに関心を持ち、その働きを理解したうえで、ことばを使って物事を伝える力を身につける必要があり、国語(日本語、特に現代文)の学習は不可欠です。具体的には、日本語の文章の内容を正確に理解し、趣旨を的確に把握し、その内容について批判的に考察できる読解力や、根拠や例を示して自己の考えを論理的に組み立てまとめることのできる表現力が必要となります。また、国語(日本語)力は単に日本語を「読む、書く」能力だけを指すのではなく、相手の言うことを正確に理解し、自分の意見を効果的に発信するという「聞く、話す」能力も含まれています。可能な限りこれらすべての能力向上に努めてください。日頃からことばに対する感覚を磨き、ことばに対する関心を深めることが最も大切です。新書や新聞の社説・評論など、身近なところにある論理的な文章を積極的に読むように心がけてください。
地理歴史・公民:グローバル社会で異文化間交流をスムーズに進めるためには、自国の歴史はもちろん、相手国(地域)の歴史や文化についてもしっかり理解しておくことが必要です。とりわけ日本と長い歴史を共有する中国語圏の人びとと交流する際には、必要不可欠と言っても過言ではありません。本学部中国語コースでは中国語圏での1年間のStudy Abroadが卒業要件となっていますが、Study Abroad先で実り多い交流を実現するためにも、また将来中国語圏・東アジアを中心としたグローバル社会で活躍する際に求められる素養を身につけるためにも、近代における日本と中国語圏・東アジアとの関係についてしっかり学び、理解を深めておいてください。中国語コースでは、卓越した中国語コミュニケーション能力の修得を目ざしながら、政治や経済、社会、文化、言語などさまざまな領域から中国語圏の諸事象を学びますが、歴史的背景や歴史的経緯を把握していることで、より深い洞察や理解が可能となります。世界と日本の歴史、とくに近現代史により強い関心を持って歴史関連諸科目を学ぶように心がけてください。
入学者選抜制度
グローバル・コミュニケーション学部では、高等学校で学習する教科の学力のほかに、グローバル化社会に関する関心、学習意欲、表現力、コミュニケーション力などを評価する多様な入学者選抜を行うことにより、幅広い学生を受け入れています。各種の推薦入学試験では、書類審査、小論文、口頭試問あるいは面接を取り入れることにより、学力の3要素「知識・技能」、「思考力・判断力・表現力」、「主体性・多様性・協働性」について、それぞれの入試方法において重み付けを行い評価し、志願者の能力や資質等を総合的に審査しています。
一般選抜入学試験:高等学校教育を尊重しつつ、高等学校までの学習の達成・定着度を測るとともに、大学教育を受けるにふさわしい能力と適性を備えたものを公正かつ妥当に選抜するために一般選抜入学試験を実施しています。入試問題の作成にあたっては、全学的に組織された科目ごとの出題委員会において長期間にわたって慎重に審議し、検討を重ね、高等学校での着実な学習努力が報われるように難問や奇問を避け、公平で偏りのない出題に留意しています。とりわけ、本入試においては、マークシート方式ではなく記述式を用いた独自の入試問題による選抜を行うことで、知識・技能のみならず出題意図を正確に理解する力や論理的思考力、正確な表現力の評価にも重点を置き、総合的に審査しています。計算力を問う出題についても同様に記述式解答方法を用いており、結論に至るプロセス等も含め、丁寧に採点しています。
大学入学共通テストを利用する入学試験:入学志願者の高等学校までの学習の達成・定着度を測るとともに、グローバル・コミュニケーション学部中国語コースの教育を受けるために必要な学力が備わっているか、一般選抜入学試験とは異なる側面から測定できる大学入学共通テストにより評価することで多様な学生の受け入れを行います。
自己推薦入学試験(公募制):グローバル・コミュニケーション学部中国語コースで学ぶ高い意欲を持つ人物を選抜するために、出願書類では志望理由書の提出を求め「主体性・多様性・協働性」を評価します。また、外国語学習への関心や意欲を評価するため、所定の英語外部試験および学習成績の状況による出願資格条件を設定しています。小論文では学部で学ぶために必要な「知識・技能」と「思考力・判断力・表現力」が備わっているかを測るべく、日本語の長文を読んだ上で、その内容や自分の考えを論理的に述べてもらいます。さらに口頭試問では、「知識・技能」や「思考力・判断力・表現力」を測るとともに、「主体性・多様性・協働性」が備わっているかなどを適正に評価します。このように自己推薦入学試験では、出願書類、小論文、口頭試問を通じて、学力の3要素「知識・技能」、「思考力・判断力・表現力」、「主体性・多様性・協働性」を総合的に審査しますが、とりわけ本入試においては「知識・技能」と、それに基づいた高い「思考力・判断力・表現力」を重視します。
指定校制推薦入学試験:グローバル・コミュニケーション学部中国語コースで学ぶ高い意欲を持つ人物を学校長の推薦に基づいて選考するために、出願書類では志望理由書の提出を求め、「主体性・多様性・協働性」を評価します。また、外国語学習への関心や意欲を評価するため、学習成績の状況による出願資格条件を設定しています。小論文では学部で学ぶために必要な「思考力・判断力・表現力」が備わっているかを測るべく、日本語の長文を読んだ上で、その内容や自分の考えを論理的に述べてもらいます。口頭試問では、「知識・技能」や「思考力・判断力・表現力」を測るとともに、入学後の勉学における明確な志向及び意欲があるか、「主体性・多様性・協働性」が備わっているかなどを適正に評価します。このように指定校制推薦入学試験では、出願書類、小論文、口頭試問を通じて、学力の3要素「知識・技能」、「思考力・判断力・表現力」、「主体性・多様性・協働性」を総合的に審査しますが、とりわけ本入試においては優れた「思考力・判断力・表現力」と「主体性・多様性・協働性」を重視します。
法人内諸学校推薦入学試験:法人内学校での教育を通じて、同志社大学の建学の精神を深く理解し、グローバル・コミュニケーション学部中国語コースで学ぶ高い意欲を備えた人物を選考するため、出願書類では志望理由書の提出を求め、「主体性・多様性・協働性」を評価します。また、外国語学習への関心や意欲を評価するため、所定の英語外部試験および学習成績の状況による出願資格条件を設定しています。小論文では学部で学ぶために必要な「知識・技能」と「思考力・判断力・表現力」が備わっているかを測るべく、日本語の長文を読んだ上で、その内容や自分の考えを論理的に述べてもらいます。口頭試問では、「知識・技能」と「思考力・判断力・表現力」を測るとともに、高い「主体性・多様性・協働性」を備えた人物であることを審査します。このように法人内諸学校推薦入学試験では、出願書類、小論文、口頭試問を通じて、学力の3要素「知識・技能」、「思考力・判断力・表現力」、「主体性・多様性・協働性」を総合的に審査しますが、とりわけ本入試においては優れた「思考力・判断力・表現力」と「主体性・多様性・協働性」を重視します。
同志社大学 グローバル地域文化学部のアドミッションポリシー
グローバル地域文化学部は、学部で培った知見を十全に活用することにより、本学の教育理念のひとつである国際主義を更に推進し、国内外のあらゆる場面で活躍できる、良心と自由な精神を備えた人物の育成を目的としています。そのために次のような学生を求めています。
グローバル地域文化学部の求める学生像
知識・技能:グローバル地域文化学部では、国際人として外国語の重要性を十分に認識し、一定以上の英語の能力を有し、英語以外の外国語の習得にも意欲を示すとともに、世界の歴史や地理、時事問題について基礎的な知識を持つ学生を求めています。
思考力・判断力・表現力:グローバル地域文化学部では、高等学校までに培った確かな基礎学力に加え、グローバルな視点から、日本を含む各地の文化、歴史、社会について論理的に考える力や判断する力、それを的確に表現する力を身につけるとともに、現代世界が抱える諸問題に進んで関心を寄せ、それらの解決に向けて柔軟で独創的な方法を考え、社会に働きかける意欲を持つ学生を求めています。
主体性・多様性・協働性:グローバル地域文化学部では、本学部の目的をよく理解し、学部カリキュラムを通じて研かれた外国語能力と地域文化の知見に基づき、主体性とともに寛容さをもって、多様な文化的背景を持つ人々と協働しながら国際社会に貢献したいと考える学生を求めています。
高等学校段階までの学習で身につけてほしいこと
英語:世界の様々な地域の歴史や文化を理解し、そこに住む人々と意思疎通を図る上で外国語能力は不可欠です。とりわけ実質的に世界共通語の役割を担う英語の能力は重要です。文献やインターネットを通して必要な知識・情報を得るための英語の読解力はもとより、将来国際社会に貢献できる人間となるためには一定の英語コミュニケーション能力を備えていることも求められます。実用英語技能検定(英検)2級、あるいはTOEIC ® LISTENING AND READINGテスト 500点、TOEFL iBT®テスト 45点、IELTS 4.5点以上の英語力を入学までに習得できるよう努力してください。
国語(現代文):あらゆる文化的営みの基礎となるのが言語であり、他者の考えを理解し、自らの意見を主張するためにも、日本語能力は大変重要です。日本語能力は、社会に働きかけをしたり、研究内容を発信したりする上で広く求められる実用的なスキルでもあります。文学作品や論説文を的確に読み解き、その主題や趣旨を要約できる読解力や、問題点を整理し、自分の考えを論理的で説得力のある日本語の文章によって表現できる能力は、学部での学修や研究に不可欠です。本学部では卒業論文が必修であり、日頃から文学作品や、日本や世界の文化・社会問題をテーマにした評論など、幅広い分野の読書を習慣づけるとともに、自分の考えを文章で表現する訓練を継続的に行うようにしてください。
地理歴史:世界の各地域固有の文化や社会、そうした地域の枠を越えてグローバルに展開する今日の世界情勢を理解する上で、また実際に世界で様々な活動をする上で、各地域の歴史や地理の基礎知識は不可欠です。今日の世界が抱える様々な問題を把握し、その解決策を考える上で、まずその地域あるいは複数の地域が相互に作用する今日的状況や歴史的流れを理解する必要があります。入学までに地理歴史を、単なる年号や人名および地名の羅列としてではなく、現代世界の諸問題を理解するために欠くことのできないものとして学んでください。
公民:今日の世界各地域の諸問題や、地域を越えて広がる様々な課題を考えていく上で、政治や経済に関する基礎知識が求められます。また、多様な思想信条、価値観を持った人々と国や地域を越えて理解し合っていくためには、そうした多様性を受け止めることのできる倫理的な基盤を確立しておく必要があります。今日の社会を動かしている政治や経済の仕組みと、多様な思想や宗教が人間生活において果たしている役割について、理解を深めるよう心がけてください。
入学者選抜制度
グローバル地域文化学部では、高等学校で学習する教科の学力のほかに、本学部での学びに対する関心、学習意欲、表現力やコミュニケーション力などを評価する多様な入学者選抜を行うことにより、多様な学生を受け入れています。本学独自の学力試験のほかに、大学入学共通テスト、口頭試問、小論文などを取り入れることにより、学力の3要素「知識・技能」、「思考力・判断力・表現力」、「主体性・多様性・協働性」について、それぞれの入試方式において様々な角度から評価し、志願者の能力や資質などを総合的に審査しています。
一般選抜入学試験:高等学校教育を尊重し、高等学校までの学習の達成・定着度を測るとともに、グローバル地域文化学部の教育を受けるにふさわしい能力と適性を備えたものを公正かつ妥当に選抜するために一般選抜入学試験を実施しています。入試問題の作成にあたっては、全学的に組織された科目ごとの出題委員会において長期間にわたって慎重に審議し、検討を重ね、高等学校での着実な学習努力が報われるように難問や奇問を避け、公平で偏りのない出題に留意しています。とりわけ、本入試においては、マークシート方式ではなく記述式を用いた独自の入試問題による選抜を行うことで、知識・技能のみならず出題意図を正確に理解する力や論理的思考力、正確な表現力の評価にも重点を置き、総合的に審査しています。計算力を問う出題についても同様に記述式解答方法を用いており、結論に至るプロセスなども含め、丁寧に採点しています。
大学入学共通テストを利用する入学試験:入学志願者の高等学校までの学習の達成・定着度を測るとともに、グローバル地域文化学部の教育を受けるために必要な学力が備わっているか、大学入学共通テストにより評価しています。
推薦選抜入学試験(公募制):高等学校などでの学習及び課外活動を通じてこれまでに培われた基礎学力、「知識・技能」、「思考力・判断力・表現力」などを備え、グローバル地域文化学部で学ぶ高い意欲を持ち、学部の核となり他の学生をリードし、ひいては大学全体の活性化にも寄与できるような優れた人物を選抜するために、出願書類では一定水準以上の「知識・技能」が備わっているか、小論文および口頭試問では、グローバル地域文化学部で学ぶために必要な「知識・技能」、「思考力・判断力・表現力」および「主体性・多様性・協働性」が備わっているかなどを適正に評価しています。とりわけ、小論文においては「知識・技能」、「思考力・判断力・表現力」の評価、口頭試問においては「主体性・多様性・協働性」の評価に重点を置き、総合的に審査しています。
指定校制推薦入学試験:高等学校での学習及び課外活動を通じてこれまでに培われた基礎学力、「知識・技能」、「思考力・判断力・表現力」などを備え、かつグローバル地域文化学部で学ぶ高い意欲を持つ優れた人物を受け入れるために、学校長の推薦に基づき、出願書類では一定水準以上の「知識・技能」が備わっているか、小論文および口頭試問では、グローバル地域文化学部で学ぶために必要な「知識・技能」、「思考力・判断力・表現力」および「主体性・多様性・協働性」が備わっているかなどを適正に評価しています。とりわけ、小論文においては「知識・技能」、「思考力・判断力・表現力」の評価、口頭試問においては「主体性・多様性・協働性」の評価に重点を置き、総合的に審査しています。
法人内諸学校推薦入学試験:同志社の一貫教育を通じて、同志社大学の建学の精神を深く理解し、グローバル地域文化学部で学ぶ高い意欲や相応しい学力を備え、学部の核となり他の学生をリードし、ひいては大学全体の活性化にも寄与できるような優れた人物を受け入れるために、出願書類では一定水準の「知識・技能」が備わっているか、小論文および口頭試問では、グローバル地域文化学部で学ぶために必要な「知識・技能」、「思考力・判断力・表現力」および「主体性・多様性・協働性」が備わっているかなどを適正に評価しています。とりわけ、小論文においては「知識・技能」、「思考力・判断力・表現力」の評価、口頭試問においては「主体性・多様性・協働性」の評価に重点を置き、総合的に審査しています。